【馬渕磨理子氏コラム】
総選挙と大統領選後の日米経済 連載第24回
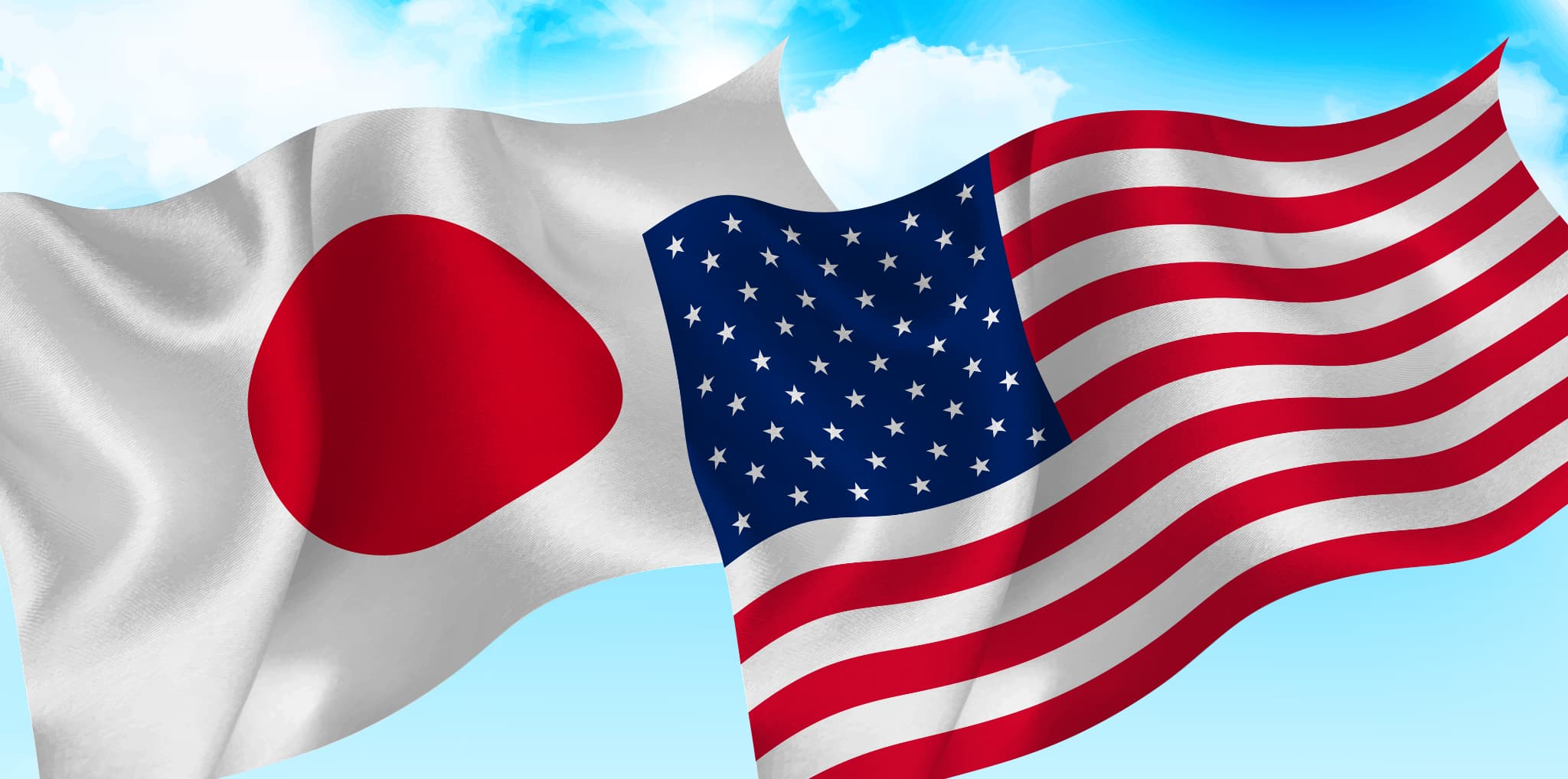
目次
日米が迎えた転換期
日本では石破茂新首相が誕生し、そして解散総選挙が行なわれるなど、政局に大きな動きがありました。そしてアメリカでは、11月5日に大統領選挙が待ち受けています。民主党のカマラ・ハリス候補と共和党のドナルド・トランプ候補のどちらが勝利を収めるにしても、4年に1度の大きな転換点を迎えることは間違いありません。日米ともに政治がきわめて不安定であり、もちろん、その影響は経済にも及びます。
まずアメリカについて分析すると、大統領選については、ハリス候補とトランプ候補の支持率が拮抗したまま10月を迎えており、接戦のまま11月5日の当日を迎えるでしょう。当初はトランプ候補の勝利が手堅いという声が日本でも聞こえていましたが、民主党の候補がジョー・バイデン大統領からハリス副大統領に変わったこと、またハリス候補が予想よりもリベラルが主張しがちなアイデンティティの話題を自重していることもあって、どちらに転ぶかわからない状況になりました。
とくにアメリカの動向で注目されるのが、金融政策です。じつのところ、民主党と共和党は意外にも経済政策に大きな違いはありません。財政については今後も悪化が続くでしょうし、移民政策についても、たとえハリス候補が勝利したとしても、この3年間の移民流入が多すぎたので、ある程度のブレーキは踏まざるを得ません。また、通商政策では対中強硬姿勢は同様だと予測されます。そのなかで、両者の相違点を見られるのが金融政策です。トランプ候補は「ドル安・低金利」を好み、FRBの政策への介入も辞さないでしょう。一方のハリス候補は、中央銀行の独立性の観点から、露骨な介入は慎むはずです。
FRBの利下げは続くか
では、今後のアメリカの金融政策はどうなるのか。9月18日、FRBは0.5%の利下げを決定したと発表しました。利下げ幅は通常の0.25%の倍であり、これは労働市場が一段と減速するリスクをふまえた大幅な利下げだと解釈できます。利下げそのものが4年半ぶりであり、FRBの金融政策は大きな転換点を迎えています。ただし、今後も利下げが続くかと言えば、アメリカでは懐疑的な見方が存在します。
アメリカでは住宅ローンを借りる際に、9割以上が固定金利で契約しています。さらに言えば、固定金利で住宅ローンを契約しているアメリカ人の8割は5%以下で借りています。ですから、近年の金利上昇で多くのアメリカ人が騒いでいるかと思いきや、それはあくまでも一部です。FRBからすれば、金利を下げることで消費マインドを喚起したいという思惑や期待があるでしょうが、そもそも固定金利の人が多かればあまり関係がない。利下げが景気刺激策になるかと言えば、じつはそうとも言い切れないのです。
とはいえ、いずれにせよアメリカの経済が好調なのは間違いなく、ニューヨークダウもS&P500も根強く、投資環境としてはポジティブでしょう。10月4日発表された9月の米雇用統計を見ても、非農業部門雇用者数は前月比で254,000人増となり、市場予想の150,000人増を大幅に上回っています。 また7月と8月の実績も上方修正され、雇用者数は合計で72,000人増。そのほか、失業率は4.2%で横ばい、時間給は前月比で0.2%の伸びから0.4%へ伸びが加速しました。
アメリカ経済の懸念点
アメリカ経済の足元がこれだけ強いのであれば、やはり利下げをする必要もないという声が上がり始めています。物価が再上昇するという懸念も囁かれていますから、決して気を緩められる状況とは言えないでしょう。私個人としては、緩やかに、なおかつ淡々と利下げしていくほうが、アメリカ経済としてはソフトランディングできるのではないかと考えています。
そのほか、アメリカ経済の懸念点を挙げるとすれば、労働市場を分析すると、フルタイムで働く正社員が減って、パートタイム労働者が増えているという傾向が見てとれます。これはつまり、経営者が景気の先行きを心配しているからこそ、コストがかからないパートタイム労働者の雇用にシフトしているのではないか、と解釈することができます。
また、アメリカでは、コロナ禍の際には給付金が支給されて貯蓄が増えましたが、現在ではそれをすでに使い切っているのか、貯蓄額がコロナ禍前よりも割り込んでいるというデータもあります。アメリカ国民からすれば、そんな状況下で物価が高いわけですから、これから消費が冷え込む恐れがある。これらの点については、アメリカ経済の今後を考えるうえでやや心配な点です。
それでも、先ほども紹介したように、足元の手堅い経済指標を参照すれば、大きな方向性としては好景気と言える状況が続いていくでしょう。そして実際、現時点では株高傾向です。なお、ダウやS&P500の上昇率ランキングを見ると、中東情勢の不穏な状況を受けて、石油などのエネルギー関連が好調であり、今後のその流れは続いていきます。
石破政権に期待されること
私は9月の終わりに、アメリカを訪れていました。まさしく自民党総裁選のタイミングです。そこで、石破政権に対してどのような見方をしているかを現地で尋ねたところ、あるファンド関係者は、「どのような金融政策や経済改革に取り組むのか不透明だ。市場改革という点で、岸田文雄首相が推し進めてきたことを継続するのかに注目したい」と述べていたのが印象的でした。石破首相は、総裁選の決選投票で岸田前首相と菅義偉元首相からの支持を得たこともあり、岸田路線を引き継ぐ姿勢を明言しています。
また、帰国後にあらためてアメリカの関係者に石破首相の印象を聞いたところ、「経済問題に関してはあまり知識や情熱がないのではないか」との答えが返ってきました。ただし、これは一概にネガティブな意見というわけではなく、経済政策については官僚に任せる割合が多く、結果として大きな間違いは生じないのではないか、という分析でした。とはいえ、日本が経済を成長させるならば、たとえば労働市場の流動性を高めるにあたっては政治的意思決定が必要であり、霞が関任せでは限界があることも事実です。
また、アメリカの投資機関家が石破政権の何に関心を寄せているのかというと、大きくは三つあります。すなわち、金融所得課税、法人税、原発稼働の行方が、マーケットでの懸念材料として意識されているようです。たとえば、石破首相は格差是正として金融所得課税の強化を「実行したい」と発言してきました。法人税法の弾力化、つまりは「法人税の引き上げ」にも言及しています。総選挙中は金融所得課税や法人税の引き上げの論調はトーンダウンしましたが、今後はその動きに注視すべきでしょう。
石破政権が誕生した直後、株価が下落したときには、多くの読者が先行きを不安に感じたことでしょう。じつはこの点は、岸田政権の発足時と同様なのですが、当時は経済チームが「Invest in Kishida」と打ち出すなど方針転換して、資産所得倍増や新NISAなどの政策がマーケットに評価されたと考えられています。石破政権についても、経済チームが今後、どのような政策を打ち出すかが待たれるところでしょう。その意味でも、先ほど申し上げたように政治的意思決定が必要になります。
《馬渕氏の連載コラム》
第1回 東京の価値はコロナ後にどうなる?
第2回 企業の「多様性」と「持続性」を考える
第3回 三拍子が揃っている日本市場の強さ
第4回 企業は「現状維持=衰退」の覚悟をもて
第5回 インフレ時代、投資家が評価する企業とは
第6回 「金融リテラシー」をどう高めるべきか
第7回 「歴史的円安」という言葉に踊らされないように
第8回 リスクを可視化できる企業が2023年を生き残る
第9回 日銀の金融政策決定会合が意味するもの
第10回 リクルート競争にどう打ち勝つか
第11回 黒字転換する企業は何が違うのか
第12回 上場後に伸び続ける企業、失速する企業
第13回 中小企業経営者が知るべき米国の動き
第14回 なぜ日本の商社に学ぶべきなのか
第15回 日本が自覚できていない「強み」とは
第16回 2024年問題のインパクトに備えよ
第17回 「稼ぐインフラ」が求められる時代
第18回 「中東紛争&台湾有事」と「インバウンド」のゆくえ
第19回 加速していくGXと生き残る企業
第20回 2024年も価値が上がる東京
第21回 2024年の資産運用のキーワードは「王道」
第22回 歴史的円安が招く時期尚早の利上げ
第23回 中小企業の賃上げをいかに実現するか
お話いただいた方
馬渕磨理子(まぶち・まりこ)
◎経済アナリスト/日本金融経済研究所代表理事/ハリウッド大学院大学客員准教授◎
PROFILE 京都大学公共政策大学院修士課程修了。トレーダーとして法人の資産運用を担う。その後、金融メディアのアナリスト、FUNDINNOで日本初のECFアナリストとして政策提言に関わる。イー・ギャランティ社外取締役。フジテレビ、日経CNBC、プレジデント、ダイヤモンド、Forbes JAPAN、SPA!などで活動。主な書籍に『5万円からでも始められる! 黒字転換2倍株で勝つ投資術』 『株・投資ギガトレンド10』『収入10倍アップ 高速勉強法』『収入10倍アップ超速仕事術』など。

オフィス賃貸情報は「東京オフィス検索」までお問い合わせください。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。


