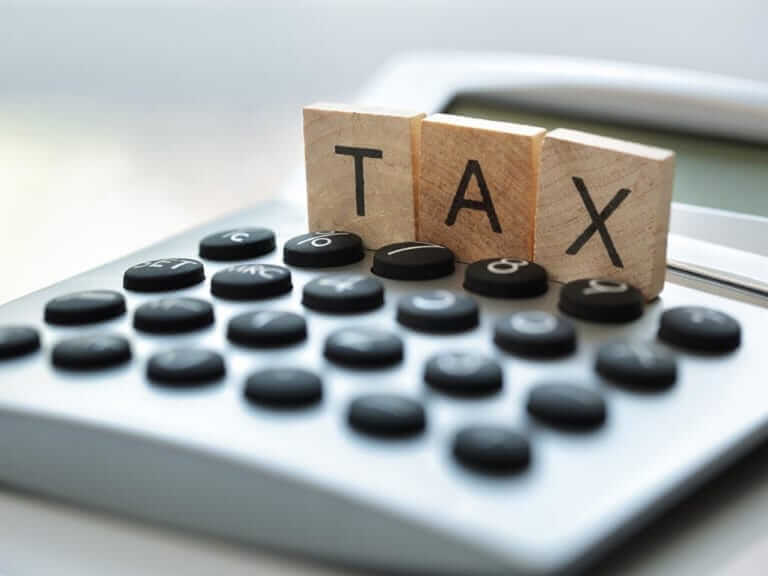目次
本記事に掲載された情報は、2021/09/24時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
兄弟・姉妹で遺産相続をする場合、遺産を公平に分けることができるように、民法では各相続人の遺産相続の割合(法定相続分といいます。)が定められています。しかし、兄弟・姉妹の遺産相続はトラブルになりやすいといわれていて、遺産分割協議でもめるケースも少なくありません。
この記事では、そんな兄弟・姉妹での遺産相続について、法定相続分やよくある兄弟間トラブル、トラブルを防ぐ方法について解説していきます。
1. 兄弟・姉妹で遺産相続をするケースと、それぞれの法定相続分
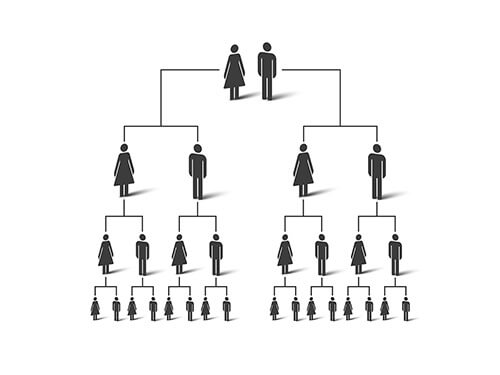
まずは、兄弟・姉妹で遺産相続をするケースはどんなときか、それぞれの法定相続分について説明します。
1-1. 親の財産を兄弟・姉妹で遺産分割するケース
兄弟・姉妹で遺産相続をするケースで最も多いのは、親の財産を兄弟・姉妹で遺産分割するケースです。この場合、どちらか一人の親が亡くなったときの相続と、さらにもう一人の親が亡くなったときの相続では相続割合が異なります。
どちらか一人の親が亡くなった場合
両親のうちどちらか一人の親が亡くなった場合、亡くなった親の遺産は法定相続人となるもう一人の親(配偶者)と子供が相続するのが原則です。子供が複数いる場合は兄弟・姉妹の人数によって遺産相続割合が変わります。
| 配偶者の相続割合 | 2分の1 |
|---|---|
| 子供の相続割合 | 2分の1(兄弟・姉妹がいる場合はこれを均等に分ける) |
例えば亡くなった親の遺産総額が1億円の場合、もう一人の親(配偶者)が5,000万円、子供が兄弟2人の場合は2,500万円ずつ、兄弟4人の場合は1,250万円ずつ相続することになります。
さらにもう一人の親が亡くなった場合
さらにもう一人の親が亡くなった場合の相続で子供がいる場合は、その子供がすべての遺産を相続することになります。子供が複数いる場合、すなわち兄弟・姉妹がいる場合は、その兄弟・姉妹で遺産を均等に分けるのが民法上のルールです。
例えば、亡くなった親の遺産総額が1億円の場合、子供が兄弟2人の場合は5,000万円ずつ、兄弟4人の場合は2,500万円ずつ相続することになります。
1-2. 亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人となるケース
亡くなった人自身の兄弟・姉妹が相続人として遺産を相続するケースもあります。
民法では法定相続人の順位が定められていて、ある人が亡くなった場合、その配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者以外で相続人となれる人は以下の順位で決まります。
| 必ず相続人となる人 | 亡くなった人の配偶者 |
|---|
+
| 第1順位 | 亡くなった人の子供 |
|---|---|
| 第2順位 | 亡くなった人の両親 |
| 第3順位 | 亡くなった人の兄弟・姉妹 |
つまり、ある人が亡くなったとしても、亡くなった人に子供がいる場合、または亡くなった人に子供がいない場合でも亡くなった人の両親が存命の場合には、亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人となることはありません。しかし、亡くなった人に子供がおらず、かつ亡くなった人の両親がすでに他界しているというようなケースでは、亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人となります。
そして兄弟・姉妹が相続人となるケースでは、配偶者の有無によって遺産相続割合が異なります。
亡くなった人に配偶者がいる場合
亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人となるケースで、亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者と兄弟・姉妹の遺産相続割合は以下のとおりです。
| 配偶者の相続割合 | 4分の3 |
|---|---|
| 兄弟・姉妹の相続割合 | 4分の1(兄弟・姉妹の人数でこれを均等に分ける) |
例えば亡くなった人の遺産総額が5,000万円の場合、配偶者が3,750万円、亡くなった人の兄弟が2人の場合は625万円ずつ、兄弟が4人の場合は312万5千円ずつ相続することになります。
亡くなった人に配偶者がいない場合
亡くなった人の兄弟・姉妹が相続人となるケースで、亡くなった人に配偶者がいない場合、亡くなった人の兄弟・姉妹がすべての遺産を相続することになります。兄弟・姉妹が複数いる場合は、その中で遺産を均等に分けるのがルールです。
例えば、亡くなった人の遺産が5,000万円の場合、亡くなった人の兄弟が2人の場合は2,500万円ずつ、兄弟が4人の場合は1,250万円ずつ相続することになります。
1-3. 亡くなった人の兄弟・姉妹に遺留分は認められていない
前述のとおり、亡くなった人の兄弟・姉妹が遺産相続をするケースも存在します。しかし、亡くなった人の兄弟・姉妹に「遺留分」は認められていません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限の相続財産を受け取ることができるように定められた制度のことです。例えば、本来は相続する予定の財産が遺言によって相続人以外の第三者に譲ると定められ、それにより相続人の相続する分が法定相続分を下回っていた場合や、他の相続人が多く相続すると定められ、それにより相続人の相続する分が法定相続分を下回っていた場合などの際、法定相続人である配偶者や子供、親は「遺留分侵害額請求」を行うことで遺留分の権利を主張することができます。
しかし、遺留分が認められていない兄弟・姉妹の場合、兄弟・姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできないのです。
2. 遺産相続でよくある兄弟間トラブル

ここまで紹介してきたとおり、兄弟・姉妹で遺産相続をする場合、相続人となるパターンによって遺産相続割合(法定相続分)が法律で定められているため、そのルールに従って遺産分割をすれば特にトラブルは起こらないと考えるのが普通かもしれません。
しかし、兄弟・姉妹の遺産相続はトラブルになりやすく、遺産分割協議でもめて裁判に発展するケースや、最悪の場合は絶縁状態になってしまうほどの争いになってしまうこともあるほどです。
ここからは、兄弟・姉妹のみで遺産相続をする場合によくあるトラブルを紹介していきます。
2-1. 兄弟・姉妹のうち一人が親の介護をしていた
親の遺産を兄弟・姉妹で相続する場合、兄弟・姉妹のうち一人が親の介護をしていたというケースがあります。この場合、「親の介護をしていたのは自分なのに、相続の割合が同じだなんて納得できない」と考える人がでてきてもおかしくはありません。
民法には「寄与分」という制度があります。寄与分とは、亡くなった人の財産の維持または増加に無償で特別の貢献をした相続人が、遺産分割で特別な処遇を受けられるという制度のことです。
しかし、兄弟・姉妹の一人が寄与分を主張した場合、ほかの兄弟・姉妹がそれに対して不満を持つことは十分考えられます。そのような場合、寄与分を主張して主張裁判を起こすケースも実際に存在しています。
2-2. 音信不通で連絡が取れない兄弟・姉妹がいる
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、音信不通で連絡が取れない兄弟・姉妹がいる場合も、音信不通の兄弟・姉妹を無視して遺産相続を進めることはできません。まずはその兄弟・姉妹を探し出して、音信不通を解消するところから始めなければならず、遺産相続が長期化する可能性が高くなります。
2-3. 特定の兄弟・姉妹だけに生前贈与がされていた

兄弟・姉妹で遺産相続をするときに、特定の人だけに生前贈与がされていたことが発覚してしまうとトラブルになることがあります。
これは「特別受益」と呼ばれるもので、特別受益があると認められた場合、相続人同士の不公平さをなくすために、生前贈与を受けた相続人の相続分から特別受益分が減額されるなどの処置がとられることにあります。
しかし、生前贈与を受けた人が特別受益に該当することをすんなり認めるとは限らず、特別受益をめぐって裁判などの争いに発展することも珍しくはありません。
2-4. 遺言書に残された相続割合に不満がある
兄弟・姉妹での遺産相続は、均等に分けることが原則です。
しかし、遺言書に均等ではない相続割合が残されていた場合、他の兄弟・姉妹よりも少ない財産しか受け取れない人が、その相続割合に不満を持つことは想像に難くありません。
親の財産を子である兄弟・姉妹で相続する場合には、子には前述した「遺留分」という制度があるため、遺言書にどのような相続割合が書かれていたとしても、遺留分を侵害されている場合、遺留分に足りない分については請求することができます。
2-5. 相続財産に不動産が含まれている
現物を分けて相続することが難しい不動産は、相続で最もトラブルになりやすい財産だといわれています。そのため、兄弟・姉妹で遺産相続する財産に不動産が含まれている場合は、特に注意が必要です。
兄弟・姉妹での遺産相続で不動産を分ける方法としては、以下の4つのパターンがあります。
| 現物分割 (土地の分筆) |
土地の分筆登記を行い、現物のまま兄弟・姉妹で分ける |
|---|---|
| 換価分割 | 不動産を共同で売却して、その売却代金を兄弟・姉妹で平等に分ける |
| 代償分割 | 兄弟・姉妹のうち一人が不動産を相続する代わりに、ほかの人の相続分相当額を金銭で支払うことで清算する |
| 共有分割 | 不動産を兄弟・姉妹で共同で保有する |
3. 兄弟・姉妹の遺産相続でトラブルを防ぐ方法はある?

兄弟・姉妹の間での遺産相続トラブルを防ぐために有効な方法はあるのでしょうか。
続いては、遺産相続で兄弟間トラブルを起こさないために知っておきたい方法を紹介していきます。
3-1. 兄弟・姉妹での遺産相続について生前から話し合っておく
兄弟・姉妹の間での遺産相続によるトラブルを防ぐには、親が元気なうちから相続について話し合っておくことが大切です。もし音信不通の兄弟・姉妹がいるなら、探して連絡を取るようにしておきましょう。
兄弟・姉妹のうちの一人に親の介護を任せているなら、介護を分担して行うなど、不満が起こらないように努めましょう。
3-2. 分けにくい不動産は分割しやすい財産に置き換える
兄弟・姉妹での遺産相続に限らずですが、現物を分けることが難しい不動産は最もトラブルに発展しやすい財産だといわれています。
兄弟・姉妹で遺産分割する場合、例えば分けにくい不動産がある場合にはそれをいったん現金化し、分割しやすい不動産に置き換えておくことで平等な遺産相続ができることが考えられます。現金のままでも兄弟・姉妹で平等に分けることはできますが、不動産の相続税評価額は一般的に実勢価格より下がる傾向があるためです。但し、そもそも不動産を現金化する際には、不動産売却についてその保有者である親が売主となる必要があること、そして不動産売却や購入について諸税や費用が掛かることに留意が必要です。
兄弟・姉妹が将来、平等に遺産相続を行うには、不動産小口化商品の活用がおすすめです。
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、都心にある中規模オフィスビルを小口化しており、500万円(1口100万円、5口以上)からの小口購入が可能です。1口単位で複数の相続人へと分割することができるため、平等な財産の分割が可能です。
また、贈与税や相続税の対象となる財産評価額を引き下げられる可能性があります。
※本コラムに記載された内容は、各種の事例や文献を基に一般論として述べたものです。弊社から当該物件の購入についての税務に関する何らの示唆
および確定的な見解を示すものではなく、本コラムに記載された算出方法や評価額など一切について正確性および確実性を保証するものではありません。
具体的な申告書の作成などにあたりましては、税理士などの専門家や所管の税務署などにご相談いただきますようお願いいたします。
※ 分譲マンションの相続税評価額については、「居住用の区分所有財産の評価について(国税庁)」に定められた評価方法が適用されます。
※ 一定期間の保有が条件となります。
※ 評価額は物件により異なります。

弊社の不動産小口化商品「Vシェア」について詳しく知りたいという方は、以下のページをご覧ください。
4. 最後に
今回は、兄弟・姉妹の遺産相続をテーマに、相続割合やよくある相続トラブル、トラブルを防ぐ方法について解説してきました。
兄弟・姉妹での遺産相続でトラブルや争いを起こさないためには、生前のうちからしっかりと準備し、予防しておくことが大切です。親族で相続について話し合う場を設けたり、不動産のように分けにくい財産については分割しやすい財産に置き換えたりと、できるだけ早いタイミングから相続について検討を始めておくことをおすすめします。
兄弟・姉妹に対して平等に財産を相続したいとお考えの方で、不動産小口化商品を検討される場合は、ぜひ弊社の「Vシェア」もご検討ください。
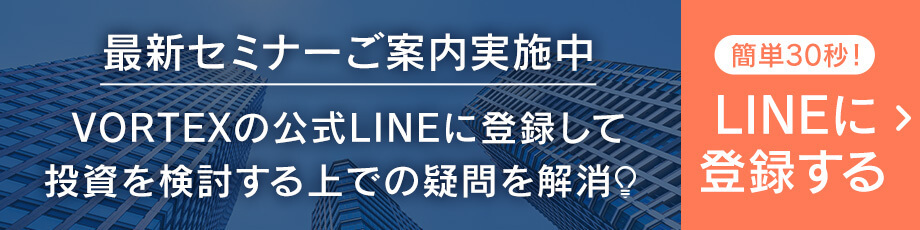
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。

記載内容の内、法務に関する内容の監修
丸山 純平まるやま じゅんぺい
東京幸せ相続相談センター 理事
丸山弁護士法人 丑和総合法律事務所 代表弁護士
「相続を争続にさせてはならない」
私は、相続案件や事業承継案件に関し、法律面、税務面、感情面からお客様をサポートすることが、相続に携わる弁護士としての使命ではないかと感じています。生前の相続準備は、争続を防ぐ最大のポイントです。法律や税務上の課題をクリアにしつつ、お客様の思いを最大限に活かした相続を実現します。一方で、相続発生後、万が一様々な課題に直面した場合でも、お客様の状況に応じてサポートいたします。私はこれまで多数の相続案件、事業承継案件に携わり、「お客様に安心していただくための解決」という視点から、最適な解決策を提案してきました。これからも自らの知見と経験を基に、相続や事業承継に関する最新情報を踏まえて日々研鑽を重ねつつ、お客様に寄り添ったリーガルサービスを提供してまいります。
一般社団法人 東京都不動産相続センター(https://fudosan-sozoku.or.jp/)
相続の記事一覧に戻る