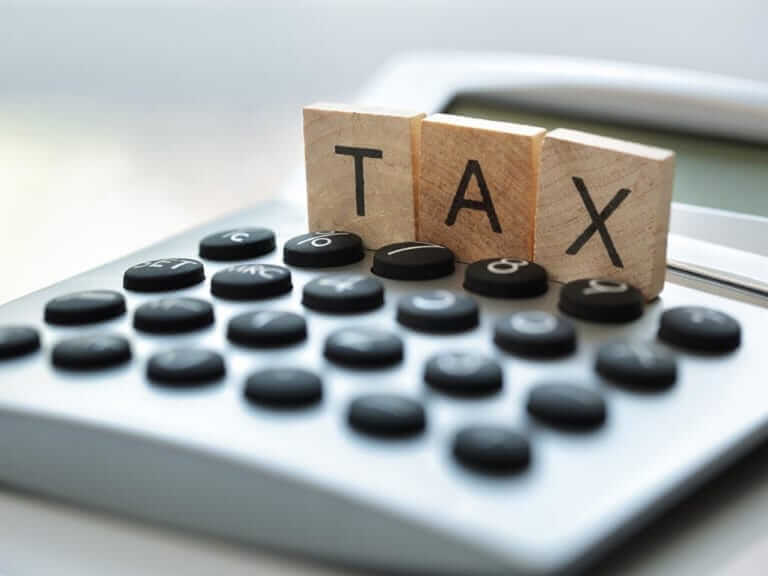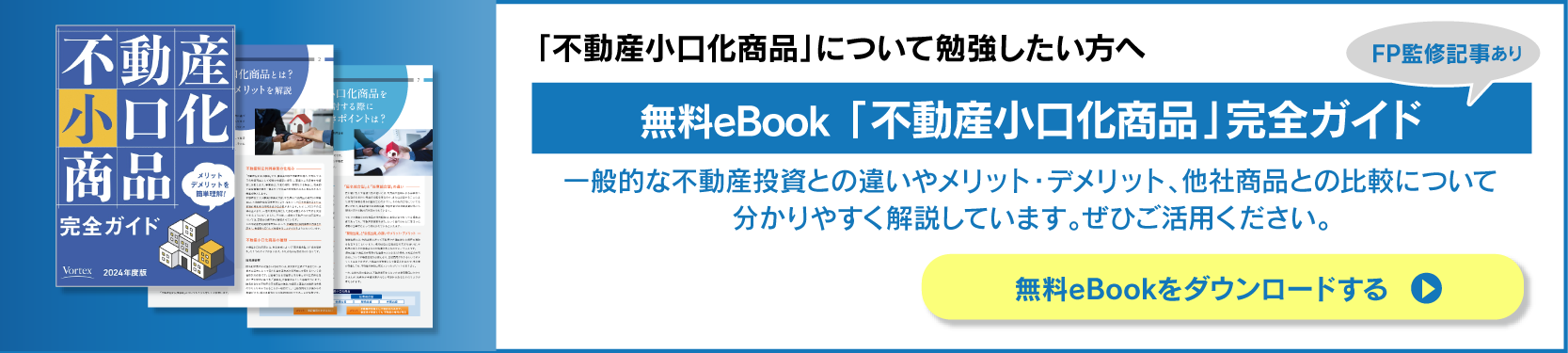目次
もしも1,000万円手元にあったら、あなたはどう使いますか?世界経済や金融市場の不安定さを考えると、1,000万円の手元資金はできるだけ減らさずに資産運用したいと考える方も多いでしょう。ここでは、「1,000万円を減らさずに運用して増やしたい」という人のために、リスクを抑えながら1,000万円を仮に10年運用する場合の運用方法についてご紹介します。
1. 1,000万円の運用は10年後の目標・ライフプランが大事
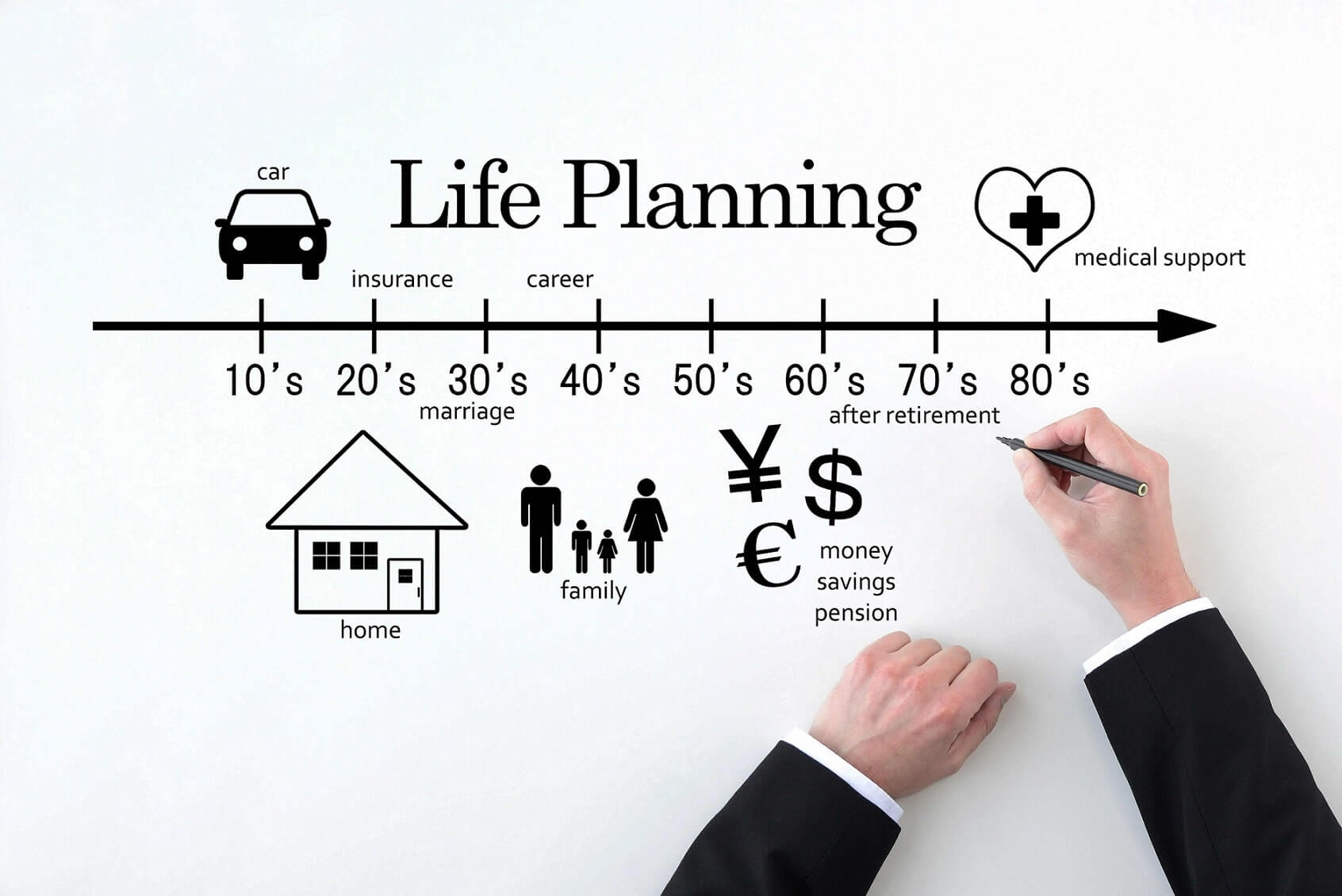
手元資金1,000万円を運用するとなった場合、まずは10年間でどれくらい増やしたいのか、10年後の目標金額を設定しましょう。
10年後の目標設定において大事なのは、ライフプランを立てること。これからの10年間でどのようなライフイベントがあるのか、資産状況・負債状況、そして老後資金はいくら必要か?など、ライフプランをしっかりと立てることで、今後の人生でどれくらいお金が必要なのかがわかり、資産運用における10年後の目標が設定しやすくなるのです。
1-1. ライフプランの立て方
ライフプランとは、自分の生涯における生活設計のことをいいます。今後の人生でどんな暮らしがしたいか、大切にしたいものは何か、実現したいことは何かなど、将来どんな自分でいたいかを想像しながら計画を立て、それを実現していきます。
ライフプランを立てるとき、考えるべき大事なポイントは「健康」「生きがい」「お金」だといわれています。10年、20年と長い年月をかけてライフプランを実現していくのですから、まずは何より自分が「健康」でいなければいけませんよね。そして人生には「生きがい」が必要です。仕事や家族、趣味や社会活動など、ライフプランのなかに自分の生きがいを組み入れることで、より楽しく豊かな人生のプランニングができるでしょう。
そして、大事なのが「お金」のプランニング。健康で生きがいのある幸せな人生を送るために、お金は欠かせないものです。ライフプランの実現に必要なお金に関するプランニングは、できるだけ早いうちから準備を始めることが大切です。
1-2. ライフプランニングの事例
「お金」に関するライフプランは、年代とともに発生する様々なライフイベントを考慮して計画しましょう。以下の表は年代別に考慮すべきライフイベントと、お金に関するライフプランニングの事例です。
| 年代 | 主なライフイベント | お金に関するライフプラン |
|---|---|---|
| 20代 |
|
|
| 30代 |
|
|
| 40代 |
|
|
| 50代 |
|
|
| 60代 |
|
|
20代から30代にかけては、結婚や出産、マイホーム購入などの大きなライフイベントがあり、仕事と子育てに追われ、10年後のライフプランまで考えていられないという方も多いでしょう。しかし、子育てがひと段落する40代は、いわゆる「2,000万円必要」と言われる老後資金の準備や退職金の資産運用について考え始めるのに適したライフステージです。
40代以降でライププランを立てるときは、老後に必要な生活費や退職金なども考慮し、10年後、20年後のライフプランに合わせていくら必要なのかという目標を立て、今ある手元資金をできるだけ減らさず、安全に行える資産運用の方法を検討されるとよいでしょう。
2. 1,000万円の10年運用シミュレーション

10年後の目標が設定できたら、仮に今手元に1,000万円があるという場合に、どれくらいの利回り、どれくらいのリスク許容度で運用すれば目標達成できるのか、下記のように運用シミュレーションができるサイトなどを利用して、具体的にシミュレーションしてみましょう。
- リンク先のページは変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
2-1. 1,000万円を10年運用する場合のシミュレーション(想定利回り別、複利計算)
| 運用資金(元本) | 1,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運用期間 | 10年 | ||||
| 想定利回り(年率) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
| 運用結果 | 1,219万円 | 1,343.9万円 | 1,480.2万円 | 1,628.9万円 | 1790.8万円 |
2-2. 1,000万円運用で目標を1500万円に設定した場合にかかる年数(想定利回り別、複利計算)
| 運用資金(元本) | 1,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標金額 | 1,500万円 | ||||
| 想定利回り(年率) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
| 達成までの年数 | 20年6カ月 | 13年9カ月 | 10年4カ月 | 8年4カ月 | 7年 |
こちらのシミュレーションは設定した条件を計算式にあてはめて計算したものです。資産運用において考慮しなければならない投資リスクが反映されていないため、実際の投資結果とは異なります。1,000万円の手元資金を減らしたくない、できるだけ安全に運用したいという場合は、リスク分散することも重要になってきます。
リスク分散の必要性について、詳しくは下記ページをご参照ください。
3. 預貯金が1,000万円を超えたら考えるべきことは?

預貯金が1,000万円を超えたら少しだけ気をつけておきたいことがあります。
3-1. ペイオフに注意する
ペイオフという制度をご存知でしょうか。
ペイオフとは、万が一預貯金をしている金融機関が破綻した場合にも、預金保護法によって、預金保険機構が預金者に一定額までの預金を払い戻すという預金保険制度のことです。
ペイオフは、預金者保護の観点から定められた制度ですが、預金のうち一定額までしか保護の対象とはならず、現在保護の対象となる預金の額は、ひとつの金融機関につき一人1,000万円までとなっています。
そのため、預貯金が1,000万円を超えた場合、まずは複数の金融機関に預貯金を分散するということを検討しましょう。
3-2. 資産運用を検討する
預貯金1,000万円がすぐに必要なお金でない場合、そのまま眠らせておくのはもったいないですよね。預貯金が1,000万円を超えたら、資産運用について具体的に検討してみてもよいかもしれません。「お金がお金を生む」という話を耳にすることがあると思いますが、預貯金1,000万円はまさにその仕組みを検討するべきよいタイミングです。
資産運用を検討する際は、せっかく貯めた預貯金1,000万円を減らさないように、ライフプランを見据えた長期投資の目標を設定することが大切です。また、手元資金を減らすことなくどのようにして増やすのか、リスクを抑えた資産運用方法を検討しましょう。
4.リスクを抑えながら1,000万円を10年運用する方法とは
実際に1,000万円をリスクを抑えながら10年間資産運用するとなったら、選ぶべき運用方法はどれなのでしょうか?ここからは、元本保証など低リスクな運用方法からミドルリスクな運用方法まで、それぞれの商品の特徴や想定利回り、始め方についてご紹介します。
4-1. 定期預金
銀行の定期預金は、元本保証があるという点で最もリスクの低い金融商品です。
想定利回りはメガバンクでは0.01%程度、ネットバンクで0.02%~0.2%程度となっています。銀行に口座を開設し、預け入れをするだけで簡単に始めることができます。
4-2. 個人向け国債/地方債
国債とは、国が発行する債券のことで、地方債とは地方自治体が発行する債券のことです。利子、元本とも国や地方自治体が責任を持って保証するため、低リスクで安心感のある金融商品だといえます。
個人向け国債には変動金利型10年、固定金利型5年、固定金利型3年の3種類あり、固定金利型、変動金利型とも最低で0.05%の金利が保証されています。個人向け国債は、銀行や証券会社で購入できます。
4-3. 社債
社債は、企業が資金調達を目的として投資家に発行する債券のことです。企業から不定期に募集されます。最近では、2018年に販売されたソフトバンク社債が有名です。企業が倒産しない限り元本・利子ともに戻ってくるため、信用度の高い企業の発行する社債であれば、比較的リスクは低いといえるでしょう。
利率は商品によって0.02%~5%程度と幅広く、証券会社で購入できます。
4-4. 保険

個人年金や養老保険、学資保険といった貯蓄型保険でも資産運用は可能です。貯蓄型保険とは、満期までの積み立てによって支払った保険料以上の保険金が戻ってくるというものです。
貯蓄型保険の利回りは商品によって異なります。支払った保険料を100%とすると、100%を超えた分が利回りです。保険会社で加入申し込みできます。
4-5. 不動産小口化商品

不動産小口化商品とは、個人単位ではなかなか購入しづらい不動産物件を一口100万円などの単位で小口化し、販売する金融商品です。実際の不動産を少額な資金で保有し、運用することができます。
また、相続財産の評価において、任意組合型(現物出資)の不動産小口化商品は現物不動産と同等の扱いとなるため、相続税評価額が低く抑えることができる可能性がある場合があります。低リスク・ミドルリターンな資産運用という側面に加え、相続や贈与のお取り組みにも活用いただける点も不動産小口化商品の特徴です。
不動産小口化商品の利回りは、2%~7%程度と物件によって異なります。価格変動リスクがありますので、利回りだけに囚われず、物件の立地や築年数、周辺の賃料相場など、様々な視点から購入する不動産の見極めが重要です。
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、都心の中規模オフィスビルを中心に取り扱っております。不動産投資におけるリスクを可能な限り抑えたローリスクミドルリターンな商品となっており、個人単位ではなかなか購入しづらい都心の中規模オフィスビルなど、賃貸収入や将来的な値上がりが見込まれる優良な不動産物件を1口100万円単位・5口以上(最低口数は変更となる場合があります)から小口化商品としてご購入いただくことが可能です。
4-6. 投資信託

投資信託とは、資金だけを用意して資産運用自体は運用の専門家(ファンドマネージャー)に任せるという資産運用の方法です。主に国内外の株式や債券で運用しますが、投資信託によって投資対象や運用方針が異なります。国内の公社債で運用するものはリスクが大きくありません。
ただし、投資信託の場合、利益を得るだけなく費用や手数料なども発生いたします。投資信託の購入手数料、運用時にかかる信託報酬、監査報酬、売買委託手数料など、直接負担する費用と信託財産から差し引かれる手数料に分けられますが、0.1~3%程度で設定されている場合が多いです。運用期間中にどのようなコストが発生するかを事前に確認しておきましょう。投資信託は銀行や証券会社で購入できます。
4-7. REIT

REITとは上場不動産投資信託のことです。不動産投資法人が投資家から集めた資金で収益不動産を購入し、賃料や売買益を分配するという商品です。日本ではJ-REITと呼ばれています。
J-REITの利回りは3~8%程度が一般的ですが、価格変動があります。証券会社で購入できます。また、J-REITの売買を行う際は、証券会社ごとに定められた売買手数料の支払いが必要になります。
運用方法別 - 比較まとめ
| 運用方法 | 特徴 | 想定利回り | 始め方 |
|---|---|---|---|
| 定期預金 |
|
0.01%~0.2% | 銀行口座に預入 |
| 個人向け国債/地方債 |
|
最低0.05% | 銀行や証券会社で購入 |
| 社債 |
|
0.02%~5% ※ 商品によって幅あり |
証券会社で購入 |
| 保険 |
|
商品による | 保険会社で加入申し込み |
| 不動産小口化商品 |
|
2%~7% ※ 物件によって異なる |
販売事業者から購入 |
| 投資信託 |
|
投資対象や運用方針により異なる | 銀行や証券会社で購入 |
| REIT |
|
3~8% | 証券会社で購入 |
5. 1,000万円を資産運用するときの注意点

預貯金や退職金などの資金1,000万円を使って資産運用を始めるなら、できるだけ手元資金を減らさないようにしたいですよね。リスクを抑えながら資産運用を始めるためには、気をつけておきたい注意点があります。
5-1. 預貯金と投資に分ける
1,000万円の手元資金で資産運用を始める場合、まずは1,000万円のうちいくらを運用に回せるのかを検討しましょう。現在は定期的な収入があるという方の場合も、今後何が起こるかは分かりませんので、万が一のために1年程度の生活資金はそのまま預貯金として残しておくことをおすすめします。また、今後10年以内に使う予定があるお金についても、預貯金や個人向け国債など、元本保証のある運用方法で安全に保有しておくとよいでしょう。
つまり、1,000万円から1年程度の生活資金と使途のある資金を除いた残りが、資産運用に回せる資金ということになります。
5-2. ハイリターンは狙わない

資産運用となるとどうしてもリターンに注目してしまいがちですが、大きなリターンが期待できる運用商品は、その分大きな損失を被るリスクもあります。
手元資金を減らさずにリスクを抑えて資産運用を始めるなら、ハイリターン商品は敢えて避け、10年後の目標を達成するための着実なリターンを求める方がよいでしょう。
5-3. 長期分散投資を行う

長期分散投資とは、投資する商品を複数に分け、長い期間をかけて運用することで収益率を安定させ、リスクを軽減する投資の方法のことです。
資金を小口化して複数の商品へ投資する分散投資は、短期的に大きな利益が見込めるわけではありませんが、長い運用期間をかけることで、損失の可能性が小さくなる傾向があり、かつ取引の回数が少ないことから売買手数料や税金などの運用コスト負担が少ないというメリットがあるため、手元資金1,000万円をできるだけ減らさず安全に増やしたいという方に向いています。
6. 最後に
リスクを抑えながら1,000万円の資金を10年で増やす方法についてご紹介しました。仮に1,000万円の手元資金があるとした場合、どんな運用方法でどう増やすかは、ライフプランをしっかりと立てることで、今後の人生でどれくらいお金が必要なのかがわかり、資産運用における10年後の目標が設定しやすくなります。手元資金はできるだけ減らさずに運用をしたいという方は、今回ご紹介した運用方法を参考になさってください。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。

監修者
村井 英一むらい えいいち
ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士、証券アナリスト、宅地建物取引士)
1965年生まれ。大手証券会社で法人営業、個人営業、投資相談業務を担当する。2004年にファイナンシャル・プランナーとして独立後は、相談者の立場にたった顧客本位のコンサルタントを行う。特に、資産運用、住宅ローン、年金問題、ライフプランニングなどを得意分野とする。
家計の診断・相談室(https://kakeinoshindan.com/)
資産運用の記事一覧に戻る