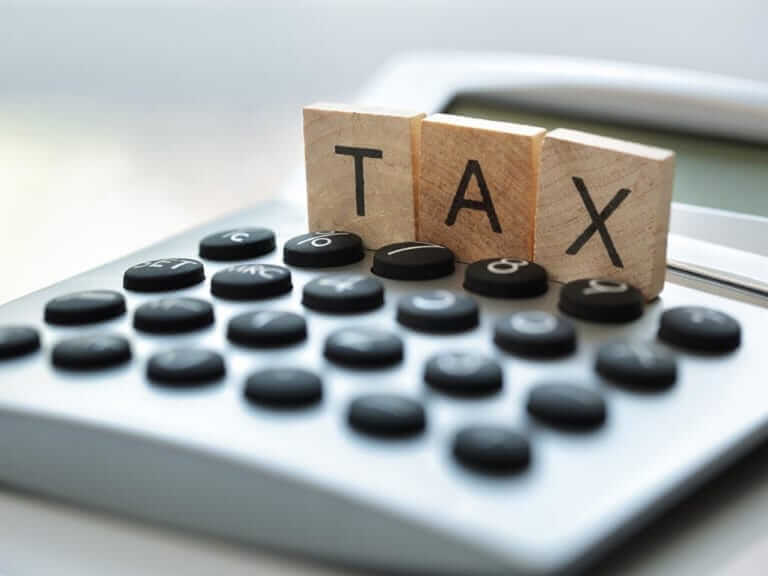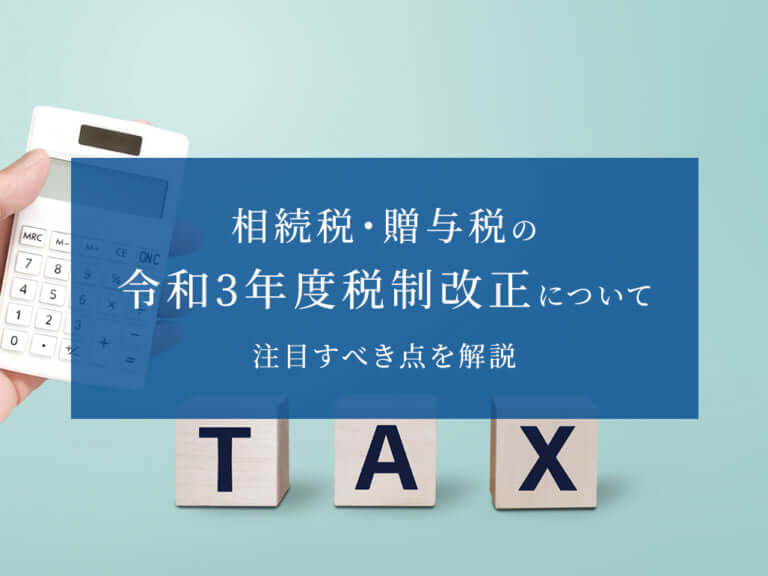目次
本記事に掲載された情報は、2021/08/03時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
贈与税には申告期限があり、うっかり期限を過ぎてしまった場合には罰則が科せられることもあるため注意が必要です。
この記事では、贈与税の申告期限や罰則、知っておきたい注意点について分かりやすく解説します。
1. 贈与税の申告期限はいつ?

贈与税の課税方法には「暦年贈与(暦年課税)」と「相続時精算課税」の2種類があります。まずは、それぞれの贈与税の申告期限について解説します。
1-1. 暦年贈与の場合
暦年贈与(暦年課税)の場合、贈与税の申告期限は、原則、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年分贈与税の申告期限は、令和3年4月15日までに延長されました。)
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税を課すというものです。1年間に受け取った財産が110万円を超えた場合、超えた分については贈与税の課税対象となるため、翌年3月15日までに管轄の税務署に贈与税申告書を提出しましょう。
1-2. 相続時精算課税制度の場合
相続時精算課税制度の場合も、贈与税の申告期限は暦年贈与と同じです。
ただし、相続時精算課税制度を選択する場合は、かかる贈与税の金額にかかわらず、必ず贈与税申告が必要です。
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産を生前贈与する際に選択することができる贈与税の課税方法で、生前贈与する財産が2,500万円以下であれば贈与税は非課税となりますが、相続時には相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。
2. 贈与税の申告期限を過ぎてしまった!罰則はある?
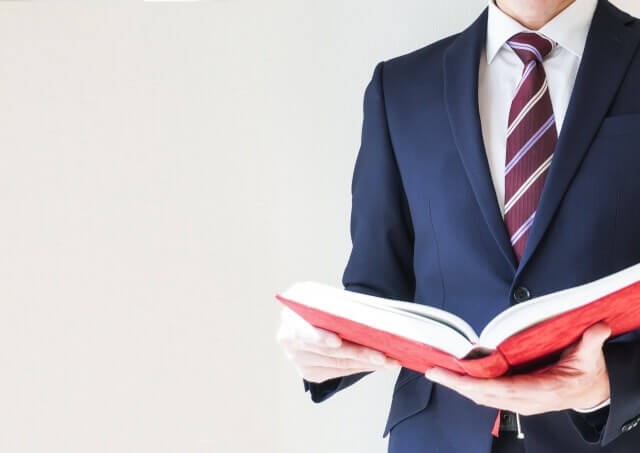
暦年贈与(暦年課税)や相続時精算課税による生前贈与で財産を受け取ったけれど、贈与税申告の手続きをうっかり忘れていた…という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合には、以下の罰則・ペナルティが課せられるため注意が必要です。
2-1. 無申告加算税や延滞税がかかる
生前贈与で財産を受け取った後、贈与税の申告期限までに贈与税申告手続きをしなかった場合は、通常かかる贈与税のほかに、罰則として「無申告加算税」や「延滞税」を支払わなければいけません。
無申告加算税や延滞税は、贈与税の申告期限を過ぎてしまった後、どのタイミングで申告するかによってペナルティが異なります。
無申告加算税の場合、申告期限を過ぎてしまった後、自主的に期限後申告をした場合は5%ですが、税務調査の事前通知がされた後に申告した場合は、本来の贈与税額のうち50万円までは最大15%、50万円を超える場合は最大20%の無申告加算税が課せられます。
延滞税は、申告期限から2カ月以内に申告した場合は原則として年7.3%、2カ月を過ぎた場合は原則として年14.6%となっています。
2-2. 重加算税がかかる場合もある
贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合に課せられる重加算税とは、申告義務があることを認識していたにもかかわらず、隠蔽または仮装によって意図的に申告しなかった場合や過少に申告した場合に課せられるペナルティのことです。
贈与税を意図的に申告しなかった場合は、前述した無申告加算税に加えて最大40%の重加算税が課せられる場合があります。
2-3. 刑事罰が科されるリスクも
贈与税の申告期限を過ぎた後、いつまでも申告しない状態が続いた場合、悪質な不正行為だと認められれば、刑事罰が科されるリスクもあります。
刑事罰が科された場合のペナルティは、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。
3. 贈与税申告が必要ないケースもある?

贈与税申告は、個人から財産を受け取った人が行う手続きですが、なかには贈与税申告が必要ないケースも存在します。
そこで続いては、贈与税申告が不要なケースについてご説明します。
3-1. 生活費や養育費には贈与税がかからない
個人から財産を受け取ったといっても、通常の日常生活に必要な生活費や学費を親子間や夫婦間で受け渡したというケースでは、贈与税はかかりません。そのため、贈与税申告も不要です。
ただし、生活費として受け取ったお金を使わずに貯金したり、株式や不動産への投資資金として使ったりした場合には、贈与税がかかるため、贈与税申告も必要となります。
3-2. 年間110万円以下なら贈与税申告は不要
暦年贈与の場合、1年間に受け取った財産が基礎控除の110万円以下であれば、贈与税がかからないため贈与税申告は不要です。
つまり、年間110万円以下の暦年贈与は、贈与税がかからず相続財産を減らせるため、相続へのお取り組みとして広く活用されています。
3-3. 贈与税申告が不要な非課税制度もある
贈与税にはいくつかの非課税制度がありますが、なかでも以下の非課税制度を利用する場合、財産を受け取った人ではなく一時的に財産を預ける金融機関や信託銀行から税務署に届出が行われるため、贈与税申告の手続きは不要となります。
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 特定障害者に対する贈与税の非課税
4. 贈与税申告で注意しておきたい点

ここからは、生前贈与や贈与税申告を行うにあたって知っておきたい注意点について解説していきます。
4-1. 贈与税申告手続きでの注意点
贈与税の申告手続きは、どんな非課税制度を利用するかによって必要書類が異なるため、慣れていない方の場合は負担に感じるかもしれません。また、贈与税申告をした場合も内容に誤りがあった場合は、「修正申告」や「更正の請求」という手続きが必要となり、場合によっては無申告加算税や延滞税がかかってしまうこともあります。
税務署では贈与税申告の無料相談も受け付けているため、贈与税申告に必要な書類の用意や作成に不安がある場合は、管轄の税務署に相談するか、または税理士などの専門家に依頼することも可能です。
4-2. 相続時精算課税についての注意点
生前贈与で相続時精算課税を利用する場合、2,500万円以下の贈与であっても、必ず贈与申告が必要です。
また、相続時精算課税は過去に遡って申告することができません。そのため、うっかり贈与税申告を忘れてしまうと、すでに行われた生前贈与に対しては特別控除が適用されず、贈与税を支払わなければならなくなるため、注意が必要です。
4-3. 住宅取得等資金贈与についての注意点
生前贈与で住宅取得等資金の贈与を受けた場合も、相続時精算課税と同じく、贈与税申告期限後に遡って特例を適用することはできません。
うっかり贈与税申告を忘れてしまうと、贈与税だけでなく無申告加算税や延滞税がかかるリスクもあるため、必ず期限内に申告手続きを行いましょう。
4-4. 贈与契約書は作成すべき?
贈与税申告の必要書類に、贈与契約書は含まれていません。
しかし、生前贈与で財産を受け取る場合、贈与者が亡くなった後の相続において税務調査が入ったときに、きちんと生前贈与の事実を証明するためにも、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書が無いと税務調査で贈与契約が成立しているとみなされない可能性があり、その場合は生前贈与で受け取った財産に対しても相続税が課せられてしまうため注意が必要です。
5. 最後に
今回は贈与税の申告期限や罰則、贈与申告における注意点について解説してきました。
うっかり贈与税の申告期限を過ぎてしまったという場合、罰則・ペナルティが課されるだけでなく、贈与税の非課税制度が利用できなくなってしまうこともあります。
そのため、生前贈与を行う際は、贈与税の申告が必要かどうか、申告期限はいつなのかを事前に確認し、期限内に忘れずに申告手続きを行うことが大切です。
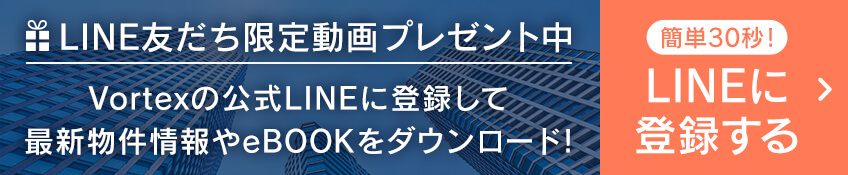
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。

監修者
萱谷 有香かやたに ゆか
叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー
大学卒業後は、英会話教材を飛び込み営業により訪問販売しておりましたが、一生働ける仕事をしたいと思い税理士を目指しました。
不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら、沢山の収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自分でも不動産投資を始めました。
現在では5棟の物件を保有しつつ、不動産投資家さんの気持ちがわかる税理士になるよう日々勉強し、色々な情報を集めています。
不動産投資専門の叶税理士法人(https://tax.kanae-office.com/)
贈与税の記事一覧に戻る