目次
本記事に掲載された情報は、2025/05/02時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
相続や贈与について調べるなかで「相続時精算課税制度」という制度があることを知って、興味をお持ちになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、相続時精算課税制度とは何か、相続時精算課税制度を利用するメリットやデメリット、手続き方法などをまとめて解説していきます。
1. 相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、贈与財産2,500万円までを限度として贈与税を非課税とし、贈与税を支払うことなく生前贈与ができるという贈与税の制度のことです。贈与する財産の種類、贈与回数に制限はなく、何度でも贈与を行うことが可能です。
相続時精算課税制度の1番のメリットは、「贈与財産2,500万円までが非課税になる」という点にありますが、一方で生前贈与された財産は、相続発生時には相続財産として加算されることになり、相続税の課税対象となってしまいます。つまり相続時に精算される贈与税の課税制度になるわけです。
であれば、やる意味があるのだろうか?と疑問に思うかもしれませんが、実は、生前贈与された財産は相続時ではなく贈与時の評価額で加算されるため、例えば不動産を生前贈与する場合など、相続時において贈与時よりも財産の価値が上がっていれば、その分財産の評価額を低く抑えることができる可能性があるのです。
ただし、相続時精算課税制度を選択できるのは、原則として贈与年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対して財産を贈与する場合のみという要件があります。
生前贈与における贈与税の課税方法にはもうひとつ、「暦年課税(暦年贈与)」という制度があります。暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額が、贈与税の基礎控除額110万円以下であれば贈与税は課税されないという制度です。暦年課税(暦年贈与)には、贈与者と受贈者の年齢や関係性に関する要件はなく、贈与を受ける全ての個人に対して適用されますので、子や孫が若いうちは暦年課税、18歳を迎えたら、相続時精算課税の選択も視野に入れつつ、贈与方法を検討していくべきことになります。
悩ましいのは、同一の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度と暦年課税制度は2つの制度を使い分けることはできないところになります。一度、相続時精算課税制度を選択してしまったら暦年贈与に戻ることができないため、慎重に検討していくことが必要になってしまうのです。
また、令和6年以降の贈与から相続時精算課税制度についても、年110万円までの基礎控除が創設されました。相続時精算課税制度を選択した場合でも、基礎控除内の贈与であれば、先にご説明したような相続時に加算する必要が無くなりました。その他、暦年課税のように相続開始前7年以内の贈与についても相続財産に加算されることはありません。
これら改正により贈与に対する課税への対応の幅が広がった、言い換えれば複雑になったとも言えますので、各ご家庭においては、贈与予定額や、贈与財産の種類、贈与者、受贈者の年齢なども考慮して、さらに慎重に検討して進めていく必要があることになります。
2. 相続時精算課税制度と暦年課税を比較
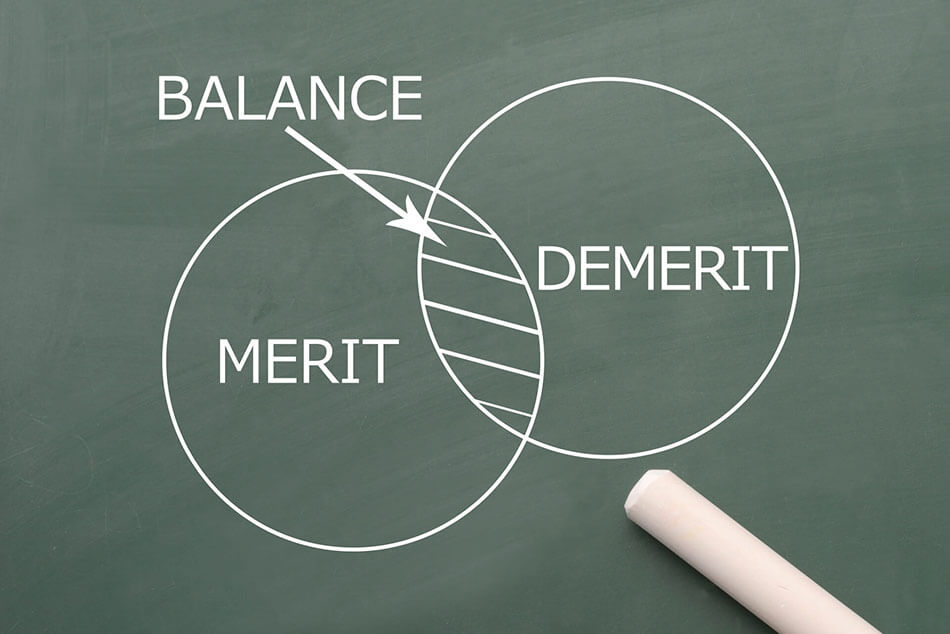
贈与税の軽減制度を利用する場合には、相続時精算課税制度と暦年課税(暦年贈与)のどちらかを選択しなければいけません。そう言われてもどちらを選べばいいか分からない…という方のために、相続時精算課税制度と暦年課税(暦年贈与)をわかりやすく比較してみましたので参考になさってください。
| 相続時精算課税制度 | 暦年課税(暦年贈与) | |
|---|---|---|
| 適用要件 | 60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対して財産を贈与する場合のみ(年齢は贈与年の1月1日で判断) | 特になし 親子間、親族間以外にも、第三者からの贈与にも適用できる |
| 非課税限度額 | 贈与者1人につき2,500万円(令和6年以後は年110万円の控除後)まで | 受贈者1人につき、1年間で110万円まで |
| 贈与税の計算 | (譲り受けた財産の合計金額-特別控除2,500万円)×一律20% | (1年間で譲り受けた財産の合計金額-基礎控除110万円)×税率(10%~55%)
|
| 申告手続き | 令和6年以後は年110万円以内は申告不要 | 贈与税が0円(非課税枠内)の場合は申告不要 |
| 相続時の加算 | 譲り受けた財産を贈与時の評価額で相続財産に加算する
|
相続時の加算はなし
|
| メリット | 年110万円以内の贈与であれば直前贈与であっても相続税の財産に加算されない。 価値の上昇が見込める住宅や土地などの財産を贈与することで、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある |
贈与した財産は相続税の課税対象とならないため、生前に贈与することで相続財産が減り、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある |
| デメリット | 住宅や土地などの財産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外の税金がかかる | 非課税枠が小さい |
3. 相続時精算課税制度はどんなケースで活用できる?
相続時精算課税制度のメリットは、価値の上昇が見込める住宅や土地などの財産を生前に贈与することで、相続時においても贈与時の評価額で相続財産として加算されるため、相続税評価額を低く抑えられる可能性があるということです。つまり、値上がりが見込める不動産などの高額な財産を生前贈与する場合には、相続時精算課税制度が効果的に活用できる可能性があります。
また、先に記載したように令和6年以降から相続時精算課税制度についても、年110万円の基礎控除が創設されており、基礎控除内であれば直前贈与であっても暦年課税のような相続開始前の贈与について相続財産に加算されることはありませんので、110万円以内の贈与のみを検討されるのであれば、積極的な活用も見込まれているところです。
4. 相続時精算課税制度の手続き方法や必要書類

4-1. 作成する書類と手続きをする人
相続時精算課税制度の手続きの方法は、それほど難しくはありません。手続きをするのは、財産を譲り受けた人(子や孫)となります。
まず、作成が必要な書類は下記となります。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
相続時精算課税制度を選択したときは、2,500万円の非課税枠内の贈与で贈与税が0円という場合でも、必ず「贈与税の申告手続き」が必要になります。
なお令和6年以降の贈与で年110万円の基礎控除以内であれば申告は不要となります。
「相続時精算課税選択届出書」は、国税庁のホームページから取得できます。
- 相続時精算課税選択届出書(令和元年分用)
出典:贈与税の申告|国税庁 … 申告書等の様式一覧より
相続時精算課税選択届出書の書き方
- 「受贈者」の欄に財産を譲り受けた人(子や孫)の住所や氏名などの情報を記載し、特定贈与者との続柄には、長男、長女、孫などの続柄を記載します。
- 「1. 特定贈与者に関する事項」の欄に、財産を譲った人(父母又は祖父母)の情報を記載します。
- 「2. 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合」は、養子縁組などによって年の途中から相続時精算課税制度を選択することができるようになった人が記載する欄です。該当しない場合、記載する必要はありません。
4-2. 提出が必要な添付書類
相続時精算課税選択届出書の添付書類として、次の書類も提出が必要です。
受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本(以下の情報がわかるもの)
- 受贈者の氏名、生年月日
- 受贈者が特定贈与者の推定相続人又は孫であること
出典:No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|国税庁
4-3. 申告・届け出の期限
書類が用意できたら、相続時精算課税選択届出書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告期間)までに、贈与税の申告書(第一表及び第二表)に添付して税務署に提出します。税務署に直接持ち込む以外にも、電子申告(e-Tax)や郵送でも申告手続きは可能です。
贈与税の申告書(第一表及び第二表)の入手方法や贈与税の申告手続きについて、詳細は下記ページをご参照ください。
4-4. 手続に関する注意点
複数回にわたって贈与を行う場合
相続時精算課税制度を利用した贈与を複数年に渡って行う場合、初回の贈与税申告で上記添付書類のすべてを提出すれば、2回目以降の申告では添付書類の提出は不要です。
ただし、贈与税申告書については、贈与する財産や金額が毎回異なりますので、年110万円(基礎控除)超の場合にはその都度、提出が必要となります。
贈与税の申告をする前に受贈者が亡くなってしまった場合
相続時精算課税制度を利用した贈与が行われた後、贈与税の申告をする前に受贈者が亡くなってしまったというケースでは、受贈者の相続人が手続きを行うことで、相続時精算課税の適用を受けることができます。
相続人は、受贈者が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書、必要な添付書類を用意して、受贈者が亡くなったときに住んでいた地域を管轄する税務署に提出しましょう。
出典:No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与税の申告期限前に受贈者が死亡した場合)|国税庁
5. 相続時精算課税制度でよくある疑問
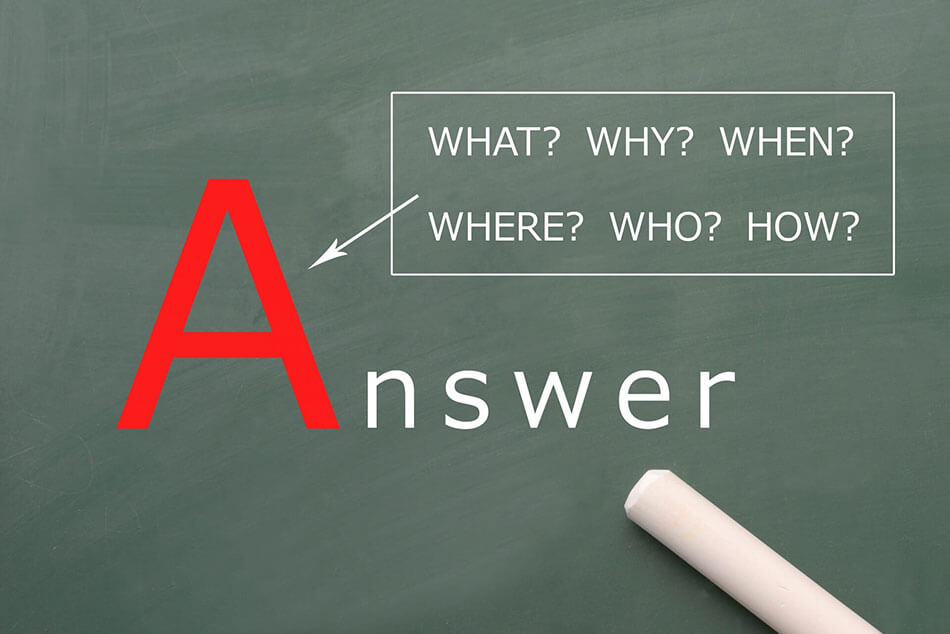
相続時精算課税制度とは何か、手続きの方法などについてご説明してきました。
最後に、相続時精算課税制度を利用する方が疑問に感じるポイントについて、回答していきます。手続きがスムーズに進められるよう、参考にしてみてください。
Q:相続時精算課税制度を利用して生前贈与をしたけど贈与税の申告を忘れてしまった!期限後でも申告はできる?
A:相続時精算課税制度では、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書などの添付書類をあわせて、納税地を管轄する税務署に提出しなければいけません。提出が1日でも遅れてしまった場合には、相続時精算課税制度の特別控除を受けることはできませんので、申告忘れがないようくれぐれも注意しましょう。
Q:相続時精算課税制度を利用した後、相続のタイミングで被相続人に多額の債務があることがわかった!相続放棄はできるの?
A:相続時精算課税制度を利用していたとしても、相続放棄は可能です。相続放棄をすると、被相続人からの相続に対する相続人としての権利を失いますが、生前に譲り受けた財産はすでに相続人が所有する財産となっているため、被相続人に多額の債務があったとしても、相続人が返済義務を負う必要はありません。
ただし、相続時精算課税制度を利用して譲り受けた財産については、遺贈により取得したものとみなされるため、相続放棄の手続きを行ったとしても相続税の納税義務がなくなることはありません。
6. 最後に
今回は、生前贈与を検討するなかで気になる相続時精算課税制度について、そのメリットやデメリット、手続き方法などを解説してきました。
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、長期的な収益の安定性が見込める都心の商業地にある中規模ビルを小口化し、個人でも資産運用しやすくした商品です。500万円(1口100万円・5口以上)から購入が可能で、贈与する際も現物不動産より分けやすいというメリットがあるため、生前贈与にも適した商品として、多くのお客様にご活用いただいております。
- ※本コラムに記載された内容は、各種の事例や文献を基に一般論として述べたものです。弊社から当該物件の購入についての税務に関する何らの示唆 および確定的な見解を示すものではなく、本コラムに記載された算出方法や評価額など一切について正確性および確実性を保証するものではありません。 具体的な申告書の作成などにあたりましては、税理士などの専門家や所管の税務署などにご相談いただきますようお願いいたします。
- ※分譲マンションの相続税評価額については、「居住用の区分所有財産の評価について(国税庁)」に定められた評価方法が適用されます。
- ※一定期間の保有が条件となります。
- ※評価額は物件により異なります。
生前贈与のメリットや「Vシェア」について、より詳細に知りたいという方は、下記ページをご参照ください。
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 相続税の圧縮効果を含めた税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
生前贈与の記事一覧に戻る















