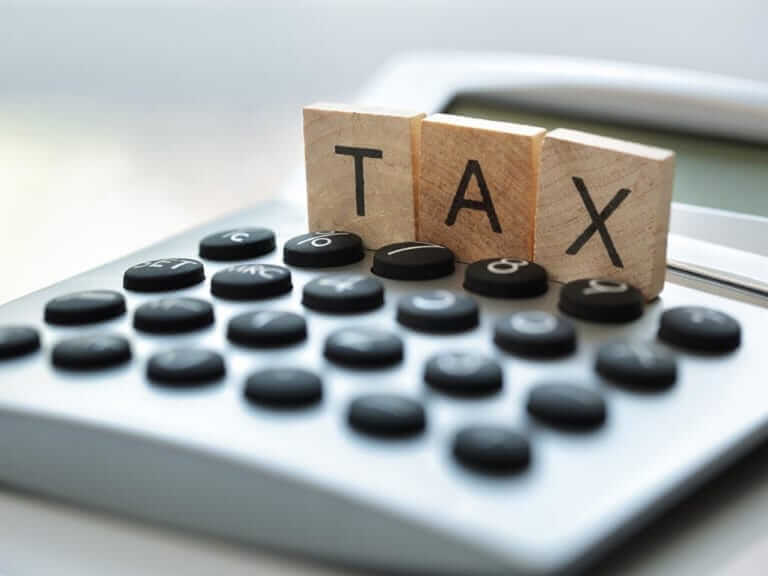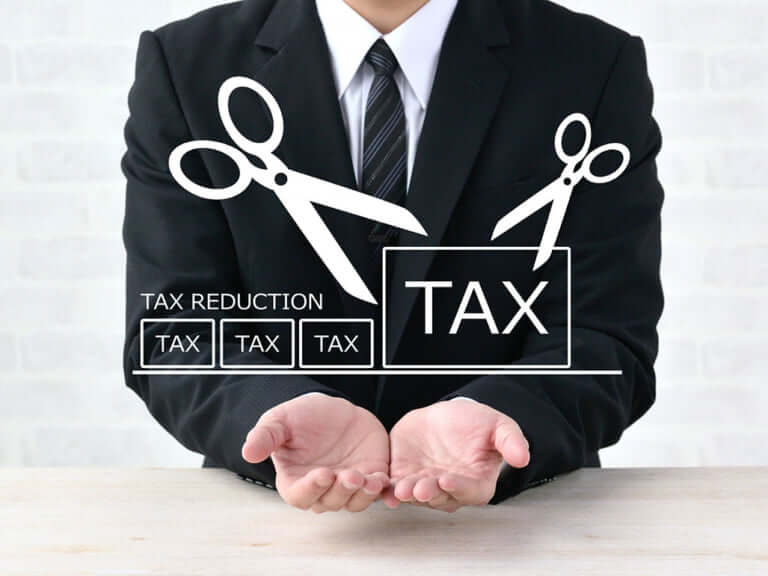目次
本記事に掲載された情報は、2024/07/19時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
自分が保有する財産を子や孫などへ譲りたいと考えたときに、注意しなければならないのは「贈与税」です。贈与税は、財産を譲る側ではなく受け取る側に支払い義務が発生します。そのため、できるだけ大切な子や孫へ財産を贈与してあげたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
子や孫への贈与において、贈与税がかからない方法には以下のようなものがあります。
贈与税がかからない方法
| 方法 | いくらまで |
|---|---|
| 1. そもそも贈与税がかからない贈与範囲 | - |
| 2. 年間110万円までの贈与(暦年贈与) | 年間110万円以下 |
| 3. 相続時精算課税制度を利用 | 2,500万円まで |
| 4. 「配偶者控除の特例」を利用する | 2,000万円まで |
| 5. 「住宅取得資金等の非課税特例」を利用する | 最大1,000万円まで |
| 6. 「結婚、子育て資金の非課税特例」を利用する | 1,000万円まで |
| 7. 「教育資金の非課税特例」を利用する | 1,500万円まで |
| 8. 障害者への贈与 | 最大6,000万円まで |
それぞれの方法に関して、注意しなければならない点や必要な手続きについて、以下でご説明していきます。
この記事では、贈与税がかからない方法やその注意点についてご紹介いたします。
1. 贈与税の基本知識
贈与税とは、個人(生きている人)から財産をもらったときにかかる税金のことです。
贈与税の支払い義務は、財産を受け取った人(受贈者)に発生します。
そのため、自分が保有する財産を子や孫などへ譲りたいと考える方の中には、相続税と贈与税の違いについて気になる方も多いのではないでしょうか。
1-1. 相続税と贈与税の違い
相続税と贈与税の基本的な違いと税率の違いについては、以下の比較表をご確認ください。
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 税金が発生するとき | 被相続人(亡くなった人)から遺産を相続したとき | 個人(生きている人)から財産をもらったとき |
| 税金を払う人 | 財産をもらった人(相続人) | 財産をもらった人(受贈者) |
| 税金がかからない範囲 | 遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)以下の相続 | 1年間に110万円以下の贈与
|
| 相続税 | 贈与税 | ||
|---|---|---|---|
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 基礎控除110万円を引いた贈与額 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% | 200万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% | 400万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% | 600万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% | 1,000万円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% | 1,500万円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% | 3,000万円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% | 4,500万円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% | 4,500万円超 | 55% |
- 贈与税率は、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子や孫などへ贈与の場合の税率となります。
贈与税と相続税では税率が異なるため、一見すると相続よりも生前贈与のほうが、子や孫にかかる負担が大きくなるようにも見えます。
しかし、生前贈与は少額ずつ分割することで基礎控除内に収めることができるため、早めの相続へのお取り組みを行うことで、子や孫にかかる負担を抑えることができる可能性があります。
1-2. 現金手渡しの贈与はバレない?

子や孫に直接現金を渡せばバレないのでは?とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続開始後に税務調査が入った場合には、被相続人の過去の銀行口座の取引を調査されることになります。そこで使途の不明な金銭の移動があり、その使途が贈与であったことを明確に証明できない場合には、実際のところは非課税範囲内の暦年贈与であったとしても、その金銭相当額が被相続人の財産に帰属するものとして相続税の課税対象として見なされてしまう可能性があります。
そのためにも適正な贈与を行い、適正な税務申告をしておくことが必要です。
2. 贈与税がかからない方法
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、大切な子や孫へ財産を贈与するためにも、まずは、どんなときに贈与税がかからないのかを把握しておきましょう。
2-1. そもそも贈与税がかからない贈与範囲
祖父母や父母から子供や孫へ日常的に渡される「生活費」や「養育費」、また「結婚費用」「出産費用」「生活費の仕送り」など生活に必要と考えられる使途のための贈与は扶養義務の範囲と考えられるため、社会通念上相当であると認められる範囲内の金額であれば、そもそも贈与税がかかりません。
なお、子供名義の銀行口座を作ってそこに預金をしているという場合でも、通帳の管理を祖父母や父母が行うのであれば、子供に対して贈与税はかかりません。 しかしその場合には、そもそもその預金が誰のものになるのかという問題が生じるので注意が必要です。また、高額な金銭の貸し借りを行った場合には、贈与税がかかる可能性がありますので注意しましょう。
2-2. 年間110万円までの贈与(暦年贈与)【年間110万円以下】
子や孫へ財産を贈与する場合、1年間で110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与税の規定には、すべての個人に対して1年間で110万円の基礎控除があるため、この110万円以下の贈与額であれば課税対象にならないのです。
さらに、贈与額が110万円以下の場合は税務署への申告も不要です。
ただし、令和6年から大きな改正が加わり波紋を呼んでいます。改正前においても、相続人に対する贈与のうち相続発生3年内に行われた贈与は、相続財産に加算され相続税の対象とされていましたが、令和6年以降の贈与から3年が7年に延長されました。
したがって、仮に10年前から少しずつ贈与を実行していっても、当初3年分の贈与しか被相続人の財産を減らす効果しかないことになります。
生前贈与を実施するにはより早い時期から実施していくことが必要となります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-3. 「相続時精算課税制度」を利用する【2,500万円まで】
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合に選択することができる贈与税の課税方法です。
贈与財産を非課税とする特別控除額が2500万円もあり比較的大きな財産を贈与できる制度にはなるのですが、この制度を使って贈与された財産については、相続発生時に相続財産に加算されることになるので、多額の現金を贈与しても、被相続人の相続財産を圧縮する効果などはありませんでした。
しかし、税制改正により、令和6年以後に相続時精算課税を使って贈与された財産については、まず受け取った財産の額から110万円/年を控除することができ、その超える部分の金額について2,500万円の特別控除額を差し引く仕組みに変わりました。
将来の相続時に加算することになるのは、2500万円の特別控除額を利用した部分になるので、つまり、年110万円の贈与であれば相続時の加算が不要となることになります。
この110万円には、暦年贈与のような7年内加算の対象にもならないため、年110万円以下の贈与のみを予定している方にとっては、相続時精算課税制度を利用することが得策になる可能性もあるのです。
ただし、非課税だからと何もしなくてよいわけではなく、相続時精算課税制度を選択するいといった届出を提出する必要があり、また、一度選択したら暦年贈与に戻ることはできないため、被相続人、相続人の年齢や財産の内容なども考慮しつつ、今後どういった資産管理をしていくかをしっかり考えていくことが必要になります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 適用条件 ※ 概要のみ抜粋 |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-4. 「配偶者控除の特例」を利用する【2,000万円まで】

夫婦間で居住するための不動産(もしくは居住用住宅の購入資金)を贈与する場合には、2,000万円までが非課税となる特例を利用することで、贈与税がかかりません。
配偶者控除の特例は、同じ配偶者同士間の贈与で1回限り利用することができる制度で、婚姻期間が20年以上あることが制度を利用するための条件となっています。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 適用条件 ※ 概要のみ抜粋 |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-5. 「住宅取得資金等の非課税特例」を利用する【最大1,000万円まで】

祖父母や父母から子や孫に対して住宅を取得するための資金を贈与する場合、住宅取得資金等の非課税特例を利用することで、省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となり、贈与税がかかりません。
ただし、住宅取得資金等の非課税特例には期限があり、さらに住宅取得をする取得する年や消費税率、住宅の種類によって非課税限度額が異なりますので、しっかりと理解したうえで進めることをおすすめします。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 適用条件 ※ 概要のみ抜粋 |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-6. 「結婚、子育て資金の非課税特例」を利用する【1,000万円まで】

親から子に結婚資金や出産・子育てのための資金を一括贈与する場合、子ひとりに対して1,000万円までの贈与が非課税となる特例です。(そのうち、結婚資金の非課税限度額は300万円)
なお、子や孫に対して結婚・子育てにかかる費用の援助をする場合、そもそも生活費援助として社会通念上適当と認められる範囲であれば、贈与税の課税対象にはなりません。この特例を利用せず、その都度、援助を行う方法を取られる方も多く、制度を利用する際にはよく検討されることをおすすめします。
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用する際の注意点については、下記記事もご覧ください。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 適用条件 ※ 概要のみ抜粋 |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-7. 「教育資金の非課税特例」を利用する【1,500万円まで】
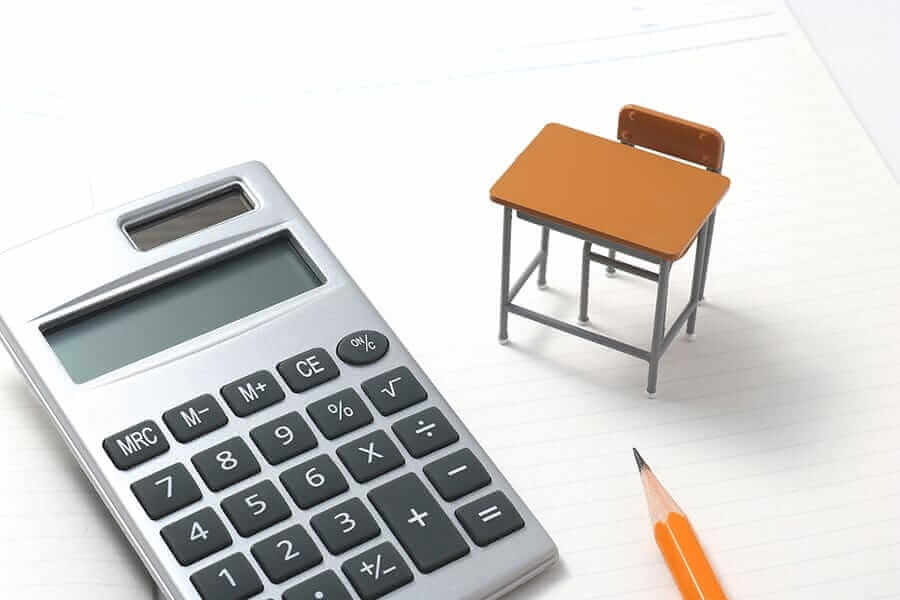
祖父母や父母から子や孫に対して教育資金を一括贈与する場合、教育資金の非課税特例を利用することで、受贈者1人につき1,500万円までが非課税となります。
教育資金の一括贈与の特例には、将来必要とするであろう教育資金を1,500万円まで非課税で贈与することができるというメリットがある一方、金融機関で専用口座を開設し、都度領収書を提出するなど、手続きに手間がかかるなどというデメリットもあります。特例を利用する際は、メリット・デメリットをよく理解したうえで進めましょう。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 適用条件 ※ 概要のみ抜粋 |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
2-8. 障害者への贈与【最大6,000万円まで】
障害者に対して生活費や治療費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて資金を贈与する場合には、贈与税がかかりません。
特別障害者である特定障害者へは最大6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者へは、3,000万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 注意点 |
|
| 必要な手続き |
|
控除枠、非課税枠に関する制度については、国税庁のWebサイトに掲載されています。ご自身のケースで活用できるものがないか、一度確認してみることを推奨します。
3. 受贈者同士のトラブルにも注意
ここまで、贈与税の非課税控除や特例を利用する方法についてご説明してきましたが、大切なのは贈与できる金額を増やすことだけではありません。複数名へ贈与を行う場合は、受贈者同士でトラブルが発生しないための準備もとても大切です。特に不動産などの現物資産を贈与する場合などは、受贈者間でのトラブルにつながるリスクも高まります。
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、個人では購入が難しい都心のプライムエリアにある中規模オフィスビルに、500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資できる商品です。
都心プライムエリアの土地×オフィスビルは、市場価格と路線価の差から、不動産評価額が引き下げられる可能性があります。
※商品によって異なる場合があります。
現物不動産と違って1口単位に分割できるため、複数人に対する相続や生前贈与がしやすくなります。
複数名への贈与をご検討の方は、ぜひ弊社の不動産小口化商品「Vシェア」をご活用ください。
※本コラムに記載された内容は、各種の事例や文献を基に一般論として述べたものです。弊社から当該物件の購入についての税務に関する何らの示唆
および確定的な見解を示すものではなく、本コラムに記載された算出方法や評価額など一切について正確性および確実性を保証するものではありません。
具体的な申告書の作成などにあたりましては、税理士などの専門家や所管の税務署などにご相談いただきますようお願いいたします。
※ 分譲マンションの相続税評価額については、「居住用の区分所有財産の評価について(国税庁)」に定められた評価方法が適用されます。
※ 一定期間の保有が条件となります。
※ 評価額は物件により異なります。
Vシェアを活用した贈与へのお取り組みについて、より詳細な事例をご覧になられたい方はお気軽に弊社までお問い合わせいただければと思います。
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 相続税の圧縮効果を含めた税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
贈与税の記事一覧に戻る