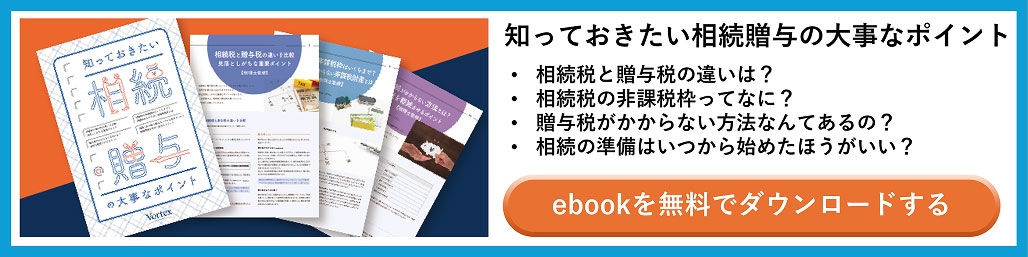目次
生前贈与を検討する際、「贈与税はいくらかかるのか」「非課税で贈与できる制度はあるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。
贈与税の税率は、課税方式や贈与者と受贈者の関係によって異なるため、税率や計算方法を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、贈与税の税率や計算方法に加え、贈与時に活用できる非課税制度を解説します。さらに、生前贈与を行う際の注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
贈与税の3つの税率

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税を課す方式のことです。
さらに、暦年課税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」に2種類分けられます。
それぞれの税率を詳しく見ていきましょう。
1. 暦年課税の一般税率
一般税率とは、特例贈与に該当しない贈与に適用される税率です。たとえば、兄弟や第三者、夫婦、18歳未満の子供や孫への贈与では、以下の一般税率が適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
2. 暦年課税の特例税率
特例税率とは、贈与を受ける年の1月1日において18歳以上の人が直系尊属(父母)や祖父母から贈与を受ける際に適用される税率です。 特例税率は、以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
3. 相続時精算課税の税率
相続時精算課税とは、贈与者1人あたり合計2,500万円まで非課税で贈与できる制度のことです。
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子供または孫に贈与する際に選択できます。贈与者が亡くなったときは、贈与時の評価額で相続財産に加算されます。
相続時精算課税を選択して贈与された財産のうち、2024年1月1日以降に贈与された財産は、特定贈与者ごとに毎年110万円の基礎控除が適用されるため、基礎控除内の贈与であれば贈与税がかかりません。基礎控除を差し引いた贈与合計額が2,500万円を超えると、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度については「相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや手続きの方法【税理士監修】」でより詳しく解説しています。
【シミュレーションあり】贈与税の計算方法
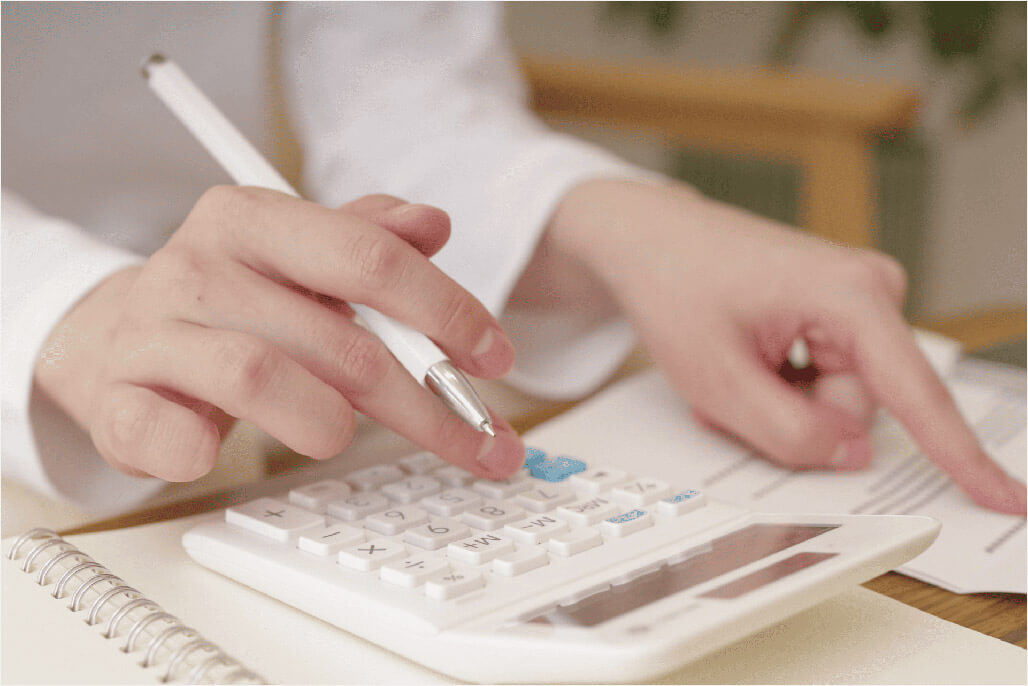
贈与税の基本的な計算方法は、以下のとおりです。
1.贈与額から基礎控除110万円を差し引き、課税価格を算出する。
[ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]
2.税率一覧表に基づき、贈与税を計算する。

ここでは、暦年贈与と相続時精算課税における贈与税の計算例を紹介します。
暦年贈与の場合
暦年贈与では、1年間の贈与額が110万円を超えたときに贈与税がかかります。
暦年贈与は「誰が誰に贈与するのか」によって適用する税率が異なるため、注意しましょう。たとえば、父から15歳の子供に700万円を贈与するときには、一般税率を用いて以下のように贈与税額を計算します。
| 700万円-110万円=590万円 590万円×30%-65万円=112万円 |
一方、父から21歳の子供に700万円を贈与するときには、特例税率が適用されます。
このときの贈与税額は、以下のとおりです。
| 700万円-110万円=590万円 590万円×20%-30万円=88万円 |
相続時精算課税を適用した贈与の場合
相続時精算課税制度を選択したときは、年110万円の基礎控除が受けられます。110万円を超える贈与であっても、贈与者1人あたり2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
ただし、以下のように贈与者1人から数年にわたって贈与を受け、基礎控除後の贈与額が2,500万円を超えると、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|---|
| 贈与額 | 1,000万円 | 1,500万円 | 500万円 |
| 基礎控除後の金額 | 890万円 | 1,390万円 | 390万円 |
| 基礎控除後の贈与合計額 | 2,670万円 | ||
このケースでかかる贈与税額は、以下のとおりです。
| 2,670万円-2,500万円=170万円 170万円×20%=34万円 |
贈与に活用できる非課税制度

生前贈与をする際に活用できる非課税制度には、以下のようなものがあります。
- 配偶者控除の特例
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金一括贈与の特例
- 住宅取得等資金の非課税の特例
- 特定障害者に対する贈与税の非課税
それぞれ詳しく解説します。
配偶者控除の特例
配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または住宅購入資金を贈与する場合に、年110万円の基礎控除に加えて最大2,000万円の控除を受けられる制度です。
適用要件として、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与された居住用不動産または贈与を受けた住宅購入資金で購入した居住用不動産に受贈者が住み、その後も引き続き住む見込みがあることが定められています。
この特例の適用を受けるためには、配偶者控除を適用して贈与税が非課税となったとしても、贈与税の申告手続きが必要になるため注意しましょう。
配偶者控除については「贈与税の配偶者控除とは?メリット・デメリットや手続きの流れ【税理士監修】で詳しく解説しています。
教育資金の一括贈与の特例
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子供または孫が2026年3月31日までに教育資金の一括贈与を受けたときに、最大1,500万円(学校や塾や習い事など、学校に直接支払うもの以外の資金については最大500万円)まで非課税となる特例のことです。
この特例の適用を受けるためには、受贈者が教育資金口座を開設し、金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
なお、契約終了日までに贈与者が死亡すると、教育資金口座の残額が相続財産に加算されます。契約終了時点に残っている資金は、贈与税の課税対象となるため注意しましょう。
教育資金の贈与については「教育資金は一括贈与で非課税になる?教育資金の非課税特例について【税理士監修】」で詳しく解説しています。
結婚・子育て資金一括贈与の特例
結婚・子育て資金一括贈与の特例とは、2027年3月31日までに18歳以上50歳未満の子供または孫に対して結婚や出産、子育てのための贈与をしたときに1,000万円(結婚資金としては最大300万円まで)まで非課税になる特例です。
この特例の適用を受けるためには、受贈者が金融機関で結婚・子育て資金口座を開設し、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
贈与者が契約期間中に亡くなると、口座残額が相続財産に加算されます。また、契約期間終了時点で口座に残っている資金には贈与税がかかるため注意しましょう。
住宅取得等資金の非課税の特例
住宅取得等資金の非課税の特例とは、2026年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築や取得、増改築のための資金の贈与を受けた子供または孫が、一定要件を満たすことで、非課税で贈与を受けられる特例です。
非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円です。この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅に住み始めるか、住むことが見込まれる状態でなければなりません。ほかにも、建物の床面積や建築条件などの適用条件があります。
住宅取得資金贈与については「住宅取得資金贈与は最大1,000万円非課税|特例の概要や申請方法を徹底解説」で詳しく解説しています。
特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者に対する贈与税の非課税とは、特定障害者の生活費を一定の信託契約に基づいた贈与が一定額まで非課税となる制度です。特別障害者に該当する特定障害者は6,000万円、特別障害者に該当しない精神障害者は3,000万円まで贈与税がかかりません。
生前贈与をする際の注意点

生前贈与をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 定期贈与と判断されると贈与税がかかる
- 名義預金とみなされると相続税の課税対象になる
- 遺留分侵害に注意する
- 不動産の生前贈与では贈与税以外の税金がかかることがある
それぞれ詳しく解説します。
定期贈与と判断されると贈与税がかかる
基礎控除額110万円以下の贈与であっても定期贈与とみなされると、贈与税を課せられる可能性があります。定期贈与とは、あらかじめ決めた贈与額を分割して一定期間贈与することです。
たとえば「500万円を毎年100万円ずつに分けて贈与する」といった取り決めをした贈与は、定期贈与とみなされる可能性があります。定期贈与とみなされないためには、贈与時期と贈与額を変えたり、贈与のたびに贈与契約書を作成したり、申告することが必要です。
名義預金とみなされると相続税の課税対象になる
名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金のことです。たとえば、親が子供の通帳を管理していると名義預金とみなされ、親が亡くなったときに相続財産として加算されます。
名義預金と判断されないためにも、受贈者が通帳の管理をしたり、贈与のたびに贈与契約書を作成したりするようにしましょう。
遺留分侵害に注意する
祖父母から孫への生前贈与では、遺留分に配慮することが大切です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている一定の相続割合のことです。
祖父が保有している財産のほとんどを孫に生前贈与した場合、祖父が亡くなったあとに配偶者や子供が遺留分の権利を主張し、侵害された部分の財産を請求する可能性があります。一部の相続人に多額の生前贈与をするときは、相続後に予期せぬトラブルが起きないように配慮しましょう。
遺留分侵害については「生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象になる?【税理士監修】」で詳しく解説しています。
不動産の生前贈与では贈与税以外の税金がかかることがある
保有する土地や建物などの不動産を贈与する際は、贈与税以外の税金にも注意しましょう。不動産を贈与するときは「不動産取得税」「登録免許税」「固定資産税」、収益物件の場合はさらに「所得税」「住民税」などの税金がかかります。想定外の納税に慌てることがないように、どれほどの税金がかかるのかを把握して納税資金を用意しておきましょう。
※税金のほか「司法書士手数料」が必要になる場合があります。
不動産の生前贈与については「不動産の生前贈与をする際のポイントとは?【税理士監修】」で詳しく解説しています。
よくある質問

贈与税の税率に関するよくある質問に回答します。
贈与税と相続税の税率の違いは?
贈与税の税率は、相続税の税率よりも高く設定されています。
それぞれの税率は、以下のとおりです。
| 贈与税(特例税率) | 相続税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除後の贈与額 | 税率 | 控除額 | 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - | 1,000万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
出典:No.4155 相続税の税率|国税庁
たとえば、父から18歳以上の子供に課税価格5,000万円の財産を譲る場合、贈与税は以下のとおりです(5,000万円は基礎控除を考慮しないものとする、特別税率を適用する)。
| 5,000万円×55%-640万円= 2,110万円 |
5,000万円の相続する場合の相続税は、以下のとおりです(5,000万円は基礎控除を考慮しないものとする)。
| 5,000万円×20%-200万円= 800万円 |
しかし、必ずしも生前贈与のほうが納税額が多くなるということではありません。生前贈与では、資産を分割して贈与することで贈与税の基礎控除内に収めることができます。
相続税の税率が低いことに注目するのではなく、早いタイミングから少しずつ贈与を検討することが大切です。
相続税と贈与税の違いについては「相続税と贈与税の違いを比較 - 見落としがちな重要ポイント【税理士監修】」で詳しく解説しています。
教育費や仕送りにも贈与税がかかる?
父母や祖父母から子や孫に対する贈与のうち、扶養義務の範囲と考えられる生活費や養育費、結婚や出産にかかる費用として認められれば贈与税はかかりません。
ただし、教育費や仕送りとして受け取った資金を預金したり、投資資金として使ったりすると、贈与税の課税対象となる場合があるため注意しましょう。
贈与税の非課税については「贈与税がかからないケースや計算方法、注意点までを網羅解説!【税理士監修】」で詳しく解説しています。
贈与税の申告期限は?
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。申告期限までに申告しなければ、延滞税や加算税などのペナルティが科せられることがあるため、期限内に申告と納税を済ませましょう。
贈与税の申告については「贈与税の申告期限はいつ?罰則はある?注意事項を分かりやすく解説【税理士監修】」で詳しく解説しています。
争続にしないために-早めの準備がカギ-
贈与税の税率は、課税方式や贈与者と受贈者の関係によって異なります。年間110万円以上の贈与をすると贈与税がかかる可能性があるため、適用税率を確認したうえで贈与税を計算しましょう。年間110万円を超える贈与であっても、非課税特例の適用を受けられれば一定額まで非課税での贈与が可能です。
そして贈与を行う場合は贈与契約書を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。円満に資産を相続するためにも、早めに準備することをおすすめします。
贈与契約書の書き方についてまとめた記事がありますので、ぜひご活用ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
竹中 啓倫たけなか ひろみち
竹中啓倫税理士事務所 代表
税理士・米国税理士
岐阜県出身。現在4名のスタッフとともに竹中啓倫税理士事務所を運営。
かつて上場会社の経営企画部・経理部に長年在籍しており、大会社への対応も可能。
スタッフには社会保険労務士の有資格者がおり、司法書士行政書士事務所の勤務経験者も在籍しているため、所得税法人税だけでなく相続税贈与税を含む幅広い業務に対応。
竹中啓倫税理士事務所(工事中)
生前贈与の記事一覧に戻る