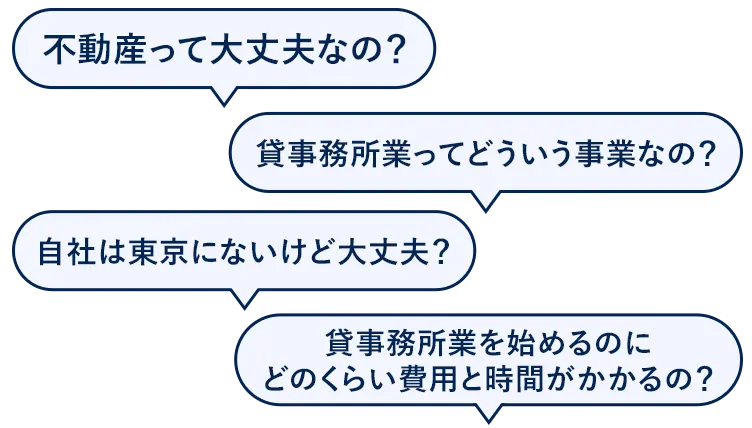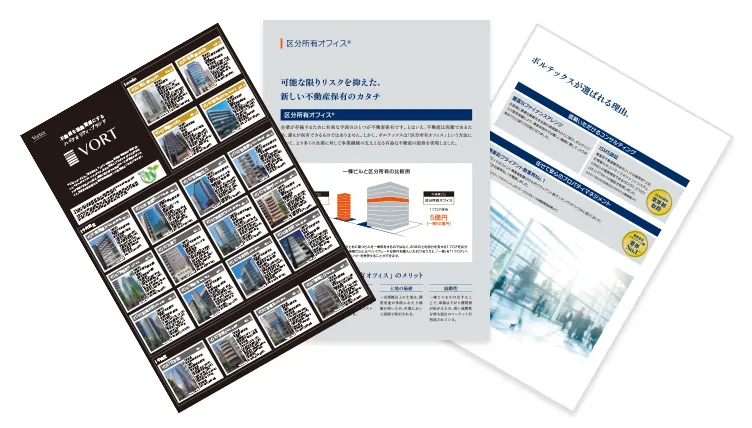事業承継とは?事業譲渡との違いや流れを分かりやすく解説

目次
※本記事に掲載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
事業承継とは、会社の資産である人(経営権)や株式などの資産、ノウハウを次の世代に引き継ぐことをいいます。
中小企業庁が公表した「事業承継ガイドライン」によれば、事業承継には5~10年の期間が必要とされています。円滑に事業承継を進めるためには、事業承継の概要や直面する課題、事業承継の種類といった基礎を押さえておくことが大切です。
本記事では、事業承継の基礎知識や流れ、事業譲渡との違いを分かりやすく解説します。
事業承継とは
事業承継とは、企業の経営を後継者に引き継ぐことです。
企業が持つ技術や人財を次の世代に引き継ぎ、安定的に経営を続けていく仕組みを整えることを意味します。これらの資産は、今後の経営に欠かせないものであるため、会社にとって大切な手続です。
事業承継を行う際は、「誰に」「どのように」引き継ぐかを考え、より早い段階から計画を立てましょう。
事業承継についてさらに詳しく知りたい人は、こちらも参考にしてください。
事業承継と事業継承の違い
「承継」と混同されやすい言葉のひとつに「継承」があります。
「継承」とは、王位継承のように地位や財産を継ぐことを指す言葉です。
一方、「承継」で引き継ぐものは地位や財産だけに限りません。企業理念や方針、社風、ブランドなどの要素も引き継ぎます。そのため、ビジネスを引き継ぐ場合は一般的に「事業承継」といいます。また、税制などの法律や制度上においても「事業承継」と表記されています。
事業承継と事業譲渡、ほかの承継方法との違い
事業や会社を引き継ぐことを意味する用語として、事業承継以外にも次のような言葉があげられます。
- 事業譲渡
- 会社分割
- 株式譲渡
それぞれの意味を見ていきましょう。
事業譲渡とは
事業譲渡は、会社が行っている事業のうち全部または一部を譲り渡すことをいい、「事業売却」とも呼ばれています。事業譲渡で引き渡す資産は比較的自由に選択できます。例えば、事業単位ごとに譲渡することも可能なため、会社の経営権を維持し続けられるメリットがあります。
事業譲渡で譲渡できるもののうち、代表的なものに以下の5つがあげられます。
- 事業
- ブランド
- 人材
- 設備
- 施設
会社分割とは
会社分割とは、事業の一部を子会社または兄弟会社として切り出し、一方の会社をほかの会社に承継させることを指します。
会社の不採算事業を切り出すことによって事業のスリム化が図れ、会社のよい部分のみを残せるため、得意分野と苦手分野を明確にした事業の選択と集中が可能です。なお、事業譲渡は取引先や契約先の同意が必要ですが、会社分割はすべての契約を引き継げるため個別の手続は不要です。
会社分割について詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。
こちらも読まれています
>会社分割による事業承継の方法|メリット・デメリットと流れをわかりやすく解説
株式譲渡とは
株式譲渡とは、譲渡企業の経営者が保有している株式を譲受企業に譲渡し、子会社化する方法です。法人自体を譲渡するため、保有する資産や負債、知的財産、許認可などはそのまま引き継ぐことができます。
株式と金銭のやり取りのみで事業のすべてを引き受けることができるため、M&Aで広く活用されています。
事業承継で引き継ぐ3つの要素

事業承継で引き継ぐ3つの要素に、「人(経営権)」「資産」「知的資産」があります。これらの要素を「誰に」「どのように」引き継ぐのかが、事業承継の重要なテーマです。
1.人(経営権)
会社の経営権を、現経営者から後継者に承継します。中小企業の経営は、経営者の資質や能力などに依存しているケースが多く、経営者の交代は業績や企業に大きな影響を及ぼします。後継者の選定方法を慎重に検討するだけでなく、育成も含めた綿密な計画が必要です。
2.資産
株式や借入金、設備、不動産といった会社の資産をどのように引き継ぐかを、経営者と後継者が一緒になって計画します。資産の承継には税や法律の問題が絡むため、事業承継に詳しい専門家を交えて進めるのが一般的です。
3.知的資産
知的資産とは、経営理念やノウハウ、技術、信用、人脈などの目に見えない資産のことです。知的資産は会社の大切な資産のひとつであるため、適切な方法で引き継がなければなりません。知的資産の棚卸しは、経営者が会社の強みや事業が成功した秘訣などを考えることから始めます。
事業承継の種類
事業承継は、引き継ぎ先によって次の3つに大きく分けられます。
- 親族内承継(経営者の親族)
- 親族外承継(主に従業員、役員)
- M&A(社外)
親族内承継
親族内承継とは、子供や孫などの親族へ事業を引き継ぐ方法を指します。中小企業には家族経営の企業が多く、親族内承継は一般的な承継方法のひとつといえます。オーナー家系の思想や企業理念を継続しやすい点が大きな特長です。
また、早期から後継者の育成を行えるため、長期的な視点で事業承継の準備ができます。一方、後継者個人の能力や意欲に左右されやすいという懸念点があります。
親族外承継
親族外承継とは、従業員や役員のなかから後継者を選ぶ方法です。親族内承継と比べて、能力に基づいた選考が可能であり、社内の理解も得やすいでしょう。
事業内容を熟知した人材が経営を引き継ぐことで、事業の継続性も確保されます。ただし、株式の取得や経営権の移転に関する資金面で課題が生じる可能性があります。
M&A
M&Aとは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略で、会社を売却したり、企業同士が合併したりする形の承継方法です。親族や従業員に適任者がいない場合でも、外部企業や投資家とのマッチングによって事業を存続させられます。
例えば、同業他社との合併によって規模を拡大し、コスト削減や新事業の展開を可能にするのが、その一例です。売却する場合は経営権や株式を移転し、新たなオーナーが主導して事業を継続します。
売却益を得やすい一方で、社名や雇用、企業文化が大きく変化する可能性があります。引き継ぎ後の経営方針や従業員の処遇について、十分な話し合いを行うことが不可欠です。
事業承継の課題
ここでは、事業承継を進めるなかで直面する3つの課題を解説します。
- 経営者の高齢化
- 後継者不足と廃業
- 税金の負担
経営者の高齢化
帝国データバンクの調査によると、経営者の平均年齢は2024年時点で60.7歳と34年連続で過去最高を更新したとされています。また、社長が交代する際の平均年齢は68.6歳となり、前年の68.7歳からほぼ横ばいの状態が続いています。
経営者の年代別構成比では、50代が30.0%を最も大きな割合占めますが、「50歳以上」に広げると81.7%とこちらも前年の81.0%を上回り、経営者の高齢化が問題視されています。
出典:全国「社長年齢」分析調査(2024年)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250325-presidentage2024/
後継者候補が見つからないまま経営者の高齢化が進行し、結果として廃業に至るケースもあります。事業承継の準備や引き継ぎを先送りにしたまま、経営者が年齢を重ねている会社も少なくありません。
後継者不足と廃業
経営状況は良好であっても、後継者が見つからないことを理由に廃業を余儀なくされる企業もあります。
親族内に後継者候補がいない場合や、子供がいる場合でも「苦労をさせたくない」「経営者としての資質に不安がある」「子供自身に引き継ぐ意思がない」といった理由から廃業を選択する経営者もいます。
こちらも読まれています
>後継者不足の現状と解決策|中小企業の事業承継について
税金の負担
事業承継では、後継者に対して相続税や贈与税の納税義務が発生します。中小企業であっても自社株の評価額が高い場合は、納付する税額が大きくなる可能性があります。
後継者の資金が不足すると借り入れなどで工面する場合もあり、結果として経営に悪影響が出る可能性も否めません。
こちらも読まれています
>事業承継にまつわる問題と解決策|承継トラブルのリスク回避方法
事業承継と事業譲渡のそれぞれのメリット
ここでは、事業承継と事業譲渡の違いを把握するために、それぞれのメリットを比較していきましょう。
事業承継のメリット
事業承継のメリットは以下のとおりです。
- 従業員の雇用を守りやすい
- 取引先の理解を得やすい
- 手続が複雑ではない
- 事業承継税制を使える
事業承継においては、基本的に従業員の雇用契約は継続されます。
また、社名や社風が変わらないため、取引先や顧客に受け入れてもらいやすいほか、手続も煩雑になりにくいです。後継者の資金不足を解消するための事業承継税制も使えます。
事業譲渡のメリット
事業譲渡には以下のメリットがあります。
- 特定の事業のみを売却できるため譲渡先を見つけやすい
- 会社を存続できる
- 売却益を得られる
事業譲渡は、特定の事業のみを売却するため、継続したい事業については経営権を失いません。さらに、負債を抱えている事業と切り離すことで、譲渡先を見つけやすくなる点もメリットです。
事業売却によって得た利益は、借入金の返済や新規事業の資金に充てられるため、経営改善にもつなげられます。
事業承継と事業譲渡のそれぞれのデメリット
続いて、事業承継と事業譲渡のそれぞれのデメリットを見ていきます。
事業承継のデメリット
事業承継のデメリットは、主に以下の2つです。
- 条件に合う承継先を見つけにくい
- 負債も引き継がなければならない
社内に後継者候補がいない場合や、M&Aを活用した承継先を探さなければなりません。しかし、条件が合わないなどの理由により、承継先を見つけにくいことがデメリットです。条件次第では長期化するおそれがあります。
また、事業承継では会社全体を承継するため、負債も引き継ぐ必要があります。
事業譲渡のデメリット
一方、事業譲渡のデメリットには次のデメリットがあります。
- 手続には時間と手間がかかる
- 売却益には法人税がかかる
- 競業避止義務により同じ事業ができない
譲渡する事業に関わる従業員や取引先、債権者などから個別に同意を得なければならず、手続に時間と手間がかかります。
また、売却益から仲介手数料などの費用を差し引いた利益に法人税が課税されます。
さらに、事業譲渡のあと、譲渡企業は類似事業を行わないよう競合避止義務が課されることが一般的です。競合避止義務の期間は原則20年間とされており、交渉により期間の延長・短縮は可能です。
事業承継の流れ
ここからは、事業承継の流れを次の2つに分けて解説します。
- 親族内承継・親族外承継
- M&A
親族内承継・親族外承継
親族内や親族外(従業員など)で後継者が決まっている場合は、次のような流れで進めます。
- 事業承継の準備の必要性を認識
- 経営状況・課題の把握
- 経営改善
- 事業承継計画の策定
- 事業承継の実行
1.事業承継の準備の必要性を認識
経営者と後継者で事業承継について話し合いを始めます。事業承継の支援機関や税理士、弁護士などの専門家への相談もあわせて進めます。
2.経営状況・課題の把握
企業の経営状況や課題を把握することで、後継者に「何を残すべきなのか」が明確になります。まずは、自社の経営状況を可視化し、事業承継に向けて課題を洗い出しましょう。市場環境や将来的な企業の目標を考慮し、自社の強み・弱みを客観的に分析します。
3.経営改善
後継者が「引き継ぎたい」と思える魅力的な企業にするために、経営改善を行います。また、事業承継後も成長し続ける企業にするため、企業の価値を高めていくための取り組みも欠かせません。
4.事業承継計画の策定
事業承継計画とは、中長期的な経営方針や事業承継の方向性など、具体的な進め方を定めた計画書のことです。経営者と後継者が会社の10年後を見据え、逆算して事業承継計画を立てます。
5.事業承継の実行
事業承継計画をもとに、事業承継を実行します。事業承継の準備をスタートしてから実行するまでには時間を要するため、余裕を持って着手する必要があります。また、円滑な事業承継のためには、随時、公的機関や専門家に相談をしながら実行するのが望ましいです。
こちらも読まれています
>親族内承継とは?メリット・デメリットと円滑に引き継ぐポイントを解説
M&A
M&Aの場合も基本的な流れは親族内承継・親族外承継と同様ですが、各フェーズでM&Aならではの注意点があります。
- M&Aの検討
- 仲介者の選定
- 企業価値評価をする
- 譲受側の選定
- 交渉
- 基本合意の締結
- デューデリジェンス
- 最終契約の締結
- M&Aの実行
1.M&Aの検討
M&Aは売り手と買い手の交渉や専門的なプロセスをともなうため、当事者同士で進めるのは困難な場合が多いでしょう。そのため、必要に応じて支援機関や仲介会社に相談し、M&Aの実施を検討します。
2.仲介者の選定
M&Aは多くプロセスでは高度な専門知識が求められます。そのため、企業の選定から契約成立までの間、M&A専門の業者や法務・財務の専門家と協力することが有効です。
専門業者や仲介業者には、それぞれ提供するサポートの範囲や料金体系が異なります。自社がどのような支援を必要としているかを明確にしたうえで、サービス内容と費用のバランスを考慮した適切な業者を選ぶことが重要です。
選定した業者と契約する際には、「アドバイザリー契約」を結ぶことになります。この契約書には、成功報酬、守秘義務、個人情報の管理、責任免除などについての条項が記載されています。
3.企業価値評価をする
企業価値評価は、仲介者や専門家が譲渡側企業の価値を算定し、適正な譲渡価格や交渉の基盤を形成するプロセスです。その際、財務資料、現地調査、経営者との面談、業界分析などを材料として活用します。
主に使用される評価手法には、収益還元法、DCF法、純資産価値法、類似企業比較法などがあり、これらを組み合わせ、多角的に企業の価値を評価します。
4.譲受側の選定
M&Aプロセスにおいて、譲受側(買収側)の選定は重要な工程です。これは、譲渡側企業が自社の価値を高め、事業の継続性や成長を確保するために、最適な相手を見つける「マッチング」のステップとなります。
譲受側の選定では、単に譲渡価格や条件だけでなく、譲受側の経営戦略、財務力、業界内での立ち位置、企業文化の適合性など、多角的な視点で相手を評価します。
5.交渉
譲受側を選定したあとは、譲渡側・譲受側の経営者同士の面談を行います。ここでは譲受側の経営理念・企業文化や経営者の人間性を直接確認します。その後の円滑な交渉のためにも重要です。
6.基本合意の締結
M&Aプロセスにおいて、譲渡側と譲受側が主要な条件について合意し、基本合意書(LOI: Letter of Intent)を締結する段階です。基本合意書は法的拘束力の有無が状況によって異なり、一般的には意向を示す文書として扱われる場合が多いですが、一部の条項(例えば秘密保持や独占交渉権)は法的拘束力を持つことがあります。
7.デューデリジェンス
デューデリジェンス(Due Diligence)は、主に譲受側が譲渡側企業の実態を詳細に調査するプロセスです。譲渡後のリスクを最小限に抑えるため、財務・法務・ビジネス・税務などの各分野について、専門家の協力を得て徹底的に分析を行います。
デューデリジェンスは、M&Aの成功を左右する重要なステップであり、専門家の知見を活用して慎重に進めることが求められます。
8.最終契約の締結
デューデリジェンスで発見された点について再交渉を行い、最終的な契約を締結します。
9.M&Aの実行
株式や事業の譲渡、譲渡代金の支払いを行います。
事業譲渡の流れ
事業譲渡は、次の流れで進めていきます。
- 取締役会の承認
- 事業譲渡契約書の締結
- 株主への通知・公告
- 株主総会招集手続
- 株主総会
1.取締役会の承認
事業譲渡契約締結に関して、取締役会で承認を得る必要があります。
取締役会での決議は、取締役の過半数以上の承認が必要です。
2.事業譲渡契約書の締結
売り手企業と買い手企業の条件交渉が進んで合意を得られたら、事業譲渡契約書を締結します。
契約書には以下の内容を記載します。
- 譲渡対象事業部門
- 譲渡資産
- 譲渡価格および支払い方法
- 効力発生日
- 従業員の対応
- 競業避止義務
- その他特約事項
3.株主への通知・公告
事業譲渡する会社は、事業譲渡の実施や株主総会の開催について、効力発生日の20日前までに株主へ通知します。
反対株主は会社に対して買取請求権(保有株式を買い取ることを会社に請求できる権利)があることを周知する必要があります。
4.株主総会招集手続
各株主に対し、原則として株主総会の2週間前までに招集通知を送付する必要があります。
5.株主総会
事業譲渡を行う当事会社は、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議で事業譲渡契約の承認を受ける必要があります。
議決権の過半数以上を持つ株主が出席をし、2/3以上の同意を得られれば事業譲渡が承認されます。
円滑な事業承継のために必要なこと
期間に余裕を持って準備をすることで、経営者と後継者の双方が満足のいく事業承継を実現できます。
事業承継に向けた早期の計画
後継者の選定や育成、経営状況の改善、買い手企業とのマッチングなどには時間がかかります。「まだ早い」と思わず、早期に事業承継の準備と計画を進めることが重要です。
自社株評価の計算
2/3以上の同意を得られれば事業譲渡自社株を相続する際には相続税がかかります。評価が高い場合は税金が大きな負担となり、それが課題となって事業承継が実現できなくなる可能性もあります。自社株評価について理解を深め、金額を把握しておきましょう。
こちらも読まれています
>円滑な事業承継のために知っておきたい株価算定|自社株評価の算出方法
事業承継税制の活用
事業承継税制とは、事業の引き継ぎ時にかかる多額の贈与税や相続税の納税を猶予・免除することで、事業承継を後押しするための制度です。
制度の適用には一定の条件があり、すべての企業にとって事業承継税制の活用が最善の手段とは限りません。手続も複雑なため、専門家のアドバイスをもとに進める必要があります。
こちらも読まれています
>事業承継税制に必要な特例承継計画とは|書き方と提出方法を解説
こちらも読まれています
>事業承継で起こりうるトラブル5選|失敗しないための対策と注意点
事業承継は専門機関にご相談を
事業承継には準備から引き継ぎまでに相当の期間が必要です。不確定要素も多く、早期から専門家を交えて計画的に進めることが求められます。
まずは、事業承継のプロフェッショナルとともに、ご自身の悩みを棚卸しするところから始めてみてはいかがでしょうか。
後継者が継ぎやすい経営状態をつくる
後継者不在でお悩みの場合、不動産賃貸業を導入することが有効な選択肢になる可能性があります。
不動産賃貸業を活用し、強固な経営基盤を築くことで、後継者が見つかる可能性が高まることも考えられます。また、大切な本業を承継後も安定して継続できる環境を整えることが可能です。
強固な経営基盤を構築するには、優良な不動産を取得することが重要です。そして、ボルテックスでは、優良な不動産の条件として以下の特性をあげています。
- 都心の商業地に位置していること
- 駅からのアクセスが良好であること
- 優れた設備や、清潔感があること
これらの条件を満たすオフィスビルは、テナント市場で非常に高い需要があります。その結果、長期間の空室が発生しにくい傾向にあり、収益性が安定している場合が多いとされています。このような物件は投資家からも高く評価されています。ただし、こうしたオフィスビルを取得するには多額のコストが必要であり、取得できる層が限られている点は課題といえます。
ボルテックスではより多くの方にご取得いただけるよう、一棟では高額なオフィスビルを1フロア(物件によっては1部屋)ごとに分割して販売する「区分所有オフィス」を展開しています。
「区分所有オフィス」についてより詳しく知りたい方は下記のリンクからご覧ください。
ボルテックスの「区分所有オフィス」とは
※不動産取得は後継者探しの一助となる可能性がありますが、保証するものではありません。
※区分所有オフィスには、管理費や修繕費などのコストが発生するほか、空室リスクや市場価格の変動リスクが伴います。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。