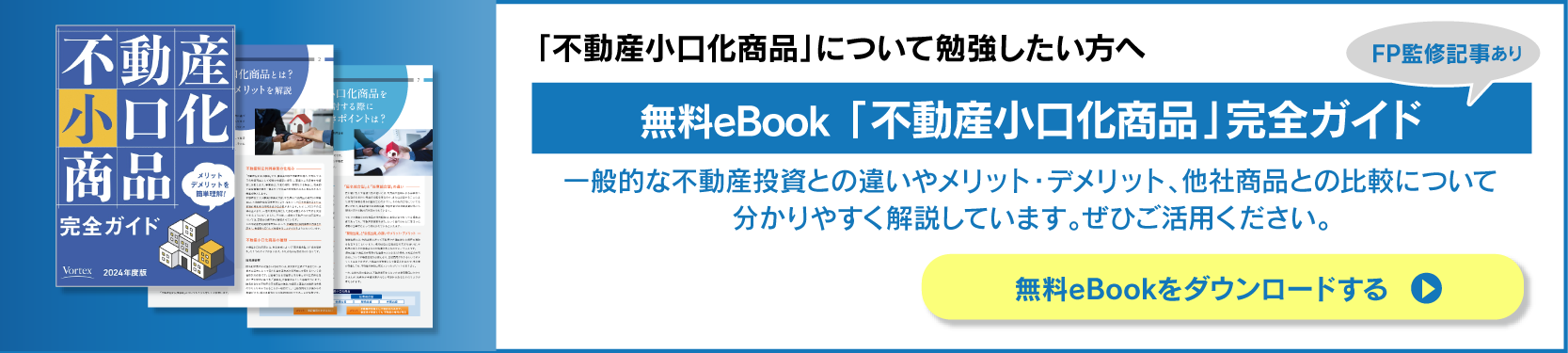目次
定年退職後のお金の不安を軽減するために、退職金運用を検討している方は多いのではないでしょうか。退職金の運用方法には、退職金定期預金や投資信託、不動産小口化商品といったさまざまなものがあります。リスクの高い方法を選ぶと、元本割れを起こしたり、十分な老後資産を準備できなくなる可能性があります。そのような状況を避けるためにも、各金融商品の違いを知ったうえで自分に合った運用方法を選ぶことが大切です。
そこで本記事では、退職金運用におすすめの方法を紹介します。退職金運用のポイントも紹介するので、老後の生活に対する不安を減らしたい方はご参考にしてください。
退職金を運用するメリット

退職金運用には、以下のようなメリットがあります。
- 収入減少を補える
- 退職後の生活が豊かになる
- インフレリスクの備えになる
それぞれの理由を詳しく紹介します。
収入減少を補える
退職後は、年金以外の収入がなくなったり減ったりする人が多くいます。厚生労働省は、残業代や休日出勤手当などを除く1カ月分の平均賃金を以下のように公表しています。
| 年齢 | 男性 | 女性 | 男女計 |
| 55~59歳 | 427,400円 | 281,700円 | 376,400円 |
| 60~64歳 | 334,200円 | 246,600円 | 305,900円 |
| 65~69歳 | 293,300円 | 217,100円 | 269,800円 |
出典:厚生労働省 「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」を基に作成
このデータから分かるように、60歳以降は賃金が下がる傾向にあります。再雇用として働き続けることもできますが、現役と同程度の収入を得るのは難しいでしょう。
退職後は年金を受給できるものの、令和5年度の1カ月あたりの平均年金受給額は、147,360円と公表されています(厚生年金加入者の場合)。
出典:厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
退職前の給与に比べて大きい金額とはいえないため、年金受給額の範囲で生活費を確保できないケースも考えられるでしょう。そのような状況に備えるためにも、退職金運用で資産を増やし、退職後の収入減少を補うことが大切です。
退職後の生活が豊かになる
厚生労働省の令和5年簡易生命表によると、65歳時点の平均余命は、男性19.52年、女性24.38年となっています。
出典:厚生労働省「令和5年簡易生命表」
退職後の20~25年の生活費は、これまでの預貯金と年金、退職金でまかなうことになります。総務省統計局の調査によると、60歳以降の1カ月あたりの平均支出は下表のとおりです。
| 単身世帯 | 二人以上の世帯 | |
| 60~64歳 | 152,743円 | 269,961円 |
| 65~74歳 | 149,033円 | 285,522円 |
| 75歳~ | 234,948円 |
出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)」
厚生労働省のデータでは、公的年金を受給している世帯の41.7%が公的年金のみで暮らしていると公表されています。
出典:厚生労働省「2023年(令和5)年 国民生活基礎調査」
一方で、58.3%の世帯が公的年金のみで生活できていない状況が読み取れます。退職後の生活費が不足するような状況をつくらず、豊かな生活を送るためにも、退職金運用をしておきましょう。
インフレリスクの備えになる
日本の物価は、2022年から上昇し続け、インフレ傾向にあります。どれほどの物価上昇があるのかは、下表のモノやサービスの物価変動を表した消費者物価指数から読み取れます。
| 調査年 | 消費者物価指数 |
| 2020年 | 100.0 |
| 2021年 | 99.8 |
| 2022年 | 102.3 |
| 2023年 | 105.6 |
| 2024年 | 108.7 |
※2020年を100として算出
出典:総務省「2020年基準消費者物価指数」
インフレが継続すると、現状は1万円で買えるものが、将来的に2万円支払わなければ買えないというような状況になる可能性があります。そのため、退職金を運用することなく保有していると、お金の価値が下がってしまうことが懸念されます。
そのような状況を防ぐには、株式や不動産といったインフレに強い資産の運用が推奨されます。老後資金に不安がある方は、退職金の運用を検討してみてはいかがでしょうか。
おすすめの退職金運用方法

おすすめの退職金運用方法には以下のようなものがあります。
- 退職金定期預金
- 保険
- 投資信託
- 株式
- 不動産小口化商品
- REIT
- 個人向け国債
それぞれ詳しく紹介します。
退職金定期預金
退職金のみを対象とした退職金定期預金は、通常の定期預金より高い金利で預け入れができます。金利は金融機関によって異なり、年1%以上の金利が設定されている商品もあります。元本割れするリスクが低い点もうれしいポイントです。
ただし、多くの金融機関が預入期間を3カ月程度に設定しており、満期後は特別金利が適用されなくなるため、長期運用にはあまり向きません。ほかの投資方法を検討する間のつなぎとして、少しでも高い金利で預金したい場合に利用するとよいでしょう。
| メリット | 普通預金や通常の定期預金より金利が高い元本割れのリスクが低い金融機関が破綻しても元本1,000万円と破綻日までの利息が保証される |
| デメリット | 高金利が適用される期間が短く長期運用には向かない一般的な投資商品より高い利回りが期待できない投資信託の契約が条件となっている場合がある |
保険
保険には「掛け捨て型」と「貯蓄型」の2種類があります。掛け捨て型は、解約したり満期を迎えたりしたタイミングでお金を受け取ることはできませんが、貯蓄型は満期になると支払った保険料満額、またはそれ以上の金額を受け取れる場合があります。退職金を運用するときは、満期にお金が受け取れる貯蓄型を選びましょう。
退職金を保険で運用するメリットは、比較的安全に運用できる点や、万が一の場合に死亡保険金を受け取れることです。加えて、支払保険料のうち一定額までは所得から生命保険料控除として差し引けるため、所得税や住民税を抑える効果も期待できます。
| メリット | 比較的安全に運用できる支払う保険料のうち一定額までは所得控除の対象となる万が一の場合の備えとなる |
| デメリット | 一般的な投資商品に比べて高い利回りが期待できない保険商品の種類によってはリスクが高いものがある途中解約すると払戻率が低くなる可能性が高い |
投資信託
投資信託とは、複数の投資家から集めた資金を、投資のプロが代わりに運用する金融商品です。運用益は投資家の投資額に応じて分配されたり、より多くの利益を得るために再投資されたりします。資産運用を専門家に任せられるため、投資知識があまりない方でも気軽に始めやすい特長があります。
加えて、投資信託では国内外の株式や債券といった複数の銘柄を組み合わせて投資できることから、投資先を分散してリスクを軽減できます。特定の株式が値下がりしても、ほかの株式や債券が値上がりしていれば、大きな損失を受けるリスクを抑えられるでしょう。
| メリット | 投資初心者でも気軽に始めやすい分散投資が簡単にできる積立投資として運用しやすい |
| デメリット | 元本割れを起こすリスクがある銘柄が多いため、銘柄選びに時間がかかる場合がある購入手数料や信託報酬など複数の手数料がかかる |
株式
株式投資では、証券取引所に上場している企業の株式を購入してリターンを狙います。株式とは、株式会社が資金調達のために発行する有価証券のことです。
株式投資で狙えるリターンには、株式の売買で得られるキャピタルゲインと、企業の利益を配当金として受け取れるインカムゲインがあります。株式投資にはリターンを得られるだけでなく、応援したい企業の株式を自由に選べる魅力があります。
| メリット | 配当金や株主優待を受けられる場合がある好きな企業の株式を購入できる短期的に高いリターンを得られる可能性がある |
| デメリット | 元本割れを起こすリスクがある銘柄選びや相場分析の知識が必要となるまとまった投資資金が必要になる場合がある |
不動産小口化商品
退職金運用の選択肢として、不動産投資を検討する方もいるでしょう。ただし、不動産投資には多額の資金が必要となり、ローンを組まなければ物件購入ができないケースも多くあります。退職金のすべてを不動産投資に回すのはリスクが高いため、推奨はできません。
一方、不動産小口化商品であれば1口数万円から数百万円程度に小口化された不動産に投資できるため、退職金の一部を使って運用できます。加えて、不動産の管理をプロに任せられることから、資産運用初心者でも始めやすいでしょう。
| メリット | 1口数万円から数百万円程度の少額から不動産投資ができるプロが選んだ物件に投資できる任意組合型では実物不動産を保有できる |
| デメリット | 商品の種類が少ないため、選択肢が狭い実物不動産への投資と異なり、融資を受けられない元本や賃料収入の保証がない |
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」では、個人で購入することが難しい都心の商業地にある中規模オフィスビルに500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資できます。
また「Vシェア」は複数人に分割しやすいことから、相続の準備としてもおすすめです。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
≫不動産小口化商品「Vシェア」とは
≫不動産小口化商品「Vシェア」の物件情報を見る
REIT
REIT(不動産投資信託)とは、不動産投資法人が投資家から募った資金を活用して、マンションや商業施設、オフィスビルといった不動産を複数購入し、賃貸収入や売却益を投資額に応じて分配する金融商品です。
REITは証券取引所に上場しているため、株式と同じように投資家のタイミングで売買できます。現物不動産への投資と比較して、投資資金を少額に抑えられるのもメリットのひとつです。
| メリット | 1銘柄で複数の不動産に分散投資できる現物不動産への投資より少額で始められる流動性が高く、好きなタイミングで売買しやすい |
| デメリット | 投資物件を自分で選定できない実物不動産への投資と異なり、融資が受けられない元本割れのリスクがある |
個人向け国債
個人向け国債とは、国が資金調達をするために個人へ発行する債券のことです。国債を購入すると、半年ごとに利子を受け取れます。国債は経済環境が変わっても元本割れを起こすことがなく、比較的安心して保有しやすいといえますが、リターンは限定的です。また、1万円から購入できるのも気軽に始めやすい理由のひとつです。
| メリット | 元本割れのリスクがない国が発行しているため、比較的安全最低金利が0.05%に設定されている |
| デメリット | インフレによって価値が下がりやすい大きなリターンは期待しにくい購入から1年間は換金できない |
退職金運用をする際のポイント

退職金運用をする際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 退職金の色分けをする
- 資産運用の知識を身に付ける
- 長期的な視点で運用する
- 運用方法や投資先を分散する
- 積立投資で運用する
- 専門家の力を借りる
それぞれ詳しく紹介します。
退職金の色分けをする
退職金の運用方法には、株式投資や投資信託といった元本割れを起こす金融商品があるため、退職金を全額運用に回すのはおすすめできません。運用に回す金額を決める際は、退職金を以下の3つに分けてみましょう。
- 日常の生活費や万が一のときに備えるお金
- 数年後に必要になりそうな資金
- その他の資金(余剰資金)
色分けをスムーズに行うためには、毎月の支出や今後のライフプランなどを明確にしておくことが大切です。以下のようなライフイベントが予定されている場合は、預入期間が短い定期預金などでの管理がおすすめです。
- 子供の結婚や孫の誕生
- 自宅のリフォーム
- 家電や車の買い替え
その他の資金(余剰資金)は、投資信託や不動産小口化商品などで運用するとよいでしょう。
資産運用の知識を身に付ける
退職金を受け取れる年齢に近づくと、さまざまな金融機関から運用方法についての提案を受けることになります。退職金の運用方法を決める際は、自身でもしっかりと勉強したうえで自分に合った商品かを見極めることが大切です。資産運用の知識がなければ、リスクの高い商品を購入したり高い手数料を支払ったりすることで、期待した利益が見込めなくなる可能性があります。
退職金運用の失敗を避けるためにも、資産運用の知識や各金融商品のメリット・デメリットを理解しておきましょう。
長期的な視点で運用する
短期的に大きなリターンを見込める投資方法は、リスクが高い傾向にあります。株式や投資信託といった商品は、災害やテロといった要因で大きな価格変動を起こすことがあります。値動きが大きい時期に短期売買をすると、大きな損失を出してしまうこともあるでしょう。
一方、長期保有であれば一時的な価格の上下はあるものの、災害やテロなどの値動きは時間とともに軽減されていく傾向があり、値動きによる影響を小さくできます。短期トレードで退職金を失うことがないよう、長期的な目線をもって安定的な利益を目指すようにしましょう。
運用方法や投資先を分散する
退職金運用を成功させるには、運用方法や投資対象を分散することが効果的です。ひとつの金融商品に絞って運用した場合、その資産が値下がりしたときには大きな影響を受けることになります。一方、株式や不動産、債券といった性質の異なる金融商品を複数保有しておけば、大きな値動きに巻き込まれる心配も少なく済みます。
退職金を運用するときは、運用方法や投資先を分散するようにしましょう。
積立投資で運用する
退職金の運用をする際は、一括投資をするのではなく、少しずつ積み立てていくのがおすすめです。投資で利益を狙うには、株式や投資信託などを安いときに買い、高いときに売る必要があります。しかし、値動きを完全に予測するのは専門家でも難しく、投資するタイミングによっては大きな損失を受けてしまう可能性があります。
そのような状況を避けるためにも、積立投資によって価格変動のリスクを抑えることが大切です。
専門家の力を借りる
退職金運用をする際は、普段から利用している銀行や証券会社の窓口、FPなどの専門家の力を借りるのも手段のひとつです。退職金運用のリターンを最大化するためには、早い段階から運用を始めることが重要です。
しかし、資産運用の勉強を始めてはみたものの、自分に合った運用方法が分からず、行動に移せなくなっている人もいるでしょう。適切な運用方法を見極められず時間が過ぎてしまう場合は、専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
また、投資信託や不動産小口化商品などでは、プロの力を借りながら資産運用ができます。自力での運用が難しい場合は、資産運用や管理を任せられる金融商品を選ぶことも視野に入れましょう。
最後に
退職金運用のメリットは、老後生活を豊かにできたり、退職後の収入減少を補えたりする点です。退職金運用方法には、退職金定期預金や投資信託、不動産小口化商品などがあります。それぞれの金融商品ごとにメリット・デメリットがあるため、違いを押さえたうえで自分に合ったものを選ぶことが大切です。
なかには、子供や孫に資産を残してあげたいと考える方もいるでしょう。「Vシェア」は長期的に安定した収益が期待できることから、相続の取り組みとしてもおすすめです。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
村井 英一むらい えいいち
ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士、証券アナリスト、宅地建物取引士)
1965年生まれ。大手証券会社で法人営業、個人営業、投資相談業務を担当する。2004年にファイナンシャル・プランナーとして独立後は、相談者の立場にたった顧客本位のコンサルタントを行う。特に、資産運用、住宅ローン、年金問題、ライフプランニングなどを得意分野とする。
家計の診断・相談室(https://kakeinoshindan.com/)
老後資金の記事一覧に戻る