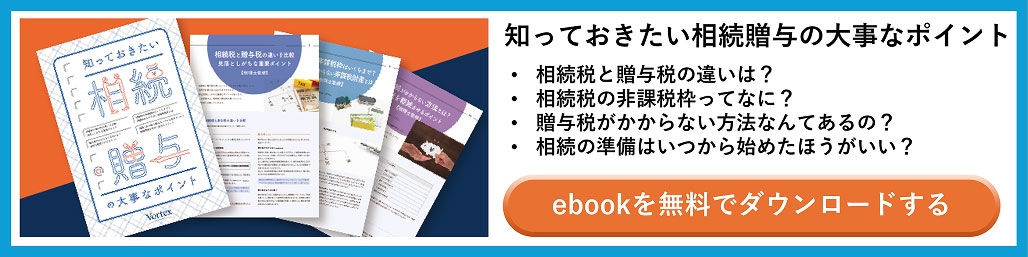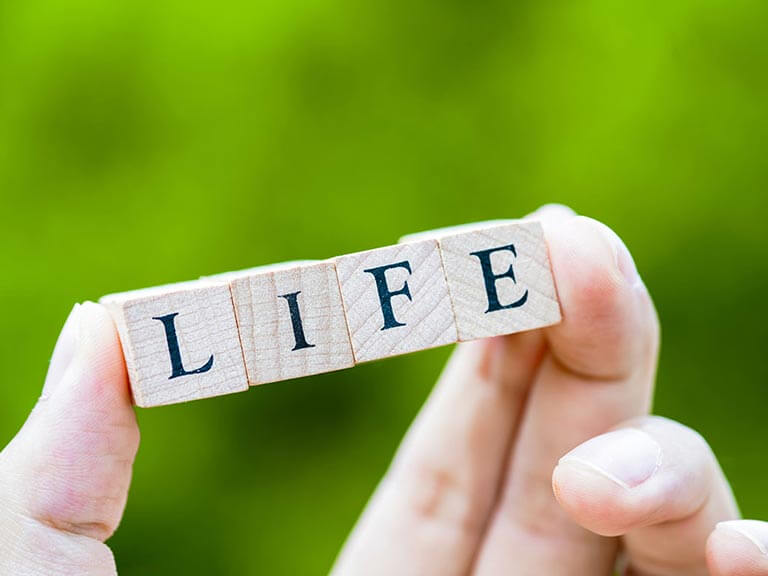目次
住宅や土地などの生前贈与を検討するときに知っておきたいのが「贈与税の計算方法」です。
本記事では、贈与税の計算方法やケース別の計算シミュレーションをわかりやすく解説します。贈与税がかからないケースや生前贈与の注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
贈与税とは?
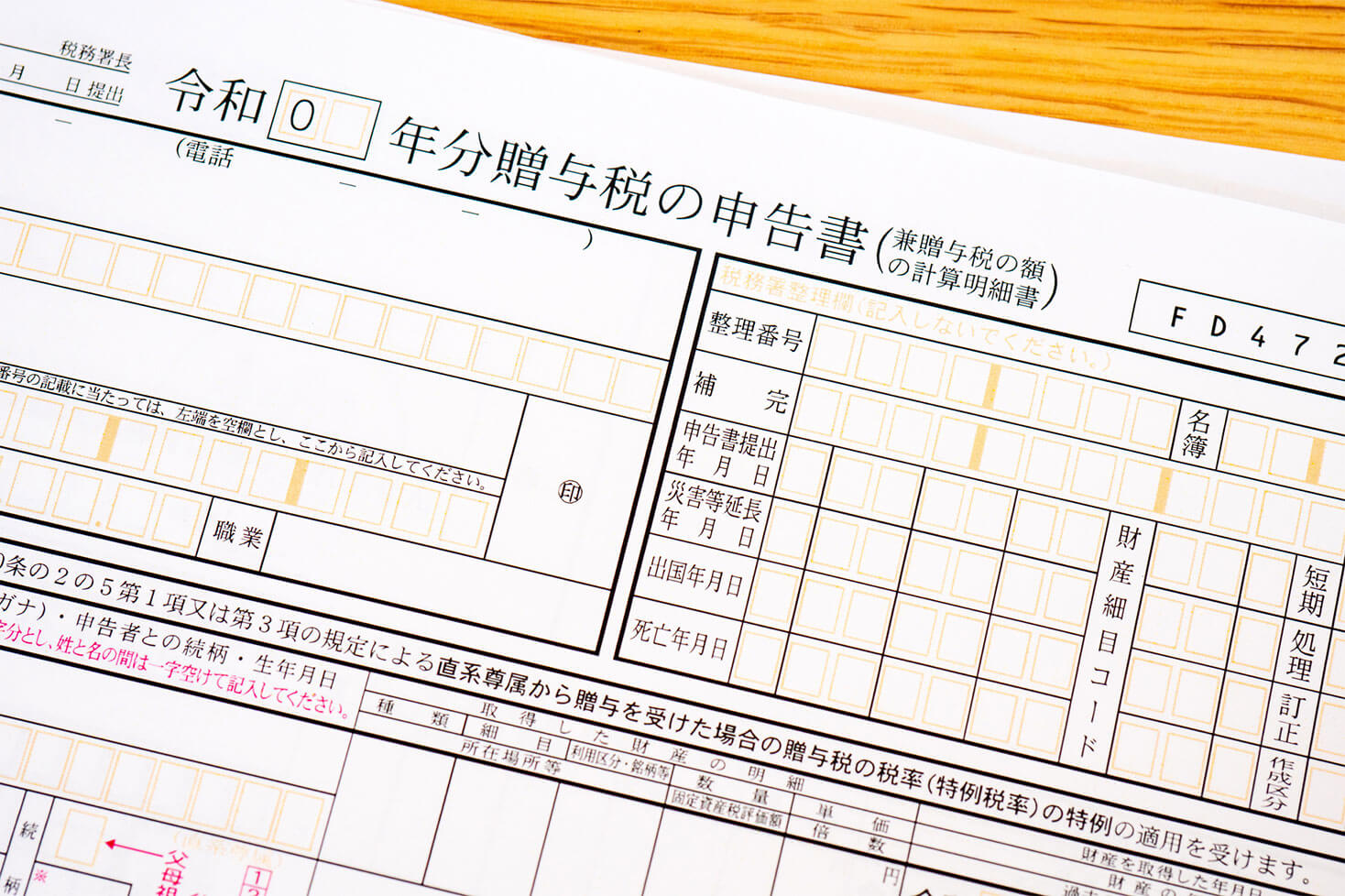
贈与税とは、個人から無償で財産を受け取った場合にかかる税金のことです。
贈与は、贈与者(贈与する人)の一方的な意思で成立するものではなく、受贈者(贈与を受ける人)が受諾することで成立します。贈与は口頭での合意によっても成立しますが、贈与契約書を作成することで贈与がおこなわれた証明を残すことができます。
ただし、相手から無償で財産を受け取ったとしても、以下のようなケースでは贈与税がかかりません。
- 個人ではなく法人から財産を受け取った場合(※ 贈与税ではなく所得税がかかります)
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から通常必要とされる生活費や教育費をその都度受け取った場合
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業に確実に使う財産を受け取った場合
- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託など、財務大臣の指定した特定公益信託から金品が交付された場合
- 精神や身体に障害のある人や、その人を扶養する人に対して、心身障がい者共済制度に基づいて支給された給付金を受け取った場合
- 選挙における公職の候補者が選挙運動で取得した財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされた場合
- 特定障がい者扶養信託契約に基づく信託受益権を取得した場合
- 社会通念上相当と認められる香典やご祝儀、お見舞いなどの金品を受け取った場合
贈与税の計算方法

贈与税の基本的な計算方法は、以下のとおりです。
1.贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を出す。
[ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額 110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]

2.税率一覧表に基づき、贈与税の計算をおこなう。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があり、どちらを選択するかによって計算方法が異なります。
それぞれの課税方式を詳しく見ていきましょう。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から110万円の基礎控除を差し引いた残額に贈与税を課す方式です。暦年課税では、「一般贈与」と「特例贈与」の2種類の税率があり、贈与者と受贈者の関係によって適用税率が異なります。
一般贈与
一般贈与とは、兄弟や配偶者、親族といった直系尊属(祖父母や父母など)以外からの贈与のことをいいます。ただし、直系尊属から贈与を受けた場合でも、受贈者が18歳未満※であれば一般贈与に該当します。
※2022年3月31日以前の贈与は「20歳未満」
一般贈与における贈与税の税率と控除額は、以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
特例贈与
特例贈与とは、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者※ への贈与のことです。たとえば、祖父から孫、父から子への贈与が当てはまります。なお、養子縁組をしていない配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではないので、贈与を受けても特例贈与には該当しません。
※2022年3月31日以前の贈与は「20歳未満」
特例贈与における贈与税の税率と控除額は、以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
贈与税は、簡易シミュレーションを活用すれば簡単に算出できます。
贈与税(暦年課税) - 高精度計算サイト
※リンク先のページは変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、2,500万円までの贈与を非課税とし、贈与者が亡くなったときに相続財産にその相続時精算課税を適用した贈与財産を加算して相続税を計算する制度です。相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して贈与をする場合に選択できます。なお、相続時精算課税を選択すると暦年贈与に戻ることはできません。
相続時精算課税を選択し、贈与された財産が2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税がかかります。ただし、2024年1月1日以降に相続時精算課税によって贈与された財産には、毎年110万円の基礎控除が適用されるため、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、暦年贈与のような相続時の生前贈与の加算対象になりません。
贈与財産は、贈与時の時価で相続財産に加算されるため、値上がりしそうな土地や建物は相続時精算課税制度で贈与することで相続税評価額を抑えられる可能性があります。なお、2024年1月1日以降に贈与された土地や建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、贈与時の時価ではなく相続時に再評価されることになります。
【ケース別】贈与税の計算シミュレーション
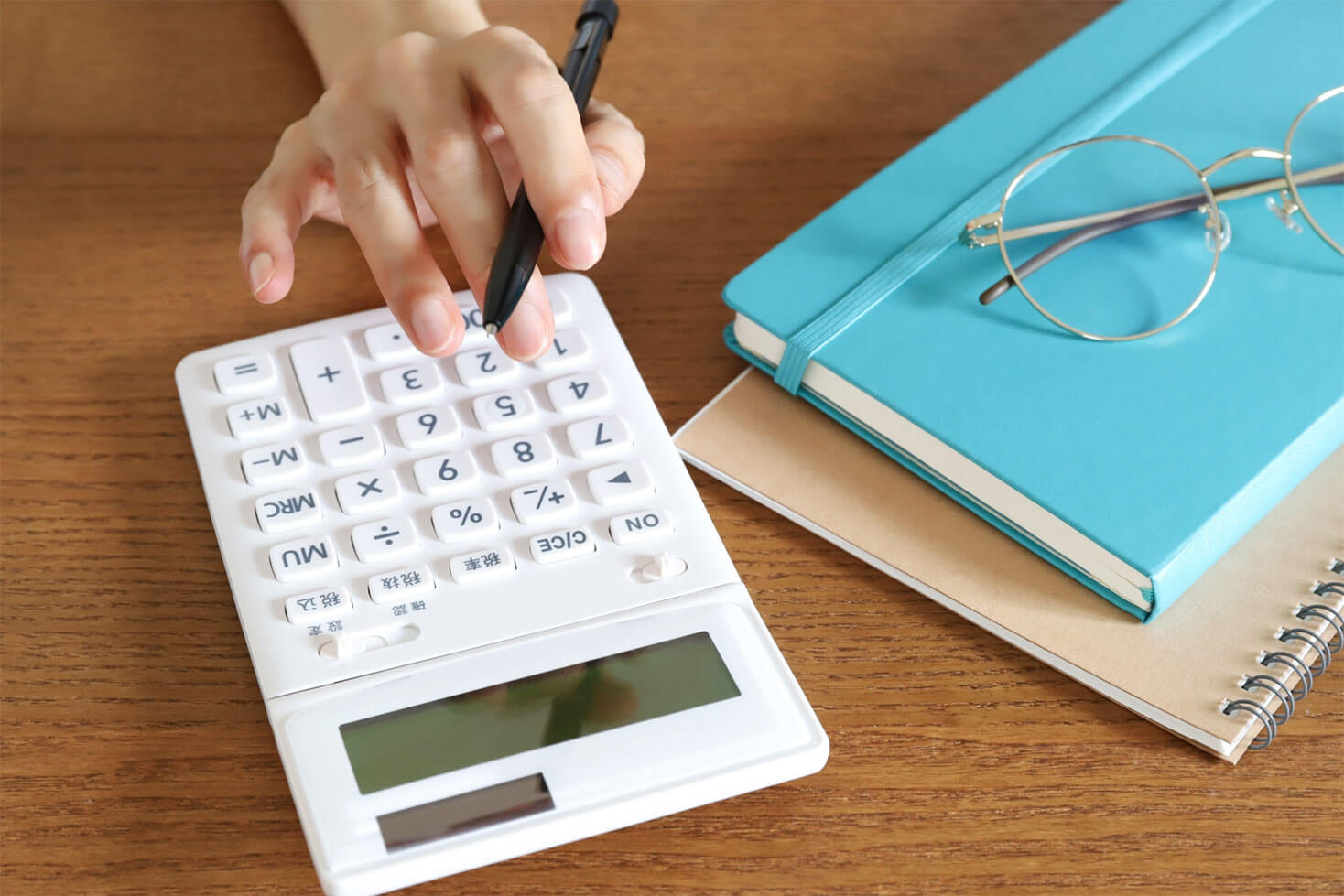
贈与税の特例は、贈与財産の種類や状況によって適用されるかが異なります。
ここでは、ケース別の贈与税の計算シミュレーションを紹介します。
不動産(建物、土地)の贈与を受けた場合
建物や土地などの不動産を贈与する場合、贈与の対象となる不動産の評価額を調べる必要があります。
建物の評価額を調べるときは、納税通知書で「固定資産評価額」を確認しましょう。土地は、路線価方式または倍率方式のどちらかで評価額を算出します。
まずは国税庁ホームページで路線価を確認し、土地の評価額を算出しましょう。
路線価方式による評価額=路線価×地積(㎡) ※補正率等の調整あり
路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と評価倍率を用いて倍率方式によって評価額を算出します。
倍率方式による評価額=固定資産税評価額×地域別の評価倍率
贈与金額別の贈与税額をシミュレーションした結果が以下のとおりです。
| 贈与金額 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈与税額 | 一般贈与 | 53万円 | 231万円 | 695万円 | 1,195万円 | 2,289.5万円 | 5,039.5万円 |
| 特例贈与 | 48.5万円 | 177万円 | 585.5万円 | 1,035.5万円 | 2,049.5万円 | 4,799.5万円 | |
「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用する場合
父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫に自己の居住用の住宅の新築・取得・増改築のため資金を贈与する場合は、一定金額の贈与が非課税になる「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の適用を受けられます。2026年12月31日までの贈与が対象となり、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税になります。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用する場合の贈与税の計算式は、以下のとおりです。
(住宅取得等資金贈与額-非課税控除額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
たとえば、省エネ住宅以外の住宅を建てるために、父から住宅取得資金として1,000万円の贈与を受けた場合、贈与税の計算は以下のようになります。
(1,000万円-500万円-110万円)=390万円
390万円×特例税率15%-控除額10万円=48.5万円
住宅取得等資金贈与の非課税の特例には、建物の床面積や建築条件、受贈者の年齢、贈与年の所得などの条件があります。適用が受けられない状況にならないためにも、事前に適用要件を確認しておきましょう。
「相続時精算課税の特例」を利用する場合
「相続時精算課税の特例」は、住宅取得等資金贈与の非課税の特例とあわせて利用することも可能です。
相続時精算課税の特例を選択したときの贈与税の計算式は、次のとおりです。
(特例適用の贈与者から贈与を受けた財産の合計評価額-年間110万円の基礎控除-2,500万円)×一律20%
相続時精算課税の特例と住宅取得等資金贈与の非課税の特例を併用するときの贈与税は、以下の計算式で求めます。
(特例適用の贈与者からの住宅取得等資金贈与額-住宅取得等資金贈与の非課税の特例の非課税控除額-年間110万円の基礎控除-2,500万円)×一律20%
たとえば、省エネ住宅を購入するために祖父から4,000万円の住宅取得資金の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、次のようになります。
(4,000万円-1,000万円-110万円-2,500万円)×一律20%=78万円
相続時精算課税を選択して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算されて相続税が課されます(住宅取得資金贈与の非課税額と基礎控除以外の贈与財産)。すでに納めた贈与税がある場合は贈与税相当額が相続税額から控除されます。
「教育資金の一括贈与の特例」を利用する場合
父母や祖父母などの直系尊属が子や孫に対して教育資金を贈与するときは「教育資金の一括贈与の特例」の適用を受けることで1,500万円まで非課税で贈与できます。2026年3月31日までの贈与が対象で、塾や習い事など学校以外の贈与をするときの非課税限度額は500万円になります。こちらは通常の贈与とは異なり、信託銀行などの金融機関を通じて所定の手続きを行い進める必要があります。
教育資金の一括贈与の特例で受け取った資金を契約期間終了までに使いきれなかった場合、贈与税がかかるので注意が必要です。
教育資金の一括贈与の特例で贈与税が課税されるときの計算式は、以下のとおりです。
(教育資金口座の残額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
たとえば、教育資金管理契約終了時に500万円の残金があった場合の贈与税は、以下のように計算します。
500万円-110万円=390万円
390万円×一般税率20%-控除額25万円=53万円
「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」を利用する場合
「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、父母や祖父母などの直系尊族が、子や孫などに結婚や妊娠、出産、子育てに必要な資金を一定額まで非課税で贈与できる制度です。2025年3月31日(2025年度税制改正大綱により2027年3月31日まで2年延長予定)までの贈与が対象で、子・孫ごとに1,000万円までが非課税になります(結婚式は300万円まで)。こちらは通常の贈与とは異なり、信託銀行などの金融機関を通じて所定の手続きを行い進める必要があります。
教育資金の一括贈与の特例と同様に、契約期間終了時点で資金が残っていると贈与税がかかってしまうので注意しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例でかかる贈与税は、以下の計算式で求めます。
(結婚・子育て資金口座の残額-基礎控除(110万円))×税率-控除額
たとえば、結婚・子育て資金管理契約終了時に400万円の残高があった場合、贈与税の計算は次のようになります。
400万円-110万円=290万円
290万円×一般税率15%-10万円=33.5万円
生前贈与をするときのポイント

ここでは、生前贈与をするときのポイントを紹介します。
個人年金保険・生命保険の契約者と受取人を統一する
保険金を受け取る際は、契約形態によって贈与税がかかることがあります。
たとえば、個人年金の契約者が夫、受取人が妻となっている状況で基礎控除を超える年金受給権を受け取ると、妻が贈与税を納めることになります。
死亡保険などの生命保険は、保険料を負担している契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税がかかります。具体的には、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子であれば、子が贈与税を納めることになります。
生前贈与である証明を残しておく
生前贈与は、贈与の事実を証明するものがなければ税務署から否認されることがあります。生前贈与が否認されると、相続財産として見なされて相続税が課される可能性があります。税務署から否認されないためにも、贈与契約書を作成したり、口座振込でお金を渡したりするなど、生前贈与である証明を残しておきましょう。
納税資金を準備しておく
生前贈与によって贈与税が発生したときは納税資金が必要になります。贈与税は、相続税のように物納が認められていないので、現金で準備しておかなければなりません。納税資金が足りない状況にならないためにも、事前に贈与税がいくらかかるのかをシミュレーションしたうえで納税資金を準備しておきましょう。
生前贈与における注意点

生前贈与の財産は、相続財産に加算されたり、贈与税以外の税金がかかったりする場合があるので注意が必要です。ここでは、生前贈与をするときの注意点を解説します。
2024年1月1日以降の贈与は7年さかのぼって相続財産に加算される
2023年12月31日以前に贈与された財産は、相続開始時から3年さかのぼって相続財産に加算されます。
一方、2024年1月1日以降の贈与財産は、税制改正によって相続開始時から7年さかのぼって相続財産に加算されることとなりました。ただし、延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されません。
相続開始日ごとの相続財産への加算対象期間は、以下のとおりです。
| 贈与者の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2024年1月1日~2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~相続開始日 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
贈与税以外の税金や費用がかかることがある
生前贈与では、贈与税以外の税金や費用がかかることがあります。
たとえば、不動産を贈与するときは、不動産取得税や登記費用などがかかる場合があります。また、受贈者が亡くなったときは、生前贈与で受け取った財産に対して相続税が課されることもあります。
贈与後にどのような税金がかかるのかわからない場合は、贈与税や相続税などに詳しい税理士に相談するのがよいでしょう。
名義預金に見なされると生前贈与が認められないことがある
生前贈与した財産が名義預金に見なされると生前贈与ではなく、相続財産として課税される可能性があるので注意しましょう。名義預金とは、口座の名義人と実質的な管理者が異なる預金のことをいいます。具体的には、親が生前贈与をするために子供名義の預金口座に入金し、預金通帳や印鑑を親が管理している状況が該当します。
生前贈与しているつもりでも、相続税の税務調査で指摘されることで納税額が増えてしまう可能性があります。生前贈与であることを証明するためにも、入金先の口座を受贈者が管理するようにしましょう。
最後に
贈与税の計算方法は、課税方式や贈与者と受贈者の関係によって異なります。贈与税を正しく算出するためには、適用税率や控除額、特例制度を考慮したうえで適切なシミュレーションをすることが大切です。どのように計算すればいいのかわからないときは、贈与税や相続税に詳しい税理士に相談してみましょう。
生前贈与をする際は、弊社の不動産小口化商品「Vシェア」のご活用をご検討ください。「Vシェア」は、都心プライムエリアの中規模オフィスビルを小口化し、1口100万円で5口以上から購入できる商品です。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
≫不動産小口商品について詳しく知りたい方はこちら
≫不動産小口商品「Vシェア」についてはこちら
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
贈与税の記事一覧に戻る