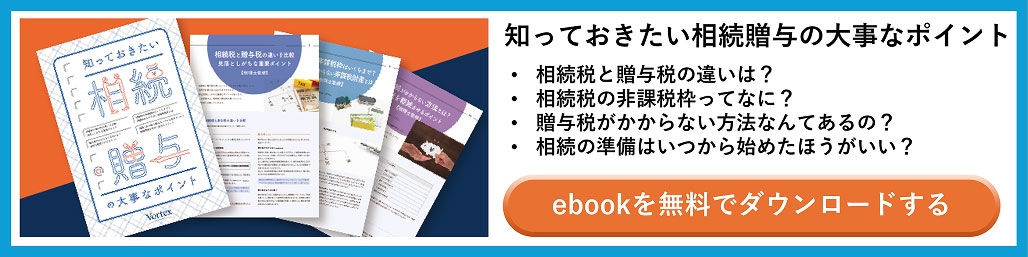目次
生前贈与を検討しているなかで、「暦年贈与ではいくらまで非課税になるのか」「暦年贈与はどのような流れでするのか」といった疑問を感じた方もいるのではないでしょうか。暦年贈与をする際は、贈与税の計算方法や手続きの流れを把握しておくことが大切です。
本記事では、暦年贈与にかかる贈与税の計算方法や暦年贈与の流れ、注意点を解説します。暦年贈与と併用できる特例制度も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産から基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税を課す制度のことです。暦年贈与では、受贈者1人につき年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。たとえば、10人の子や孫に1年間で1,100万円(110万円×10人)、10年間で1億1,000万円を非課税で贈与することも可能です。
暦年贈与には、相続財産を減らす効果があるため、早いうちから少しずつ財産を移しておくとよいでしょう。
暦年贈与にかかる贈与税の計算方法

暦年贈与にかかる贈与税は、以下のように計算します。
1.贈与財産の価額から基礎控除110万円を差し引き、課税価格を算出する。
[ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]

2.税率一覧表に基づき、贈与税を計算する。
暦年贈与は、贈与者と受贈者の関係によって「一般贈与」と「特例贈与」の2種類に分類され、適用税率が異なります。
一般贈与
一般贈与とは、特例贈与に該当しない夫婦や兄弟、父母または祖父母から18歳未満の子・孫などに贈与することをいいます。
一般贈与における贈与税の税率は、以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、父から16歳の子へ600万円を贈与するときの贈与税額は、以下のようになります。
| 600万円-110万円=490万円 490万円×30%-65万円=82万円 |
特例贈与
特例贈与とは、贈与年の1月1日において18歳以上の子や孫が、父母や祖父母などから受けた贈与のことをいいます。
特例贈与における贈与税の税率は、以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、父から19歳の子へ600万円を贈与するときの贈与税額は、以下のようになります。
| 600万円-110万円=490万円 490万円×20%-30万円=68万円 |
暦年贈与と相続時精算課税制度の違い
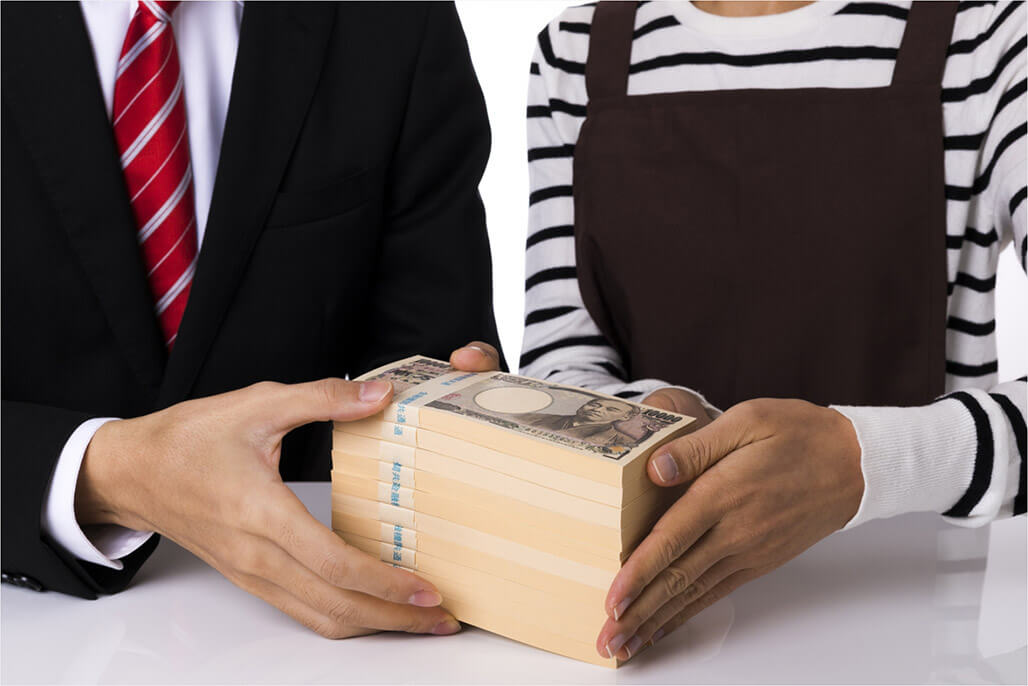
生前贈与をする際は、暦年贈与以外に相続時精算課税制度を選択することも可能です。相続時精算課税制度とは、年間110万円の基礎控除後(2024年1月1日以後の贈与から)の残額の累計額が特別控除額2,500万円までは贈与税がかからない制度のことです。60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できます。
相続時精算課税制度を適用した贈与は、特別控除額以内であれば贈与税がかからない代わりに贈与者がなくなったときの相続財産に加算されます。加算対象とされる財産は、2024年以降の贈与から年間110万円の基礎控除後の残額となります。また基礎控除以内であれば暦年贈与のように相続開始前7年以内(2023年以前の贈与は3年)の加算となることもありません。
暦年課税と相続時精算課税制度の違いは、以下のとおりです。
| 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | |
|---|---|---|
| 適用要件 | 特になし | 60歳以上の父母や祖父母などから贈与年の1月1日で18歳以上の子や孫への贈与 |
| 非課税額 | 受贈者1人につき年110万円まで | 贈与者1人につき2,500万円(2024年以降は年110万円の控除後)まで |
| 贈与税の計算 | (1年間で譲り受けた財産の合計金額-110万円)×10%~55% | (譲り受けた財産の基礎控除後の合計金額-2,500万円)×20% |
| 相続時の加算 | 相続開始3~7年以内に譲り受けた財産が相続財産に加算される(加算年数は相続開始時期によって変動する) | 年110万円超えの贈与財産を贈与時の評価額で相続財産に加算 |
| 適用手続き | 特になし | 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などとあわせて管轄の税務署に提出 ※一度選択すると暦年課税に戻れない |
同じ贈与者から財産を受け取っている場合は、暦年課税と相続時精算課税制度を併用することはできません。ただし、同じ受贈者であっても、贈与者が異なれば課税方式を選択できます。
父からの生前贈与を相続時精算課税にした場合は、暦年贈与を選択することはできませんが、母から暦年贈与で財産を受け取ることは可能です。
暦年贈与が適しているケース
暦年贈与が適しているのは、以下のようなケースです。
- 早いうちから財産を移したい
- 相続税の税率が高い場合(贈与税を払ってでも税率差で有利になるため)
- 推定相続人以外に贈与する
贈与者や受贈者の年齢条件がない暦年贈与は、双方が若いうちから少しずつ財産を贈与したいときに活用できます。また、暦年贈与の受贈者が相続人にならなければ、贈与財産が相続財産に加算されないため、推定相続人以外に財産を渡すときにも適しているでしょう。ただし遺言や生命保険によって財産を取得すると7年以内加算の対象となるので注意が必要です。
相続時精算課税制度が適しているケース
相続時精算課税制度が適しているのは、以下のようなケースです。
- 一括で財産を贈与する
- 余命が短いときに年110万円以内の贈与をする
- 将来値上がりする可能性のある不動産を生前贈与する
相続時精算課税制度は、特別控除額2,500万円まで贈与税がかからないため、一括で財産を贈与する際に活用できます。また、相続時精算課税制度の適用を受けておけば、年110万円以内の財産を相続開始7年以内に贈与したとしても相続財産に加算されることはありません。余命が短いときに18歳以上の子に年110万円以内の贈与をすれば、非課税で財産を移せます。
相続時精算課税制度による贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算されます。ただし、相続時には贈与財産が相続財産に加算されるため、将来的な課税リスクを十分に検討する必要があります。
暦年贈与をするときの流れ

暦年贈与の流れは、以下のとおりです。
- 贈与契約書を作成する
- 財産を移す
- 110万円超えの贈与をしたら贈与税申告をする
それぞれ詳しく解説します。
贈与契約書を作成する
贈与契約書とは、贈与内容を客観的に証明するための書類です。贈与契約は口約束でも成立するため、契約書を作成する必要はありません。しかし、贈与契約書を作っておかなければ、税務調査や遺産分割のときに生前贈与があった事実を証明することが難しくなってしまいます。生前贈与の内容を証明するためにも、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくことがおすすめです。
財産を移す
財産を移すときは贈与契約書を作成するだけでなく、資金移動を客観的に証明できるようにすることが大切です。たとえば、現金の贈与は手渡しにするのではなく、銀行口座を利用することがおすすめです。資金移動に銀行口座を使えば、贈与日や金額、贈与者および受贈者の情報が残るため、贈与についての客観的な証明として活用できます。
110万円超の贈与をしたら贈与税申告をする
年間110万円を超える暦年贈与をすると、贈与税がかかります。贈与税が発生した受贈者は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに管轄の税務署に贈与税申告をしなければなりません。
贈与税申告で主に必要なものは「贈与税申告書」と「マイナンバー」です。贈与税申告書の種類は、適用を受ける制度によって以下のように異なります。
| 贈与税申告書の種類 | 提出が必要な人 |
|---|---|
| 第一表 (兼贈与税の額の計算明細書) | 贈与税を申告する人全員 |
| 第一表の二 (住宅取得等資金の非課税の計算明細書) | 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人 |
| 第二表 (相続時精算課税の計算明細書) | 相続時精算課税制度の適用を受ける人 |
贈与税申告をするときは、申告書の種類と必要書類を事前に確認しておきましょう。
暦年贈与の注意点

年110万円以下の暦年贈与であっても、定期贈与とみなされたり、名義預金と判断されたりすることで課税対象となるケースがあります。思わぬ税金を納めることにならないためにも、暦年贈与の注意点を押さえておきましょう。
定期贈与とみなされると贈与税がかかる
年110万円以下の暦年贈与であっても定期贈与とみなされると、贈与税が課せられる可能性があります。
定期贈与とは、あらかじめ贈与の約束をした金額を分割して贈与することを指します。たとえば、1,000万円を毎年100万円ずつに分割して贈与する約束をしていた場合は、定期贈与とみなされる可能性があるため注意しましょう。
そのような状況を防ぐには、毎年の贈与時期や贈与金額を変え、暦年贈与のたびに贈与契約書を作成するといった工夫が推奨されます。
名義預金と判断されると相続税の課税対象になる
贈与財産が名義預金とみなされると、相続税の課税対象になることがあります。
名義預金とは、口座の名義人と管理者が異なる預金のことです。たとえば、親が子供名義の口座に入金し、預金通帳と印鑑を親が管理している状況は名義預金と判断され、口座内のお金が相続財産に加算される可能性があります。
名義預金と判断されないためには、贈与契約書を作成したり、受贈者が通帳や印鑑を管理したりすることが大切です。
相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算される
相続開始前3〜7年以内に暦年贈与で受け取った財産は、年間110万円以下であっても相続財産に加算されます。加算期間は、贈与のタイミングによって以下のように異なります。
| 贈与者の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2024年1月1日~2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~相続開始日 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
なお、延長された4年間に贈与された財産は、総額100万円まで相続財産に加算されません。
暦年贈与と併用できる特例制度

暦年贈与と併用できる特例制度には、以下のようなものがあります。
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 住宅取得等資金の非課税の特例
- 贈与税の配偶者控除
それぞれ詳しく見ていきましょう。
教育資金の一括贈与の特例
教育資金の一括贈与の特例とは、2026年3月31日までに父母や祖父母などが30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合に、1,500万円まで非課税となる制度です。塾や習い事といった学校以外の資金は、500万円が上限となります。
ただし、教育資金の一括贈与の契約期間終了時点で受贈した資金が銀行口座に残っていると、贈与税がかかるため注意しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、2027年3月31日までに父母や祖父母などの直系尊属が18歳以上50歳未満の受贈者に結婚や子育てに必要なお金を贈与する際に、1,000万円まで贈与税がかからない制度です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用を受けるには、取扱金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。契約期間終了時点で口座にある残高には贈与税がかかります。
住宅取得等資金の非課税の特例
住宅取得等資金の非課税の特例とは、2026年12月31日までに、父母や祖父母などが18歳以上の子や孫に対して、住宅の新築・取得・増改築のための資金を、一定の要件を満たすことで非課税で贈与できる制度です。非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円までです。
住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるときは、建物の床面積や建築条件などの適用条件を確認しておきましょう。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で住宅または住宅購入資金の贈与をする際に、基礎控除額110万円に加えて2,000万円の控除が受けられる制度です。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた翌年の3月15日までに受贈者が住み始め、そのあとも引き続き住み続ける見込みがなければなりません。
最後に
暦年贈与では、通常贈与した資産が年110万円以下の基礎控除内に収まる場合、贈与税がかかりません。また、基礎控除額110万円を超える財産を贈与する際は、相続時精算課税制度を活用することで贈与税を抑えられる可能性があります。相続時精算課税制度は贈与時の資産額で相続税を計算する特徴があるため、相続時に相続税を計算するよりも結果として税負担が減少する場合があります。
※将来的に制度が変更される場合がありますので、専門家に相談しましょう。
しかし、定期贈与とみなされた場合のように、年110万円以下の贈与であっても課税される可能性があるため、個人の判断でおこなわず、専門家に相談のうえで進めることを推奨します。
また、贈与を検討する場合は、贈与契約書の作成について考えておくことをおすすめします。書面にしておくことで、贈与の内容を整理しやすくなり、後々の確認に役立つこともあるでしょう。
贈与契約書の書き方や注意点について、司法書士監修のコラムがありますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
生前贈与の記事一覧に戻る