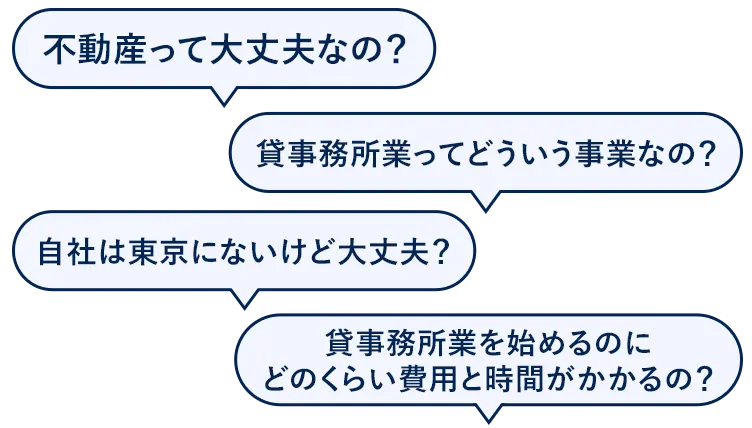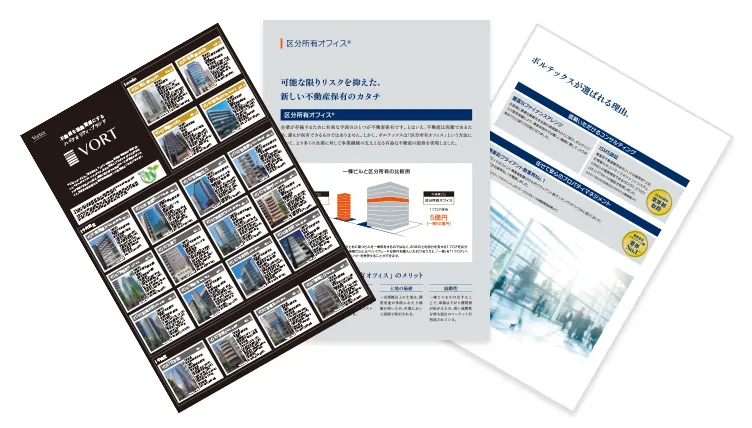後継者不足の現状と解決策|中小企業の事業承継について【税理士監修】

目次
現在日本には、経営者の高齢化にともない、事業を後継者に引き継ぐ事業承継を実施する企業が多く存在します。しかし、後継者不足を理由に廃業せざるを得ない企業も存在し、社会問題になっていることをご存じでしょうか。
この記事では、日本における後継者不足の現状や背景、それに対しての具体的な解決策を解説します。事業承継は早期に取り組みを開始し、専門家を交えて中長期的なプランに沿って進めていくことが大切です。将来的な事業承継に向けて、現状把握や課題の整理に本記事をお役立てください。
後継者不足の現状
日本国内において、後継者不足による廃業が増加しています。その背景にはどのような問題があるのでしょうか。現状を踏まえて解説します。
後継者不在に起因する倒産件数は6年連続で増加
東京商工リサーチのデータによると、2024年における後継者不在に起因する倒産は462件。7年連続で前年度を上回り、調査を開始した2013年度以降で最多件数になりました。
倒産した462件のうち、代表者の「死亡」が257件(同29.1%増)で全体の55.6%を占めており、2022年の223件を超え、過去最多を更新しました。後継者不在の状況で代表者に不測の事態が発生した場合、破産を選択するケースが多くなっています。
経営者の平均年齢の上昇が顕著
日本では経営者の高齢化が進んでおり、今後数年で多くの企業が、事業承継のタイミングを迎えると予測されています。
東京商工リサーチの『社長の平均年齢過去最高の63.59歳 最高は秋田県66.07歳、最年少は広島県62.45歳』のデータによると、2024年における全国の社長の平均年齢は63.59歳となっています。また、同社の調査をもとにしたデータを見てみると、休廃業企業の代表者の平均年齢は72.61歳で、前年の72.00歳から上昇。年齢別分布は70代以上が67.9%(前年66.6%)となっており、2021年以降、4年連続で60%を超えました。
経営者が高齢となっている状況のなか、後継者がいないことで、黒字であっても廃業せざるを得ないケースもあります。廃業してしまえば、従業員が職を失うことになり、長年培ってきた技術も途絶えてしまいます。
不本意な廃業を避けるためにも、事業承継について早期から検討することが重要です。
事業承継にまつわる問題について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>「事業承継にまつわる問題と解決策|承継トラブルのリスク回避方法」
後継者不足の原因
中小企業では、業種を問わず深刻な後継者不足が起きています。帝国データバンクの『全国企業「後継者不在率」動向調査(2024年)』によると、後継者不在率は全国で52.1%となっており、半数以上が後継者不在の状態です。ここでは、後継者不足の主な原因を5つ解説します。
- 親族や身内への承継が一般的ではなくなった
- 事業の将来性に不安がある
- 負債を抱えていることに不安がある
- 事業承継の準備が進んでいない
- 事業承継支援策の不足
1. 親族や身内への承継が一般的ではなくなった
一昔前は経営者の子供や、子供の夫などの身内で事業承継を行うケースが一般的でした。しかし、昨今は身内による事業承継の割合が減少しています。
その原因として、少子化による後継者候補の減少や、職業選択の多様化などがあげられます。また、経営者が後継者候補に対して、「経営者としての能力に欠ける」と判断し事業承継を渋るケースや、子供が自ら「自分は経営者の器ではない」と事業承継を忌避するなどの問題も生じています。
親族内承継について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>「親族内承継とは?メリット・デメリットと円滑に引き継ぐポイントを解説」
2. 事業の将来性に不安がある
事業の将来性も、事業承継を検討するうえで大切な判断材料です。昨今の状況などを鑑みて、経営者自らが「継がせたくない」、子供も「継ぎたくない」と考える現状があります。
後継者候補が事業を継ぎたいと思う理由について、中小企業庁の『事業承継ガイドライン(令和4年3月改訂)』によると、「事業がなくなると困る人(取引先・従業員など)がいるから」と回答した人が31.2%ともっとも多く、次いで「事業に将来性があるから」と回答した人が30.0%と、ほぼ同じ割合になっています。
後継者が事業を継ぐ理由のうち、「事業を引き継ぐことへの使命感」と「事業に将来性を感じている」が多いことが分かります。
将来性がないといわれた業界においても、ユニークな発想によって事業がV字回復したサクセスストーリーは数多く存在します。経営者には、外部の力も借りながら、後継者が「この会社を継ぎたい」と思えるような環境を整えることが求められています。
3. 負債を抱えていることに不安がある
事業承継では、負債も引き継がれる点に注意が必要です。負債があることがネックとなり、経営者と後継者の双方が事業承継に対して積極的になれない場合もあります。
4. 事業承継の準備が進んでいない
中小企業庁の『事業承継ガイドライン(令和4年3月改訂)』によると、事業承継には5年から10年ほどの期間が必要だとされています。事業承継の手続きは複雑で、日々の業務が忙しいことを理由に、準備が進んでいないことも後継者が不足する要因のひとつです。
事業承継において、特に時間がかかるのが後継者の育成です。準備をしなかったことで、いざ事業承継が必要になったときに適当な後継者が見つからず、悩んでしまう人も多いのです。
5.事業承継支援策の不足
事業承継支援策が不足していることも原因のひとつと考えられます。中小企業の事業承継が円滑に進むか否かは日本経済を左右するため、国をあげて取り組むべき課題です。
実際に、国はいくつかの支援策を用意しており、その一例として事業承継・引継ぎ支援センターによる後継者のマッチングがあげられます。ほか、事業承継・引継ぎ補助金の制度実施や中小企業成長支援ファンドによる資金提供なども行われています。
これらの支援策が講じられているものの、いまだ後継者不足が解消されるには至っていません。
後継者不足の解決方法
後継者不足の現状や原因を踏まえ、ここからは主な解決方法を6つお伝えします。
- 早い段階から親族を後継者として育成する
- 従業員のなかから後継者を選定する
- 外部の人材を後継者として登用する
- M&Aで合併・売却を行う
- 株式公開を行う
- 事業承継に関する窓口で相談する
それぞれの特徴やメリット・デメリットを押さえておきましょう。
1.早い段階から親族を後継者として育成する
後継者に事業を引き継ぐうえで、やるべきことは多岐にわたります。中小企業庁の『事業承継ガイドライン(令和4年3月改訂)』によると、事業承継について44%の経営者が課題としてあげたのが「後継者の経営力育成」で、「事業の将来性」に次いで2番目に多い割合となっています。
後継者を育てるには時間を要するため、少しでも早く候補者を選定し、育成を始めることが重要です。
親族を後継者にするメリット
親族を後継者にする方法には、主に以下のメリットがあります。
- 後継者の候補者との交渉を進めやすい
- 従業員や取引先から受け入れられやすい
- 早い段階から教育がしやすい
- コストが少ない
親族であれば、今まで接点のなかった人と比べ、話をしやすいでしょう。承継することが決まれば、早い段階から入社してもらい、まずは社員として学んでもらうことも可能です。
専門家による仲介が入らないため、コストも抑えやすくなります。また、現在の経営者の親族であれば従業員や取引先からの反発も少なく、スムーズに事業承継ができると考えられます。
親族を後継者にするデメリット
一方、親族を後継者にする場合の主なデメリットは、次のとおりです。
- 後継者に適した人材がいない場合もある
- 相続税や贈与税の負担がある
- 親族内でトラブルが発生する可能性がある
少子化で候補者が限られることや、経営者への適性の有無などにより、親族内で適任の人物が見つからない場合が少なくありません。反対に子供が複数人いる場合は、後継者候補の選定で意見が割れてトラブルに発展することもあります。
また、株式の贈与、相続には税金がかかることもあるため、その負担が問題となるケースもあります。
2.従業員のなかから後継者を選定する
事業承継では、子や孫といった身内に引き継ぐだけでなく、親族外に引き継ぐという選択肢もあります。そのなかでも、まずあげられるのが従業員に事業を引き継ぐ方法です。
従業員を後継者にするメリット
従業員を後継者にする場合は、以下のようなメリットがあります。
- 会社のことを理解している役員や社員に承継できる
- 多くの候補者のなかから選定できる
これまで働いてきた従業員であれば、経営理念や実務の進め方もすでに身についているでしょう。教育の手間や時間がかからないことは、事業承継を進めるうえで大きなメリットといえます。
さらに、会社の規模にもよりますが、親族内から選定するよりも対象者の人数が多くなることが考えられます。多数のなかから選定すれば、より適した人材を選べる可能性が高まります。
従業員を後継者にするデメリット
従業員を後継者にする場合、実務の引き継ぎはスムーズであるものの、金銭面や保証関係においてデメリットがあります。
- 会社を引き継ぐための資金調達が必要
- 個人保証の引き継ぎが難しい
会社の経営を引き継ぐ場合、株式を買い取るため等の資金を用意しなければなりません。しかし、多額の資金を調達することは容易ではありません。
また、企業が金融機関から融資を受けている場合、代表者が保証人となっているケースが多いです。事業承継をする際には個人保証も引き継ぐ必要がありますが、親族内承継と比べて金融機関からの承認を得にくいことが予想されます。
従業員への事業承継について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>「従業員へ事業承継するメリット・デメリットと3つの選択肢」
3.外部の人材を後継者として登用する
外部から経営者を招き入れるのも、親族外承継の方法のひとつです。広く候補者を探す点は従業員への承継と同じですが、外部からの登用ならではの特徴もあります。
外部の人材を後継者にするメリット
外部の人材を後継者として登用するメリットは、主に以下のふたつです。
- 今までの社風やしがらみにとらわれない
- 事業の効率化や施策などを進めやすい
外部からの登用で引き継いだ経営者は、社風やしがらみにとらわれず、新しい施策などを進めやすい傾向があります。従来のやり方に固執せず、効果や数字を見て判断することができるでしょう。
外部の人材を後継者にするデメリット
外部の人材を後継者にする場合にも、デメリットがあります。
- 社内で理解を得にくい場合がある
- 元経営者の親族や社員、株主などからの反発がある
外部の人材を登用した場合、親族内承継や従業員への承継と比べ、社内で十分な理解が得られない場合があります。元経営者の親族や社員、株主などと衝突することも考えられます。
また、実績がある経営者でも、これまでの環境と変わることによって経営手腕を発揮できないこともあるでしょう。
4.M&Aで合併・売却を行う
M&Aとは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略で、企業の合併買収を意味します。
親族や身内、従業員に適当な後継者がいない場合でも、M&Aを活用することで適任者に事業を承継し、会社を存続できる可能性があります。
M&Aを行うメリット
M&Aを行う場合、次のようなメリットが考えられます。
- 法人や経営者から幅広く後継者を探せる
- 専門家に相談できる
- 事業拡大の可能性がある
親族や従業員のなかで候補者が見つからない場合は、外部で後継者を探すことになります。その際、M&Aを視野に入れれば、ほかの法人や経営者まで対象者が広がるのです。
M&Aや事業承継の専門家なら幅広い情報を保有しているため、相談することで自社に適した事業の引き継ぎ先を見つけられる可能性があります。さらに、M&Aには、新規事業への参入や既存事業の強化といったメリットもあります。
M&Aを行うデメリット
M&Aを行うことによる主なデメリットは、次のとおりです。
- 社風や労働条件などが変わる可能性がある
- 成立までに時間がかかるケースがある
- 専門家に仲介を依頼するとコストがかかる
M&Aでほかの法人と合併すると、社風や労働条件、経営方針が変わる場合があります。従業員の説得などが必要になり、手間が発生するというデメリットが考えられます。
手続きが複雑で、身内に事業承継する場合に比べて長期化する傾向もあるため、専門家を交えた早めの取り組みが必要です。専門家による仲介は手数料がかかることも認識しておきましょう。
5.株式公開を行う
株式公開とは証券取引所に上場し、自社の株式を証券市場に流通させることで、誰でも売買できる状態にすることです。株式公開を行うことで、後継者不足の解消につながる可能性もあります。
株式公開を行うメリット
株式公開を行うメリットには、次のふたつがあげられます。
- 企業の信頼性や透明性が高くなる
- M&Aで買い手が見つかりやすくなる
株式公開することで企業としての知名度や社会的な信用が増すため、採用面でも優秀な人材が集まりやすくなることが期待できます。後継者候補を見つけられる可能性も高まるでしょう。
また、上場企業としてのガバナンスを確立することで透明性や信頼性が増すため、M&Aを行う際にも交渉を進めやすくなると考えられます。
株式公開を行うデメリット
株式公開を行うデメリットとしてあげられるのは、主に次のふたつです。
- 公開準備中は新規事業ができない場合がある
- 公開するまでに多くの手続きが必要
株式公開の準備中に新規事業を行うことは可能ではあります。ただし、公開準備中に行われる審査には企業の財務状況などが含まれるため、リスクのある新規事業を開始することで、審査が厳しくなる場合もあるでしょう。
また、株式公開をするまでには多くの手続きが必要なため、手間や時間がかかることもデメリットといえます。
6.事業承継に関する窓口で相談する
全国各地にある、事業承継の相談窓口の利用も検討しましょう。自社や身内だけでは解決できないことも、第三者のサポートを受けることで解決の糸口が見つかる可能性があります。具体的な相談窓口は、この記事の「後継者不足や事業承継の相談先」で解説します。
事業承継に関する窓口で相談するメリット
窓口で相談する場合のメリットは、主に以下のふたつです。
- 専門知識に基づいたアドバイスを得られる
- 事業承継の手続きもサポートしてもらえる
事業承継の専門家は幅広い専門知識を持っているうえに、多くの企業とのつながりもあります。的確なアドバイスを受けられるほか、条件に合う後継者を紹介してもらえる可能性もあります。
また、専門家であれば手続きまで一貫してサポートしてもらえる場合があるので安心です。
事業承継に関する窓口で相談するデメリット
窓口で相談するデメリットは少ないですが、依頼先への手数料の支払いが発生することがあげられます。報酬体系は各社で異なるため、依頼する前に確認することが大切です。
後継者不足や事業承継の相談先
ここまで解説したように、事業承継は早期の準備や取り組みが必要です。わからないから、忙しいからといって放置するのではなく、次のような相談窓口に連絡してみましょう。
- 公的機関
- 事業承継の支援を行う企業
1. 公的機関
事業承継の問題を相談できる代表的な公的機関は、次のとおりです。
| 相談先 | 相談できること | 設置場所 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 後継者不足やM&Aによるマッチングの検討など 事業承継に関すること全般 | 47都道府県 |
| よろず支援拠点 | 中小企業、小規模事業者の経営課題全般 | 47都道府県 |
事業承継のガイドラインなどの資料は中小企業庁により公開されています。
参考:中小企業庁 |事業承継ガイドライン(令和4年3月改訂)(P132)
2. 事業承継の支援を行う企業
事業承継に関する支援を行っている企業への相談もおすすめです。
後継者不足には早期の取り組みが重要
経営者は日々、資金繰りや従業員の育成など、さまざまな問題に直面しています。事業承継の必要性は理解していても、目の前の問題を解決することに意識が向いてしまうのは、当然のことといえます。
しかし、事業承継は決して遠い未来の話ではありません。候補者の選定から始まって、株式の譲渡や後継者の育成などを、日々の業務と並行して計画的に進める必要があります。
日本では後継者不足が大きな問題になっていますが、そのほかに「後継者候補は存在するけれど、さまざまな問題があってうまく物事が進まない」というケースも多いと考えられます。早めの取り組みや外部への相談によって解決できることもあるため、ひとりで抱え込まずに相談することが大切です。
事業承継に関するお悩みはボルテックスにご相談ください。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。