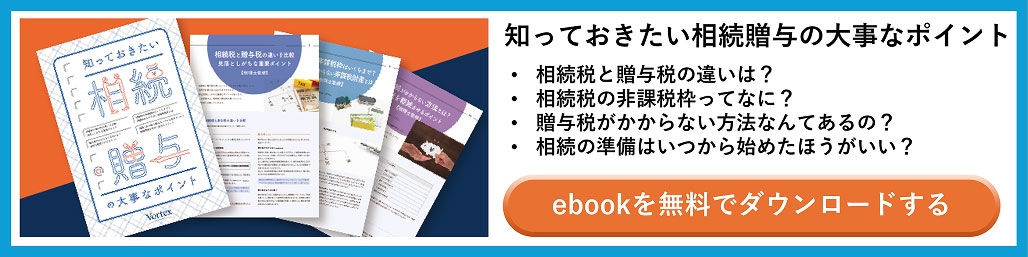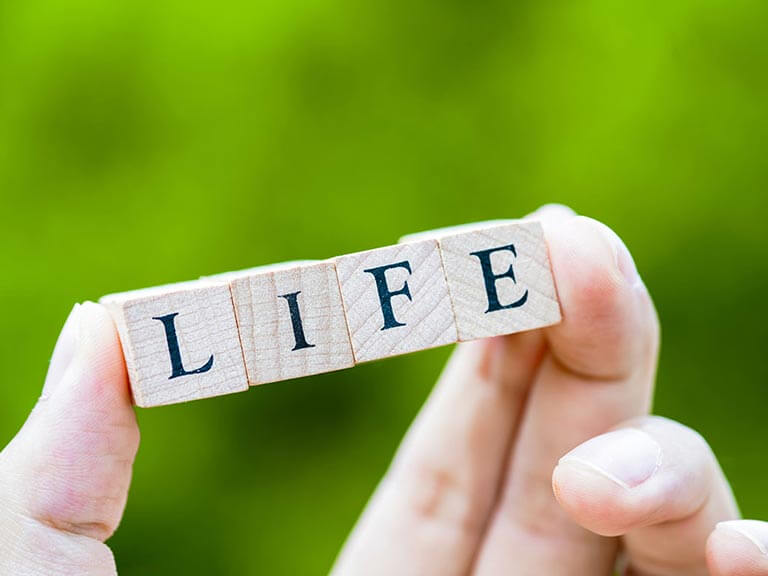目次
本記事に掲載された情報は、2025年4月22日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
夫婦間であっても、年間110万円以上の金銭を贈与したり、高額なプレゼントを贈ったりすると贈与税が発生する場合があります。一方、生活費や教育費の贈与、配偶者控除を利用した贈与であれば、非課税になります。夫婦間の贈与で課税されるかは、金額や資金の用途によって異なるため、贈与税の仕組みを知っておくことが大切です。
本記事では、夫婦間で贈与税がかかるケースとかからないケースを解説します。夫婦間で贈与をするときの注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
夫婦間の贈与でも贈与税がかかる
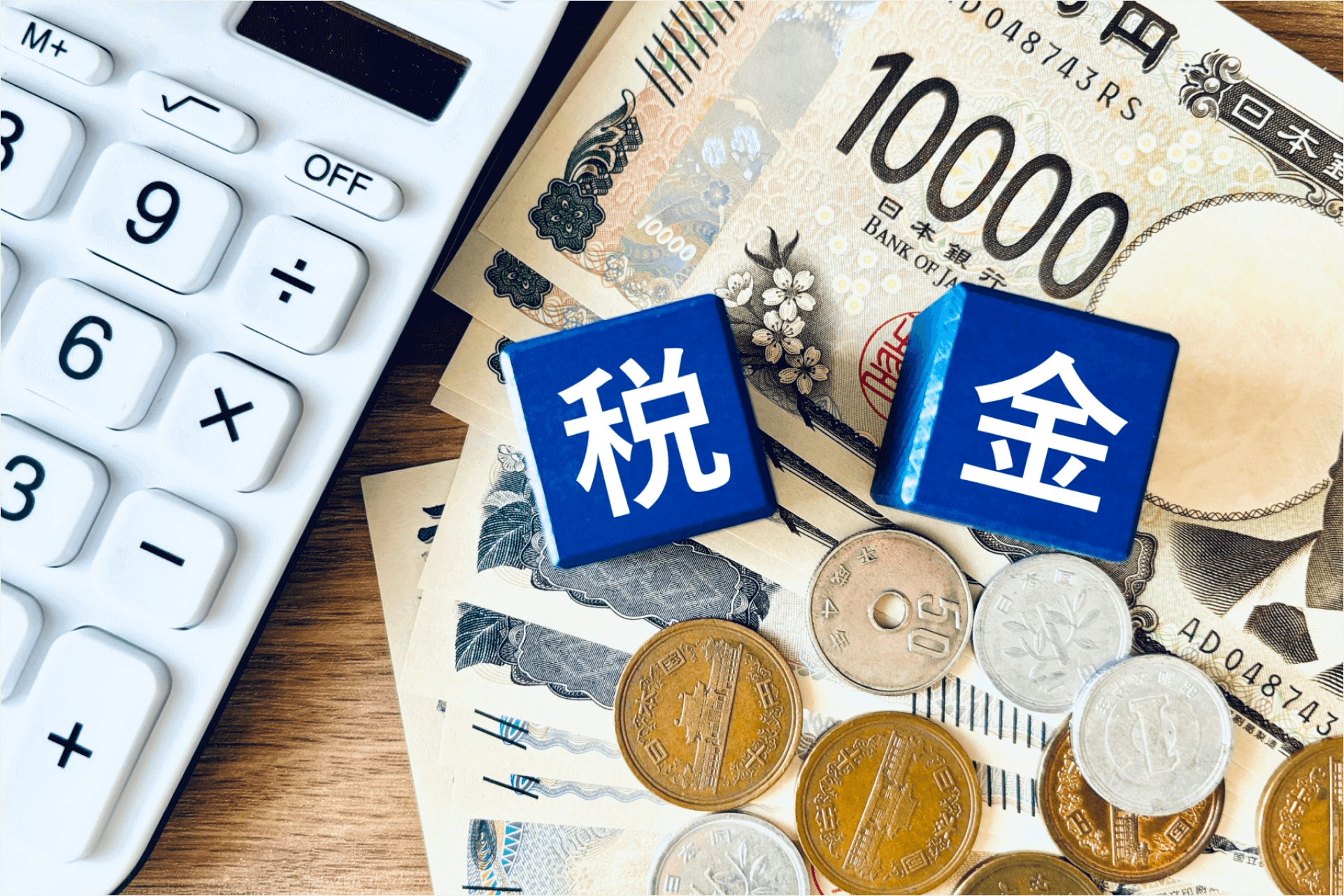
夫婦間の贈与でも、金額や用途によっては贈与税の課税対象です。贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金で、贈与者(贈与をする人)ではなく、受贈者(贈与を受ける人)が納めます。現金以外にも、不動産や宝石などの財産を贈る場合も贈与に該当します。
夫婦間で贈与税がかからないケース

夫婦間で贈与税がかからないのは、以下のようなケースです。
- 生活費や教育費を贈与する
- 110万円以下の贈与をする
- 贈与税の配偶者控除を利用して贈与する
それぞれ詳しく紹介します。
生活費や教育費を贈与する
夫婦には配偶者に対して扶助をする義務があります。たとえば、夫婦の一方に収入があり、一方に収入がない場合は、収入があるほうが配偶者の生活に必要な費用や子供の生活費、教育費を負担することになります。そのため、通常必要と認められる範囲の生活費や教育費には、贈与税がかかりません。
ただし、贈与した金銭を株式や不動産の購入費に充てるなど、生活費や教育費以外の目的で使用すると課税対象になる可能性があります。
110万円以下の贈与をする
贈与税は、原則として基礎控除の110万円を超える贈与に対して課税されます。そのため、夫婦間で生活費や教育費以外の金銭のやり取りをしたり、プレゼントを贈ったりしても、1年間に110万円以下の贈与であれば課税されません。
なお、贈与税の課税方式には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に基づいて、贈与税を計算する方法です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選べる制度です。この制度では累計2,500万円までの贈与が非課税となりますが、贈与者が亡くなったときに相続財産に持ち戻されるため相続税がかかる可能性があります。なお、年間110万円の基礎控除は、どちらの制度にも適用されます。
贈与税の配偶者控除を利用して贈与する
夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産の取得費用を贈与するときに「配偶者控除の特例」を活用すれば、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで贈与が非課税になります。この特例を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与対象の居住用不動産に住むこと
- その不動産に継続して居住する見込みがあること
この特例を利用すれば、婚姻期間が長い夫婦間で、自宅やマイホームの購入資金を贈与するときの贈与税が非課税になります。
夫婦間の贈与で贈与税がかかるケース

以下のようなケースは、贈与税がかかる可能性があります。
- 年間110万円の基礎控除を超える贈与をする
- 夫婦間で多額の預貯金を口座移動する
- 夫婦間で高額なプレゼントを贈った
- 夫婦間で高額な金銭の貸し借りをする
- 資金を贈与目的外で使う
- 不動産の持分割合と異なる取得費を負担する
- 契約者や受取人が異なる契約の保険金を受け取る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
年間110万円の基礎控除を超える贈与をする
年間110万円までの贈与は原則非課税ですが、年間110万円を超える贈与には税金がかかります。たとえば、夫が妻に生活費や教育費以外に使うための資金として150万円を1年間で贈与をした場合、110万円を超えた40万円分に課税されます。
夫婦間で多額の預貯金を口座移動する
夫婦間で預貯金の口座移動をした資金の用途が生活費や教育費であれば贈与税はかかりません。一方、夫が保有財産の一部を妻に譲渡するなど、贈与目的で移動させた場合は贈与税がかかります。
贈与税がかからないようにするためにも、生活費や教育費以外の贈与をするときは年間110万円以下に抑えるようにしましょう。
夫婦間で高額なプレゼントを贈った
夫婦間で年間110万円を超える贈り物をすると、贈与税が発生する可能性があります。たとえば、高額なアクセサリーや高級車は日常生活に必要な物品とみなされず、贈与税の課税対象となります。以下のような高額な物品を贈与した場合は、贈与税が課せられる可能性が高いでしょう。
- 不動産(土地や建物)
- 有価証券
- 骨董品
- 貴金属 など
夫婦間で高額な金銭の貸し借りをする
夫婦間で高額な金銭の貸し借りをする際に贈与税がかかる場合があります。無利子や返済期限を定めない貸し借りは、実質的に贈与と判断されることがあります。贈与とみなされないようにするには、金銭消費貸借契約書を作成し、贈与ではなく貸し借りである証拠を残しておくことが大切です。
資金を贈与目的外で使う
夫婦間の生活費や教育費の贈与には、原則として贈与税がかかりません。また、20年以上の婚姻期間がある夫婦間で居住用不動産の取得費用の贈与をした場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで非課税になる制度を利用できます。
しかし、生活費や教育費、住宅の取得費として受け取った資金を別の目的で使用すると、課税対象になってしまいます。たとえば、生活費として受け取った資金を株式投資に使うと、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。そのような状況を避けるためにも、夫婦間で贈与目的をしっかり伝えるようにしましょう。
不動産の持分割合と異なる取得費を負担する
夫婦で不動産を共同購入する際に、所有権登記の持分割合と異なる金額を負担すると、贈与とみなされる可能性があります。たとえば、持分割合が夫50%、妻50%であるにもかかわらず、夫が取得費の全額を支払った場合、妻への贈与と判断されることがあります。加えて、以下のようなケースも、贈与が発生していると判断されることがあるため注意が必要です。
- 夫名義で購入した住宅の頭金を妻が支払う
- 夫名義の住宅ローンを妻の資金で繰り上げ返済する
想定外の贈与とならないためにも、持分割合と住宅取得費の負担割合を一致させるようにしましょう。
契約者や受取人が異なる契約の保険金を受け取る
契約者や受取人が異なる契約の保険金を受け取る場合、贈与税がかかる場合があります。保険金が課税対象になるのかは、保険の種類や契約内容によって以下のように異なります。
| 保険金の種類 | 贈与税の対象となる契約内容 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる |
| 満期保険金や解約返戻金 | 保険料負担者と受取人が異なる |
たとえば、夫が保険料負担者・被保険者、妻が受取人となっている保険で、妻が満期保険金を受け取ったときは贈与とみなされます。保険契約を結ぶ際は、契約者・被保険者・受取人によってどのような税金がかかるのかを確認しておきましょう。
夫婦間で贈与するときの注意点
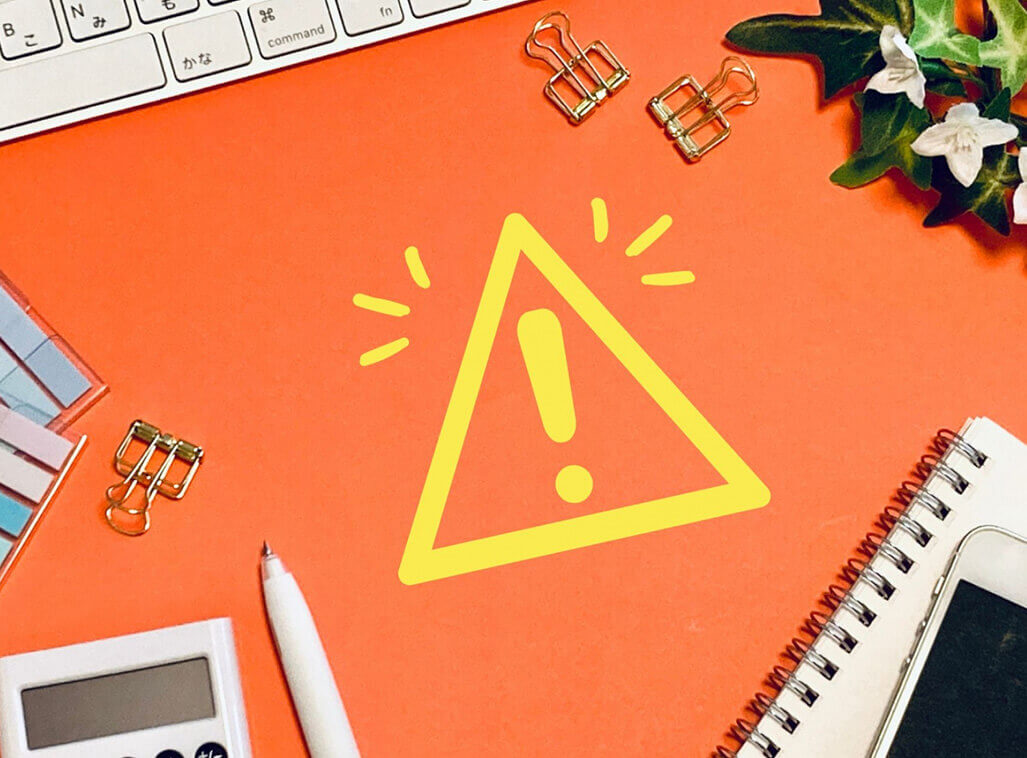
夫婦間で贈与するときは、以下の点に注意しましょう。
- 贈与税の配偶者控除を利用するには申告が必要になる
- 相続開始前7年以内の生前贈与には相続税がかかる
- 定期贈与とみなされると基礎控除内でも贈与税がかかる
ひとつずつ詳しく解説します。
贈与税の配偶者控除を利用するには申告が必要になる
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産、または居住用不動産の取得費用を贈与する場合、配偶者控除の特例を利用できます。配偶者控除の特例を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所を管轄する税務署で贈与税の申告が必要です。贈与税の申告時には、以下の書類を提出する必要があります。
- 贈与税の申告書
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の謄本または抄本
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の附票の写し
- 贈与を受けた人がその不動産を取得したことを証明できる書類(居住用不動産の登記事項証明書など)
配偶者控除の特例を利用して贈与税が0円の場合でも申告が必要です。申告が漏れると、特例の適用を受けられなくなり、通常通りの贈与税が課税される可能性があるため注意しましょう。
相続開始前7年以内の生前贈与には相続税がかかる
暦年課税制度を利用した生前贈与の場合、贈与から7年以内に贈与者が亡くなると、贈与財産の一部が相続税の課税対象になる可能性があります。これを「生前贈与加算」といい、令和5年度の税制改正によって適用期間が3年から7年に延長されました。
ただし、相続開始の4~7年前までの4年間に贈与された財産については、合計100万円までであれば相続財産に加算されません。たとえば、4~7年前に合計500万円を贈与し、直近3年間で毎年200万円ずつ贈与していた場合、加算対象となるのは総額1,000万円(500万円-100万円+200万円×3年)です。
7年の生前贈与加算が全面的に適用されるのは、令和13年1月1日以降に適用されます。それ以前の贈与に対する加算対象期間は、贈与時期によって以下のように異なります。
| 贈与時期 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
定期贈与とみなされると基礎控除内でも贈与税がかかる
毎年一定額を継続的に贈与することを「定期贈与」といい、年間110万円以内の贈与であっても贈与税が課税されることがあります。たとえば「3年間にわたって毎年100万円を贈与する」という契約のもとで贈与を続けたときに、「総額300万円の贈与をした」とみなされると贈与税の課税対象となってしまいます。
定期贈与とみなされないためには、毎年の贈与ごとに契約書を作成したり、通帳に記録を残したりすることが大切です。税務署に「その年ごとに独立した贈与」であることを証明できれば、定期贈与とみなされるリスクを減らせるでしょう。
夫婦間贈与に関するよくある質問

最後に夫婦間贈与に関するよくある質問に回答していきます。
夫婦間贈与はどのようにバレる?
夫婦間での贈与が税務署に発覚する主な要因は、相続時の財産調査です。たとえば、亡くなった配偶者の遺産状況を調べているときに過去の贈与が明らかになることがあります。贈与税申告がされていなかった場合は、延滞税や加算税などのペナルティが発生します。
離婚前の贈与は課税対象になる?
離婚前であっても、通常の贈与と同様に年間110万円を超える贈与は課税対象になります。離婚時の財産分与は原則として贈与税の対象外ですが、離婚前の贈与は課税対象となるため注意が必要です。
へそくりは課税対象になる?
専業主婦(主夫)が生活費として受け取ったお金で貯めたへそくりは、夫婦の共有財産として課税対象外となることが多いです。ただし、へそくりで高額な物品や金融商品を購入するなど、生活費ではない用途で使うと、贈与税の課税対象となります。
なお、生活費を渡していた配偶者が亡くなって相続が発生したときは、へそくりが相続税の対象となります。
夫婦間の贈与税に時効はある?
贈与税の時効は原則として6年間です。ただし、無申告や虚偽の申告があった場合は、時効が最長7年間に延長されることがあります。時効が成立する前に税務署に指摘されれば、ペナルティ(延滞税、加算税)を課せられます。そのような事態を避けるためにも、贈与が発生した翌年の2月1日から3月15日までに適切な申告をしましょう。
最後に
夫婦間で生活費や教育費のほか、年間110万円以下の贈与をする場合には原則税金はかかりません。一方、高額なプレゼントを贈ったり、金銭の貸し借りをした場合、贈与税がかかる場合があります。予期せぬタイミングで贈与税が発生するのを防ぐためにも、贈与税の仕組みや課税条件を把握しておきましょう。
しかし、非課税の範囲内で合っても例外的に課税される可能性はあります。不安な場合は専門家に相談をしておきましょう。
現金による贈与に加え、運用資産を活用した贈与を検討することも有効な手段です。運用資産を贈与する場合、市場動向や資産価値の変動によっては、贈与後に資産価値が上昇する可能性があるでしょう。また、定期的な運用益が見込める資産、例えば不動産のような賃料収入が得られる資産を贈与することで、受贈者に副収入を作ることができる可能があるでしょう。
しかし、不動産を取得する際に発生する高額な初期投資が大きなハードルとなる場合があります。このような課題の解決策として注目されているのが「不動産小口化商品」です。
不動産小口化商品は、従来の不動産投資と同様に運用益を得られる可能性がありながら、1口あたり数万円から数百万円といった額から投資を開始できる仕組みを提供しています。不動産に興味がある層にとって、ひとつの魅力的な選択肢となるでしょう。
ボルテックスでは、不動産小口化商品「Vシェア」を展開しています。「Vシェア」は、都心の商業地に位置するオフィスビルを対象とした商品であり、個人投資家でも1口100万円、最低5口から投資を行える仕組みです。これにより、従来の不動産保有のハードルを低減し、都心のオフィスビルへの投資を可能にしています。
不動産小口化商品をお考えの方はぜひ「Vシェア」をご検討ください。
※不動産小口化商品は、運用状況や市場動向によって損失が生じる可能性があります。また、不動産は流動性が低く、売却に時間がかかる場合があります。投資をご検討の際は、商品の詳細を十分に確認し、リスクを理解したうえで判断してください。
※投資額は商品ごとに異なり、追加の費用が発生する場合があります。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
もしくは
無料ご相談窓口
0120-948-827
受付時間 平日 9:30-18:00
今すぐの相談をご希望される方は
【無料ご相談窓口】までお電話ください。

記事執筆
萱谷 有香かやたに ゆか
叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー
大学卒業後は、英会話教材を飛び込み営業により訪問販売しておりましたが、一生働ける仕事をしたいと思い税理士を目指しました。
不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら、沢山の収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自分でも不動産投資を始めました。
現在では5棟の物件を保有しつつ、不動産投資家さんの気持ちがわかる税理士になるよう日々勉強し、色々な情報を集めています。
不動産投資専門の叶税理士法人(https://tax.kanae-office.com/)
生前贈与の記事一覧に戻る