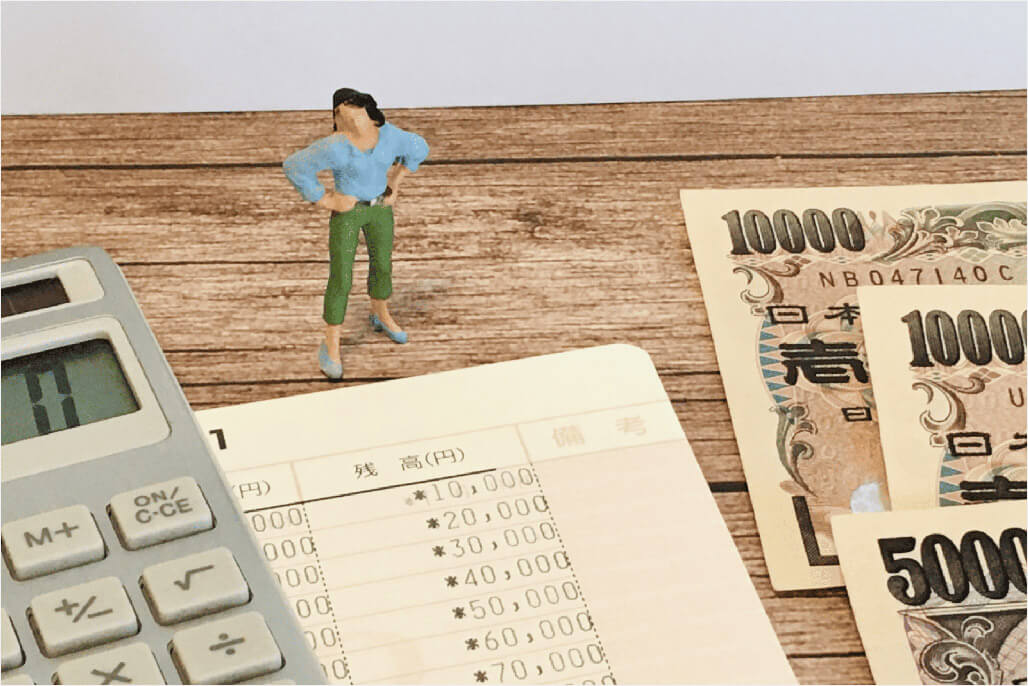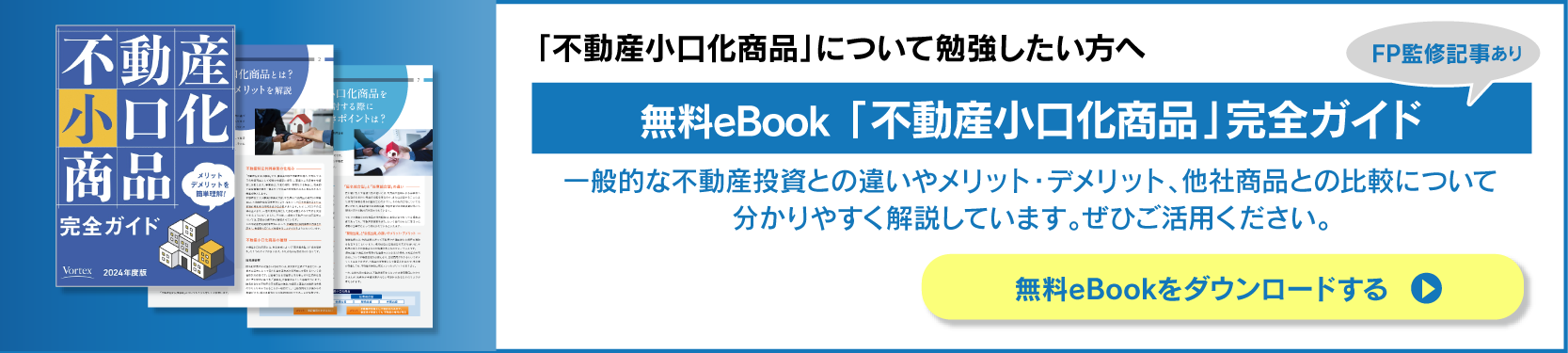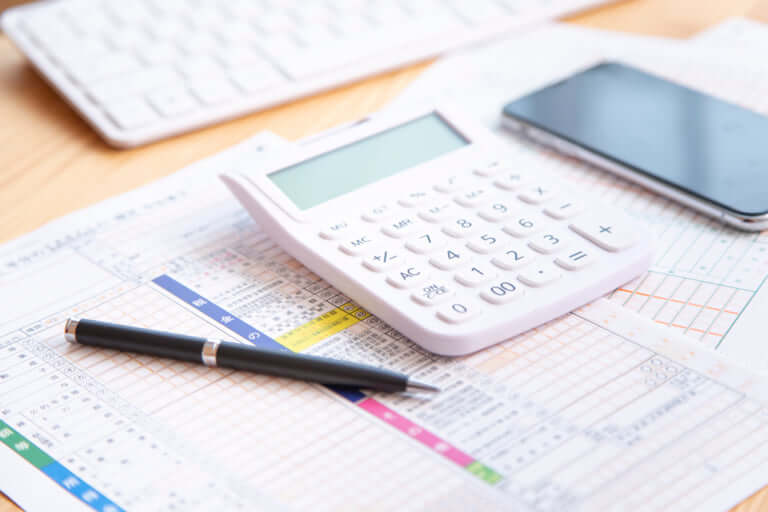目次
タンス預金について、銀行預金との違いや税金面の不安など、疑問をお持ちの方もいるかもしれません。まとまった現金を自宅に保管することは、いざというときにすぐに使える安心感がある一方で、考慮すべきリスクもあります。
本記事では、タンス預金とほかの資産運用の違いから、メリット・デメリット、法律・税金面の注意点まで幅広く解説します。将来に向けた資産の置き方も説明しますので、資産管理を見直すきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。
タンス預金とは

はじめに、タンス預金の定義や銀行預金との主な違いについて、把握しておきましょう。
タンス預金の定義
タンス預金とは、金融機関に預け入れることなく、自宅で現金を保管することを指します。かつては現金をタンスに隠して保管する家庭が多かったことから、このような呼び名が定着しました。
現代では、保管場所がタンスであるか否かにかかわらず、自宅に置いているまとまった現金の総称として「タンス預金」という言葉が使われるのが一般的です。金庫や引き出し、あるいはその他の場所に保管している現金もタンス預金に含まれます。
銀行預金との違い
タンス預金と銀行預金の大きな違いは、お金の保管場所と管理方法です。タンス預金は自宅で自己管理するのに対し、銀行預金は金融機関にお金を預け、金融機関が管理します。そのため、銀行預金には利息が付く可能性がある一方、タンス預金には利息は付きません。
また、銀行預金はATMや窓口で引き出す手間や手数料がかかる場合がありますが、タンス預金はいつでも手数料なしで使えます。しかし、銀行預金は盗難や災害時の紛失リスクが低いのに比べ、タンス預金はこれらのリスクを負います。
タンス預金のメリット

タンス預金には、銀行預金にはないメリットが存在します。特に、手数料がかからない点や緊急時への備えができる点は、タンス預金を選ぶ理由のひとつかもしれません。ここでは、タンス預金の主な2つのメリットを見ていきましょう。
- 手数料の回避
- 緊急時に現金をすぐ用意できる
手数料の回避
タンス預金のメリットのひとつは、銀行の各種手数料を気にする必要がない点です。
銀行預金では、ATMの利用時間や回数によっては時間外手数料が発生したり、ほかの銀行への振込には手数料がかかったりすることが一般的です。タンス預金であれば、このような利用時間や手数料の支払いを心配することなく、現金をそのままの形で手元に置いておけます。
緊急時に現金をすぐ用意できる
災害時やシステム障害などで金融機関の機能が停止した場合でも、タンス預金ならすぐに現金を用意できるというメリットがあります。大規模な地震や停電が発生すると、ATMが利用できなくなったり、銀行の窓口が閉鎖されたりする可能性があります。
そのような状況下でも、手元に現金があれば、当面の食料品や生活必需品の購入に充てることができます。また、急な出費が必要になった際にも、銀行へ行く手間や時間をかけずに対応できる点は、タンス預金の便利な点といえるでしょう。
タンス預金のデメリット
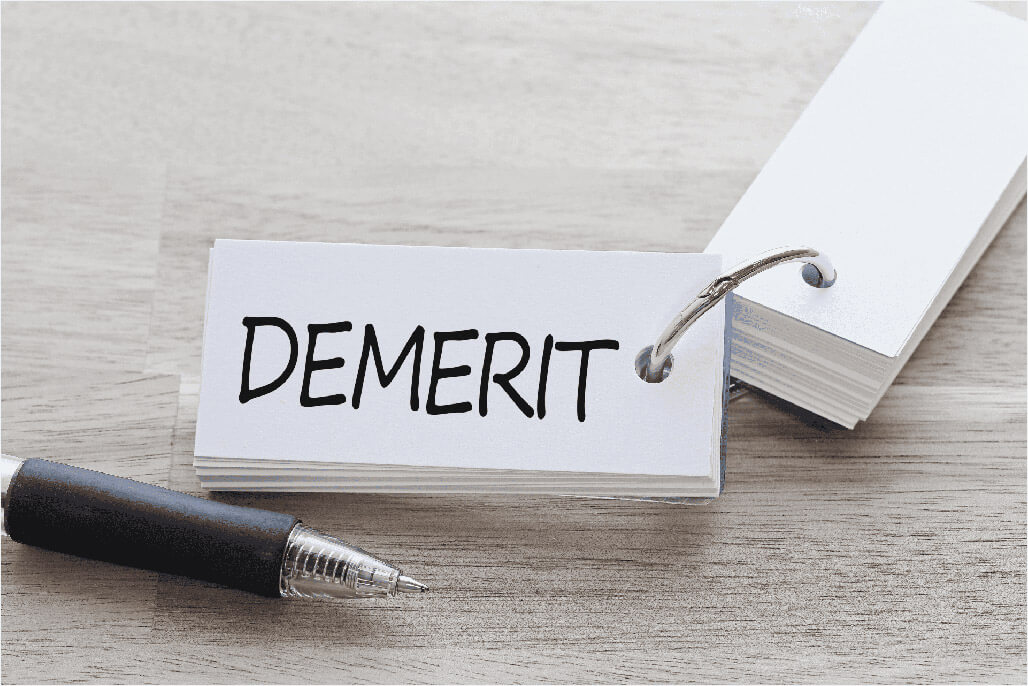
手軽さや安心感から選ばれることもあるタンス預金ですが、デメリットやリスクも存在します。資産管理を適切におこなううえで、これらの問題点を理解しておくことは不可欠です。ここでは、タンス預金の主なデメリットについて解説します。
- 盗難や災害によるリスク
- インフレ・金利変動の影響
- 相続・税金面で注意が必要
盗難や災害によるリスク
タンス預金のデメリットとして、盗難や災害によって資産を失うリスクがあげられます。空き巣などの犯罪被害に遭った場合、自宅に保管している現金は真っ先に狙われる対象となり得ます。
また、火災や水害、地震といった自然災害が発生した場合、現金がなくなったり、焼失したりする可能性も否定できません。
金融機関に預けていれば、このような物理的な滅失・毀損のリスクは軽減されますが、タンス預金の場合は自身で責任を負います。
インフレ・金利変動の影響
タンス預金は、インフレや金利変動の影響を受けやすいというデメリットがあります。インフレとは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。
タンス預金として現金を保有している場合、インフレが進行すると、同じ金額で購入できるものやサービスが減ってしまい、実質的な資産価値が目減りしてしまいます。
銀行預金であればわずかながらも利息が付きますが、タンス預金には利息が付かないため、金利上昇局面では機会損失が生じる可能性が考えられます。
相続・税金面で注意が必要
タンス預金は、相続や税金の面で注意が必要な点もデメリットといえます。故人がタンス預金を遺していた場合、その存在を相続人が正確に把握していないと、遺産分割協議が難航する可能性があります。
また、相続税の申告漏れにつながると、後にペナルティが科されるリスクがあるため、適切な取り扱いが求められます。詳しくは、次の章で解説します。
タンス預金に関わる法律・税金

タンス預金を保有している場合、法律や税金の観点から注意点があります。あらかじめ、以下のポイントを把握しておきましょう。
- 贈与税・相続税のリスク
- 税務調査と申告義務
贈与税・相続税のリスク
タンス預金は、贈与税や相続税のリスクにも注意が必要です。
たとえば、親が子にタンス預金の現金を渡し、それが年間110万円の基礎控除額を超える場合、贈与税の申告・納税が必要です。手続きを怠ると、後日税務署から指摘を受け、加算税や延滞税を支払うことになるかもしれません。
また、相続発生時にタンス預金の存在が明らかになった場合、ほかの相続財産と合算して相続税を計算します。
税務調査と申告義務
タンス預金であっても、相続財産の一部であることに変わりはなく、相続が発生した際には相続税の申告義務が生じます。税務署は、KSK(国税総合管理)システムなどを通じて、被相続人や相続人の資産状況、収入、過去の税務申告状況などを把握しています。
そのため、相続人の預金口座に多額の入金があったにもかかわらず、相続財産として申告されていなければ、税務調査の対象となる可能性があります。
申告漏れがあった場合には、修正申告とともに不足分の税金を納める必要が出てくるため、正確な申告が重要です。意図的に隠匿したと判断されれば、重加算税や延滞税などのペナルティが科されることもあります。
ほかの資産運用との比較

資産をどのように保有するかを考える際、タンス預金以外の選択肢と比較することは重要です。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、ご自身のライフプランやリスク許容度に合わせて選択する必要があります。
ここでは、タンス預金とほかの代表的な資産運用方法との違いや、リスク分散の重要性について解説します。
銀行預金や投資との違い
タンス預金は、銀行預金や株式投資、不動産投資といったほかの資産形成手段と比較すると、安全性、収益性の面で異なります。
銀行預金は安全性が高いものの収益性は期待しにくい点が特徴です。株式投資や不動産投資は、高い収益が期待できる反面、価格変動リスクや元本割れのリスクをともないます。
タンス預金は、すぐに現金化できるメリットがありますが、収益性はありません。さらに、盗難や災害、インフレによる価値減少のリスクがあります。それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが大切です。
リスク分散の重要性
資産運用において、リスク分散は基本的な考え方のひとつです。すべての資産をひとつの方法で保有・運用すると、その方法がうまくいかなかった場合に大きな損失を被る可能性があります。
たとえば、全財産をタンス預金にしていると、盗難やインフレのリスクが大きくなります。株式投資だけに集中すれば市場の暴落リスク、不動産投資だけなら空室リスクや災害リスクがあります。
複数の異なる種類の資産に分けて投資することで、特定のリスクが顕在化してもほかの資産でカバーし、全体として安定した運用を目指すことができます。
タンス預金を続ける場合の注意ポイント

タンス預金を選択する場合でも、そのリスクを理解し、適切な対策を講じることが大切です。防犯対策や災害への備えなど、万が一の事態に備えて、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 大金を保有するリスク管理
- 家族への共有方法
大金を保有するリスク管理
タンス預金として大金を自宅に保管する場合、盗難や火災、水害などのリスク管理が不可欠です。防犯対策としては、防盗性に優れた金庫の利用が考えられます。人目につきにくい場所に設置し、持ち去られにくい工夫をするとよいでしょう。
また、現金を一箇所に集中させず、複数の場所に分散して保管することもリスク軽減につながります。災害対策としては、防水・耐火性能のあるケースに入れたり、避難時にすぐに持ち出せるよう準備したりすることが重要です。ただし、完璧な対策は難しいため、自宅での保管額は必要最小限に留めるのが賢明です。
家族への共有方法
タンス預金の存在や保管場所を、信頼できる家族に共有しておくことは、万が一の事態に備えるうえで重要です。
もし自分に何かあった場合、家族がタンス預金の存在を知らなければ、後の相続トラブルの原因にもなりかねません。遺したお金を見つけられなかったり、相続手続きの際に申告漏れが生じたりする可能性があります。
共有する際は、どの家族に、いつ、どの程度の情報を伝えるか慎重に検討しましょう。エンディングノートなどを活用し、保管場所や金額の目安を記しておくのもひとつの方法です。
資産の「置き方」を見直す視点

低金利が長期化し、将来への不安も増す現代において、資産をどのように管理・運用するかを見直すことは重要です。タンス預金は現金を手元に置くという安心感がありますが、その他の選択肢にも目を向け、より賢明な資産形成を目指しましょう。
ここでは、資産の置き方を見直すための3つの視点を紹介します。
- 預けるだけでなく、資産として「動かす」選択肢
- 生活資金とは別に「守る資産」を設計する
- 形ある資産で「保有する」という考え方
預けるだけでなく、資産として「動かす」選択肢
現金をタンス預金として保有しているだけでは、インフレによって実質的な価値が目減りするリスクがあるうえに、資産が増えることもありません。
そこで考えたいのが、資産を「動かす」という選択肢、つまり投資です。投資にはリスクがともないますが、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用したり、不動産小口化商品のように比較的少額から始められるものもあります。
現金をただ寝かせておくのではなく、将来のために育てるという視点を持つことが、これからの時代には求められるでしょう。
生活資金とは別に「守る資産」を設計する
日々の生活に必要な資金と、将来のために「守りながら増やす」資産は、分けて考えることが大切です。生活防衛資金は、病気や失業など不測の事態に備えるため、すぐに使えるように銀行の普通預金やタンス預金で確保しておくのが一般的です。
一方、老後資金や子供の教育資金など、長期的な視点で準備するお金は、インフレに強く、安定的な成長が期待できる方法で「守る資産」として設計する必要があります。タンス預金だけに頼るのではなく、目的と期間に応じた資産配分を考えましょう。
形ある資産で「保有する」という考え方
現金は流動性が高い一方で、インフレに弱いという側面があります。そこで、現金の一部を「形ある資産」である実物資産として保有する考え方も有効です。実物資産の代表例としては、不動産や金(ゴールド)などがあげられます。
これらの資産は、インフレ局面で価値が上昇する傾向があり、現金の価値が目減りするリスクをヘッジする効果が期待できます。近年では、不動産小口化商品のように、個人でも比較的容易に不動産の一部を保有できる仕組みも登場しており、資産の置き換え先の選択肢として注目されています。
タンス預金のリスクを理解し、資産を守り増やす第一歩を
タンス預金は、手元に現金がある安心感や、手数料がかからないといったメリットがある一方で、盗難や災害、インフレによる価値減少といったリスクも存在します。相続時には税務上の問題が生じる可能性も考慮しなければなりません。
タンス預金のリスクを正しく理解したうえで、災害時の備えや生活防衛資金など、手元に置くべき必要額を見極めることが大切です。余剰資金は現金で保有するだけでなく、将来のために「守りながら増やす」という視点で活用することが賢明といえるでしょう。
資産を「守りながら増やす」ための選択肢のひとつが、不動産小口化商品「Vシェア」です。ボルテックスが提供する「Vシェア」は、都心のプライムエリアに立地するオフィスビルを1フロア単位(商品によっては区画単位)で保有できる仕組みです。
従来、このような好条件の物件は取得価格が高く、個人では手が届きにくいものでした。そこで、多くの方に購入いただけるよう、小口化した商品が「Vシェア」です。
購入は1口100万円・最低5口(最低口数は物件により異なる場合があります)から可能です。タンス預金の置き換え先として検討の余地があり、資産を分散しながら将来に備える手段としても有効です。リスクを抑えながら資産を守りたいと考えている方は、ぜひ「Vシェア」をご検討ください。
※不動産投資には元本保証がなく、市場環境や運営状況によって損失が生じる可能性があります。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
村井 英一むらい えいいち
ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士、証券アナリスト、宅地建物取引士)
1965年生まれ。大手証券会社で法人営業、個人営業、投資相談業務を担当する。2004年にファイナンシャル・プランナーとして独立後は、相談者の立場にたった顧客本位のコンサルタントを行う。特に、資産運用、住宅ローン、年金問題、ライフプランニングなどを得意分野とする。
家計の診断・相談室(https://kakeinoshindan.com/)
不動産投資の記事一覧に戻る