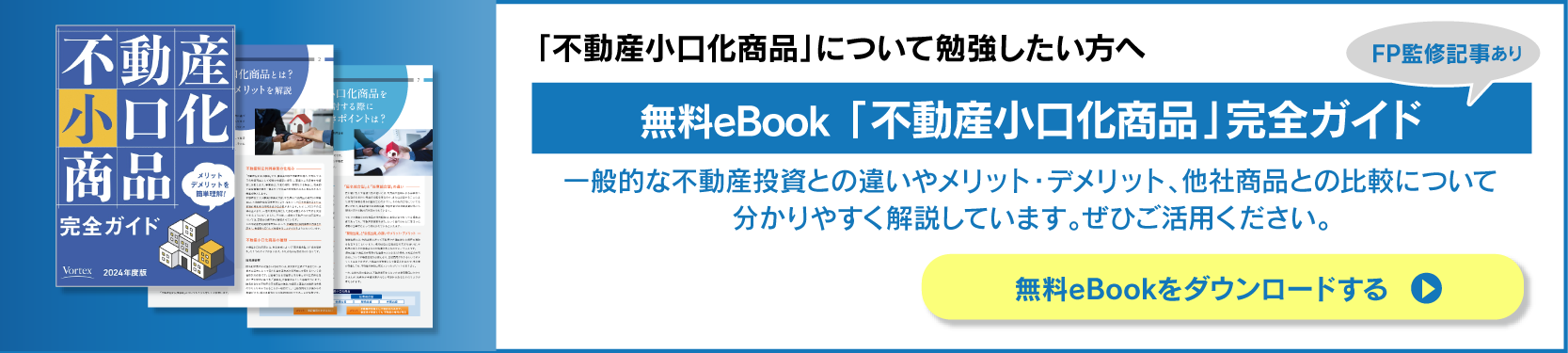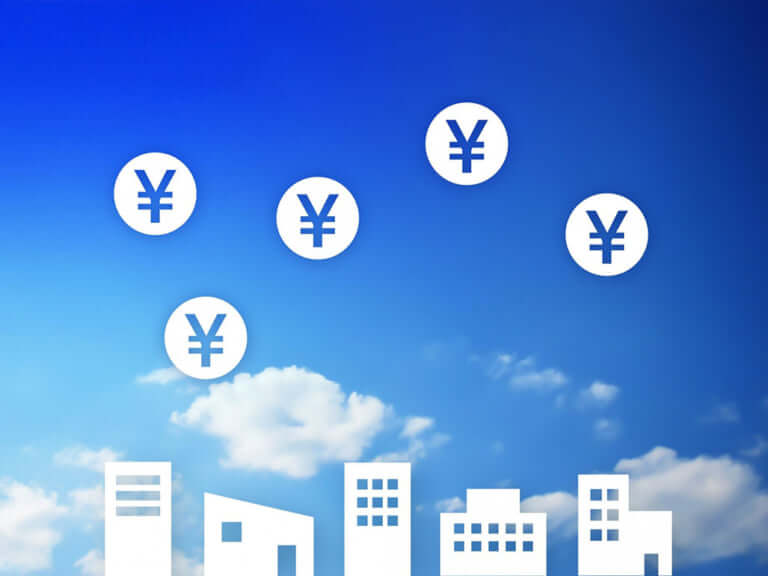目次
「年収1000万円を超えたら資産運用が大切」と聞いたことがありませんか?
年収1000万円を超えると、個人の所得税や住民税などの税負担が高まり、思ったほど手取りが増えないケースが少なくありません。そのため、将来のライフプランに合わせた資産形成を検討する必要があります。
本記事では、年収1000万円を超える場合の手取り額の変化を簡単にシミュレーションし、手取りの目安を理解していただきます。さらに、所得が高い会社員の方でも始めやすい投資信託や不動産投資などを例に、メリットと気をつけたいポイントをご紹介します。資産形成を考え始める第一歩として、ぜひ参考にしてください。
1.年収が1000万円超えたら資産運用が必要な理由
年収が1000万円を超えると、資産運用を始めるべきだとよく言われます。その背景には、いくつかの理由があります。ここでは、特に重要な3つのポイントをご紹介します。
1.税金負担の増加
年収が600~700万円を超えると、所得税の税率が高くなり、手取りが減少します。具体的には、所得税と住民税の税率が合わせて約30%となり、さらに雇用保険料や社会保険料も収入に比例して増加します。これにより、収入が増えても実際に使える金額が思ったほど増えないことがあります。
2.生活費の増加
収入が増えると、それに伴って生活レベルが上がることがあります。例えば、住居費のアップグレードや交際費、子どもの教育費などの支出が増える傾向があります。この結果、収入が増えても貯蓄が思うように増えないケースが多く見られます。
3.老後の不安
年収が高い人でも、老後の生活費や社会保障制度への不安は変わりません。むしろ、現役時代の生活水準を維持しようとすると、引退後にはより多くの貯蓄や資産が必要になります。そのため、若いうちから計画的な資産運用を行い、将来に備えることが重要です。
これらの理由から、年収が1000万円を超えた場合には資産運用を真剣に考える必要があります。手取り額の減少や支出増加に対応し、将来の不安を軽減するために、早めに資産形成をスタートさせることがポイントです。
2.年収1000万円の人が支払う税金と手取り額
年収が1000万円を超えたら、支払う税金と手取り額はどのように変化するのでしょうか。年収1000万円にかかる税金と手取り額をシミュレーションすると、以下のとおりです。
年収1000万円の会社員が支払う税金
年収1000万円に対する税金の種類と税率はこのようになります。
<年収1000万円にかかる税金の種類>会社員の場合
| 税金の種類 | 税率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 所得税 | 課税所得の20% | 330万円~694.9万円:20%(控除額:427,500円) |
| 住民税 | 課税所得の10%+均等割5000円 |
住民税10%の内訳は区市町村民税6%+道府県民税・都民税4% 均等割は所得金額にかかわらず一律で割り当てられる。年額5000円 |
| 雇用保険料 | 賃金の0.55%(0.65%) |
賃金には通勤手当なども含まれる 業種によって料率が変動する 毎年4月1日に更新 |
| 社会保険料 |
賃金の約15%前後 ※東京都を参考 |
健康保険料と厚生年金保険料(40歳からは介護保険料も徴収)を合わせた費用 勤務先企業と従業員が折半して負担する 毎年3月1日に更新 |
※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」、総務省「個人住民税」、厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」、全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
税金の大部分を占めるのが所得税です。所得税は課税所得額に応じて税率が変わる累進課税制度のため、年収1000万円の方は多くの場合、税率20%が適用されるでしょう。
※配偶者控除や扶養控除などにより課税所得は変動します
それに加えて住民税や社会保険料も課税所得または給与に応じて変動します。
年収1000万円の会社員の手取り額
これらの税金がかかると実際の手取り額はいくらになるのでしょうか。まず課税所得から計算してみましょう。
年収1000万円の独身者である場合、課税所得額は下記の通りです。
課税所得 = 給与収入 - 給与所得控除 - 基礎控除 - 社会保険料控除
6,307,000 = 10,000,000 - 1,950,000 - 480,000 - 1,262,212
※課税所得は1000円未満切り捨て
※住民税の基礎控除は43万円
<年収1000万円の会社員の手取り額の概算>
※例:35歳、東京在住、賞与なし、通勤手当なし、各種手当てなし、他控除なしで計算
※全国健康保険協会「令和7年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」より計算
※厚生労働省「令和7年度雇用保険料率(一般の事業)」より計算
※定額減税など考慮せず
| 収入 | 支出 | |
|---|---|---|
| 年収 | 10,000,000 | |
| 社会保険料 | 1,207,212 | |
| 雇用保険料 | 55,000 | |
| 所得税 | 833,900 | |
| 住民税 | 640,700 | |
| 計 | 10,000,000 | 2,736,812 |
手取り額=約7,263,188円
概算ではありますが。このように所得税、住民税、保険料を差し引くと、手取り額は726万円程度になります。
年収1000万円を超えたら家計にゆとりができると思われがちですが、実際は約3割程度を税金などが差し引かれます。※各控除などによって金額や税率は変わります。
3.年収1000万円の人の生活水準
次に年収1000万円の生活水準を考えみましょう。家賃相場は15~20万円、月ごとの娯楽費は3~10万前後が一般的です。また年収1000万を越えたら住宅ローンは5000万円~8000万円まで組めるといわれていて、立地や間取りなどの好条件の住宅を購入することもできます。
比較的ゆとりのある生活水準である一方、将来的な貯蓄を考えると安心できないという方もいるでしょう。さらに、高い教育水準を求める場合は子供の教育費も高くなります。
それに加えて、今後の日本は社会保険制度に不安があり、老後資金がより多く求められるとも考えられています。老後にも今と同じレベルの暮らしを維持するには、早い段階から将来を見据えた資産形成を検討する必要があります。
4.年収1000万円超えた会社員におすすめの投資
年収1000万を越えたら、将来的な子供の教育費や自分たちの老後に備えるために投資などで資産形成をすることが推奨されます。
安定した投資を希望する方におすすめの資産運用として不動産賃貸業があげられます。ですが、収益が賃料のみのため、安定的に収益を得るには賃貸されている必要があります。
物理的な資産である特徴から、建物が古くなったとしても、土地には一定の価値が残り続けます。このため、投資の元本が完全に失われる可能性は低いといえます。
また、少額投資や運用を委託できる不動産投資商品であれば、忙しい会社員でも資産運用を始めやすいでしょう。
少額で不動産投資ができる方法のひとつが不動産小口化商品です。特定の不動産を数万円~数百万円に小口化して販売し、収益を分配する投資方法で、不動産の管理・運用は事業者が行います。さまざまな不動産に分散して投資ができるため、空室のリスクを管理しやすいのもメリットです。
また不動産クラウドファンディングも少額から不動産投資を始められます。クラウドファンディング事業者は1つの不動産に対する資金を複数の投資家から集め、運営していきます。投資家は管理を委託しつつ、家賃収入などの分配を受けられる仕組みです。
インターネット上で掲載されている案件の中から投資したい物件を選べるため、マンションや住宅、商業施設など様々な物件から選べるため興味がある物件の動きや特徴を学ぶのにも最適です。
5.年収1000万円を超えたら資産をつくるのがおすすめ
年収が1000万円を超えたら、所得税などの税金が大幅に増えるため手取りは概算で720万程度になるのが一般的です。また生活レベルが上がるにつれ出費も増え、貯金がなかなか増えず、老後資金もより必要になる傾向がみられます。
そのため、年収が1000万を超えたら早くから将来に備えた資産形成を推奨します。
忙しい会社員の資産運用としておすすめなのは、比較的安定していてリターンが期待できる少額の不動産投資です。不動産小口化商品や不動産クラウドファンディングなど運営・管理を委託する投資方法をから始めるといいでしょう。
また、ボルテックスでは不動産小口化商品「Vシェア」を展開しています。「Vシェア」は、個人では購入が難しい都心のプライムエリアにあるオフィスビルを500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資が可能です。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
吉田 美子よしだ よしこ
Plus-プリュス- 代表
株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング 所属
日本では数少ない独立系FPとして、資産運用、相続、不動産、保険、リタイアメントプランなど年間延べ450組超のコンサルティングを実施。
キャッシュフローによる人生の可視化と正しい知識を身に付けることの重要性を女性FPの視点からお伝えしている。
Plus−プリュス−(https://www.fp-plus.net/)
不動産投資の記事一覧に戻る