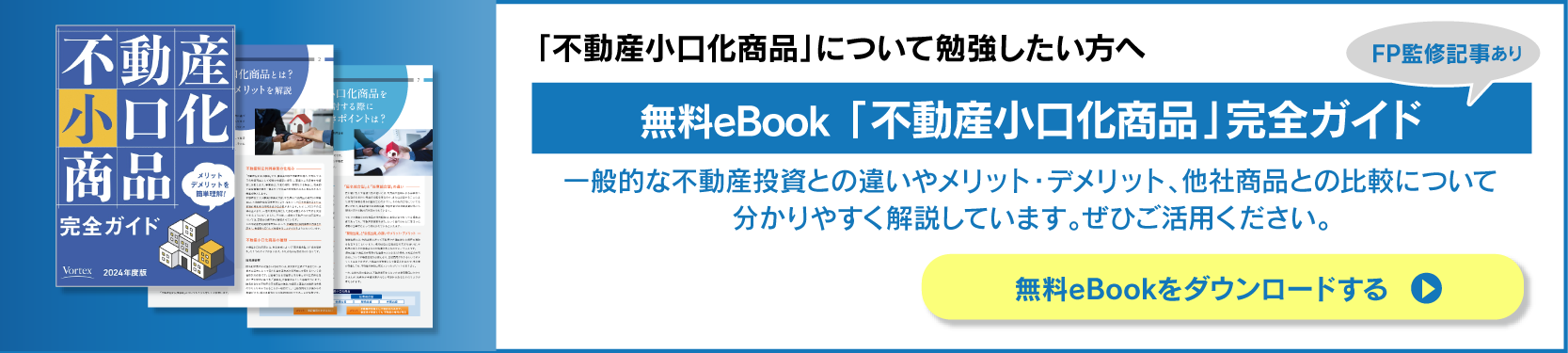目次
資産運用に興味があるものの、「リスクが大きい」「なんだか怖い」というイメージがあり一歩踏み出せない方もいるかもしれません。
しかし、投資にはさまざまな種類があるため、低リスクの金融商品を選べば堅実に資産形成をできるでしょう。
この記事では、資産運用のリスクの基礎知識と低リスクの資産運用について解説します。
1.資産運用リスクの考え方や種類
まずは、資産運用において「リスク」が何を指すのか確認しておきましょう。
資産運用におけるリスクとは?
資産運用におけるリスクとは「リターン(得られる収益)が不確実であること」「値動きの幅」を表します。
リスク=損をするというイメージを持ちがちですが、実際にはリターンの振れ幅が大きいことを「リスクが大きい」、リターンの振れ幅が小さいことを「リスクが小さい」といいます。
資産運用リスクの種類
資産運用のリスクは、リターンを左右する要因ごとに大きく6種類に分けられます。
価格変動リスク
金融商品の価格は、さまざまな要因により変動します。例えば、企業の業績や市場の需給バランス、さらには経済全体の状況などが価格に影響を与えることがあります。この変動によって、購入時よりも価格が下落して損失が発生する可能性があります。一方で、価格が上昇することで利益を得ることもありますが、予測が困難であるため、常にリスクが伴います。
金利変動リスク
金利の変動は、特に債券投資において重要な要素です。通常、金利が上昇すると債券価格は下落し、金利が低下すると債券価格は上昇します。この関係により、金利の変化が投資結果に直接的な影響を与えることとなります。そのため、金利の予測を誤ると損失が発生する可能性があり、投資家にとって注意が必要なリスクです。
為替変動リスク
外貨建ての金融商品に投資する際、為替相場の変動によって資産価値が変動するリスクが存在します。例えば、円高が進むと外貨建て資産の円換算額が減少するため損失が発生する可能性があります。このリスクは、為替市場の動向を注視しながらヘッジを行うことで軽減することができますが、完全に排除することは困難です。
流動性リスク
流動性リスクとは、金融商品を希望するタイミングで売却できない可能性を指します。市場で買い手が見つからない場合、資産を現金化できず、資産価値が大きく下がることもあります。このリスクは、取引量が少ない商品や市場が不安定な状況で特に顕著になります。流動性リスクを軽減するためには、取引が活発な商品を選ぶか、ポートフォリオ全体で流動性を確保することが重要です。
信用リスク
信用リスクは、債券やその他の金融商品の発行体が債務を履行できなくなる可能性に関連します。具体的には、企業や政府が経済的困難に陥り、利子や元本が支払われなくなるケースが該当します。このリスクは、発行体の信用格付けや経営状況を分析することである程度予測できますが、予期せぬ事態が発生する可能性もあるため、完全には回避できません。
カントリーリスク
投資対象地域の政治や経済の状況が変化することで、投資商品の価値が影響を受けるリスクです。例えば、政変や経済危機、自然災害などが発生すると、その国の金融市場が不安定になり、資産価値の下落を招く可能性があります。このリスクを管理するためには、対象国の情勢を継続的に監視し、分散投資を行うことが有効です。
リスクとリターンの関係性
資産運用において、リスクとリターンは比例します。低リスクの商品はリターンも少なく、高リスクな商品ではリターンも大きくなります。
低リスクで堅実に資産形成をしたい場合は、値動きの小さい金融商品を選ぶと安定的な運用ができるでしょう。ただし、繰り返しになりますがリターンも少なくなるため、効率的な資産形成には収益性も考慮したポートフォリオが理想的です。
2.資産運用を低リスクで始めたい方におすすめの投資商品
できるだけリスクを抑え、コツコツ資産運用をしたい方におすすめの投資商品を5つご紹介します。
定期預金・定期貯金
定期預金・定期貯金は、期間を指定して金融機関にお金を預ける方法で、元本保証がある低リスクな商品です。
指定した期間中にお金を引き出す場合は途中解約の手続きが必要ですが、普通預金より金利が高く設定されており、メガバンクよりネットバンクの方がさらに金利が高い傾向にあります。
将来の予定に合わせて預入期間を選べるため、資産運用のおおよその期間が決まっている方に向いています。
国債
国が発行している債券、個人向け国債も安全性の高い低リスク商品のひとつです。債券とは借用証書のようなもので、満期時に受け取れる額面や利子などの条件が決められています
元本保証はありませんが、「額面で買い取ること」「最低金利(年率0.05%)」は保証されています。1万円から投資できるため、初心者も始めやすいでしょう。
ただし、原則1年間は中途換金できません。また、中途換金時に手数料がかかるためタイミング次第で元本割れの可能性があります。
社債(事業債)
社債とは、企業が資金調達を目的として発行する債券です。個人向け社債は数十万円から購入でき、預貯金や国債よりまとまった資金が必要になりますが、比較的高い利率が設定されています。
同じく事業会社が発行する株式への投資と比べ、市場相場に左右されるリスクを抑えられます。また、社債は借入金ですので会社には返済義務があり、倒産時の弁済も株式より社債の保有者の方が優先されます。
外国債券(外債)
外国債券とは、発行市場、発行体、通貨のうちひとつ以上が外国にある債券のことです。円安になれば為替差益を受け取れる、発行体によって高い利回りを期待できるなどのメリットがあります。
債券投資自体は低リスクですが、外国債券では為替変動リスクやカントリーリスクなどが大きくなります。発行体の格付けを確認し、投資先を分散することでリスクを抑えられるでしょう。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をプロが債券や株式、不動産などに分散投資し、成果として生じた利益を還元する商品です。
1万円程度の少額から始められる上、豊富なノウハウを持つ投資のプロが運用してくれるため、投資初心者にとっては安心できます。
元本保証はありませんが、投資先を分散するパッケージ商品なのでリスクを軽減できます。しかし、収益性を重視するもの、堅実な運用を行うものなど、投資信託ごとに運用方針が異なるため、慎重に選ぶことが必要です。
3.低リスクで安定的に資産運用をするポイント
リスクを抑えながら安定的にリターンを得ている方には、いくつかの共通点が存在します。3つのポイントに分けてご紹介します。
分散投資をする
資産運用の基本は分散投資です。複数の投資先に資金を分けることで、資産全体で見たときの値動きの幅を小さくすることが期待できます。分散する対象は主に3つです。
- 資産:特徴の異なる金融商品を組み合わせる
- 地域:複数の通貨や地域を組み合わせる
- 時間:投資のタイミングを分ける
積立投資をする
積立投資は、長期的な視野に基づき、複数回に分けて定期的に資金を投じる手法です。
なかでも「定額購入法(ドル・コスト平均法)」は、毎回一定の金額を投資することで、市場価格の変動による影響を緩和する効果が期待できます。
具体的には、価格が上昇した際は購入量が減少し、価格が下落した際は購入量が増加するため、結果として購入単価が平準化される仕組みです。この手法によって、価格変動リスクを抑えながら、長期的な資産形成を図ることが可能となります。
長期運用をする
投資初心者であれば、資産運用は長期的な目線で行うことがおすすめです。
短期的な目線で行うデイトレードは大きなリターンも期待できますが、ボラティリティ(値動き)が激しく大きな損失を被る可能性もあります。
しかし、数年単位で同じ金融商品を保有すれば、短期的な価格変動リスクを受けることがなく、複利効果(※)を見込めます。
※運用益を元本にプラスして再び投資することで、利益が利益を生みふくらむこと
4.資産運用はリスクとリターンを考えたポートフォリオが大切
資産運用を始める際には「どの程度のリスクなら受けられるか」を明確にしておくことが大切です。
一般的に低リスクの金融商品といわれていても、日常生活に支障をきたすほど気になってしまうならリスクを取りすぎていると考えられます。
反対に、収入も資産もあり、年齢も若く、リスク志向な性格であればリスク許容度は高いと考えられるため、収益性が高い金融商品もポートフォリオに組み込むといいでしょう。
「低リスクだからいい」「ハイリスクだから危険」とは一概にいえないのが投資です。ご自身の運用目的に合わせ、ポートフォリオを組みましょう。
5.まとめ
資産運用においてリスクが大きいとは「リターンの振れ幅がおおきいこと」を指します。低リスクの金融商品は安全性が高いですが、リターンも少なくなります。
低リスクな資産運用の種類には、定期預金・定期貯金、国債、投資信託などがあります。安定的な運用をするにはそれぞれの特徴を理解し、長期的な目線で分散投資をすることがおすすめです。
分散投資には不動産投資を組み込むことでリスクを軽減できる場合があります。近年は少額から投資が可能な不動産小口化商品や不動産クラウドファンディングなどの商品が増えているため、分散投資がしやすくなっています。
また、ボルテックスでは不動産小口化商品「Vシェア」を展開しています。「Vシェア」は、個人では購入が難しい都心のプライムエリアにあるオフィスビルを500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資が可能です。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
投資の記事一覧に戻る