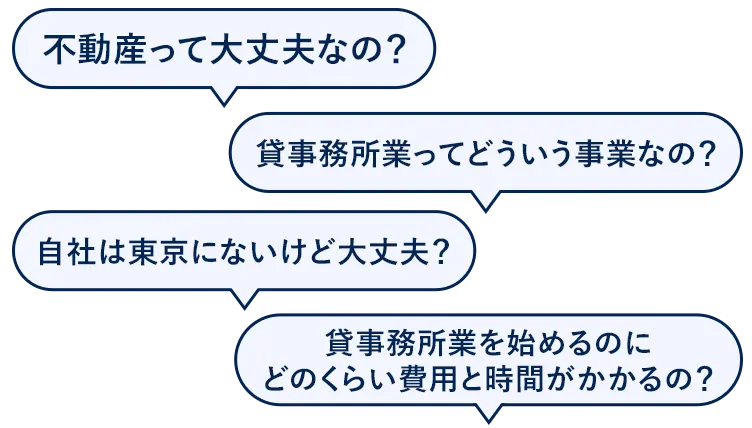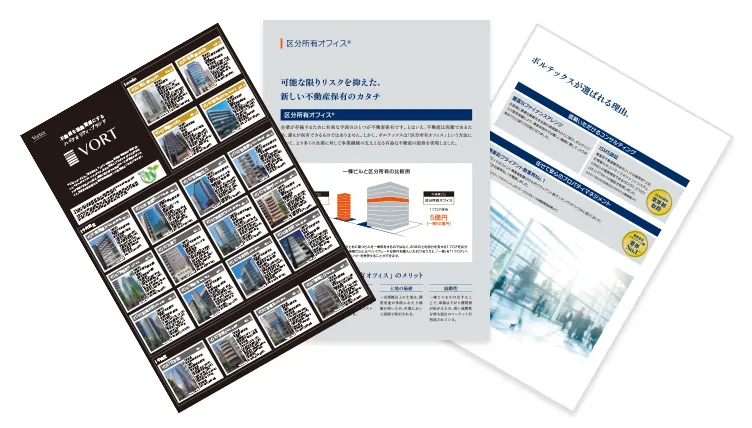持株会社を活用した事業承継とは|手順とメリット・デメリットを解説

目次
事業承継を行う際のひとつの方法として、持株会社を新設し、承継元である事業会社の株式を買い取ることで傘下に加える方法があります。
持株会社はホールディングスとも呼ばれるため、大企業のグループを想起しやすく、中小企業には無関係だと考える経営者も多いかもしれません。しかし、M&Aで中小企業を効率的にグループ化できるほか、中小企業の親族内承継で後継者に十分な資金がない場合にも、持株会社は重要な事業承継のスキームとして活用されています。
この記事では、持株会社による事業承継のメリットやデメリットを解説します。自社の事業承継の手段として、持株会社の設立が適しているかを考える参考にしてください。
持株会社とは

持株会社は、他社の株を保有してその会社の事業を支配する目的で作られます。事業承継のスキームで活用される際は、現行の事業会社の株式を取得して子会社化するために、後継者が代表となって設立される会社です。
持株会社は、次の2タイプに分けられます
- 純粋持株会社
- 事業持株会社
純粋持株会社は独自の事業を行わずに子会社からの株式配当のみを収入とし、事業持株会社は自らの事業も行います。
また持株会社は、中小企業での事業承継時に利用されるケースも多くあります。主に株式の分散防止など、親族内承継での課題解決に活躍します。
純粋持株会社とは
純粋持株会社は、自ら製造や販売などの独自の事業を行わない形態の持株会社を指します。1997年の独占禁止法改正以降に設置が認められた、比較的新しいタイプの持株会社です。
持株会社の目的である「別の会社の株式を保有すること」に特化し、そこから得られる株式配当のみを自社の売り上げとします。純粋持株会社は、複数の会社を子会社化しグループ全体の俯瞰した戦略立案などを担います。
事業持株会社とは
一方の事業持株会社では、純粋持株会社とは対照的に自身でも事業を行います。
子会社の管理を行いながら、自らの事業でも売り上げをあげる持株会社です。いわゆる一般的な親会社と子会社の関係とも言い換えることができるでしょう。
なお持株会社以外の事業承継スキームについてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
> 事業承継スキームとは?重要性と承継を成功させるための選択肢を解説
事業承継で持株会社を活用するメリット
持株会社を作り、承継元である事業会社の株式を引き受けることで事業承継を成立させる場合、次のようなメリットが得られます。
- 相続時の株式分散を防止できる
- 先代経営者が利益を得られる
- 自社株評価額が下がる可能性がある
承継を行う側の経営者と、後継者が双方ともに恩恵を受けられるでしょう。
1.株式の分散を防止できる
後継者が持株会社を設立し事業会社の株式を一括して買い取ると、経営者の相続が発生した際に株式が分散するリスクを回避できます。先代経営者がすでに手放した株式は相続時の遺産には含まれず、現金化された状態で相続されるため、事業会社の株式が後継者以外の相続人の手にわたることを防げます。
持株会社が株式を買い取ることで、代表である後継者はオーナーシップを発揮して事業会社を経営できるでしょう。
2.先代経営者が利益を得られる
多くの中小企業では、先代経営者が自社株式を保有しています。持株会社が事業会社の株主になる際に、経営者が自社株式を譲渡するため、手元には現金が残ります。
利益は個人の資産として、退職後の生活資金にも活用できます。自社株として保有したままでは現金化しにくいため、手元に現金を増やす手段として有効です。ただし譲渡した利益に対しては所得税がかかります。また、そのまま現金として残していた場合、先代経営者の相続が発生した際には、親族に相続税が課せられる可能性があります。
3.自社株評価額が下がる可能性がある
持株会社が、事業会社の株式取得資金を金融機関から借り入れる場合、事業会社の自社株評価額が下がる場合があります。これは、株価算定にあたっては負債額が会社の価値から差し引かれて計算されるためです。
株式譲渡にあたって生じる所得税や贈与税、相続税の負担額は、自社株の評価によって計算されるため、承継時に自社株評価額が下がれば課税額も下がります。
仮に持株会社を作らずに事業承継をする場合、後継者が自社株を個人として買い取るのは資金面で難しいケースが多いほか、無償で後継者が自社株の贈与を受けると贈与税がかかります。一方で、持株会社が自社株を買い取る場合には、後継者個人には贈与税が課せられなくなります。
ただし、意図的に税の引き下げを目的とした持株会社を設立しても、税務署に認められない場合もあることは念頭に置いておく必要があります。
事業承継で持株会社を活用するデメリット
持株会社への事業承継がスムーズに進んでも、デメリットを被る可能性があります。
- 配当金が少なければ融資の返済が滞る可能性がある
- 譲渡益が出れば先代経営者に課税される
- 租税回避行為として否認されるリスクがある
こうした懸念点について順に解説します。
1.配当金が少なければ融資の返済が滞る可能性がある
持株会社では、事業会社の株式を買い取るにあたって金融機関から融資を受ける場合が多くあります。返済の原資となるのは、事業会社の事業が順調に推移した結果得られる株式の配当金です。
入念な返済計画をたてたとしても、もし事業会社が安定して利益を上げられなければ配当金が少なくなり、返済が滞ってしまうリスクがあります。
2.譲渡益が出れば先代経営者に課税される
経営者が保有していた自社株を持株会社に譲渡する際、発生する譲渡益に対して譲渡所得税(譲渡所得税20%+復興特別所得税2.1%)が課税されます。
税額の計算式は次のとおりです。
譲渡所得税額 = (売却価格 - 取得費 - 売却にかかる手数料)×(20%+2.1%)
株式を売却したときの価格から、取得時の購入代金のほか、かかった購入手数料や購入時の名義書換料などを差し引いたものが課税対象金額にあたります。
なお譲渡所得は分離課税となるため、そのほかの所得とは分けて独自に税率を計算します。
3.租税回避行為として否認されるリスクがある
持株会社が承継の際に、意図的に事業会社の自社株評価を下げると、申告内容が税務署に認められない場合があります。
持株会社の設立から事業承継までの一連の行為が、租税回避を目的としていると見なされる可能性があるということです。
評価額の差額の目安や、どのようなケースで否認されるかの基準は明らかにされておらず「不当に株式の金額が下がっている」などと税務署長が判断する場合による(相続税法64条)とされています。
ただし租税回避行為として否認された場合でも、持株会社の設立、存続が認められないわけではありません。否認された場合は、追徴課税が求められるケースもあるでしょう。したがって持株会社の設立の前段階で税理士など専門家への相談をおすすめします。
事業承継で持株会社を設立する手順
持株会社を設立し、事業承継を完了させるまでの具体的な流れを整理しましょう。
主に次の5つのステップに分けて、解説します。
- 後継者が出資をして持株会社を設立する
- 金融機関から融資を受ける
- 事業会社の株式を買い取る
- 譲渡承認の請求を行う
- 持株会社の取締役会で承認手続をする
1.後継者が出資をして持株会社を設立する
まず、後継者の出資により承継先にあたる持株会社を新設します。持株会社の設立手続は通常の法人登記と同じです。したがって設立にあたっては最低限の資本金や手続にかかる費用のみを用意すれば十分です。
ただし持株会社には、承継元である事業会社の株式をすべて買い取るだけの資金を用意しなくてはなりません。先代経営者のもつ議決権を後継者に渡すために、持株会社が株式を受け入れる必要があるためです。
2.金融機関から融資を受ける
後継者自身に十分な資金がない場合は、持株会社の設立にあわせて株式取得のための資金調達を並行して行う必要があるでしょう。
持株会社は多額の借り入れを行うため、取締役会の承認を得るか取締役の過半数の同意を得なくてはなりません。
返済時には承継した株式からの配当が見込まれるため、事業会社の業績が順調であればスムーズに融資が受けられる可能性があります。
3.事業会社の株式を買い取る
融資がおりて資金調達できたら、持株会社が事業会社の株式を買い取ります。
株式譲渡契約書を取り交わし、持株会社が株式を取得すると現在の事業会社は子会社になります。これで事業会社の経営権が持株会社のオーナーである後継者に移るため、事業承継は完了です。
後継者個人としては株式の相続税、譲渡による所得税の負担がかかりません。また個人的な資金調達も不要な点は魅力でしょう。
ただし、次項で解説する「譲渡承認の請求」を先代経営者が行う場合には、株式を買い取る前に事業会社側の承認を得ておく必要があります。
4.譲渡承認の請求を行う
承継元の事業会社によっては、株式譲渡の承認手続が必要な場合もあります。多くの中小企業では、第三者による買収を防ぐため株式に譲渡制限がかけられており、取締役会や株主総会への譲渡の承認決議が求められるためです。
手続の流れを詳しく見ていきましょう。
- 承認の請求を行う
まず事業会社に譲渡承認を手続する際は、次のふたつのパターンがあります。
• 先代経営者が譲渡承認を請求
• 持株会社が先代経営者と共同で譲渡承認を請求
先代経営者は単独で譲渡承認を請求できます。株式譲渡の契約を取り交わす前に手続を行わなくてはなりません。前項「事業会社の株式を買い取る」前に手続が必須です。
一方、持株会社が請求する際は、先代経営者と共同で手続されます。この場合は、当事者間で譲渡契約を行った後に承認請求を行います。
- 承認決議をする
既存の事業会社の取締役会または株主総会で承認決議を行います。
これは先代経営者、持株会社との共同の2パターンの請求方法での差はありません。
取締役会が設置されている事業会社では取締役会にて決議されますが、取締役会のない会社では株主総会での特別決議を行います。
- 承認したことを通知する
事業会社側で譲渡が承認されたら、譲渡承認の請求を行っていた相手に承認の通知を行います。
先代経営者による単独請求の場合は先代経営者へ、持株会社が請求した場合は先代経営者と持株会社の双方へ通知する定めになっています。
5.持株会社の取締役会で承認手続をする
事業会社側で譲渡が承認されたら、譲渡承認の請求を行っていた相手に承認の通知を行います。
「重要な財産を譲り受ける」ため、会社法で決められたとおり取締役会での承認を得ましょう。取締役会がなく複数の取締役が存在する場合は、過半数の同意が必要です。
ここまでの手続を経て、事業承継は完了します。
事業承継の持株会社化を相談するなら専門家がおすすめ
事業承継の方法はひとつではありません。持株会社の設立が有利にはたらくか否かは、会社や経営者、後継者の状況によって最適解が異なり、自社だけで判断するのは容易ではないでしょう。
会社の未来を左右する事業承継に関しては、早めに専門家に相談することをおすすめします。事業承継の公的な支援機関も力を貸してくれます。
※期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
※税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合が

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。