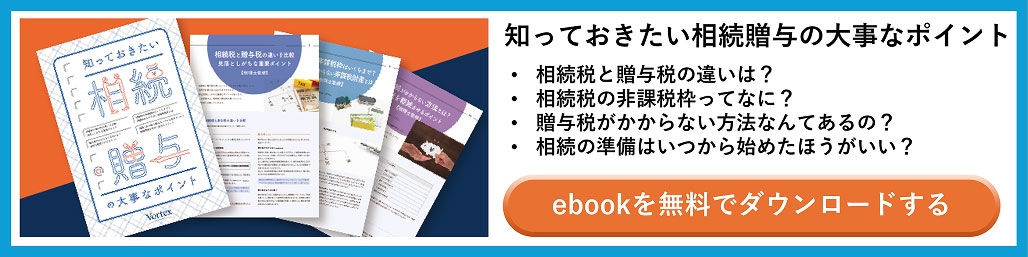目次
本記事に掲載された情報は、2025年8月1日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
孫への生前贈与を検討しているなかで、「どのような流れで贈与すればいいのか」「いくらから贈与税がかかるのか」といった疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。孫へ生前贈与をする際は、贈与の流れと非課税特例を知っておくことが大切です。
本記事では、孫への贈与の流れや非課税で贈与する方法を解説します。孫に贈与する際の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
孫に生前贈与をするメリット

孫への生前贈与には、1世代飛ばして財産を渡せたり、相続財産を減らせたりするメリットがあります。
ここでは、孫に生前贈与をするメリットを紹介します。
孫が資金を必要とするときに支援できる
孫に生前贈与をすれば、教育や住宅取得をするタイミングに財産を渡せます。孫は法定相続人ではないため、亡くなった子供の代わりに相続人となる代襲相続をしたり、遺言書を活用したりしない限り相続人にはなりません。
孫が資金を必要とするときに財産を渡したいのであれば、生前贈与がよいでしょう。
1世代飛ばして財産を渡せる
孫に生前贈与をすれば、1世代飛ばして財産を渡せます。通常、被相続人の財産は子供へ相続されたのちに孫へ相続されることになるため、孫が財産を受け取るまでに相続税が2回課されます。一方、祖父母から孫へ1世代飛ばして贈与すれば、相続税の課税が1回になります。
生前贈与加算の対象外となる
生前贈与加算とは、相続開始3~7年前に受けた贈与財産が相続財産に加算される制度のことです。生前贈与加算は、受贈者が相続人でなければ適用されないため、孫が相続人にならなければ、相続財産として加算されません。そのため、孫への生前贈与は、相続税の課税対象額を減らす効果が見込めます。
ただし、孫が代襲相続をしたり、遺言書によって相続人になったりすると、相続開始前3~7年以内に贈与された財産が相続財産に加算されるため注意しましょう。孫への贈与が生前贈与加算の対象になるのかわからない方は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
孫への生前贈与のやり方
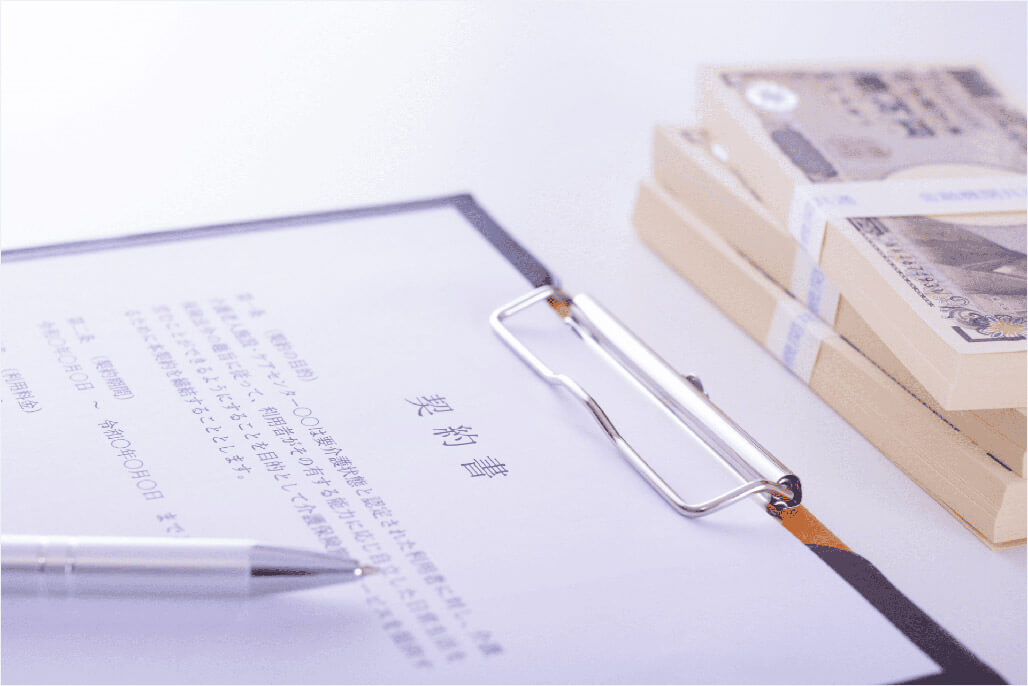
孫への贈与の流れは、以下のとおりです。
- 贈与契約書を作成する
- 財産を移す
- 贈与額が年110万円を超えたら贈与税申告をする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
贈与契約書を作成する
孫へ贈与する際は、財産を渡すたびに贈与契約書を作成することをおすすめします。贈与契約書とは、贈与内容を証明するための書類のことです。
贈与契約は口約束でも成立するため契約書の作成は必要ありませんが、税務調査や遺産分割時に生前贈与があった事実を客観的に示す証拠となります。相続時のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成しておくのがよいでしょう。
財産を移す
財産を移すときは、贈与契約書を作成するだけでなく、贈与したことを客観的に証明できる方法を選ぶことが大切です。たとえば、金融機関での振り込みを選べば、贈与日や金額、贈与者および受贈者の情報の履歴が残ります。一方、現金による手渡しは、贈与があった事実を証明できない可能性があり、トラブルの原因になることも考えられます。
贈与額が年110万円を超えたら贈与税申告をする
年110万円を超える贈与を受けたら、翌年の3月15日までに管轄の税務署に贈与税申告書を提出する必要があります。
贈与税は、以下のように計算します。
1.贈与財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を算出する。
[ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額 110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]

2.税率一覧表に基づき、贈与税を計算する。
孫への贈与では、受贈者である孫の年齢によって贈与税率が異なります。
その年の1月1日時点で18歳未満の孫への贈与では、以下の一般税率が適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、祖父から16歳の孫へ500万円を贈与するときの贈与税額は、以下のとおりです。
| 500万円-110万円=390万円 390万円×20%-25万円=53万円 |
18歳以上の孫への贈与では、以下の特例税率が適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
たとえば、祖父から19歳の孫へ500万円を贈与するときの贈与税額は、以下のようになります。
| 500万円-110万円=390万円 390万円×15%-10万円=48万5,000円 |
孫に非課税で贈与する方法

孫に非課税で贈与する方法には、以下のようなものがあります。
- 生活費や教育費として贈与する
- 年110万円以下の基礎控除額内で贈与する
- 相続時精算課税制度を活用する
- 贈与目的にあわせて特例の適用を受ける
それぞれ詳しく解説します。
生活費や教育費として贈与する
孫が必要とする生活費や教育費は、非課税で贈与できます。ただし、生活費や教育費として受け取った資金を目的外に使うと、贈与税がかかります。必要以上の資金を渡したり、タイミングが早すぎたりすると、別の目的に使ってしまう可能性があるので注意しましょう。
生活費や教育費を非課税で贈与したいときは、必要な金額を必要なタイミングに贈与することが大切です。贈与をするときは、贈与があった客観的な事実を残すために金融機関での振り込みを活用することをおすすめします。
年110万円以下の基礎控除額内で贈与する
受贈者1人につき年110万円以下の贈与であれば、贈与税がかかりません。孫への贈与を非課税にしたい方は、贈与額が年110万円を超えないように注意しましょう。
年110万円以下に収めるのが難しい不動産を贈与する際は、不動産小口化商品を活用する方法があります。不動産小口化商品とは、不動産を数万円から数百万円単位に小口化して販売する商品のことです。
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度とは、年110万円の基礎控除に加えて、贈与者ごとに特別控除額2,500万円まで非課税で贈与できる制度のことです。相続時精算課税制度の適用を受けたときの贈与合計額が特別控除額2,500万円を超えると、超過した部分に一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子供または孫に贈与する際に選択可能です。相続時精算課税制度には、累計2,500万円の特別控除とは別に年110万円の基礎控除があります。この控除を活用すれば、相続開始前3〜7年以内に年110万円以下の贈与をしていた孫が相続人になったとしても、相続財産に加算されません。
ただし、年110万円を超える贈与財産は、相続財産に加算されるため注意しましょう。
贈与目的にあわせて特例の適用を受ける
贈与目的にあわせて活用できる主な特例には、以下の3つがあります。
| 贈与税の特例 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円 |
| 結婚・子育て資金一括贈与 | 1,000万円(結婚資金は300万円) |
| 住宅取得等資金の贈与 | 省エネ等住宅:1,000万円 それ以外の住宅:500万円 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
教育資金の一括贈与の特例
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子供または孫が2026年3月31日までに教育資金の一括贈与を受けたときに、1,500万円まで非課税となる特例です。この特例を適用すれば、孫が教育資金を必要とするタイミングに資金援助することが可能です。
教育資金の一括贈与の特例の適用を受けるためには、受贈者が教育資金口座を開設し、金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出しなければなりません。契約終了日までに贈与者が死亡すると、口座残額が相続財産に加算されます。契約終了時点に残っている資金は、贈与税の課税対象となるため注意しましょう。
結婚・子育て資金一括贈与の特例
結婚・子育て資金一括贈与の特例とは、2027年3月31日までに18歳以上50歳未満の子供または孫に対して結婚や出産、子育てのための贈与をしたときに1,000万円まで非課税になる特例です。この特例の適用を受けるためには、受贈者が金融機関で結婚・子育て資金口座を開設したうえで「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
贈与者が契約期間中に亡くなると、結婚・子育て資金口座の残額が相続財産に加算されます。また、契約期間終了時点で口座に残っている資金には贈与税がかかります。注意しましょう。
住宅取得等資金の非課税の特例
住宅取得等資金の非課税の特例とは、2026年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築や取得、増改築のための資金の贈与を受けた子供または孫が、一定要件を満たすことで非課税で贈与を受けられる特例です。非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円です。
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅に住み始めるか、住むことが確実に見込まれる状態でなければなりません。ほかにも、建物の床面積や建築条件などの適用条件があるため、事前に確認しておきましょう。
孫に贈与する際の注意点
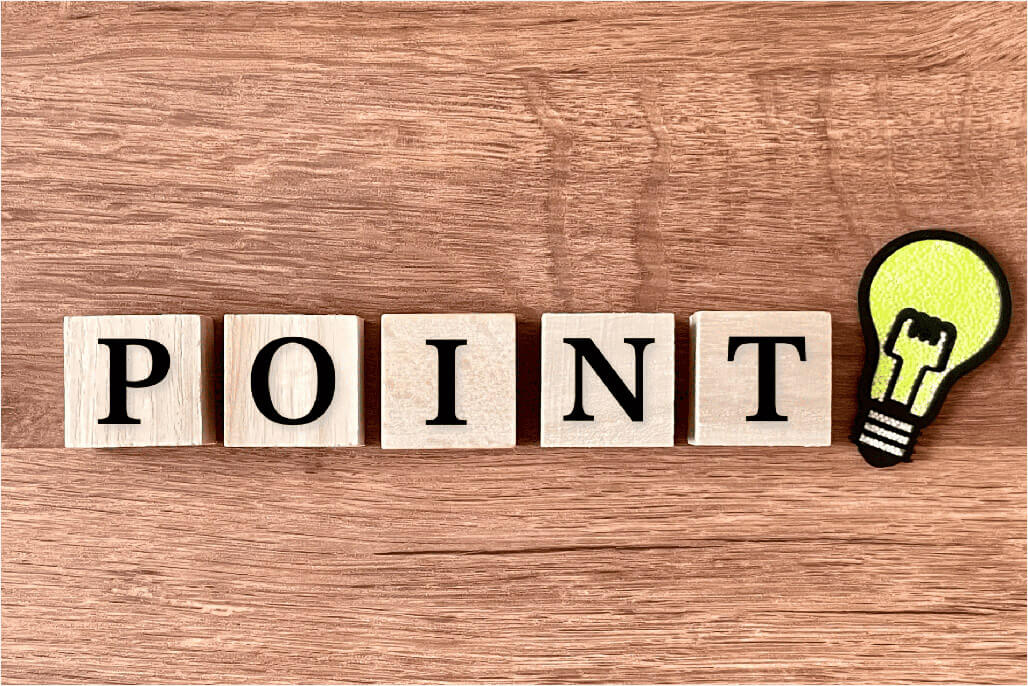
ここからは、孫へ贈与する際の注意点を紹介します。
想定外の税金を納めることになったり、トラブルになったりすることを避けるためにも、あらかじめ注意点を押さえておきましょう。
定期贈与と判断されると贈与税がかかる
基礎控除額110万円以下の贈与であっても定期贈与とみなされると、贈与税を課せられる可能性があります。定期贈与とは、あらかじめ決めた贈与額を分割して一定期間贈与することをいいます。たとえば、「1,000万円を毎年100万円ずつに分けて贈与する」といった取り決めをした贈与は、定期贈与とみなされる可能性が高いので注意しましょう。
定期贈与とみなされないためには、毎年の贈与時期や贈与額を変更したり、贈与のたびに贈与契約書を作成したりすることが大切です。
名義預金とみなされると相続税の課税対象になる
名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金のことをいいます。たとえば、祖父母が管理している孫名義の銀行口座が該当します。
名義預金にみなされると、贈与ではなく、名義預金の管理者(祖父母)の相続財産に加算されるため注意しましょう。そのような事態を避けるには、孫が通帳の管理をしたり、贈与のたびに贈与契約書を作成したりすることが大切です。
贈与した目的以外の用途で使わせない
贈与目的が限定されている非課税特例を活用するときは、目的以外で資金を使わないようにしましょう。贈与財産を目的外に使った場合は、贈与税が課されることになります。
これらの特例を受けたときは、金融機関から使用目的を証明する領収書の提出を求められます。領収書を提出できなければ贈与税の課税対象となるため、領収書を発行できるのかを支払い先に確認しておきましょう。
遺留分を侵害しない範囲で贈与する
孫へ贈与する際は、遺留分を侵害しないように配慮することが大切です。遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、親といった兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された最低限の相続割合のことです。遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分の相続権を主張するための遺留分侵害額請求をすることができます。
孫に多額の生前贈与をすると、法定相続人とトラブルになる可能性もあるため、推定相続人と話し合ったうえで贈与するようにしましょう。
最後に
生前贈与は、気持ちを込めて行う大切な手続きだからこそ、あとから誤解が生じないようにしておきたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
特に110万円以下の贈与であっても、契約書を用意しておくことで、やり取りの内容を整理しやすくなる場面もあるようです。
贈与契約書の書き方や注意点について、司法書士の監修による解説がありますので、よろしければこちらもご覧になってみてください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
税務の取扱に関する監修
マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン
渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)
生前贈与の記事一覧に戻る