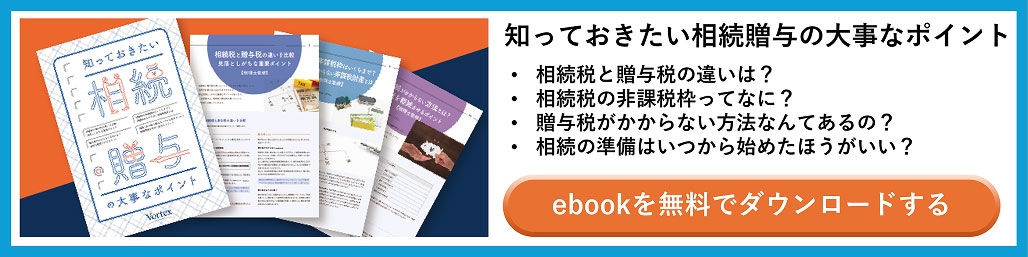目次
本記事に掲載された情報は、2025年5月19日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
贈与契約書は、自分の財産を無償で譲る人と受け取る人が合意した契約内容を証明するための書類です。贈与契約は口約束でも成立するため、契約書を作成しなければならないわけではありません。しかし、贈与契約書がなければ一方的に契約を取り消されたり、相続時の税務調査や遺産分割の際に生前贈与を受けたことを証明できなくなったりする可能性があります。トラブルを避けるためには、贈与契約書を作ることを推奨します。
本記事では、贈与契約書を作成するメリットや作成手順、贈与契約書の書き方と雛形を紹介します。贈与契約書を作成するときの注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
贈与契約書とは

贈与契約書とは、財産を贈与する際に任意で作成する書類です。たとえば、親が子供に結婚祝いを贈る場合や、祖父母が孫に教育資金を贈る場合などに作成します。
贈与契約は、贈与者(財産を譲る人)が財産を無償で与える意思を示し、受贈者(財産を受け取る人)が受諾する意思表示をするだけで契約が成立します。そのため、贈与契約書の作成は必須ではありません。
しかし、贈与契約を口約束だけで書面にしていない場合は、認識のずれが生じたり、一方的に契約を解除されたりする可能性があります。さらに、相続時の税務調査や遺産分割の際に贈与があったことを証明できないリスクがあります。そのようなリスクを避けるために、「いつ・誰が・誰に・何を贈与したのか」を明記した贈与契約書を作成するのです。贈与契約書の書き方は「贈与契約書の書き方と雛形」で解説しています。
贈与契約書を作成するメリット

贈与契約書の作成には、以下のようなメリットがあります。
- 一方的な贈与契約の解除を防げる
- 遺産分割トラブルを防止できる
- 名義預金や定期贈与ではないことを証明できる
- 不動産の登記手続きがスムーズになる
それぞれ詳しく解説します。
一方的な贈与契約の解除を防げる
贈与契約書を作成していない場合、すでに履行された部分を除き、贈与者または受贈者が一方的に贈与契約を解除できることが民法で定められています。
たとえば、親から子供へ現金300万円の結婚祝いを渡すという口約束をしていた場合、親子関係が悪化したときに親が一方的に贈与を解除することができます。子供が親からの贈与をあてにして結婚式や新居の準備を進めていると、資金が不足してしまう可能性があるでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、贈与契約の内容を明記した契約書の作成が大切です。
遺産分割トラブルを防止できる
相続が発生したときに、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をするか、法定相続分どおりに相続することになります。遺産分割協議では、公平な分割のために生前贈与を考慮した遺産分割をされるのが一般的です。
このとき、贈与契約書を作っておけば、生前贈与財産の内容を客観的に示せます。ほかの相続人から、実際に贈与を受けていた額よりも「多くの財産を生前にもらっていたのではないか」と主張されるのを防げるでしょう。
名義預金や定期贈与ではないことを証明できる
贈与契約書があれば、税務調査のときに名義預金や定期贈与でないことを証明できます。
名義預金とは、口座の名義人と管理者が異なる預金のことです。たとえば、親が子供名義の預金口座に入金し、預金通帳や印鑑を親が管理している状況が該当します。名義預金とみなされると、生前贈与ではなく相続税として課税される可能性があります。
定期贈与とは、一定額の資産を定期的に渡す方法です。たとえば、1,000万円を毎年100万円ずつに分けて贈与する場合などが該当します。暦年贈与の範囲である110万円以下であれば、贈与税はかかりませんが、定期贈与とみなされると、1,000万円を100万円ずつに分けただけだと解釈され、1,000万円に対して贈与税が課税されてしまうため、注意が必要です。
生前贈与であることを証明するためにも、贈与があったたびに贈与契約書を作っておくとよいでしょう。
不動産の登記手続きがスムーズになる
不動産を贈与した際は、不動産の名義人を変更する所有権移転登記が必要です。所有権移転登記申請をする際の添付書類のひとつに「登記原因証明情報」があります。登記原因証明情報とは、登記が必要となる原因を証明する書類のことです。
登記申請時に、贈与契約書ではなく贈与内容が分かる書類を作成して手続きすることもできますが、あらかじめ贈与契約書を作っておけば、その贈与契約書を登記原因証明情報として使用できるため、スムーズに所有権移転登記が申請ができるでしょう。
贈与契約書の作成手順

贈与契約書は以下の流れで作成します。
- 契約内容を決める
- 契約書を2通作成して署名捺印する
- 1通ずつ保管する
それぞれ詳しく解説します。
契約内容を決める
贈与契約書を作る前に贈与者と受贈者で話し合って契約内容を決めましょう。贈与によって贈与税が発生したときは、納税資金が必要になります。また、不動産を贈与するときは、不動産取得税や登録免許税などがかかる場合があります。
贈与の契約内容を決めるときは贈与財産だけでなく、受贈者が納税資金などの必要な費用を準備できるのかもチェックしておきましょう。
契約書を2通作成して署名捺印する
贈与契約書を双方が保管できるように同じものを2通作成し、割印を押しましょう。契約書の書式に決まりはなく、手書きまたはパソコンのどちらでもよいとされています。ただし、双方の合意があったことを証明するためにも、直筆で署名し、実印を捺印するのがおすすめです。
なお、契約者が高齢や手が不自由などの理由で署名できない場合は、住所や氏名をパソコン入力したうえで本人が捺印したり、家族が代筆したりしてもよいとされています。ただし、双方の合意があったことの信憑性を高めるために、第三者が立ち会って立会者も署名や押印をしたり、契約書作成時の様子を映像で残しておいたりするのがよいでしょう。
1通ずつ保管する
作成した贈与契約書は、贈与者と受贈者で1通ずつ保管しましょう。契約書の紛失が不安な人は、公正証書にするのも選択肢のひとつです。
贈与契約書を公正証書として作成すれば、原本が公証役場で20年間保管されるため、紛失の心配がなくなるでしょう。
贈与契約書の書き方と雛形

贈与契約書の書き方は、贈与財産の種類によって異なりますが、基本項目は以下のとおりです。
| ・ 贈与契約締結日 ・ 贈与者の住所や氏名 ・ 受贈者の住所や氏名 ・ 贈与財産の履行日と方法 ・贈与財産の情報 |
ここからは、財産の種類別に贈与契約書の書き方と雛形を紹介します。
不動産の贈与契約書
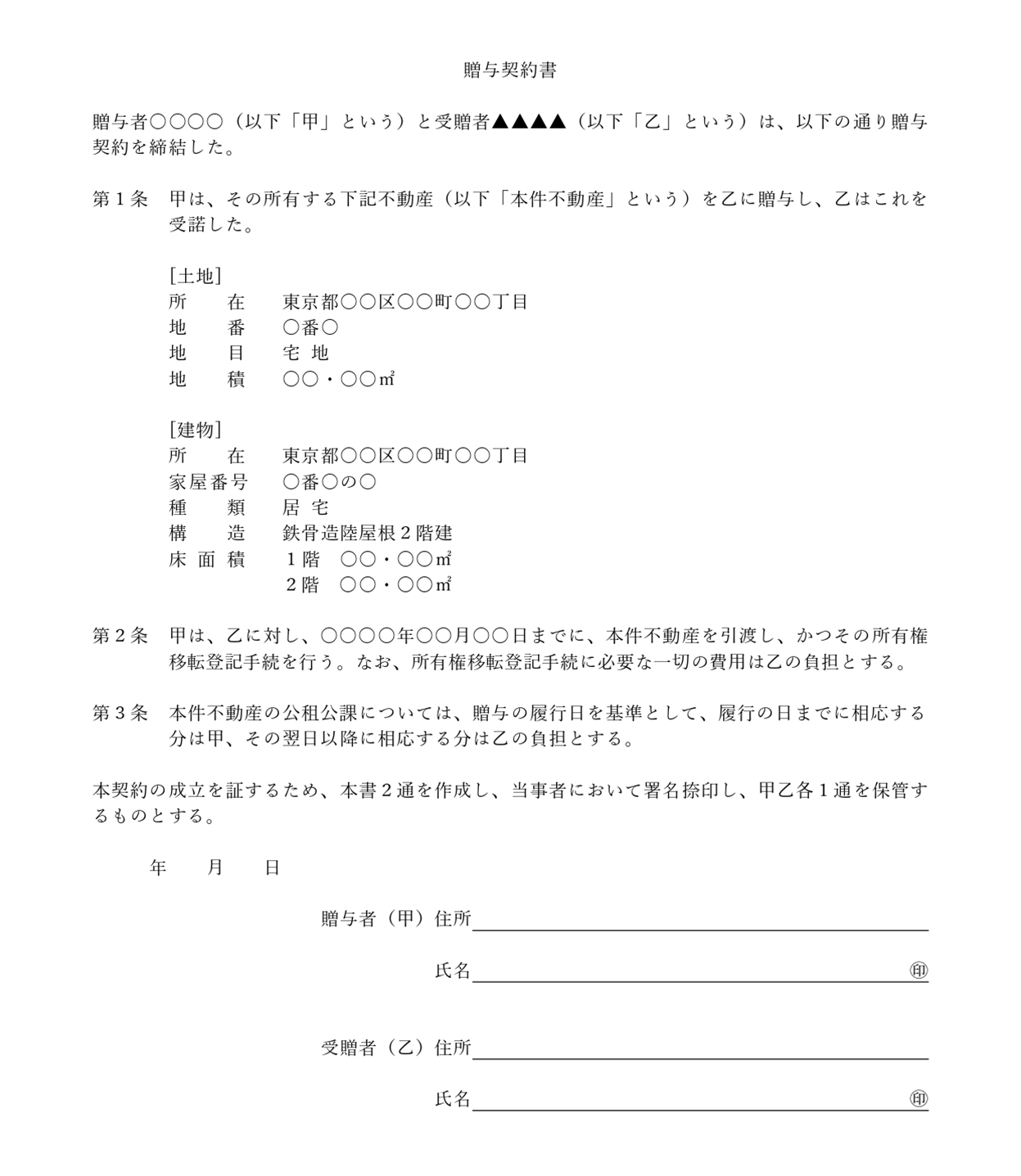
不動産の贈与契約書に記載すべき内容は、以下のとおりです。
| いつ | 贈与契約締結日、不動産の引き渡し日 |
|---|---|
| 誰が | 贈与者の住所や氏名 |
| 誰に | 受贈者の住所や氏名 |
| どのような財産を渡したか | 不動産の情報(所在、地番、家屋番号、種類、構造、地積、床面積など) |
| 注意点 | 地番や家屋番号を登記事項証明書のとおりに記載する1年の途中で贈与契約を締結する場合は、固定資産税の支払いについて明記する印紙の貼付が必要(収入印紙代は対象となる不動産の価格によって異なり、不動産の価格を記載しない場合の収入印紙代は200円) |
現金の贈与契約書
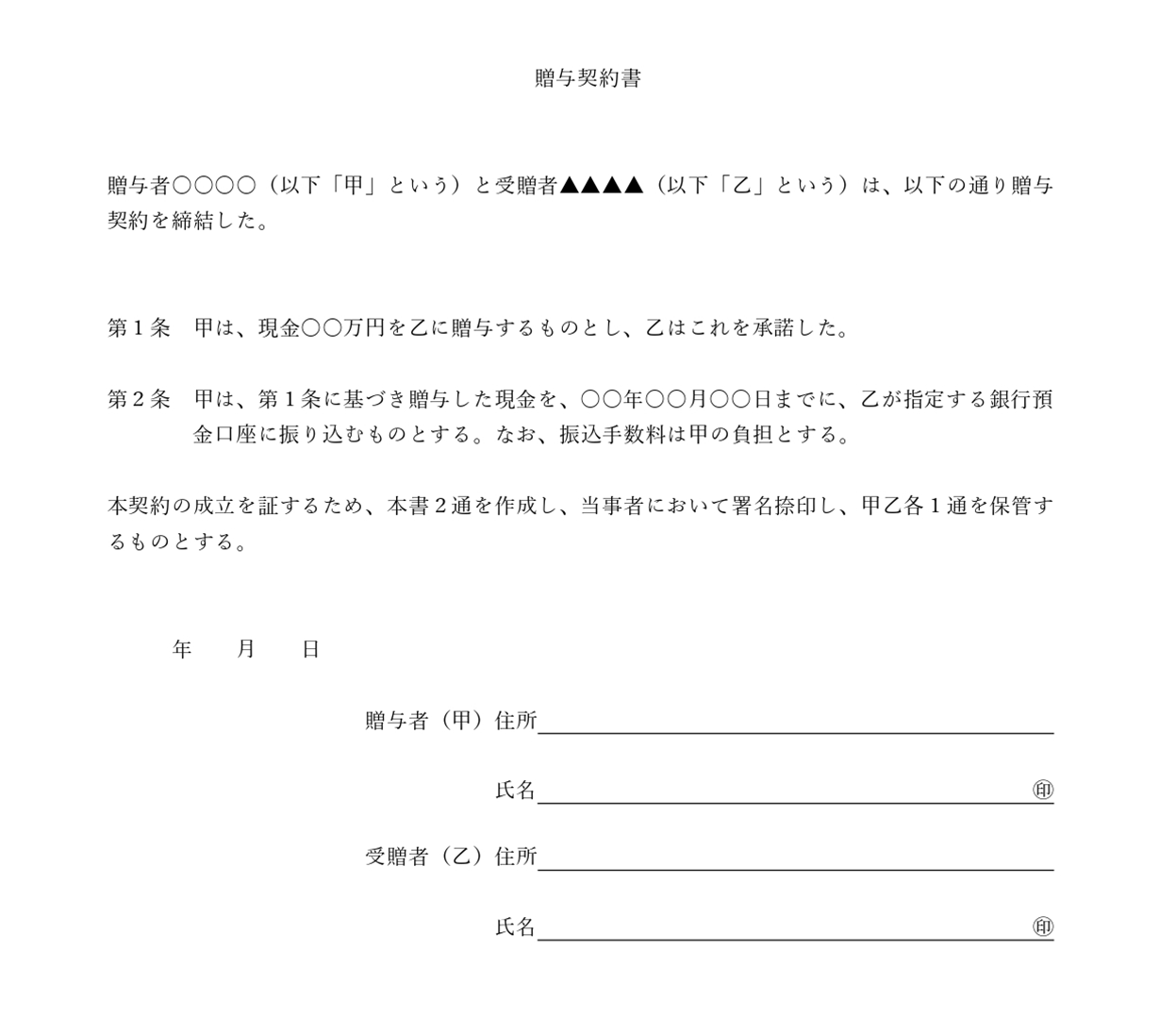
現金の贈与契約書に記載すべき内容は、以下のとおりです。
| いつ | 贈与契約締結日、現金を渡す(銀行振込する)日 |
|---|---|
| 誰が | 贈与者の住所や氏名 |
| 誰に | 受贈者の住所や氏名 |
| どのような財産を渡したか | 現金の金額 |
| 注意点 | 贈与の事実を残すために手渡しではなく銀行振込を利用する暦年贈与など複数回の贈与が予想される場合は、贈与のたびに贈与契約書を作る |
株式の贈与契約書
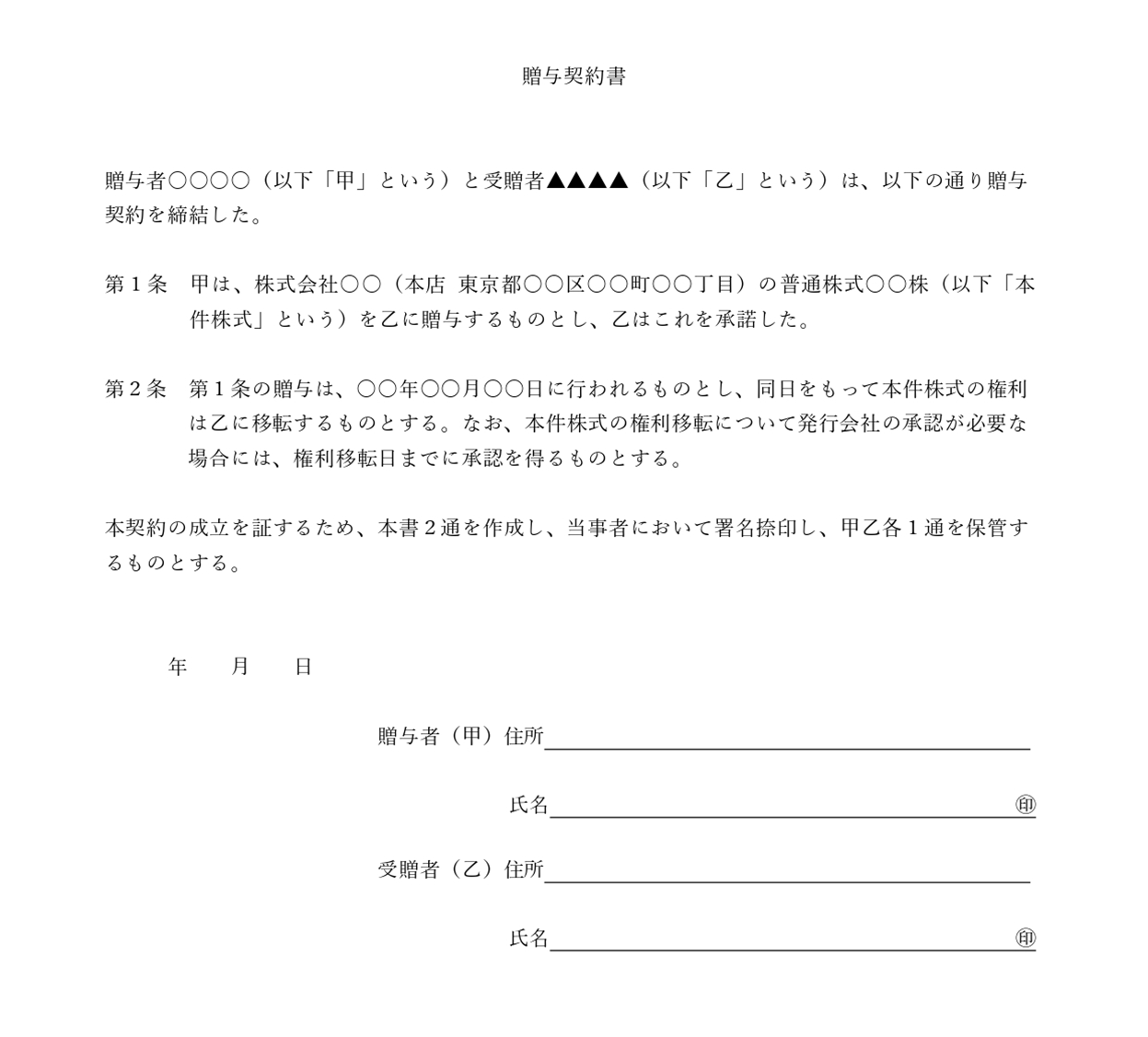
株式の贈与契約書に記載すべき内容は、以下のとおりです。
| いつ | 贈与契約締結日、株式を引き渡す日付 |
|---|---|
| 誰が | 贈与者の住所や氏名 |
| 誰に | 受贈者の住所や氏名 |
| どのような財産を渡したか | 株式の情報(会社名、会社の本店所在地、株券の記番号など)や種類、数量 |
| 注意点 | 非上場会社の場合、一般的に株式の譲渡には譲渡制限があり、株主総会や取締役会などの承認が必要 |
生命保険の原資となる金銭の贈与契約書
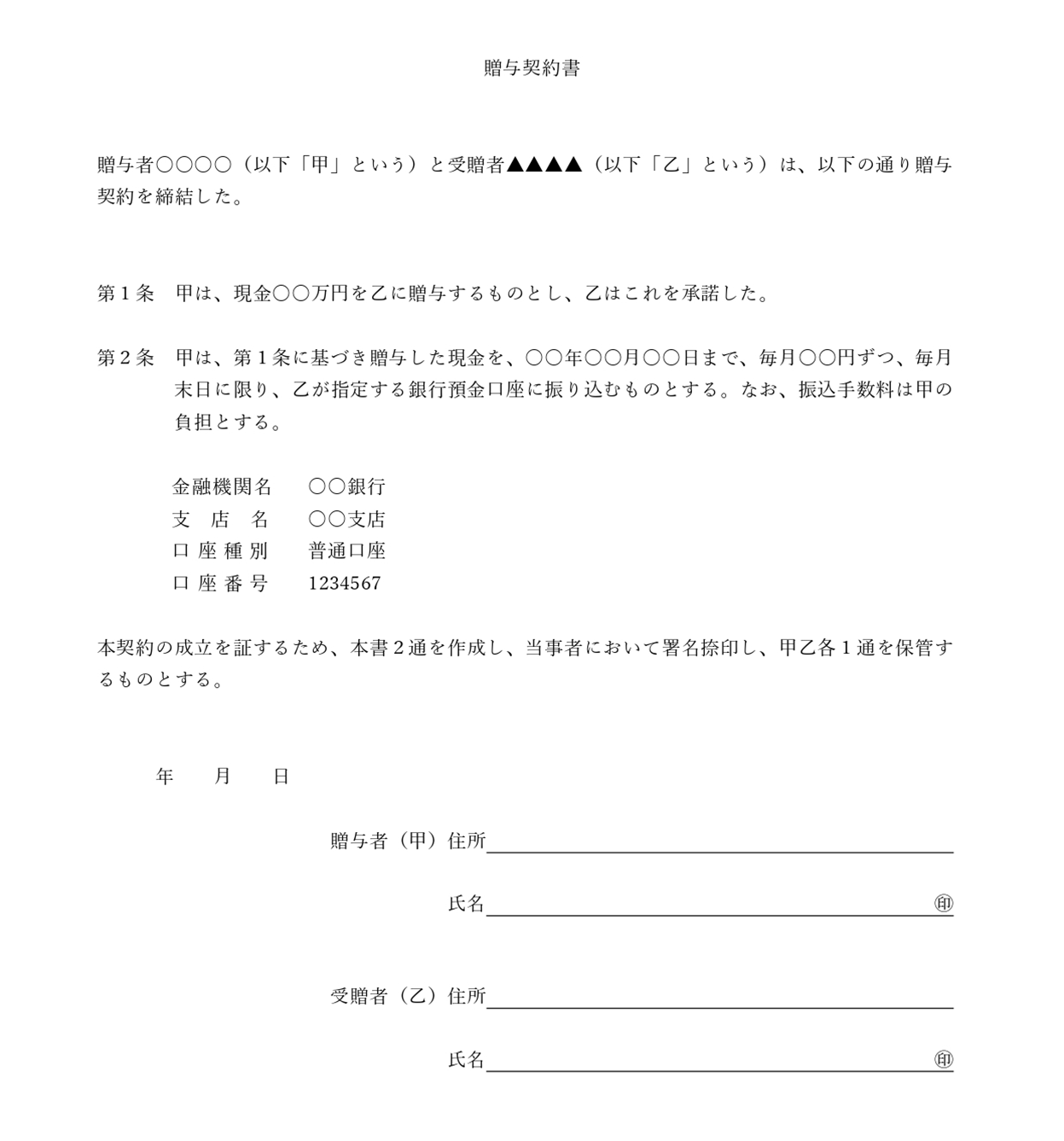
生命保険の原資となる金銭の贈与契約書に記載すべき内容は、以下のとおりです。
| いつ | 贈与契約締結日、生命保険料を渡す(銀行振込する)日 |
|---|---|
| 誰が | 贈与者の住所や氏名 |
| 誰に | 受贈者の住所や氏名 |
| どのような財産を渡したか | 現金の金額、振込先の口座情報(生命保険料の引き落とし口座情報) |
| 注意すべき点 | 暦年贈与の場合は、贈与のたびに贈与契約書を作る所得税の生命保険料控除が適用できるのは受贈者のみ |
贈与契約書を作成する際の注意点

ここからは、贈与契約書を作成する際の注意点を紹介します。
贈与財産の種類によっては収入印紙が必要
現金や株式を贈与する場合は、収入印紙の貼付は不要です。一方、不動産を贈与するときは、贈与契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
貼付する収入印紙の金額は、贈与不動産の価格によって異なります。贈与契約書に不動産の価格を記載しない場合は、200円の収入印紙を貼付しましょう。
未成年者は親権者の署名捺印が必要となることがある
18歳未満の未成年者も贈与者や受贈者として贈与契約を締結することができます。ただし、親などの法定代理人の同意を得ていない未成年者による契約は、あとで取り消すことが可能です。贈与契約を結んでから取り消されないためにも、贈与契約書を作成し、親権者に署名捺印をしてもらいましょう。
贈与のタイミングによっては相続財産に加算される
相続開始前に贈与された財産は、贈与のタイミングによって相続財産に加算されることがあります。2023年12月31日以前の贈与財産のうち、相続開始前3年以内に贈与された財産は、年間110万円以下の暦年贈与であっても相続税の課税対象です。
また、2024年1月1日以降の贈与財産は、以下のように段階的に相続財産に加算されます。
| 贈与者の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2024年1月1日~2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~相続開始日 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
なお、延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません。相続への取り組みとして生前贈与をする際は早めに始めましょう。
贈与契約に関するよくある質問

ここからは、贈与契約に関するよくある質問に回答します。
110万円以下でも贈与契約書を作成するべき?
110万円以下の贈与であっても、贈与契約書の作成がおすすめです。年間110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税となります。しかし、税務調査のときに生前贈与であることを証明できなければ、相続税を課せられることがあります。贈与があった事実を証明するためにも、110万円以下でも贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約が無効になることはある?
口頭による贈与契約は、一方的に解除することが可能です。また、贈与契約書を作成していても、以下のようなケースでは契約が無効や取消し、解除になることがあります。
- 詐欺や強迫によって契約を結んだ場合
- 重大な認識違いによって契約を結んだ場合
- 未成年者(18歳未満)が法定代理人の同意を得ずに契約を結んだ場合
- 贈与者が贈与を履行しないまたはできなくなった場合
- 贈与者と受贈者が解約に合意した場合
すでに贈与税を納付している場合は、更正の請求をすることで還付してもらえます。
贈与者または受贈者が亡くなるとどうなる?
贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じる「死因贈与契約」において、受贈者が贈与者より早く亡くなると契約が無効になることがあります。受贈者の相続人にスムーズに贈与したい場合は、死因贈与契約書に「受贈者が先に死亡した場合には、受贈者の相続人に贈与する」旨の条項を加えておきましょう。
最後に
贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与契約書がなければ一方的に契約を解除されたり、税務調査や遺産分割時に生前贈与の事実を証明できなくなったりする可能性があります。トラブルを避けるためには、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
なお、贈与契約書を作成していても、贈与のタイミングによって相続財産に加算されることがあります。相続のお取り組みとして生前贈与をするなら、早めに始めましょう。
生前贈与の非課税特例についてまとめた記事もあります。ぜひご参考ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
中島 美樹なかじま みき
一般社団法人 東京都不動産相続センター 代表理事
司法書士法人あかし 代表司法書士
東京司法書士会所属。司法書士試験合格後、司法書士試験の受験指導の講師を経験。都内司法書士法人で登記業務に従事し、その後独立開業。
年間100件近くの相談実績から、まずは現状を把握していただいたうえで、提案をオーダーメイドしてまいります。人生に何度もあるわけではない相続という経験を、心穏やかに過ごしていただくため、争いを防ぐ財産の分配方法を提案することはもちろん、なぜそのように財産を分配したのか想いの部分を大切にし、相続に心を込めた想いが続く想続を目指し、お客様のサポートをさせていただきます。
一般社団法人 東京都不動産相続センター(https://fudosan-sozoku.or.jp/)
生前贈与の記事一覧に戻る