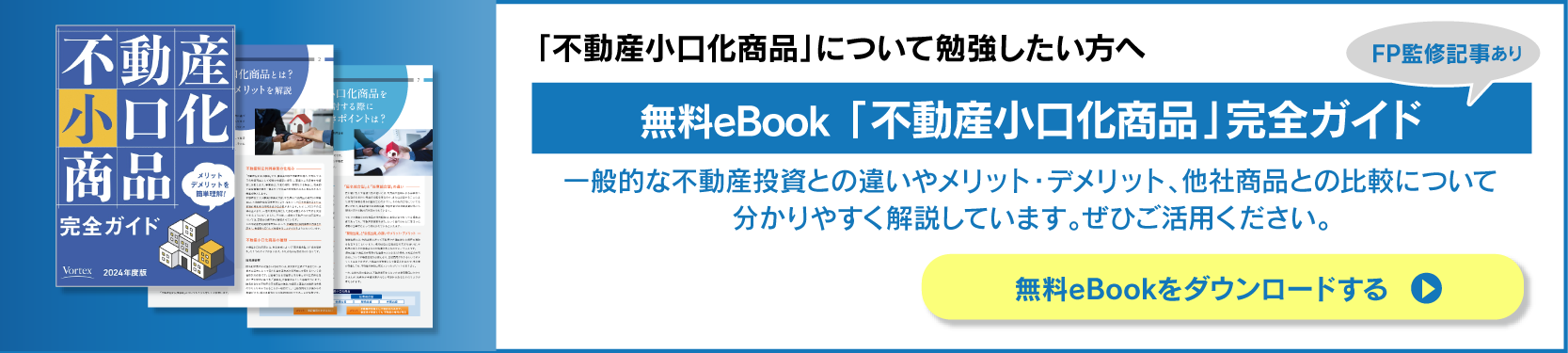目次
不動産投資を個人と法人どちらで取り組むほうが、メリットがあるのでしょうか。一般的に法人のほうが、メリットが大きいとされていますが、物件の保有数を問わず法人化したほうがよいかというとそうではありません。
本記事では、不動産投資を法人で行うことについて気になる方向けに、法人化のメリットや注意点、適切なタイミング、そして具体的な実践方法を解説します。
法人で不動産投資を行うメリット
不動産投資を個人ではなく法人として行う場合、さまざまなメリットがあります。ここでは、法人で不動産投資を行う主なメリットについて詳しく解説していきます。
経費に計上できる範囲が広い
法人で不動産投資を行う場合、個人と比べて経費として計上できる項目が多いです。具体的には以下のような項目が法人では経費として認められます。
- 役員報酬(家族を役員にして報酬を支払うことも可能)
- 役員退職金
- 生命保険料(法人契約の場合)※損金経理に一定のハードルあり
- 福利厚生費
- 交際費(一定の制限あり)
例えば、個人事業主の場合は家族に支払う給与は原則として経費にできませんが、法人であれば家族を役員や従業員として雇用し、その報酬を経費として計上することが可能です。
※勤務実態は必要です
融資を受けやすい場合がある
法人名義での不動産投資は、個人と比較して金融機関からの融資を受けやすい傾向にあります。一般的に、法人は個人よりも信用力が高いと見なされることが多く、特に本業で安定した収益を上げている法人であれば、融資審査において有利になる可能性があります。
また、法人名義の場合、個人の信用情報とは切り離して融資を受けられるため、経営者個人の住宅ローンなどの借入状況に影響されにくいという利点もあります。ただし、法人の信用度合が低い場合は、経営者個人の信用度合に左右されます。
※金融機関の審査基準や条件により異なる場合があります。詳細は各金融機関にご相談ください。
相続・贈与を見据えた資産承継の選択肢
法人の不動産投資は、将来の相続や贈与を見据えた資産承継の一手段となることがあります。法人名義の不動産であれば、経営者が亡くなった場合でも法人の資産として残り、法人の株式を承継することで間接的に不動産も承継できます。
個人所有でも継続的に使用収益を得られますが、相続・贈与の手続きが発生します。
また、法人の株式を少しずつ後継者に贈与していくことで、生前から計画的な事業承継を進めることも可能です。不動産の承継と比較して、株式の承継は手続きが簡易である場合があり、不動産取得税などの費用が発生しない点も考慮されます。ただし、その都度登記手続きが必要です。
※今後税制が変更される可能性があります。
法人で不動産投資を行うデメリット
法人による不動産投資にはメリットがある一方で、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。以下では、法人で不動産投資を行う際の主なデメリットについて解説します。
法人設立・維持のコストがかかる
不動産投資を法人で行うためには、まず法人を設立する必要があります。株式会社の場合、最低でも25〜30万円程度の費用が必要です。さらに、維持コストとして以下のような費用がかかります。
- 税理士報酬(年間20〜50万円程度)
- 法人住民税(年間7〜10万円程度の均等割)
- 社会保険料(従業員を雇用する場合)
- 法人登記費用
- 事務所維持費
これらのコストは、不動産投資の規模が小さい場合は、負担が大きく感じることもあるでしょう。
赤字でも税金がかかることがある
法人の場合、赤字であっても支払わなければならない税金があります。その代表的なものが法人住民税の均等割です。また、不動産事業が赤字でも、本業が黒字であれば法人税が課税されます。さらに、法人の場合は消費税の課税事業者となるケースが多く、一定の基準を超えると消費税の申告・納税義務が生じます。
※個人事業主も同様
管理運営の手間
法人では、会計処理や税務申告、各種届出など、さまざまな事務手続きが必要となります。
※個人事業主も同様
これらの業務は税理士などの専門家に依頼することも可能ですが、それには費用がかかります。個人での不動産投資と比較すると、法人での運営は手続きや管理の面で複雑になる傾向があります。
法人化すべきタイミングと判断基準
不動産投資を行う際、どのタイミングで法人化を検討すべきか、その判断基準について解説します。一般的に、以下のような要素を考慮して判断することが重要です。
所得水準による判断
法人化を検討する最も一般的な基準は、個人の所得水準です。一般的に、以下のような目安があります。
- 年間所得500万円未満の場合:個人での運営がおすすめ
- 年間所得500〜900万円の場合:個人・法人どちらも大きな差はない
- 年間所得900万円超の場合:法人での運営がおすすめ
ただし、法人設立・維持コストなどを考慮すると、実質的な有利・不利の判断ラインはさらに上がることもあります。
不動産規模による判断
一般的に、以下のような規模に達した場合、法人化を検討する目安となる場合があります。
- 保有物件数:5棟以上のアパート・マンション、もしくは10室以上の区分所有物件
- 年間不動産収入:3,000万円以上
- 物件の資産価値:総額1億円以上
この規模になると、物件管理の煩雑さや賃貸経営のリスク分散、金融機関からの信用確保などの観点からも、法人化のメリットが大きくなります。しかし、これらはあくまでも目安であり、最適な規模は個々の事情により異なるため、専門家にも相談しながら検討することをおすすめします。
事業計画による判断
将来の事業展開や投資計画も、法人化を検討する上で重要な判断基準です。。以下のような計画がある場合は、早めに法人化を検討する選択肢もあります。一例としては下記の通りです。
- 今後、数年間で不動産投資を積極的に拡大する予定がある
- 本業の法人と不動産投資事業を明確に分けたい
- 将来的な事業承継や資産承継を視野に入れている
- 不動産だけでなくほかの投資事業も展開する予定がある
将来的な計画が不明確な場合は、まずは個人で小規模な投資からスタートし、事業が軌道に乗ってから法人化を検討するという段階的なアプローチも賢明な選択です。
法人と個人の不動産投資の違い
不動産投資を行う際、法人と個人ではさまざまな面で違いがあります。それぞれの特性を理解して、自分の状況に合った選択をすることが重要です。ここでは法人と個人の主な違いについて解説します。
税制上の違い
法人と個人では適用される税制が根本的に異なります。個人の所得税は累進課税制度で最高税率が高くなりますが、法人税は一定税率が適用されます。また、経費として認められる範囲も法人の方が広いです。
もうひとつの大きな違いは、法人と個人では経費として認められる範囲が異なる点です。法人の場合、役員報酬や役員退職金、福利厚生費など、個人では認められない項目も経費として計上できます。これにより、法人の方がより多くの費用を経費として計上することで、課税所得に影響を与える可能性があります。
※法人であっても収支状況によっては課税所得が上がる場合があります。
また、損失の繰越期間も異なります。個人が青色申告を行う場合、損失は最大3年間繰り越しであるのに対し、法人の場合は最大10年間繰り越すことが可能です。このため、初期投資の大きい不動産投資では、法人の方が長期的な税務計画を立てやすいというメリットがあります。
売却時の税金の違い
不動産を売却した際の税金についても、法人と個人では大きく異なります。個人の場合、所有期間が5年を超える長期譲渡所得には20.315%、5年以下の短期譲渡所得には39.63%の税率が適用されます。なお、所有期間の判定は売却年の1月1日現在で判定されます。売却を検討している年の1月1日時点で5年を満了していない場合は、その年の売却はすべて短期譲渡所得が適用されるため注意しましょう。
一方、法人の場合は通常の事業所得等で約30%の税率で課税されるため、5年以下の短期保有物件の売却では法人のほうが税負担が軽く、5年超の長期保有物件の売却では個人のほうが税負担が軽くなるなど、税負担に差が出る場合があります。
融資条件の違い
個人向け不動産投資融資のメリットとしては、住宅ローン控除などの優遇措置が適用される場合があることや、金利が法人向けよりも低く設定されていることが多い点があげられます。
一方、法人向け融資では、個人の借入状況に影響されない点や、年齢制限がなく長期間の返済計画を立てられる点がメリットとなります。
法人で不動産投資を始める実践方法
法人による不動産投資を始めるにあたり、具体的な手順やポイントを解説します。法人設立から物件選び、資金調達、運営管理に至るまで、実践的なアドバイスをお伝えします。
法人設立の手順
法人で不動産投資を行うためには、まず法人を設立する必要があります。主な法人形態は「株式会社」と「合同会社」があり、設立費用や維持コストは合同会社より株式会社のほうが高くなります。法人設立後は、税務署や都道府県税事務所への各種届出(法人設立届出書、青色申告の承認申請書など)も必要です。
法人設立は専門的な知識が必要なため、司法書士や行政書士に相談することもひとつの方法です。
物件選びのポイント
物件の選び方には不動産法人がそれぞれ推奨する戦略によってポイントが異なります。そのため、ここではひとつの例として、弊社が推奨している、賃料収入で本業を支える柱を構築するための物件の選び方をご紹介します。
商業中心地に位置し、駅からのアクセスに優れたオフィスビルであること
商業中心地にあるオフィスビルは、空き地が少ないためビルの供給も少ないにもかかわらず、テナント需要が多く需給バランスに優れています。そのため、テナントが長期間付きやすく、たとえ空室になっても郊外や地方と比べると次のテナントが決まりやすいという特徴があります。
広い土地に建っていること
広い土地に建つオフィスビルに入るテナントは、相場の賃料を支払えるだけの企業規模であることが多く、賃料収入の安定化に寄与する可能性があるでしょう。また、商業地は広い土地のほうが利用価値が高いとされ、再開発の土地買い上げの際に狭い土地よりも高値が付きやすい傾向があります。
※経済状況によって賃料や買い上げ価格が変動することもあります。
新耐震基準に適合しており、十分な耐震性を備えていること
耐震強度を測る基準として「新耐震基準」というものがあります。1981年6月1日以降に建築された物件は、基本的には新耐震基準に適合しています。しかし、度重なる自然災害や経年劣化によって、気づかぬうちに強度が低下している場合もあります。そのため、弊社では「PML値(予想最大損壊率)」という、地震によって建物が受ける被害の大きさを表す指標を参考に、物件を調査しています。そして一定の基準を満たした物件を取得し、保有・販売しています。
弊社を例に説明しましたが、いずれの場合も築年数や耐震強度、修繕履歴なども確認し、将来的な修繕コストやリスクを取得する前に見極めることが重要です。
資金調達と融資活用のコツ
法人で融資をスムーズに受けるためには、押さえておきたいポイントがあります。
まず法人の信用力を高め、本業の業績を安定させ、自己資本比率を高めることが重要です。融資先の選定においては、不動産投資に対する融資に積極的な金融機関や、物件所在地に拠点を持つ金融機関を選ぶと有利になるでしょう。物件選びについても、駅近などの好立地物件や収益性の高い物件を選ぶことで融資を引き出しやすくなります。また融資交渉では、複数の金融機関に相談し、不動産投資の目的や計画を明確に説明することが効果的です。
不動産管理法人の選び方
本業がある経営者の場合、物件管理を不動産管理法人に委託するのが一般的です。優良な管理法人の基本条件としては、対象エリアでの管理実績が豊富であること、24時間対応の緊急連絡体制があること、入居者募集力があることなどがあげられます。
管理手数料は一般的に賃料収入の3〜8%程度が相場ですが、サービス内容とのバランスを考慮することが重要です。
まとめ
不動産投資の法人化は、単なる資産運用ではなく、事業の一環として戦略的に位置づけることが重要です。不動産投資を成功させるためには、法人設立、物件選び、資金調達、管理運営などの実践的なノウハウを身につけ、専門家と連携しながら進めていく必要があります。
なお、本コラムでご紹介した弊社の戦略は下記のページで詳しくご紹介しています。
取得コストを一棟よりも小さくするために、1フロアごとに分割した「区分所有オフィス」、また、さらに小口化した不動産小口化商品「Vシェア」があります。ぜひご覧ください。
区分所有オフィスとは
https://www.vortex-net.com/office/
不動産小口化商品Vシェアとは
https://www.vortex-net.com/vshare/vshare/
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
竹中 啓倫たけなか ひろみち
竹中啓倫税理士事務所 代表
税理士・米国税理士
岐阜県出身。現在4名のスタッフとともに竹中啓倫税理士事務所を運営。
かつて上場会社の経営企画部・経理部に長年在籍しており、大会社への対応も可能。
スタッフには社会保険労務士の有資格者がおり、司法書士行政書士事務所の勤務経験者も在籍しているため、所得税法人税だけでなく相続税贈与税を含む幅広い業務に対応。
竹中啓倫税理士事務所(工事中)
不動産投資の記事一覧に戻る