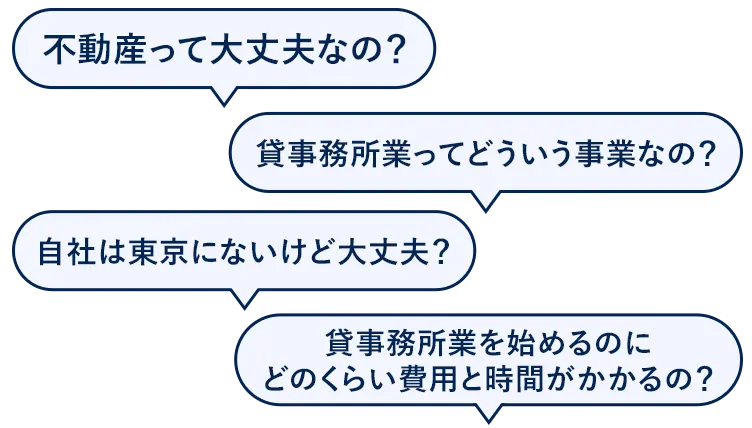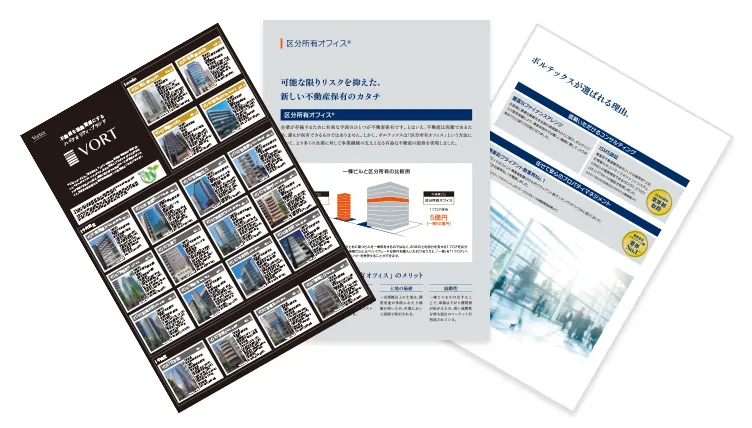株式譲渡とは?売却・事業譲渡との違いや手続きの流れを解説

目次
株式譲渡は、事業承継やM&Aの際におこなわれる重要な手続きです。事業の引き継ぎだけでなく、資金調達の手段として活用されることもあります。
本記事では、株式譲渡の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。事業承継やM&Aを円滑に進めるための参考として、ぜひお役立てください。
株式譲渡とは
株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式をほかの個人や法人に売却・移転する手続きを指します。株式譲渡によって、会社の経営権や支配権が新たな所有者に移行する場合もあります。
株式譲渡の特徴は、株主が代わるだけで会社自体は存続する点です。会社名や資産、債権・債務、従業員の雇用、取引先との契約、許認可関係などは、基本的にそのまま引き継がれます。
売り手側の株主は、株式を売却することで経営権を手放し、現金化できます。一方、買い手は一定数の株式を取得することで、会社の意思決定に関与できます。
株式譲渡をおこなう5つの目的
株式譲渡は、企業の経営戦略や状況によって、さまざまな目的で実施されます。ここでは、主な5つの目的と、それぞれの背景や活用方法について解説します。
- 事業承継のための株式譲渡
- M&Aによる企業売却
- 資金調達のための株式譲渡
- 共同経営者・株主間の関係解消
- 倒産・廃業時の株式整理
事業承継のための株式譲渡
事業承継は、株式譲渡をおこなう主な目的のひとつです。親族内承継や社内承継をおこなう場合、後継者に経営権を集中させるための有効な手段となります。
生前贈与であれば、現経営者は後継者に株式を無償で譲渡できます。(原則として受贈者は贈与税の納税義務が発生)
相続の場合は、経営者の死後、遺言や遺産分割協議により株式を承継します。また、売買の場合は、後継者が現経営者から株式を購入することで、事業承継を実現します。
M&Aによる企業売却
M&Aによる企業売却でも株式譲渡を行います。企業の株式を売買することで経営権を移転させる手法であり、売り手企業は事業の成長や多角化を図ることができます。
買い手企業は、新たな事業分野への参入や市場シェアの拡大、シナジー効果の創出などを目指します。また、ベンチャー企業が大企業のグループに入ることで、資金調達や販路拡大などのメリットを得るケースも多く見られます。
資金調達のための株式譲渡
企業が事業拡大や設備投資などで必要な資金を調達する際にも、株式譲渡が有効な手段となります。特に、ベンチャー企業ではエンジェル投資家やベンチャーキャピタルへの株式譲渡を通じて資金を獲得するケースが見られます。
また、創業者や既存株主がキャッシュアウト(現金化)したい場合にも株式譲渡がおこなわれます。ただし、株式譲渡による資金調達は、既存株主の持分比率低下により経営権が希薄化するリスクがあるため、慎重な検討が必要です。
共同経営者・株主間の関係解消
共同経営者や株主との関係解消も、株式譲渡がおこなわれる理由のひとつです。企業の経営方針を巡って対立が生じた場合に、特定の株主が保有する株式をほかの株主に譲渡することで関係を解消し、経営の安定化を図ることができます。
事前に株主間契約を締結し、特定の事由が発生した際の株式譲渡に関する取り決めを設けておくと、スムーズな関係解消が可能となります。
倒産・廃業時の株式整理
企業の経営が行き詰まり事業継続が困難になった場合、会社を清算するために、残った資産を株主に分配する必要があります。
しかし、多くの場合、倒産・廃業時には株式の価値がほとんどないか、負債が資産を上回っているため、株式譲渡による経済的なメリットは期待できません。会社清算の手続きの一環として、株式の整理がおこなわれることになります。
株式譲渡とほかの手法との違い
企業の所有権や資産を移転する手法としては、株式譲渡のほかにも選択肢があります。状況に合った手法を選択するために、それぞれの特徴を把握しておきましょう。ここでは4つの手法について説明します。
- 株式売却
- 事業譲渡
- 株式交換
- 会社合併
株式譲渡と株式売却の違い
株式売却は株式譲渡の一種であり、金銭を対価として株式を譲り渡す行為を指します。一方、株式譲渡は売却以外にも、贈与や相続などの方法で株式の所有権を移転させることを含みます。
たとえば、株式を無償で譲渡する行為は株式譲渡に該当しますが、株式売却ではありません。しかし、株式を売却する場合は、株式譲渡と株式売却のどちらにも該当します。
株式譲渡と事業譲渡の違い
株式譲渡と事業譲渡は、譲渡の対象が異なります。事業譲渡とは、企業が特定の事業をほかの企業に譲渡する手法です。譲渡対象となる事業や資産、負債を選択できるため、不採算事業を切り離したり、特定の事業だけを残したりすることが可能です。
買い手にとって必要な事業のみを取得できる方法ですが、個別の資産移転手続きが必要となり、手続きが複雑になる場合があります。
これに対し、株式譲渡は基本的に会社のすべてが譲渡対象となるため、個別の事業を選択することはできません。
株式譲渡と株式交換の違い
株式譲渡と株式交換は、対価が異なります。株式譲渡では通常、現金を対価として株式を売買します。一方、株式交換は、譲渡企業のすべての株式と譲受企業の一部の株式を交換することで、経営権を移転させる方法です。
株式交換は主に、企業グループの再編や完全子会社化を目的として使用されます。株式譲渡が現金決済を伴うのに対し、株式交換では現金の支出が不要なため、資金調達の負担が軽減されるメリットがあります。
株式譲渡と会社合併の違い
株式譲渡と会社合併は、存続する企業の形態が異なります。会社合併は複数の会社が1つの会社に統合される方法で、一方の会社が存続し、他方の会社は消滅します。
一方、株式譲渡は株式を譲渡することで経営権を移行する手法で、譲渡企業の法人格は維持されたまま、株主のみが代わります。株式譲渡では譲渡企業の独立性が保たれやすいのに対し、会社合併では組織や文化の統合が必要です。
株式譲渡のメリット・デメリット
株式譲渡には、売り手と買い手の双方にメリットとデメリットが存在します。ここでは、
それぞれの立場から見た特徴を解説します。
売り手(譲渡者)のメリット
■企業間・個人間の株式譲渡に共通するメリット
- 手続きが比較的少ない
- 会社や事業を存続できる
- 経営者が株式の売却利益を獲得できる
- 売却益にかかる税率が事業譲渡より低い
株式譲渡は、個々の資産移転や契約の引継ぎなどの複雑な手続きが不要で、基本的に株式の名義変更のみで完了します。
また、会社や事業をそのままの形で残せるため、従業員の雇用や取引先との関係維持が可能です。経営者は、株式の売却によって得た利益を、新たな事業への投資や個人の資産形成に活用できます。
さらに、個人の場合、株式の売却益にかかる税率は事業譲渡で発生する所得税よりも低く抑えられる可能性があります。
売り手(譲渡者)のデメリット
■企業間・個人間の株式譲渡に共通するデメリット
- 株主全員の同意が必要
- 株式譲渡制限がある場合は承認手続きが必要(定款を要確認)
- 不採算事業があると譲渡価額が下がる場合がある
株式譲渡をおこなうには、原則として株主全員の同意が必要です。少数株主がいる場合、同意を得るのが難しいケースもあります。
株式に譲渡制限がかけられている場合は、取締役会または株主総会の承認を得る必要があり、手続きに時間がかかるケースもあるでしょう。
また、不採算事業や簿外債務がある場合は、譲渡価額が下がる可能性があります。
買い手(譲受者)のメリット
■企業間・個人間共通
- 経営権を獲得できる
■企業間
- 許認可を引き継ぐことができる
- 自社の成長につながる
■個人間
- ほかの買収希望者との競争がない
- 支払方法や譲渡価格など柔軟な条件を相談できる
株式譲渡によって、買い手は対象企業の経営権を取得できます。これにより、事業戦略の決定や経営陣の選任など、企業経営の重要な意思決定に関与できるようになります。
企業間の株式譲渡の場合、許認可や事業に必要な資産・ノウハウを包括的に引き継ぐことができるため、新規事業への参入や事業拡大を迅速に進められます。また、個人間の株式譲渡(事業承継)の場合は、M&Aのようなほかの買収希望者との競争がなく、比較的落ち着いて交渉を進められます。
買い手(譲受者)のデメリット
■企業間・個人間共通
- 多額の資金が必要になる場合がある
- 負債を引き継ぐリスクがある
- 全株式の取得が困難な場合がある
■個人間
- 譲渡価格が市場価格より著しく低い場合は税務上の問題が生じる
株式譲渡では、対象企業の株式を取得するために多額の資金が必要となる場合があります。特に、優良企業や成長企業の株式を取得する際には、高額な対価が必要となることが一般的です。
また、株式譲渡では、対象企業の資産だけでなく負債も引き継ぐことになります。簿外債務や偶発債務が存在する場合、買い手は予期せぬ損失を被るリスクがあります。
個人間の株式譲渡の場合は、譲渡価格があまりにも低いと「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象になることがあります。適正な価格設定について、専門家への相談も検討しましょう。
株式譲渡の手続きの流れ
株式譲渡は、企業の所有権を移転する重要な手続きです。特に中小企業では、株式に譲渡制限が設けられている場合が多く、適切な手続きを踏むことが求められます。
以下に、株式譲渡の一般的な手順を説明します。
1. 譲渡承認の請求
株式を譲渡したい株主(譲渡人)は、会社に対して譲渡承認を申請する必要があります。これは、会社の定款で株式譲渡に制限が設けられている場合に必要な手続きです。
譲渡人は「株式譲渡承認請求書」を作成し、譲渡する株式の種類や数、譲受人の情報を記載して会社に提出します。この手続きにより、会社は譲渡の可否を判断できます。
2. 取締役会・株主総会での承認
譲渡承認の請求を受けた会社は、取締役会または株主総会を開催し、譲渡の承認可否を決定します。取締役会設置会社では取締役会で、設置していない会社では株主総会で審議がおこなわれます。
この際、会社は譲渡を承認するか、あるいは承認しない場合は会社自身や第三者が株式を買い取るかを決定します。この手続きにより、会社は望ましくない第三者が株主となることを防ぐことができます。
3. 決定内容の通知
取締役会や株主総会での決定後、会社は譲渡承認請求をおこなった株主に対して、決定内容を通知します。この通知は、請求を受けてから2週間以内におこなわなければなりません。
この期間内に通知がない場合、譲渡は承認されたものとみなされます。適切に通知することで、手続きの透明性と信頼性を確保できます。
4. 株式譲渡契約の締結
会社から譲渡の承認を得たあと、譲渡人と譲受人の間で株式譲渡契約を締結します。この契約では、譲渡する株式の詳細、譲渡価格、支払い方法、譲渡日などを明確に定めます。
契約書を作成することで、後々のトラブルを防止し、双方の権利と義務を明確にできます。
5. 株主名簿の書き換え、証明書交付
契約締結後、譲受人は会社に対して株主名簿の名義書換を請求します。これは、正式に株主として認められるために必要な手続きです。
会社はこの請求を受けて、株主名簿の書き換えをおこない、譲受人に対して株主名簿記載事項証明書を交付します。この証明書は、譲受人が正式な株主であることを証明する重要な書類です。
6. 決済の手続き
最後に、株式譲渡対価の支払い(決済)をおこないます。一般的には、契約締結時に一括で支払われますが、場合によっては条件を満たしたあとに支払うこともあります。
この手続きにより、株式譲渡が完了し、譲受人は正式な株主としての権利を行使できるようになります。
株式譲渡の手続きにおける必要書類と契約書
株式譲渡の手続きにおける必要書類を解説します。
株式譲渡手続きの必要書類
株式譲渡手続きに共通する必要書類は以下のとおりです。書類に特定の書式はありません。
- 株式譲渡契約書
- 株式名義書換請求書
- 株主名簿
- 株主名簿記載事項証明書交付請求書
- 株主名簿記載事項証明書
- 株式譲渡承認請求書
- 取締役の決定書 など
譲渡制限株式の株式譲渡手続きに関する書類
譲渡制限がある場合に必要な書類は以下のとおりです。
- 株式譲渡承認請求書
- 株主総会招集通知
- 株主総会議事録
- 株式譲渡承認(または不承認)通知書
株式譲渡契約書の記載事項一覧
契約書の記載事項は以下のとおりです。
- 基本合意(会社名、住所、譲渡対象の株式数、譲渡価格、株式の種類)
- 譲渡代金の支払い方法や期日
- 譲渡承認手続き
- 株主名簿の名義書換え
- 表明保証
- 契約解除
- 損害賠償
- 競業避止義務
- 合意管轄
株式譲渡にかかる税金
企業の株式譲渡は、事業承継や資本構成の見直しなど、さまざまな目的でおこなわれます。しかし、株式譲渡には税金が伴うため、適切な理解と対策が必要です。以下では、売り手(譲渡者)と買い手(譲受者)それぞれにかかる税金について詳しく解説します。
売り手(譲渡者)にかかる税金
個人の場合、株式譲渡による所得(譲渡益)は「譲渡所得(※)」として課税対象となります。具体的には、以下の税金が課されます。
※譲渡所得:株式譲渡の価格から株式の取得費や委託手数料などの経費を引いた額
- 所得税:譲渡所得の15%
- 住民税:譲渡所得の5%
- 復興特別所得税:所得税の2.1%(0.315%)
これらを合計すると、20.315%の税率が適用されます。たとえば、譲渡所得が1,000万円の場合、203万1,500円の税金が課されます。
法人の場合、株式譲渡による利益は通常の事業所得と合算され、法人税の課税対象となります。法人税率は企業の規模や所得金額によって異なりますが、原則23.2%です。たとえば、譲渡所得が1,000万円の場合、232万円の法人税が課されます。
買い手(譲受者)にかかる税金
通常、適正な時価で株式を購入した場合、買い手に直接的な税金は発生しません。しかし、時価よりも著しく低い価格(時価の1/2未満)で購入した場合、差額が贈与とみなされ、以下の税金が課される可能性があります。
- 買い手が個人の場合:贈与税
- 買い手が法人の場合:法人税
たとえば、時価1,000万円の株式を400万円で購入した場合、差額の600万円が贈与とみなされ、贈与税や法人税の課税対象となります。
一方、時価よりも高い価格で購入した場合、買い手が法人であると、その超過分が寄附金とみなされ、損金不算入となる可能性があります。これは、税務上、適正な取引価格を超える支出が寄附と判断されるためです。
以上のように、株式譲渡に伴う税金は、取引の条件や当事者の属性によって異なります。適切な税務対応をおこなうためには、専門家への相談をおすすめします。
株式譲渡の手続きをおこなう際の注意点
株式譲渡の手続きにはいくつかの注意点があり、適切に対応しないと法的な問題やトラブルの原因となる可能性があります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
株券交付が必要な場合がある
株券発行会社では、株式譲渡の際に株券の交付が必要となります。これは、株券が株主の権利を証明する重要な書類であり、株券の交付がなければ譲渡の効力が認められないためです。
株券が未発行の場合、譲渡前に速やかに発行手続きをおこなうことが求められます。この手続きを怠ると、譲渡の効力が無効となり、法的なトラブルに発展する可能性があります。そのため、株式譲渡を検討する際は、まず自社の定款を確認し、株券の発行状況を把握することが重要です。
所在不明の株主がいる場合がある
株主のなかに所在不明者がいる場合、株式譲渡手続きが複雑化します。所在不明株主を一方的に株主名簿から削除したり、その株主の株式を勝手に売却したりすることは法律で禁じられています。
この場合、会社法の規定に基づき、裁判所の許可を得て初めて所在不明株主の株式を売却することが可能となります。一定期間以上連絡が取れない株主に対して、公告や通知をおこない、それでも反応がない場合に裁判所へ申し立てをします。
この手続きを経ずに株式を処分すると、法的な問題やほかの株主とのトラブルの原因となるため、慎重な対応が求められます。
名義株があると名簿の書き換えが必要
名義株とは、株主名簿に記載されている名義人と、実際の出資者が異なる株式のことを指します。過去の慣習や税務上の理由で発生することがありますが、株式譲渡の際には大きな問題となり得ます。
名義株が存在すると、真の所有者が権利を主張できないリスクや、第三者への譲渡時に法的な効力が認められない可能性があります。
そのため、株式譲渡をおこなう前に、株主名簿の記載内容を実態に合わせて正確に修正することが必要です。名義人と実際の出資者との間で正式な譲渡手続きをおこない、株主名簿の書き換えを申請します。
まとめ
株式譲渡は、事業承継や企業売却、資金調達など、さまざまな目的で活用される手法です。株式を譲渡することで、経営権がスムーズに移転される一方で、契約の手続きや税金の負担など、慎重に進めるべき点もあります。
専門家のアドバイスを受けながらおこなうことで、リスクを最小限に抑え、適切な事業の引き継ぎを実現できるでしょう。
後継者が引き継ぎやすい経営状態をつくるという選択
もし、後継者不在による株式譲渡や、あるいは事業承継において重要な経営基盤の安定化にお悩みの場合、不動産賃貸業を導入することが有効な選択肢となる場合があります。不動産賃貸業を活用し、賃料収入を用いて強固な経営基盤を構築することで、後継者を見つける可能性を高めるとともに、事業承継後も安定した経営を継続できる環境を整えることが可能です。
強固な経営基盤を構築する上で、高い収益性が期待できる不動産を保有することが重要な要素となります。ボルテックスでは、優良資産の条件として以下の特性をあげています。
- 都心の商業地に位置している
- 駅からのアクセスが良好である
- 清潔感があり、優れた設備を有している
これらの条件を満たすオフィスビルはテナント市場において需要が高く、長期間の空室が発生しにくい傾向が特徴です。収益性が安定している場合が多く、投資家から高い評価を受けています。しかし、こうしたオフィスビルは一棟での取得には高額なコストがともなうため、特定の層のみ保有ができるという点が課題でした。
この課題を解決するために、ボルテックスでは「区分所有オフィス」という新しい不動産投資の形を展開しています。従来一棟単位でしか取得できなかった高額なオフィスビルを、1フロア(物件によっては1部屋)ごとに販売することで、より多くの方々にも取得を可能にしたサービスです。
「区分所有オフィス」についてより詳しく知りたい方は下記のリンクからご覧ください。
ボルテックスの「区分所有オフィス」とは
※不動産投資には、賃貸市場の変動、空室リスク、修繕費の増加、金利の上昇、法改正による影響などのリスクが伴います。これらのリスクを十分に理解した上での検討が必要です。
※収益性や安定性は物件によって異なり、保証されるものではありません。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。