国内不動産市況の今とこれから。需要が高まるオフィスビルの条件をデータで探る

目次
不動産関係者の間ではかねてから懸念されていた、大規模オフィスが前年の2倍以上の大量供給となる「2023年問題」ですが、マーケットへの影響は実際にはどうだったのでしょうか。最近の不動産市況動向を概観するとともに、2024年の東京都心部オフィス不動産市況はどうなるのか、ニッセイ基礎研究所の佐久間誠氏に伺いました。
オフィス不動産市況の注目点。2023 年問題は杞憂に終わった?
2023年はポストコロナへの移行が、経済面で注目されました。5月には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行し、人の移動に制限が課せられなくなりました。同年10月の訪日外客数は、2019年10月比で100.8%となり全回復しています。
こうした動きはホテルの稼働率を引き上げ、商業施設にも好影響を与えました。賃貸住宅も、コロナ禍で瞬間的に調整の兆しは見えたものの、マイナスの影響は限定的でした。在宅勤務の普及はファミリー向け賃貸にとって追い風でしたし、東京への転入超がコロナ禍前の9割程度まで回復してきたため、シングル向け賃貸も堅調に推移しました。
一方、オフィス不動産市況には注目点が2つあります。1つは在宅勤務の定着です。2023年4月の東京都心5区の出社率は7割で、出社と在宅を織り交ぜた勤務体系になったと考えられますが、一方でオフィス需要はそこで下がっていないのではと思うデータもあります。
たとえばザイマックス総研が出している1人当たりオフィス床面積は、2023年が3.9坪でコロナ禍前とほぼ同じです。一部、大手製造業は床面積を減らしましたが、全体では、実はそれほど削減されていない感を受けます。
もう1つの注目点は2023年の新規供給ですが、「2023年問題」と騒がれるほどではなかったと考えられます。これは森ビルの調査ですが、2023年から2025年にかけての新規供給面積は、東京23区内で年平均約112万㎡です。過去平均は年102万㎡なので、それに比べればたしかに増えていますが、極端に増えているわけでもありません。2023年11月開業の麻布台ヒルズも、満床では開業できなかったものの、マーケットが不安視していたほど空室ばかりではありません。
2024 年の不動産市況を左右する3つのポイント
では2024年はどうなるのか。前述した2023年の動きを、ほぼ踏襲すると私は見ています。しかし、気になる点もいくつかあるのであげておきましょう。
1つは消費動向です。実質賃金は2023年10月現在19カ月連続でマイナスとなり、消費に頭打ち感が出ているのは事実です。ただ、2024年の春闘における賃上げが、2023年に比べて高くなるのではないか、という見通しが浮上しているのも事実で、仮にそれが実現すれば、日銀がいう「賃金と物価の好循環」が生まれ、商業施設の不動産市況が堅調に推移する可能性があります。
2点目はオフィス動向です。在宅勤務と親和性の高い情報通信業や、大企業を中心とする製造業は回復が鈍いものの、不動産業やその他サービス業、卸売業、小売業など内需型企業は、徐々に回復しつつあり、その動きがどこまで続くのかが注目されます。
また製造業にしても、ニューヨーク連邦準備銀行が開発したサプライチェーン逼迫指数を見ると、コロナ禍が本格化する前の、2020年2月の水準以下にまで低下しています。供給制約が解かれ、かつ米国景気が想定外の強さを見せる中、円安の影響もあり、企業収益は絶好調です。法人企業統計の売上高を見ると、直近の数字はアベノミクスのピーク時を超えており、足元の設備投資もかなり戻ってきました。
オフィス投資も設備投資の一種ですし、売上増などによってテナントの賃料負担力が戻ってくるとすれば、2024年以降、これまで低迷ぎみだったオフィスにも、回復の兆しが見えてくるのではないかと、期待しています。
そして3点目は金利です。日銀は2023年10月にイールドカーブ・コントロールの1%上限に、かなり柔軟性を持たせました。結果、一時は1%目前まで上昇したものの、11月現在は0.78%台で推移しました。リーマンショック前の長期金利が2%であり、今の金融は相当緩和的です。したがって、秩序を持った金融緩和政策の修正であれば、特に大問題に発展することはないと見ています。
不確実性は存在するものの、2024年の不動産市況を全体的に展望すると、不動産価格が大幅に下落するような事態に直面はしない、というのがメインシナリオです。
再認識されるAクラスのオフィスビル
ニッセイ基礎研究所は三幸エステートとともに、賃貸オフィスの成約事例の各種データを活用して、「オフィス拡張移転DI」の算出を開始しています。簡単にいうと、この数字は0%から100%の間で推移し、基準となる50%を上回ると企業のオフィス拡張意欲が強く、下回ると縮小意欲が強いことを示します。
東京都心部のオフィス拡張移転DIは、コロナ禍前の2019年第2四半期が78%でしたが、直近2023年第2四半期は60%です。在宅勤務やさまざまな不確実性の影響で、まだコロナ禍前の水準には戻っていません(図表)。

さらにオフィスビルをグレード別に見ると、Bクラス*、Cクラスはコロナ禍前の水準まで完全に戻りました。ただ、Aクラスは50%を超えているものの、60%前後からの戻りが鈍くなっています。これは日本に特有の傾向で、米国ではトロフィーオフィスといわれる、ピカピカのAクラスはおおむね埋まっていて、賃料もほとんど下げられていない反面、ほんの少しでも古い、設備がやや劣るオフィスは、全く需要がないという状況です。米国は日本に比べて在宅意欲が強いので、社員が来たいと思ってもらえるオフィスは、ビルそのもののスペックが高く、周りにアメニティーが多いといった条件を満たす必要があり、そうだとすると必然的にトロフィーオフィスになるのです。
しかしこれから先を考えると、日本でもAクラスビルのよさが再認識される可能性はあります。在宅勤務がもう一段普及すれば、オフィスに求められるものが、現状とは違ったものになってくると考えられるのです。
在宅勤務のデメリットは、コミュニケーションやコラボレーション、教育など、人と人が接することによって効果を高める類の業務が遂行しにくいことです。
そして、それらの業務をスムースに遂行するための設備はAクラスのほうが優れているはずなので、かえってAクラスのよさが再認識される可能性もあります。
またAクラスの定義そのものが変わってくる可能性もあります。従来は基準階面積や天井高、電気容量、築年数などハード面に寄った条件で決められてきましたが、今後はたとえば中規模クラスのビルでもテナントが求めるサービス提供を付加価値として、Aクラス並みの賃料を取るようなビルも増えていくかもしれません。
ハード面よりも、ソフト面のサービス内容で利用者の需要を取り込み、それを賃料収入の増加につなげていくことが、これから不動産事業、とりわけオフィスビル事業には求められてくるのではないでしょうか。
*三幸エステートの定義によるもので、特定のエリア内で延床面積、基準階床面積、築年数および設備などのガイドラインを満たすビルをA・B・Cの各クラスに分類している。
[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課
[制作協力]株式会社東洋経済新報社
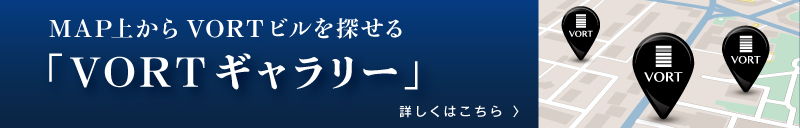
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。



