人口流動とオフィス出社率から読み解く
アフターコロナの不動産市場

目次
コロナ禍が一段落し、日常生活が戻ってきました。コロナ下では移動の自粛が要請され、働き方の変化により一時都心からの人口流出なども懸念されたほか、都心のオフィス出社率もこの3年間大きく揺れ動きました。これらは不動産市場にどのような影響を与えているでしょうか。アフターコロナにおける現在の市況を中心に、ニッセイ基礎研究所の佐久間誠氏に動向を伺いました。
ニーズの強い都心マンションの高値傾向は落ち着くか
コロナ禍のさなかはテレワークの普及もあいまって、地方移住が注目されました。
そこで東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉の各都県)から地方圏に転出した人と、地方圏から東京圏に転入してきた人の差し引きを見ると、地方圏から東京圏に転入してきた人口は、2021年こそペースダウンしたものの、転入超に変わりはありませんでした(図)。

ちなみに、東京圏への人口流入は3、4月に最も集中します。その数字を見ると、2023年3月の人口流入はコロナ禍前の2019年3月と同水準まで回復してきました。
一方で、東京圏内の人口動態を見ると、実はコロナ禍が始まる前から郊外化の動きが見られます。それは東京都心部から周辺部への人口移動です。その理由の一つは都心部の住宅価格が高すぎること。また、コロナ禍によるテレワークの普及がそれを後押ししています。
ただ、都心部から郊外への人口移動によるドーナツ化現象は、かつては中心部が空疎になっていくものでしたが、今回は都心部の不動産価格が高すぎる結果として郊外化が進んでいる一方で、都心部は都心部で、今でも非常に強いニーズがあるのです。
都心のマンション価格は2013年の異次元の金融緩和以来上昇を続け、高騰傾向が続いています。2022年度の東京23区新築マンションの平均価格は9,899万円、そして今年4月には1億円を超え※1、しばらく高値圏で推移すると思われますが、上昇トレンドが続くかといわれると、やや疑問があります。都心のマンションは、これまでパワーカップル(双方が高収入の共働き世帯)や資産家によって買われてきましたが、全体で見るとそれほど購買力は上がっていません。それでも高額物件を買えたのは、金利が低かったからです。
これから金利は、植田和男日銀総裁の政策方針からすると、サプライズ的な政策変更はないでしょう。仮に利上げをするにしても来年、再来年という時間軸であり、目先ではイールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の修正を指摘する声もありますが、仮にそれを行ったとしても、長期金利で現行の0.5%が1.0%になる程度だと予想されます。
リーマンショック時の長期金利が約2.0%だったことからすれば、今の水準から金利が上がったとしても、当時の半分の水準です。したがって、それほど大きな影響はないと思われますが、金利がこれ以上下がらないという見通しからすると、個人による都心部の高額物件の購入意欲は、ややそがれるかもしれません。
※ 1 株式会社不動産経済研究所4 月18 日付リリース「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2022年度(2022 年4 月~2023年3 月)」、同5月18日付リリース「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2023 年4月」参照。
外資が注目する日本の不動産市場
加えて、レジデンス(住宅)に関しては、もう一つ大きな資金の流れがあります。外資です。特に欧米の投資家の間で、ポートフォリオにアジア太平洋地域の不動産を組み入れる動きがあり、年金、生命保険、ソブリン・ウェルス・ファンド(政府系ファンド)といった足の長い資金を運用する投資家の中には、比較的低リスクで安定したリターンを期待できる物件への注目度が高まっています。
機関投資家の巨大なマネーを受け入れられる、アジア太平洋地域の不動産市場は、日本とオーストラリアくらいしかなく、加えてコロナ禍において、オフィスやホテルに比べて賃貸住宅が安定していたこともあり、30戸から50戸程度の中規模のワンルームマンションを中心に外資のお金が集まっています。
実際、レジデンスの賃料は東京23区内でもコロナ禍で一時的に下落しましたが、今はほぼ戻ってきました。特にこれからは本格的に上昇する可能性があります。
その根拠は賃上げの動向です。今年の春闘の平均賃上げ率は3.8%で、2024年春闘でも3%台の上昇を予想するエコノミストも出てきました。賃上げが持続すれば、入居者の入れ替わりが比較的早い賃貸住宅を中心に、この30年で初めて本格的な賃料の上昇が見られるかもしれません。
イノベーションを重視する企業はオフィスを重宝する傾向がある
アフターコロナの不動産市況に関しては、オフィスの動向にも触れておく必要があります。
その際に注視しておきたいのが、出社率です。コロナ禍真っただ中、2020年4~5月の最初の緊急事態宣言下では出社率が大幅に低下し、主要都市だと東京が36.1%、大阪40.4%、名古屋40.7%、福岡41.7%、札幌50.0%、仙台50.2%でした。その後コロナ禍が収束した2023年4月最終週では、東京76.2%、大阪81.3%、名古屋84.2%、福岡79.5%、札幌82.1%、仙台83.6%でした※2。
まだコロナ禍前の出社率には達していませんが、これは在宅とオフィスを組み合わせた、ハイブリッドな勤務形態が定着しているからと考えられます。
それを前提にオフィス需要を見ると、テレワークへの親和性が高い企業、あるいはオフィスをコストと捉えている企業はオフィス需要の回復が鈍く、特に日本を代表する大企業などでその傾向が強く見られます。
ただIT企業などは、一見テレワークに対する親和性が強いように見えるものの、大きくオフィス面積を削減する話があまり聞こえてきません。イノベーションを起こして、事業を早く拡大させる必要性のある企業は、オフィスを重宝する傾向が見られます。その点で、100坪を下回るような中小規模のテナントは旺盛な需要が見られますが、大企業や外資系、金融が入っているような大規模オフィスの需要は、やや厳しい状況にあります。
オフィスにおける売買の動向は世界的にはかなり細っている反面、日本は健闘しています。賃貸市況の悪化に加えさらなる金利低下が見込めないことから、価格が上昇するような環境にはありませんが、しばらく高値圏を維持するでしょう。
逆にオフィスの賃貸面での動向は、「2023年問題」といわれるような2023~25年にかけてのオフィスの大量供給がありますので、需給バランスの維持はやや厳しい見込みです。とはいえ、直近(5月時点)の東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)のオフィスビル空室率は6.1%程度ですから、本当に厳しい水準まで上昇しているわけでもありません。
具体的にいうと、直近では渋谷が注目されているほか、現在も再開発が続く虎ノ門・麻布台エリアは長期的には資産価値が上がる可能性があります。また中小規模のオフィスビルが多い日本橋エリアなども出社率が比較的高く需要も高めです。一方で湾岸エリアの大型ビルは厳しいなど、地域や物件、あるいはビルの規模などによって格差が広がってきています。
したがって、どの物件でもよいという雰囲気はかなり薄らいでいるので、これからはより選別的に投資していくことが重要になるでしょう。
※ 2 佐久間氏ほか著 ニッセイ基礎研レポート5月25日「コロナ禍におけるオフィス出社動向─携帯位置情報データによるオフィス出社率の分析」参照。
[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課
[制作協力]株式会社東洋経済新報社
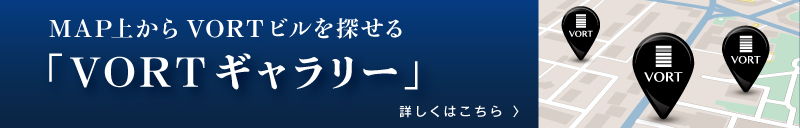
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。



