都市再生特別措置法等の改正で変わる、
開発・建築の制限

目次
集中豪雨などの異常気象による土砂災害や河川の氾濫といった甚大な被害が、毎年のように発生しています。こうした自然環境の変化をふまえ、社会インフラ強化の一環として都市計画法の一部が改正され、災害ハザードエリアにおける開発の制限が見直されました。新たにどのような制限が加わったのか、それにより土地取引や都市開発においてどのような注意が必要か、改正の要点を不動産鑑定士の北川憲氏が解説します。
開発規制の厳格化により自社ビルの建て替えができなくなる
地球温暖化にともなう気候変動の激化によって、日本各地で集中豪雨や大型台風といった水害の頻発、甚大化が顕著になっています。特に近年は宅地開発の影響による土砂災害など、天災に人災も加わる事案も相次いでいるため、居住環境の安全確保の観点から、「都市再生特別措置法」が改正され、令和4年4月1日に施行されました。
都市再生特別措置法は、都市の国際競争力の向上や自然災害に強いまちづくりの推進を念頭に平成14年に定められた法律ですが、今回の改正により災害ハザードエリア(被災の危険性が高い区域)を対象に、災害発生時に人命に危害が生ずる可能性がある「災害イエローゾーン」と、その中でも著しく危険性が高い「災害レッドゾーン」のそれぞれで、開発規制の条件が見直されています。
もともと法改正以前から都市計画法第33条第1項第8号において、自己以外の居住用施設(分譲住宅、賃貸住宅など)や自己以外の業務用施設(貸オフィス、貸店舗、貸倉庫など)の開発では、災害レッドゾーンを原則含まないこと、と定められていましたが、今回これらに加え、自己の業務用施設(自社ビル、自社店舗など)も新たに規制の対象となりました。言い換えれば、災害レッドゾーン内では、自宅として居住する建物以外の開発ができないという、かなり厳しい法改正となりました。また、災害イエローゾーンにおいても、住宅などの開発許可が厳格化されました(表)。

たとえば災害レッドゾーン内の自社ビルは、分譲住宅や貸オフィスはもちろん、自社ビルにも建て替えることができません。住宅にすることはできますが、居住実態のある自宅でなければならないので現実的ではなく、その土地の活用方法は極めて限定的とならざるを得ません。対象となるエリアにすでに建っている建物の所有者にとっては、この規制は青天の霹靂といえます。
そのため、こうした状況が多数想定されることから、所定の造成工事を行い安全性が確認できた場合に限り、災害レッドゾーンの適用から除外するという救済措置が設けられています。ただし、十分な安全性が担保できるだけの造成工事を施すには相当の追加投資が必要となります。そこまでしてその場所に残るか、あるいは売却して移転するか、実質的な選択肢はそのどちらかで、所有者は判断を迫られることになります。
市街地とそうでない場所の二極化がいっそう顕著に
一方、市街化調整区域内の開発に関しては、都市計画法第34条第11号および第12号という特例があります。このうち第11号は、別名「50戸連たん特例」とも呼ばれ、本来は市街化を抑制すべきエリアであっても、おおむね50戸以上の建物が集中し、一定の条件を満たしている場合には、市街化区域と同様に開発を行うことができるという制度です。
今回の法改正によって、この「50連たん特例」の区域内であっても、災害ハザードエリアに該当するエリアは開発を厳格化することになりました。該当する建物は今後開発許可を受けることができなくなるため、将来的には戸数が減り、「おおむね50戸以上」の要件を満たせなくなり、指定区域全体に影響がおよぶことが予想されます。
こうしたことから、不動産取引においては今後、災害ハザードエリア内の物件を扱う際に十分に注意する必要があります。適用除外を受けられるだけの技術基準を満たす造成工事を行ってまで、そこで事業を継続するだけの経済的な採算性が見込めるか。また、法改正の影響により土地が極めて低く評価される可能性が高まり、造成工事費用を上乗せしても長期的に見れば資金回収できるのか。これらを総合的、かつ、慎重に検討しなければ、容易に手を出せなくなってしまいます。
また、直接の当事者でなくても、まったく無関係の話ではありません。今後、災害ハザードエリアから病院や公園、コンビニなどの移転が進むことが考えられますし、ほかのエリアに転居する住民が増えるかもしれません。そうなれば、近隣の街の人やモノの流れが変化し、ひいてはさまざまなビジネスへの影響が起こる可能性も高まります。法改正の最大の目的は、自然災害で人命が脅かされるような事態を未然に防ぐことであり、行政は明言こそしていませんが、人口減少、過疎化などの社会変化などと相まって、ゆくゆくは災害ハザードエリア内に建物などをなくしていくことを目指していると考えることもできます。そのため、今後は災害ハザードエリアおよびその周辺部の市街化調整区域では、過疎化がより確実に加速していくでしょう。
しかし、これはネガティブな変化ではなく、広い目で見れば、人が生活するエリアとしないエリアをこれまで以上に明確に区分することにより、自然災害に強い都市へと大きく一歩近づけるための施策であり、都心部の安全、活性化にもつながるはずです。これらの法改正は、都市の総合的な価値を高めていくための施策であると期待しています。

各種土地情報の一元化の流れ
災害ハザードエリア内の開発規制は、土地の価格の算定にも影響しています。土地取引の指標となる地価公示価格や地価調査価格は、日本全国にあらかじめ設定された「標準地」において土地の鑑定評価を行い、算出されますが、その標準地の一部が災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンに該当していたため、別の場所に変更することが求められました。この措置は当然、それらの場所では十分な価値が見込めず、適正な価格評価ができないためです。
都市開発や土地活用においては、災害ハザードエリアだけでなく、地価公示価格や地価調査価格、相続税路線価、用途地域、容積率・建ぺい率、文化財保護法が定める周知の埋蔵文化財包蔵地など、さまざまな条件や情報を取得し勘案する必要があります。東日本大震災以降の国民の防災意識の高まりもあって、ハザードマップは誰でも簡単に入手・閲覧ができるようになってきていますが、そのほか情報は、それぞれの管轄行政機関の窓口に問い合わせなければ確認できないことが少なくありません。必要な情報をすべて得ようと思えば、従来は専門家に任せる必要がありました。
しかし、ここに来てようやく、土地に関する情報提供の体制が改善されようとしています。国土交通省をはじめとする所轄官庁がデータの一元化に取り組んでおり、これが実現すると、国税庁、文部科学省をはじめ各省庁が個別に管理する情報が、組織の垣根を越えてひとつの地図の中に集約される方向で現在調整が進んでいます。データの一元化が、土地取引におけるトラブルや経済的な損失を未然に防ぐ一助として期待されます。
今回の法改正は、いわば人の命を守ることを最優先にした都市構造の変革ですが、相手は自然です。この先、地球の気候がどう変化していくかは、誰にもわかりません。自然災害の猛威のさらなる甚大化や、社会環境や国民の意識の変化などにより、開発規制がさらに厳しくなることが予測されます。したがって、自然災害への対応については、今後も注視していく必要があります。
お話しいただいた方
北川憲 様
きたがわ・けん
不動産鑑定士・二級建築士・宅地建物取引士・マンション管理士。1965年、東京都生まれ。1989年、法政大学経済学部経済学科卒業。1990年、財団法人日本不動産研究所入所。仙台支所、さいたま支所勤務。2001年、財団法人日本不動産研究所退所。現在、有限会社北川不動産鑑定士事務所代表取締役。丸三住宅株式会社取締役。公益社団法人東京都不動産鑑定士協会副会長。不動産鑑定士橙法会(法政大学OBの不動産鑑定士会)副会長。宅地建物取引業法第16条第3項の登録講習講師。不動産鑑定に関する著書多数。

オフィス賃貸情報は「東京オフィス検索」までお問い合わせください。
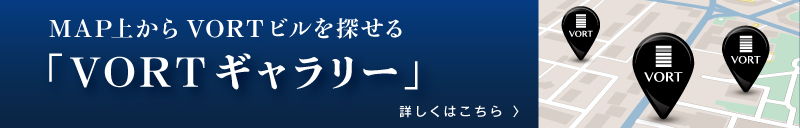
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。


