生産緑地の2022年問題は東京の不動産市場にどう影響するか
〜トレンド化する「農業と共生する都心のまちづくり」〜

目次
2022年に都市圏の多くの農地が一斉に宅地となり、不動産市場に大きな影響が生じるのではないか。地価が大暴落したり、売り急ぎや買い控えが起きるのではないか。そうした疑念が、「生産緑地の2022年問題」として注目されてきました。かつて『「2022年問題」に警鐘を鳴らす』というレポートでこの問題を世に投げかけ、都市農地の研究に取り組む塩澤誠一郎氏が、問題の趣旨ならびに懸念の真意について解説します。
このタイミングで宅地化を選択するケースは少数派
2022年問題とは、1991年の生産緑地法の改正によって「生産緑地(都市環境の向上を目的に都市計画によって定められた農地や山林で、建物の建築や宅地造成が禁じられている)」に指定され30年間の営農義務が設けられた土地が、2022年以降その縛りを解かれるため、それらが一斉に宅地へと転用されることを危惧するものです。1991年といえばバブル崩壊が始まった頃で、地価が一番高かった時期。都市部の農地を放出する意図で設けられた制度でした。
もともと三大都市圏などの都市部においては、1968年に制定された都市計画法によって、市街化区域(積極的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化せず営農を保全する区域)という線引きがなされています。つまり市街化区域内にある農地は、ゆくゆくは宅地化される前提だったのですが、生産緑地法ではさらに、市街化区域内の農地に「宅地並み課税」(農地に課される税としては非常に高い)が導入されました。そのため営農の継続を希望する所有者は、税制優遇される「農地課税」の対象となる生産緑地を選択することになりました。ただし、いったん生産緑地に指定された土地は、「買取申出」の手続きを経ないと宅地化できず、その申し出ができるのは、①主たる従事者が死亡した場合、②主たる従事者が故障(ケガ・病気)して営農できなくなった場合、③指定から30年が経過した場合のいずれかに限られていました。
しかし、年月を経て社会環境は大きく変貌し、近年ではむしろ都市にも農地があるべきだという風潮が優勢になっています。30年の縛りについても、新たに「特定生産緑地」の指定を受けることで、もう10年間「農地課税」が適用されることになり、10年毎に繰り返し再延長できるようになりました。これによって、少なくとも2022年に一斉に宅地化が進む可能性は非常に低くなりました。
ところで、1991年の時点で生産緑地を選択した人は、最も地価が高い時期に、おそらくさまざまな圧力や誘導を受けながらも、土地を売らなかった人たちだという見方ができます。それでも売らずに営農を続けることを選択し、その後も経営を維持してきた方が大勢を占めるということは、今回いざ制度上の期限を迎えたからといって、農地を手放すのは少数派であることは想像に難くありません。
また多くの農家は、「宅地化農地」(生産緑地を指定せず宅地並み課税が適用されている土地)も残しています。宅地化農地は生産緑地と異なり、届出のみで転用が可能であり、すぐに宅地化できます。だとすれば、何かあったときに先に手を付けるのは宅地化農地と考えるのが自然です。
そして何より、買取申出ができる条件には前述のとおり、主たる従事者が死亡した場合や故障して営農できなくなった場合もあることを忘れてはいけません。2022年以前も、今後も、個々の事情によって宅地への転用は起こるのであって、30年が経過した今しかチャンスがないわけではないのです。
以上から、指定30年で買取申出を選択する人は、何らかの事情により、このタイミングでの宅地化を最初から考えていた人たちと推測するのが妥当でしょう。

不動産市場への影響は別のところにある
国土交通省の2021年末の調査によれば、三大都市圏の生産緑地の約86%(8,048ha)が特定生産緑地となる見込みであり、「特定」の指定を受けないという回答が7%、不明・未定が7%という状況です。東京都に限定すると、指定を受けない(宅地化する)と回答した人は6%で、面積にすると139ha、東京ドーム約30個分に相当します。着工戸数に換算すれば、およそ2万数千戸といったところでしょう。
大きなインパクトになりかねない数字に思えますが、実は東京都内の近年の年間着工戸数は13万〜15万戸で推移しています。仮に2万数千戸が一斉に着工すれば影響はあるかもしれませんが、買取申出から、開発に至る手続きには、それなりの時間がかかりますから、今後数年間にわたって分散して出てくるはずです。そう考えると、13万〜15万戸に吸収される程度の規模ではないかと思います。いうまでもありませんが、買取申出に至る土地がどのエリアにあるのかによっても、インパクトの度合いは違います。人気のエリアも含まれるかもしれません。しかし、例えば都心3区、都心5区にはそもそも農地がありません。
このようなことから、不安視されている不動産市場への影響は全体で見れば極めて限定的だといえます。憂慮すべきはむしろ、郊外の土地活用です。エリア別に見れば、都心に近いほど生産緑地の割合が高く、郊外に行くほど宅地化農地の割合が高くなっています。郊外では、宅地化農地が多く残っているのです。宅地需要が低いにもかかわらず今後、宅地への転用が進めば、空き地・空き家がさらに増える恐れがあります。2022年問題の本質は、盛んに懸念されていた都心部の地価暴落ではなく、郊外で土地利用のアンバランスが生じ、使えない土地が増えていくことにあるかもしれません。

農地があることがむしろ魅力になりつつある
生産緑地の10年延長措置によって、多くの農地が今後も都内に残る見込みです。生産緑地法に象徴されるように、かつて都心の土地活用においては農地をつぶす流れがありましたが、今はその反対で、農地に注目が集まっています。農林水産省が三大都市圏を対象に行った調査によると、地元の農地を残したいと考えている人は75%にのぼります。逆に「宅地化すべき」と回答した人は、わずか2.2%でした。
実際、この10年ほどの間に、都市部に農園や緑地を造る動きは非常に活発になっています。大阪のあべのハルカス、表参道の東急プラザ表参道原宿、恵比寿ガーデンプレイスなどで話題になった「屋上農園」が増え続けていたり、生産緑地の一区画を借りるレンタル農園ビジネスが急成長していることからも、「農」に対する関心の高さがうかがえます。不動産事業においては、積極的な農の創出、農を絡めた商品展開を図ることが、トレンドのひとつになるかもしれません。
そしてそれには、最大の消費者数を抱える東京が有利なのです。東京の農家は戦略的に考えていて、直売を積極的に行っています。消費者側も、身近な場所で新鮮なものを買えることや、生産者の顔が見えることに、大きな魅力があると感じています。距離が近くなったことで、作って売る人(生産者)・買って食べる人(消費者)という対立関係を超え、生産者が生産過程や流通過程の情報も提供し、消費者はそれも含めて楽しむというように、消費の方法も変わりつつあります。農のアクティビティ化といってもいいでしょう。
75%もの住民の支持は、自分が口にするものが身近な土地で育つことに、豊かさを感じる人が増えていることの表れともいえます。この傾向が今後さらに発展することは明らかで、この点にきちんと目を向けることが、不動産市場の活性化につながると思います。
■お話しいただいた方
塩澤誠一郎 様
しおざわ・せいいちろう
ニッセイ基礎研究所社会研究部都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任。
2004年、(株)ニッセイ基礎研究所入社、2020年より現職。技術士(建設部門都市及び地方計画)。専門は都市・地域計画、土地・住宅政策、文化施設開発。2022年問題関連の主なレポートに『「2022年問題」に警鐘を鳴らす』(「研究員の眼」2015.6)、『生産緑地法改正と2022年問題』(「ニッセイ基礎研レポート」2017.5)など。

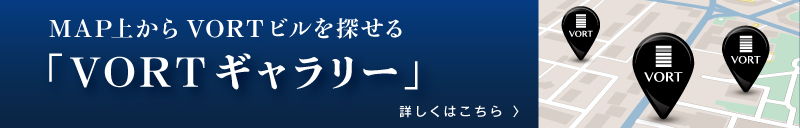
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。


