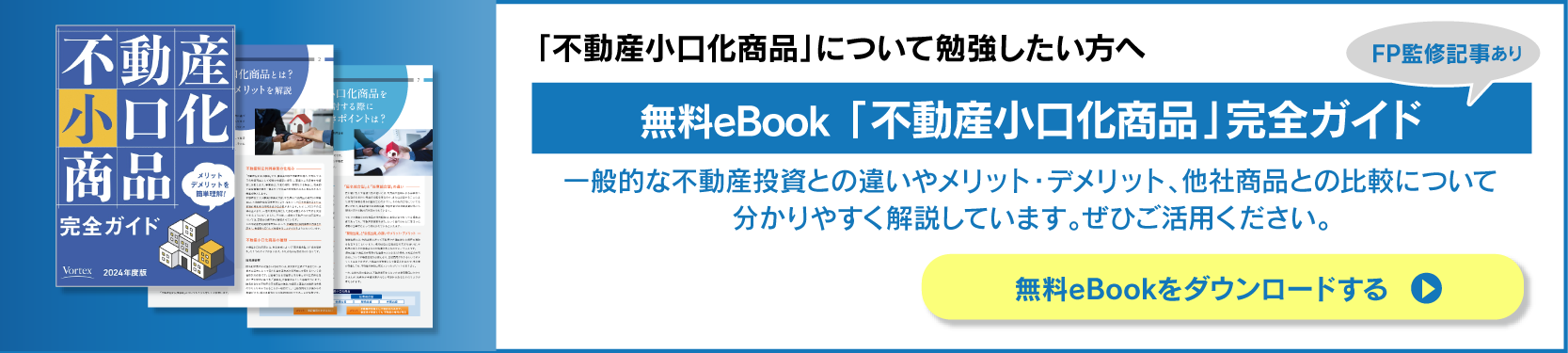目次
マンション経営によって賃料収入で生活の向上を検討される方は少なくありません。安定した賃料収入は生活レベルを高めるだけでなく、さらなる資産増加を目指すことも可能です。例えば、新たにマンションを購入することで資産を増やすこともできます。
しかし、それは安定した賃料収入があってこそ。安定した賃料収入を実現するためにはマンション経営にまつわるリスクを可能な限り抑える必要があります。
そこでこの記事では、マンション経営におけるリスクとリスクを抑える方法について解説していきます。
1. マンション経営にまつわる9つのリスク
まずは、マンション経営において想定されるリスクの種類についてご紹介します。マンション経営で失敗しないためには、どのようなリスクがあるのかをしっかりと把握しておきましょう。
1-1. 空室リスク

マンション経営を始めるときに、必ず頭に入れておかなければならないのが、空室リスクです。
空室が発生するとその期間中は賃料収入を得ることができません。
空室リスクを減らす対策として、「空室保証」と「サブリース」の2つがあります。
空室保証とは、空室期間中、保証会社が賃料の一定額を保証する制度です。オーナーが保証会社に毎月定額の保証料を支払うことにより、万が一、空室が発生し、家賃収入が一定水準以下に下がったときに、満室時家賃の80%や90%といった決められた家賃収入が保証されます。空室保証と呼ばれていますが、実際には「家賃を補てんするサービス」といえます。
サブリースとは、サブリース会社がオーナーから物件を一括して借り上げ、入居者に転貸する仕組みです。オーナーは毎月一定額の家賃をサブリース会社から受け取るため、入居者の有無にかかわらず、オーナーは安定した収入を得ることができます。ただし、オーナーの受け取る家賃は、入居者がサブリース会社に支払う家賃よりも低くなります。
「空室保証」や「サブリース」を利用すれば空室リスクを下げることはできますが、空室リスクが完全になくなるわけではありません。
そのため、多くの人が借りたいと思う、競争力がある物件を選択することが重要です。
競争力がある物件とは、たとえば下記のような条件を備えているような物件です。
- 駅からの距離が近い
- 間取りが広い、設備やセキュリティなどに優れている
- 築年数が浅い
- 近くにスーパーやコンビニ、病院があるなど、生活利便性が高い
- 管理会社によって設備のメンテナンス、清潔感が保たれている
安定して賃料収入を得るためにも、多くの入居者に好まれる物件を取得することが重要です。
なお、物件探しの際には、利回りが高い物件に注意する必要があります。地方は都市部に比べて土地の価格が安いため、利回りが高くなりやすい傾向にありますが、その一方で、人口が少なく入居需要が低いと空室率が高くなりやすいという不安もあります。
地方で物件の取得を検討する場合は、賃貸市場としての需要があるかを長期的な視点に立って確認することが重要です。
1-2. 家賃の下落リスク

一般的に、建物の築年数が経過すると家賃は下落していく傾向にあります。
また、家賃下落のリスクはこのほかにもあります。
家賃が下落するケースの例は下記のとおりです。
- 築年数が古い
- 近隣により優れた競合物件ができた
- 前の入居者の使い方によって、建物に問題が生じた
- 地震や大雨等の自然災害によって建物に損傷が生じた
また、人口減少が進み入居需要が減少したりすることも家賃の下落の原因となります。
つまり、建物価値の下落など直接的な原因だけでなく、近隣環境の変化や経済状況の変動によって家賃を値下げしないと入居者がつかない、というケースも起こり得るのです。
建物の状況確認する以外にも、近隣に新しい物件が建ちそうな空き地や計画はないか、自然災害に強い場所に建っているかなど、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
また、家賃の下落をあらかじめ想定した収益のシミュレーションを作成しておくことも重要です。
1-3. 自然災害リスク

日本では自然災害リスクを完全に回避するのは不可能と言えるため、購入時の慎重な検討とリスク軽減の対策は重要です。
1. 地震、台風、大雨、洪水などによる物理的損壊
自然災害によってマンションが損傷した場合、修理、回復に大きな費用が発生する場合があります。
2. 火災保険や地震保険の保険料の上昇
地震保険は地震被害の発生確率により料率が異なります。また、水災リスクの高い地域では、火災保険の水災料率が高くなります。
3. 入居の継続・再入居ができない
床上浸水などによって居住できなくなった、また復旧まで人が住めない場合などは賃料収入を得ることができません。また、被災したという過去によって新たな入居者づけが困難になる可能性もあります。
これらの対策としては、過去の被災状況やハザードマップなどを事前に確認し、災害リスクの高い地域を避けることが重要です。
1-4. 修繕リスク

建物は15年から20年に1回程度は大規模修繕が必要と言われています。
そのため、毎月の賃料収入から修繕費を積み立て、大規模修繕費を確保しておく必要があります。
また、大規模修繕以外にも、入居者が退室した際の原状回復、設備の修理・交換などにより突発的な修繕費用がかかることがあります。
急に高額な修繕費が必要になっても慌てないように、あらかじめ予算を計画して準備しましょう。
1-5. 不動産価格変動リスク
マンションの価格は、立地や築年数、不動産市場の動向や景気などによって左右されるため、価格変動リスクがあります。
そのため、購入したマンションを売却しようとした場合、購入価格よりも売却価格のほうが高くなることがありますが、反対に安くなってしまうこともあります。
不動産の価格に影響を与える要因は次の通りです。
- 立地条件
不動産の価値はその地理的な位置に大きく依存します。前述したとおり商業施設、学校、交通へのアクセスに優れるエリアは一般的に高価格になる傾向があります。
反対に自然災害などで建物や都市機能にダメージを受けると価格が下落する場合があります。 - 物件の老朽化
一般的に、建物の老朽化が進むと価格は下落していきます。築年数の他、建物や設備の維持管理の状態、間取りなどは価格に大きな影響を与えます。 - 需要と供給のバランス
周辺にマンションやアパートが過剰に建築され、供給が需要を上回ると、収益不動産の価格が下落する場合があります。
一方で、開発などにより地域の利便性が向上すると、人口が流入し、収益不動産の価格が上昇する傾向があります。
投資用のマンションを選ぶ際は、できるだけ価格が下がりにくい立地や構造の物件を選ぶようにしましょう。
1-6. 金利上昇リスク
マンション経営を始める場合、ローンを組んでマンションを購入することも少なくありません。
ローンの金利が低い時期に借入れをしても、その後の経済状況や社会情勢によって金利が上昇する場合があります。
金利が上昇するとローン返済額も増えてしまうため、手取り額の減少や、空室時に返済ができなくなるなどのリスクが生じます。
1-7. 入居者トラブルリスク
マンション経営においては、入居者同士のトラブルによるリスクも考慮しておく必要があります。
せっかく入居者がついたのに、隣人トラブルによって早くに退去されてしまった、ということが発生する場合もあるでしょう。
入居者トラブルでよくあるケースは下記の通りです。
- 騒音問題
音楽やテレビの音量、生活音(掃除機の音、洗濯機の音、歩く音など)、夜間や早朝の騒音(パーティーなど) - ペットによるトラブル
ペットの鳴き声や臭い、散歩時のマナーの悪さ(フンの始末など) - 共用スペースの利用
駐車場の不正利用や共用部分での物の放置、ゴミ出しのマナー違反など - 喫煙によるトラブル
廊下やエントランス、バルコニーでの喫煙による匂いや煙、吸い殻の不始末など
トラブルを未然に防ぐ配慮をすることはもちろん、トラブルの早期改善を図ることで入居者との信頼関係を築きましょう。
1-8. サブリースリスク
サブリースとは、サブリース会社が物件を賃借し、転貸する仕組みのことです。
マンション経営においては、サブリース会社がマンションの一室や全体を借り上げ、その部屋を入居者に転貸します。しかし、サブリースには以下のようなリスクが存在します。
- サブリース会社の経営破綻
サブリース会社が倒産した場合、賃料の未払いリスクが発生します。また、その後の賃貸先の確保も難しくなる可能性があります。 - 物件の管理状況
サブリース会社が物件の管理を怠ったり、テナントが物件を荒らしたりした場合、物件価値が下がるリスクがあります。また、サブリース会社とオーナーとの間で管理責任が明確になっていないと、修繕費用の負担問題も起こり得ます。
サブリースを活用することができれば、手間を減らしながら賃料収入を得ることが可能です。
メリット・デメリットやリスクを踏まえ、適切な方法を選択しましょう。
1-9. 火災リスク
マンション経営における火災リスクは非常に重要な要素です。
火災が起きない・起こさないことが理想ですが、万が一に備えて火災の影響を認識しておきましょう。
- 人命のリスク
火災が発生すると、最も大きなリスクは人命が失われる可能性です。特にマンションには多くの人が居住しているため、避難経路の確保や防火設備の整備が重要です。 - 建物の損害
火災が発生すると、マンション自体が損傷を受け、修復に大きな費用がかかる可能性があります。
また、全焼した場合は再建にはさらに時間と費用がかかります。特に、木造の場合は燃え上がるスピードが早く、全焼する可能性が高まります。 - 収益の損失
火災によりマンションが使用不能になった場合、修復が完了するまでの間、賃料収入を得ることができません。
しかし、火災や災害に備えて空室補填(収入保障)が付保できる総合保険に加入しているオーナーも多く、これにより収益の損失を軽減することができます。
火災は一度起きてしまうと建物に深刻なダメージを与え、最悪の場合建て直しが必要になってしまうこともあるでしょう。
保険等に加入しておくことで、火災による最悪の事態に備えておきましょう。
2.マンション経営を始める前に確認しておいたほうがよいポイント

ここからは、マンション経営において、事前に確認しておいたほうがよいポイントをご説明します。
2-1. 入居者が付きやすい条件を備えた物件を選ぶ
空室リスクや家賃の下落リスクを避けるためには、十分に市場調査や物件調査を行い、需要と供給のバランスがよい物件、つまり人気の物件を選ぶことが大切です。
入居者が付きやすい条件は下記の通りです。
- 駅からの距離が近い
- 間取りが広い、設備やセキュリティなどに優れている
- 築年数が浅い
- 近くにスーパーやコンビニ、病院があるなど、周辺環境に優れている
- 管理会社によって設備のメンテナンス、清潔感が保たれている
なお、市場調査については、不動産会社からの情報だけではなく、実際にその物件に足を運び、駅からの距離やアクセスの状況、周辺に学校や公共施設・商業施設があるかなど、周辺エリアの環境をご自身の目で確認したうえで、入居者が見込めるかどうかを判断することも必要です。
2-2. 賃貸管理のポイント
管理会社の選び方もマンション経営のリスクヘッジとして重要です。
マンションなどの物件管理はオーナー自身が行うことも可能ですが、かなり手間がかかります。
そのため、管理会社と管理委託契約を結び、以下の業務を任せることが一般的です。
- 入居者の募集や契約
- 家賃の集金
- 日常的な清掃
- 入居者からのクレーム対応
- 退去時の立会い
- 原状回復作業
管理会社の対応がマンション経営に与える影響は大きいため、信頼できる管理会社を選ぶようにしましょう。
2-3. 金利上昇リスクへの対策
金利上昇リスクへの対策としては、自己資金割合を増やすという方法があります。
自己資金割合を増やし、借入れ金額を減らすことにより、賃料収入に対するローン返済比率が下がるため、金利が上昇してもリスクを軽減することができます。
また、返済比率を下げることは、金利上昇リスクだけではなく、空室発生中のコスト軽減にもなります。
あらかじめ金利上昇を加味したシミュレーションを作成し、検討することが重要です。
2-4. 自然災害リスクへの対策
マンション経営における自然災害リスクへの対策として立地の選択は極めて重要です。
立地は一度選択してしまうと取り返しがつかず、失敗した場合は売却するほかありません。
そのため、下記を参考に立地を選択してください。
1. 地震
地震のリスクを評価するために、地震ハザードマップを利用して、揺れやすい地盤や液状化の可能性を確認します。また、建物の耐震性も重要な要素です。建物が現行の耐震基準を満たしているか、耐震補強が行われているかを確認しましょう。
耐震性の確認方法
- 建築年の確認
建物が建てられた年を確認し、その時期の耐震基準を調べます。一般的に、1981年6月1日以降に建築確認を申請して建てられた建物は新耐震基準を満たしています。 - 耐震診断の実施
旧耐震基準により建築された建物については、地震活動が活発な地域かどうかを調査します。地震ハザードマップを利用して、地盤の状態や過去の地震の発生状況を確認します。
また、近隣に老朽化した建物が無いか、現地を確認しておきましょう。地震が発生した際に近隣建物の倒壊によって、保有物件が損壊するリスクを避けるためです。
2. 洪水
洪水ハザードマップを確認し、洪水のおそれがある地域を避けましょう。
また、河川や海から遠く、高台にあるかも確認しておきましょう。河川から離れていてもくぼ地だった場合、氾濫した大水が流れ込む可能性があります。
3. 火災
建物の構造について確認しておきましょう。
耐火性がある鉄筋コンクリート造や耐火性の高い外装材を用いた建物であれば安心ですが、古い木造は耐火性能が劣るため、延焼や類焼による損害を受ける不安があります。
周辺の状況や隣地の建物についても確認しておきましょう。たとえば、住宅密集地で、隣家の古い木造建物が迫って建っている場合などには、隣家の火災により保有物件に被害が生じるおそれがあります。
4. その他
地滑りや崖崩れのおそれがある傾斜地や、津波のおそれがある海岸沿いの地域などは避けましょう。
ハザードマップとは、被害予測地図ともいい、各自治体が自然災害により被害が想定されるエリアや避難場所を地図にまとめたものです。
どれだけ被災しづらい立地・建物を選択したとしても万が一はつきものです。
有事に備えて、火災保険や地震保険に加入しておくことをおすすめします。
3. マンション経営はライフスタイルに合わせたリスクヘッジを

マンション経営のような不動産投資では、投資の目的やライフスタイルに合わせて許容できるリスクを把握しておくことも必要です。
たとえば定年退職後に退職金を利用してマンション経営を始め、老後資金を確保したいという方の場合、退職金をすべて使って投資用マンションを購入することはリスクが高いと言えます。
一般的に、実物不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンの投資とされています。そのため、老後の大切な資金をすべて不動産投資に投入するのは避けたほうがよいでしょう。
退職金を運用して老後資金をつくる場合は、マンション経営に退職金全額を投資するのではなく、できるだけリスクを抑えた分散投資をおすすめします。
4. 最後に
今回は、マンション経営のリスクとリスクヘッジの方法についてご説明してきました。
マンション経営は長期的に安定した収益が得られる人気の投資手法ですが、やはり投資額が高額な分、少しのリスクが大きな影響を与えます。
また、定年退職後の退職金運用など、その目的によっては適さないケースも出てくるでしょう。
************************************
もし、「不動産投資は難しそう」と感じられましたら、弊社の不動産小口化商品「Vシェア」をご検討ください。
「Vシェア」は、希少性の高い都心の中規模オフィスビルを小口化し、1口100万円単位・5口以上(最低口数は変更となる場合があります)からの購入を可能にした商品です。
マンション経営と同じく、毎月の運用収益の分配や、一定期間運用後の売却利益の分配を目的とした不動産投資や資産運用に適しています。
不動産投資のなかでもオフィスビルへの投資は、アパート・マンションなどの住居系不動産よりも需給バランスがタイトなため、賃料下落リスクが比較的低く、安定性の高い魅力的な投資対象といえます。
さらに、少額な資金で不動産投資を始めることができるため、退職金の運用をはじめとする長期分散に大変適した商品です。
もちろん、対象となるオフィスビルなどの管理・運用は弊社が責任を持って実行しますので、不動産の維持管理のために何かをしなければならない、ということは発生しません。
また、1口単位で分配することができるため、不動産小口化商品は相続対策として活用されることも多いです。
「Vシェア」についてより詳しく知りたい方は下記をクリック
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
不動産投資の記事一覧に戻る