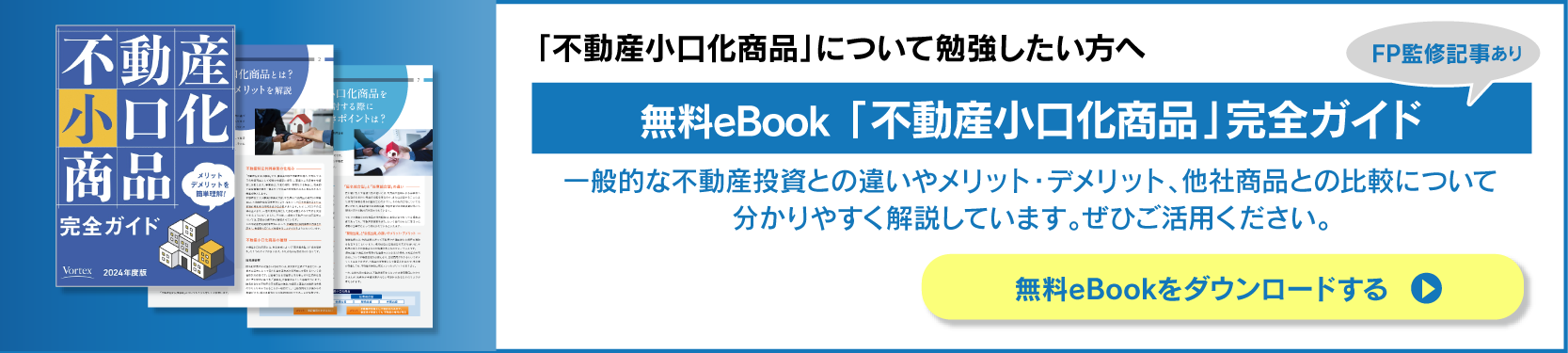目次
資産の増加や生活の向上を目的に、マンション経営を検討される方は少なくありません。賃料収入が安定し、最終的に不動産の売却益を得られれば、新たにマンションを購入してさらなる資産の増加も目指せます。
一方、こうした利益を実現するためには、マンション経営にまつわるリスクを知り、対策をとることが必要です。
そこで本記事では、マンション経営の収益構造と9つのリスク、マンション経営に着手する前に検討すべきポイントを紹介します。
1. マンション経営の概要
マンション経営とは、「経営」とはいうものの、不動産投資の一形態です。マンションを取得し、入居者を募って部屋を貸し出して得る賃料収入がおもな収益です。また、将来的に物件を購入時よりも高い価格で売却できれば、売却による収益も見込めます。
マンション経営には大きく分けて2つの方法があります。マンションを一棟まるごと購入して運営する「一棟マンション投資」と、マンションを1室単位で取得して賃貸に出す「区分マンション投資」です。(区分マンション投資は「ワンルーム投資」ともいいます。)それぞれ初期費用や発生する業務が異なり、資金力やかけられる労力に応じて選択する必要があります。
その他の不動産投資については「不動産投資7種類を徹底比較!初心者におすすめの種類は?」で解説しています。
2. マンション経営の利益構造

投資で得られる利益は、その性質から「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2種類に分けられます。ここではマンション経営におけるインカムゲインとキャピタルゲインについて整理していきましょう。
2-1. インカムゲイン
インカムゲインとは、資産を保有している期間中に得られる収益です。マンション経営では、入居者からの賃料収入がインカムゲインにあたります。
ただし、マンションの取得にあたり金融機関からの融資を受けた場合、基本的には賃料収入で借入金を返済していくことになります。そのほかにも修繕積立金や各種税金などのコストが発生するため、とくに経営の初期段階では、賃料収入から支払う費用も多い点は理解しておくとよいでしょう。
2-2. キャピタルゲイン
一方、キャピタルゲインとは、資産の売却によって得られる売買差益を指します。マンション経営においては、取得したマンションを取得金額よりも高い価格で売却できた場合に発生します。
しかし、不動産価格は経済や不動産市場の状況によって変動しますし、借り入れの状況も人それぞれです。したがって、マンション経営でキャピタルゲインを得るには、計画性やリスクへの対策が重要です。
3. マンション経営にまつわる9つのリスク

ここからは、マンション経営で想定されるリスクを9種類紹介します。失敗を防ぐためにも、どのようなリスクがあるのかしっかりと把握しておきましょう。
3-1. 空室リスク
マンション経営を始めるとき、必ず頭に入れておくべきリスクが空室リスクです。
空室が発生すると、次の入居があるまで賃料収入を得られず、収益が減ってしまいます。
空室リスクを減らす対策としては、「空室保証」と「サブリース」の2つがあります。
空室保証とは、空室期間中、保証会社が賃料の一定額を保証する制度です。オーナーは保証会社に毎月定額の保証料を支払う代わりに、万が一、空室により賃料収入が一定水準を割ったときには、満室時賃料の80%や90%など決められた賃料収入を保証してもらえます。空室保証と呼ばれていますが、実際には「賃料を補てんするサービス」といえます。
また、サブリースとは、サブリース会社がオーナーから物件を一括して借り上げ、入居者に転貸する仕組みです。オーナーは毎月一定額の賃料をサブリース会社から受け取るため、入居者の有無に関わらず安定した収入を得られます。ただし、オーナーが受け取る賃料は、入居者がサブリース会社に支払う賃料よりも低くなります。
このように、空室保証やサブリースを利用すれば空室リスクを低減できますが、その分コストがかかるため、やはり空室リスクの低い、優良な物件選びが重要です。
3-2. 賃料の下落リスク
賃料の下落は収益の下落に直結します。たとえば建物の賃料は、築年数の経過とともに下落していく傾向にあります。賃料の下落を招くおもな要素をみてみましょう。
- 築年数が古い
- 近隣に、より優れた競合物件が建った
- 前の入居者の使い方により、建物に問題が生じた
- 地震や大雨などの自然災害によって建物に損傷が生じた
- 人口減少が進み、入居需要が減少している
ご覧のとおり、賃料の下落は建物そのものの価値の下落といった直接的なものに限りません。近隣環境の変化や経済の動向により、「賃料を下げないと入居者がつかない」というケースも起こり得ます。
マンションの取得前には、建物の状況以外に、近隣に新しい物件が建ちそうな空き地や計画はないか、自然災害に強い場所に建っているか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
あわせて、賃料が下落した場合の収益まで事前にシミュレーションしておくことも重要です。
3-3. 自然災害リスク
日本では自然災害リスクの完全な回避は不可能といえるため、購入時の慎重な検討と、災害リスクへの対策は欠かせません。自然災害がマンション経営に及ぼす影響はおもに3つあります。
1. 地震、台風、大雨、洪水などによる物理的損壊
地震や台風などの自然災害は建物に大きな損傷を与えるおそれがあります。マンションが損傷すれば、損傷の度合いによっては修理や回復に大きな費用が必要になるかもしれません。
2. 地震保険や火災保険の保険料の上昇
自然災害は保険料にも影響を及ぼします。
たとえば地震保険は地震被害の発生確率により料率が異なり、水災リスクの高い地域では、火災保険の水災料率が高くなります。
3. 入居の継続・再入居ができなくなる
床上浸水などによって居住できなくなった、また復旧まで人が住めない場合などは、賃料収入を得られません。さらに「過去に被災した」という理由で新たな入居者づけが困難になる可能性もあります。
こうした自然災害リスクに対しては、あらかじめ過去の被災状況やハザードマップなどを確認し、災害リスクの高い地域を避けた物件選びが重要です。
3-4. 修繕リスク
建物は15年から20年に1回程度は大規模修繕が必要といわれています。それ以外にも、入居者が退室した際の原状回復、設備の修理・交換などにより突発的な修繕費用を要するケースもあります。
毎月の賃料収入から修繕費を積み立てて大規模修繕に備えるとともに、急に高額な修繕費が必要になっても慌てないよう、予算を立てて計画的に資金を準備しましょう。
3-5. 不動産価格変動リスク
不動産の価格は、立地や築年数、不動産市場の動向、景気などさまざまな要素で左右され、同じ物件でも常に一定というわけではありません。
そのため、購入したマンションを売却しようとする際、売却価格が購入価格より高くなることもあれば、安くなってしまうこともあります。
不動産の価格に影響を与える要因は以下のとおりです。
- 立地
不動産の価値はその地理的な位置に大きく依存します。商業施設や学校、交通へのアクセスに優れるエリアは一般的に高価格になる傾向があります。反対に、自然災害などで建物や都市機能がダメージを受けると、価格は下落することがあります。 - 物件の老朽化
建物の老朽化が進むと、不動産価格は下落するケースが一般的です。築年数のほか、建物や設備の維持管理の状態、間取りなども価格に大きな影響を与える要素です。 - 需要と供給のバランス
周辺にマンションやアパートが過剰に建築され、供給が需要を上回ると、収益不動産の価格が下落する場合があります。一方で、開発などにより地域の利便性が向上すれば、人口が流入し、収益不動産の価格は上昇する傾向があります。
物件選びの際は、時間が経ってもできるだけ価格が下がりにくい立地や構造の物件を精査しましょう。
3-6. 金利上昇リスク
マンションの取得にあたり、金融機関からの融資を受けるケースも少なくありません。
借り入れをしたときには金利が低くても、その後の経済状況や社会情勢によっては金利が上昇することもあります。金利が上昇すれば借入金の返済額も増えてしまうため、手取り額の減少や、空室時に返済が滞るなどのリスクが生じます。
3-7. 入居者トラブルのリスク
マンション経営においては、入居者間のトラブルも想定しておきましょう。
入居者トラブルでよくある例は下記のとおりです。
- 騒音によるトラブル
音楽やテレビの音量、生活音(掃除機や洗濯機など家電の音、歩く音など)、夜間や早朝の騒音(パーティーなど) - ペットによるトラブル
ペットの鳴き声や臭い、散歩時のマナーの悪さ(フンの始末など) - 共用スペースの利用マナーによるトラブル
駐車場の不正利用や共用部分での私物の放置、ゴミ出しのマナー違反など - 喫煙によるトラブル
廊下やエントランス、バルコニーでの喫煙による臭いや煙、吸い殻の不始末など
トラブル抑止の配慮はもちろん、万が一トラブルが発生した際には早期対処を図り、入居者との信頼関係を築きましょう。
3-8. サブリースリスク
先述のとおり、マンション経営におけるサブリースとは、サブリース会社がマンションの1室や全体を借り上げて入居者に転貸する仕組みです。
オーナーはサブリースの利用によって空室リスクを低減できますが、サブリース自体にも以下のようなリスクがある点は理解しておきましょう。
- サブリース会社の経営破綻
サブリース会社の倒産により、賃料の未払いリスクが生じます。さらに、その後は賃貸先の確保が難しくなる可能性もあります。 - 物件の管理状況
サブリース会社による怠慢な物件管理や、テナントによる物件の損傷は、物件価値の下落につながりかねません。また、サブリース会社とオーナーとの間で管理責任が明確になっていなければ、修繕費用の負担問題も起こり得ます。
サブリースを活用できれば、オーナーとしての手間を減らしながら賃料収入を得られます。メリット・デメリットやリスクを踏まえて適切な方法を採りましょう。
3-9. 火災リスク
マンション経営において、火災は非常に大きなリスクです。火災が起きない・起こさないことが理想ですが、万が一に備えて火災の影響を認識しておきましょう。
- 人命への影響
火災は人命が失われる可能性のある災害です。とくにマンションは多くの人が居住する建物のため、避難経路の確保や防火設備の整備が欠かせません。 - 建物の損害
火災によってマンション自体が損傷し、修復に大きな費用がかかる可能性があります。全焼となれば再建にはさらに時間と費用がかかります。なかでも木造物件は燃え上がるスピードが早く、全焼する可能性が高まるため注意が必要です。 - 収益の損失
火災でマンションが燃えて使用不能になれば、修復が完了するまでの間は賃料収入を得られません。火災や災害に備えて空室補填(収入保障)を付保できる総合保険に加入しているオーナーも多く、保険によって損失を軽減できます。
火災は人命に危険を及ぼすうえ、建物にも深刻なダメージを与え、最悪の場合には建て直しを要するかもしれません。保険などに加入して火災のリスクに備えておきましょう。
4. マンション経営のメリット
マンション経営はリスクがある一方で、上手に運用できれば資産形成に役立つ側面も持っています。
ここでは、マンション経営の代表的なメリットを3つ紹介します。
4-1. 安定的に収入を得られる可能性がある
生活拠点として利用されるマンションは入居期間が比較的長期になる傾向があり、一度入居者がつけば安定的な賃料収入を見込みやすい点が特徴です。
とくに一棟マンション投資などで部屋数が多くなるほど、一部の空室があっても収益全体への影響を抑えやすいとされています。一方、区分マンション投資で1室のみを運用するケースでは、空室はそのまま無収入につながるため、空室リスクへの備えがより重要になります。
また、物件の取得にあたって金融機関から融資を受けた場合は、賃料収入から借入金を返済するため、キャッシュフローは黒字化しにくいといえるでしょう。自己資金で物件を取得していれば、初期段階から黒字で運営できる可能性があります。
4-2. 金融機関から融資を得る場合、自己資金より大きな投資に取り組むことができる
収入や資産の状況など個人の属性にもよりますが、マンション経営では、マンションの取得にあたって金融機関からの融資を利用できます。融資を受けられれば、自己資金の範囲を超えた規模の投資も可能となるでしょう。
とくに区分マンション投資においては、頭金なしで物件価格の全額の融資を受けられるケースもあります。
金融機関からの借り入れを利用できる点は実物不動産投資ならではの特徴です。ほかの不動産投資や金融商品と比較しても、投資額に対して少ない初期資金で始められる点が魅力とされています。
とはいえ、借入額が大きくなるほど返済負担も大きくなるため、収支のシミュレーションをおこない、無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
4-3. インカムゲインとキャピタルゲインの両方を狙える
マンション経営では、インカムゲインにあたる賃料収入と、売却時に得られるキャピタルゲインの双方を期待できる点も特徴です。
これは株式投資でも同様ですが、株式の配当金や株価は企業の業績や景気によって比較的大きく変動するため、価格変動リスクは大きいといえるでしょう。一方、マンションの賃料や不動産価格も変動はするものの、株式に比べると緩やかな傾向がみられます。
安定的な賃料収入と将来の売却益を得るためには、物件選びや、売却を見据えた計画性が重要です。具体的には、金融機関からの融資を利用する場合は月々の賃料収入で借入金を返済し、物件価格が残債を上回るタイミングで売却するなど、出口戦略を事前に考えておきましょう。
5. マンション経営を始める前に検討しておきたいポイント

マンション経営では、物件選びやリスク対策のほかにも、事前に確認しておきたいポイントがあります。ここからは、マンション経営におけるおもな検討項目を紹介します。
5-1. 入居が見込める条件の充足
空室リスクや賃料の下落リスクを避けるためには、市場調査や物件調査を十分におこない、需要と供給のバランスがよい物件、つまり人気の物件を選ぶことが大切です。
一般的に入居者がつきやすいとされている物件の条件は以下のとおりです。
- 駅からの距離が近い
- 間取りが広い
- 設備やセキュリティなどに優れている
- 築年数が浅い
- 近くにスーパーやコンビニ、病院があるなど、生活利便性が高い
- 管理会社によって設備のメンテナンス、清潔感が保たれている
市場調査は不動産会社からの情報に目を通すだけでなく、実際に現地に足を運ぶことも大切です。駅からの距離やアクセスの状況、近隣の施設や周辺エリアの治安などを入居者の立場になって確認し、住みやすく、魅力的な物件かどうか判断しましょう。
また、利回りが高い物件には少し注意が必要です。地方は都市部に比べて土地の価格が安く、利回りが高くなりやすい傾向にあります。その一方で、人口が少なく入居需要が低いと空室率が高くなりやすい点が懸念されます。
地方で物件の取得を検討する方は、賃貸市場として需要があるかを長期的な視点で確認しましょう。
不動産投資の利回りについては「不動産投資の利回りとは?利回りが高い物件に潜むリスクと不動産投資で重要なポイント【FP監修】」でより詳しく解説しています。
5-2. 賃貸管理のポイント
管理会社の選び方もマンション経営のリスクヘッジとして重要です。
オーナー自身がマンションを管理しても構いませんが、かなり手間がかかります。したがって、管理会社と管理委託契約を結び、以下の業務を任せることが一般的です。
- 入居者の募集や契約
- 賃料の集金
- 日常的な清掃
- 入居者からのクレーム対応
- 退去時の立会い
- 原状回復作業
管理会社の対応がマンション経営に与える影響は大きいため、信頼できる管理会社を選びましょう。
5-3. 金利上昇リスクへの対策
金利上昇リスクへの対策としては、自己資金の割合を増やす方法があげられます。
自己資金割合を増やして借入金額を少なくすると、賃料収入に対して借入金の返済比率が下がります。これによって金利上昇のリスクを軽減できるとともに、空室発生中の返済負担の軽減にもつながります。
あらかじめ金利上昇を加味したシミュレーションを作成し、自己資金の割合を検討しておきましょう。
5-4. 災害リスクへの対策
マンション経営における自然災害リスクへの対策として、立地の選定は極めて重要です。一度物件を取得してしまうと取り返しがつかず、失敗した場合は売却するほかありません。立地の選定には以下を参考にしてください。
1. 地震・津波
地震のリスクを評価するには「地震ハザードマップ」を利用し、揺れやすい地盤や液状化の可能性を確認します。ハザードマップは被害予測地図ともいい、自然災害による被害が想定されるエリアや避難場所を各自治体が地図にまとめたものです。
また、建物の耐震性も重要な要素です。建物が現行の耐震基準を満たしているか、耐震補強がおこなわれているか、以下の方法で確認しましょう。
- 建築年の確認
建物が建てられた年を確認し、その時期の耐震基準を調べます。一般的に、1981年6月1日以降に建築確認を申請して建てられた建物は新耐震基準を満たしています。 - 耐震診断の実施
旧耐震基準により建築された建物については、地震活動が活発な地域かどうかを追加で調査しましょう。地震ハザードマップを利用して、地盤の状態や過去の地震の発生状況を確認します。あわせて、近隣に老朽化した建物がないか、現地を視察しておきましょう。地震が発生した際、近隣建物の倒壊によって保有物件が損壊するリスクを避けるためです。
2. 洪水・地すべり・崖崩れ
洪水のリスクについては「洪水ハザードマップ」を確認し、洪水のおそれがある地域を避けましょう。また、河川や海から遠く、高台にあるかどうかも調べておきます。河川から離れていても、くぼ地の場合は氾濫した大水が流れ込む可能性があるため注意が必要です。
そのほか、地すべりや崖崩れのおそれがある傾斜地や、津波のおそれがある海岸沿いの地域なども避けましょう。
しかし、どれだけ被災しづらい立地・建物を選択したとしても、万が一はつきものです。有事に備えて、火災保険や地震保険へ加入しておくことをおすすめします。
3. 火災
火災のリスクは、建物の構造からある程度分かります。耐火性がある鉄筋コンクリート造や耐火性の高い外装材を用いた建物であれば安心ですが、古い木造は耐火性能が劣るため、延焼や類焼による損害を受ける不安があります。
あわせて、周辺の状況や隣地の建物についても確認しておきましょう。具体的には、住宅密集地かつ隣家の古い木造建物が迫って建っている物件では、隣家の火災により保有物件に被害が生じるおそれがあります。
5-5. リスク許容度
マンション経営に限りませんが、投資においては目的やライフスタイルに応じて、ご自身が許容できるリスクを把握しておくことも大切です。
たとえば「定年退職後に退職金を活用してマンション経営を始め、老後資金を確保したい」と考える方の場合、退職金の全額をマンション購入に充てるような資金配分はリスクが高いといえます。
一般的に、実物不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンの資産運用と位置づけられています。したがって、この場合は老後の大切な資金となる退職金をすべて不動産投資に投じるのではなく、分散投資に取り組んでリスクを抑える方法がおすすめです。
5-6. 使える金額
リスク許容度と似ていますが、マンション経営を始める前に、投資に使える自己資金を現実的に考えておきましょう。
先ほどのように退職金を活用する場合でも、退職後の収入や生活資金、突発的な支出への備えなどを差し引いたうえ、無理のない範囲で計画を立てる必要があります。
マンション経営においては、満室になるまでの初期段階ではとくに、赤字が続く可能性も考慮しておかなければなりません。感覚に頼るのではなく、不安な方はFPなどの専門家の力も借りながら、現実的に使える金額を把握しておきましょう。
6. 最後に
マンション経営は長期的に安定した収益を得られる人気の投資手法ですが、投資額が大きい分、少しのリスクが大きな影響を与えます。また、近年少子高齢化という背景もあり、住居系の不動産を投資対象とすることにリスクを感じる方も少なくありません。
もしマンションやアパートといった不動産投資にこだわらないのであれば、弊社が取り扱っているような商業中心地のオフィスビルに投資する方法があります。商業中心地に位置するオフィスビルは、空いた土地が少ないことから供給が少なく、それでいてエリアを厳選すればテナント需要が強い傾向が見られます。
ご自身の投資の目的を実現できるようであれば、ひとつの選択肢として検討してみるとよいでしょう。
※オフィスビル投資であっても賃料収入が不安定になるリスクや、物件の資産価値が減少するリスクがあります。これらのリスクを十分に理解した上で判断する必要があります。
オフィスビルへの投資については「投資物件としてのオフィスビルのメリット・デメリットと今後の市況」で解説しています。
商業中心地に位置するオフィスビルは、物件によっては数億円になるものもあり、個人投資家にとっては手が出しづらいという問題があります。
そのため、一棟で保有するのではなく、不動産小口化商品やREIT、不動産クラウドファンディングといった、小口でオフィスビルに投資する方法も注目を集めています。
それぞれの小口化商品については「不動産投資を少額から始めるには? - REIT、不動産小口化商品、不動産クラウドファンディング【FP監修】」で解説しています。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
紗冬 えいみさとう えいみ
office mondays 代表
金融ライター、編集者
保有資格:CFP®認定者、1級FP技能士、日商簿記検定2級
大学を卒業後、証券会社に入社。リテール営業やコンサルティング業務、バックオフィス業務を担当しました。その後は公認会計士・税理士事務所でのアシスタント業務を経て金融ライターへ転身。FP事務所や金融系ベンチャー企業のWeb発信支援、機関投資家向け季刊誌やFP向け季刊誌などでの執筆に携わっています。情報発信を通じて、世の中のお金の悩みをひとつでもなくすべく活動中です。
不動産投資の記事一覧に戻る