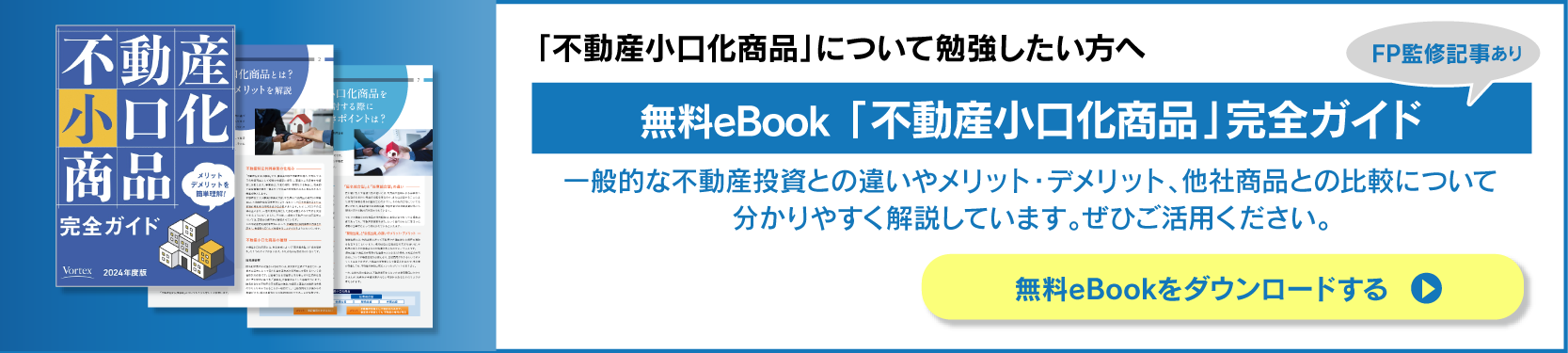目次
不動産投資に興味があっても、空室リスクや自然災害リスクがあると見聞きして、不動産投資を始められない方も多いのではないでしょうか。不動産投資にはさまざまなリスクがあり、必ずしも安定した収益を得られるわけではありません。ただし、不動産投資のリスクを把握したうえで適切な対策ができれば、リスクの軽減は可能です。
そこで本記事では、不動産投資のリスクとその対策について解説します。不動産に関連した投資商品も紹介するので、自分に合った投資先を探している方もぜひ参考にしてください。
この記事の要点まとめ
- 不動産投資には空室リスクや修繕リスクなど多くのリスクがありますが、適切な対策で軽減可能。
- 本記事では、8つの主なリスクとその対策、リスクヘッジの具体的な方法を詳しく解説。
- 初心者でも安心して始められる不動産小口化商品やREITなど代替手法も紹介。
不動産投資の8つのリスクとその対策

不動産投資では、一定の入居率が維持できれば、安定的な家賃収入を得られます。また、所有している物件の価値が高くなったときは、売却して利益を得ることも可能です。
その反面、以下のようなリスクがあります。
- 空室リスク
- 賃料下落リスク
- 滞納リスク
- 金利上昇リスク
- 自然災害リスク
- 修繕リスク
- 物件価格の下落リスク
- 経営上の精神的リスク
不動産投資を始める際は、事前にどのようなリスクがあるのかを知り、適切な対策をすることが大切です。まずは、リスクとそれぞれの対策を詳しく解説していきます。
空室リスク
空室リスクとは、入居者が見つからない状況が続くことで空室となり、家賃収入が得られないリスクのことをいいます。空室が発生しやすい物件の特徴には、以下のようなものがあげられます。
- 駅やバス停から遠い
- 周辺に競合物件が多い
- 周辺にスーパーやコンビニ、病院、学校がない
- 設備が古い
- 建物の老朽化が進んでいる
- 周辺の物件より家賃が高い
- 周辺の治安がよくない
空室リスクを抑えるためには、立地のよい物件や住宅であれば1~2人暮らし向けの物件といった賃貸需要の高い物件を選ぶのが効果的です。
対策:立地のよい物件を選ぶ
空室リスクを抑えるには、以下のような立地のよい物件を選ぶことが大切です。
- 駅から徒歩圏内
- 周辺にスーパーやコンビニがある
- 大学が近い
- 人口が増えているエリアにある
- 周辺の治安がよい
このようなエリアは、入居者が集まりやすい傾向があります。生活しやすく、賃貸需要の高いエリアで物件を探しましょう。
対策:1~2人暮らし向けの物件を選ぶ
住宅の場合、ワンルームマンションのような1~2人暮らし向けの物件は、一定数の需要があります。総務省の国勢調査では、単独世帯の割合は1990年代から右肩上がりに増えていることが公表されています。そのため、今後も単身者は増加傾向が続き、単身者向けの物件の需要も高まると予想できるでしょう。
また、一人暮らしの場合、住む人自身の意思で入居を決められるケースが多いため、内覧から契約までの期間が短い傾向があります。一方、ファミリー向けの物件は、配偶者の意見を聞いたり子供の通学のしやすさを考慮したりする必要があり、入居までに時間がかかりやすくなります。したがって、次の入居者が比較的早く決まりやすい単身者向けの物件のほうが空室リスクを抑えやすいといえるでしょう。
賃料下落リスク
建物の老朽化が進むと賃貸需要が下がりやすくなるため、家賃が下落する傾向があります。また、賃料が高い時期に入居し、長く住んでいた入居者が退去したあとは、家賃を大幅に下げなければ次の入居者が決まりにくいといったケースも考えられます。賃料が下落して収益が悪化すれば、ローン返済が滞ったり月々の収支がマイナスになったりすることもあるでしょう。
対策:入居者の満足度を高める
賃料を下げる主なタイミングは、入居者が入れ替わるときです。たとえば、空室が埋まらず、やむを得ず家賃を下げる状況などがあげられます。
したがって、既存の入居者に長く住んでもらえると、賃料下落リスクを抑えやすくなります。具体的には、共有部分の定期的な清掃や、トラブル発生時に迅速な対応をするなど、入居者の満足度を高めることが大切です。
対策:設備を整える
設備が整っている物件であれば、相場より高い賃料でも入居者を見つけやすくなります。たとえば、無料インターネットや浴室乾燥機などが利用できる物件は、需要が高い傾向にあります。
インターネットを使って賃貸物件を探すときは、設備の欄にチェックを入れて検索し、絞り込むのが一般的です。需要のある設備が備わっている物件であれば、検索で絞り込まれたときに競合が減り、選ばれやすくなるでしょう。
滞納リスク
入居審査をした場合でも、退職や転職、家庭の事情などで経済状況が変わり、家賃の滞納が発生することがあります。家賃滞納によって収入が入らない状況になると、ローン返済やランニングコストの負担が重くなってしまうでしょう。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「日管協短観」では、2023年度の滞納率は全国で1.2%と公表されています。100人中1人は滞納する確率であり、どのような物件にも滞納リスクは潜んでいるといえるでしょう。
対策:適切な入居審査をする
入居審査では、入居希望者の職業や年収を確認し、家賃を確実に支払えるのかを審査します。適切な審査ができていれば、滞納リスクを軽減できるでしょう。ただし、どのような入居者が滞納するのかを判断するのは難しいのが現状です。そのようなときは、入居審査のノウハウがある管理会社に審査依頼をするのがおすすめです。
対策:連帯保証人をつけることを義務化する
滞納リスクを抑えるポイントは、連帯保証人を立ててもらうことです。連帯保証人とは、入居者が家賃を滞納したり、設備を壊したりしたときに借主の代わりに支払い義務を負う人を指します。連帯保証人をつけることを義務付ければ、滞納が発生しても家賃を回収しやすくなります。
対策:家賃保証会社を利用する
家賃保証会社とは入居者の連帯保証人を代行する会社のことをいいます。「保証人を引き受けてくれる親族がいない」「周囲に保証人を頼みにくい」といったケースでも、家賃保証会社を利用すれば滞納リスクを抑えられるでしょう。なお、家賃保証会社に支払う保険料は入居者が負担します。
金利上昇リスク
不動産投資はローンを組んで始めるケースが多くあります。変動金利型ローンを選択した場合は、金利上昇によって毎月の返済金額が増えるリスクがあります。想定していた収入を得られなければ、毎月のローン返済を給料や貯金で補わなければならない状況になりかねません。
対策:金利上昇の影響を受けにくい住宅ローンを選ぶ
ローンは主に以下の3種類に分けられます。
| 変動金利型 | 返済期間中に金利が変動する |
| 全期間固定金利型 | 返済開始から完済まで金利が完全に固定される |
| 選択型固定金利型 | 一定期間に限り固定金利が反映され、期間経過後は固定金利と変動金利のいずれかを選択可能または変動金利のみ(金融機関による) |
変動金利型は、比較的低い金利が設定されているものの、返済途中で金利が上昇し、毎月の返済額が増える可能性があります。全期間固定金利型を選べば、金利上昇の影響を受けないため、返済計画を立てやすくなりますが、変動金利型などよりも金利は高く設定されています。選択型固定金利型は、変動金利型より高い金利が適用されますが、全期間固定金利型より低金利になるのが特長です。ただし、固定期間終了後に、適用金利などの見直しが行われるため、返済額が大きく増加する可能性もあります。
変動金利型であっても、以下の5年ルールや125%ルールを定めている金融機関であれば、返済額が大幅には増えません。
| 5年ルール | 金利が上昇しても5年間は返済額が変わらない |
| 125%ルール | 5年ごとの見直しで金利が上昇した場合でも、それまでの返済額の125%を超えない |
ただし注意も必要です。5年ルールや125%ルールによって毎月の返済額が大きく変わらないとしても、返済期間中にローン完済の義務を免れるわけではありません。これらのルールでは、毎月の返済額に大きな変動が生じないように、元本の返済を後回しにし、支払い利息の割合が増えることになります。つまり、金利の上昇による影響は、毎月の返済額に対する利息の割合が増えることにより元金がその分減らないというデメリットになります。元金の減りが遅いと、結果的に総返済額も増えます。また、未払利息が発生した場合は、最終的に一括返済で清算しなくてはならないこともあります。滞りなく住宅ローン返済を進めるために資金を蓄えておくことが大切です。
対策:自己資金の比率を上げる
利息は借入金額に対して発生するため、自己資金の比率を上げて借入金額を減らせば、支払う利息を抑えられます。以下の条件で、自己資金額に応じた返済額や利息を比較してみましょう。
- 物件購入費用:5,000万円
- 返済期間:30年
- 金利条件:全期間固定金利型1.5%
- 返済方式:元利均等返済
自己資金を500万円準備したケースと2,000万円を準備したケースの返済額や利息は、以下のとおりです。
| 自己資金 | 借入額 | 毎月の返済額 | 利息 | 総返済額 |
| 500万円 | 4,500万円 | 約15.6万円 | 約1,091万円 | 約5,591万円 |
| 2,000万円 | 3,000万円 | 約10.4万円 | 約728万円 | 約3,728万円 |
自己資金を500万円準備したケースと2,000万円のケースでは、支払う利息に363万円ほどの差が生じます。ただし、金利上昇のリスクを抑えようと無理に自己資金を捻出すると、修繕費やランニングコストの支払いが難しくなってしまう可能性があります。どれほどの自己資金を入れるべきか悩むときは、数年分の収支シミュレーションをしてみるのがおすすめです。
対策:金利上昇時に繰り上げ返済できる資金を用意する
繰り上げ返済とは、ローンを前倒しで返済することです。繰り上げ返済をすれば、返済した部分にかかる利息の支払いが不要となり、金利上昇の影響を受けにくくなります。
繰り上げ返済する際は、以下の2つ方法から選択します。
| 返済期間短縮型 | 毎月の返済額は変わらず、返済期間が短くなる |
| 返済額軽減型 | 返済期間は変わらず、毎月の返済額が少なくなる |
ローンの利息は、元本の金額と返済期間によって決まるため、返済期間の短くなる短縮型のほうが利息を減らす効果が大きくなります。金利上昇が起こりそうなタイミングで繰り上げ返済ができるように資金を蓄えておくことが大切です。
自然災害リスク
地震や台風などで建物が破損した場合、オーナーが修繕工事をする必要があります。火災保険や地震保険に加入することで修繕費用を抑えられるケースもありますが、自己資金でまかなわなければならない状況も考えられるでしょう。さらに大規模な修繕工事が必要になれば、修繕費が高くなるだけでなく、入居者に一時的な立ち退きを求めることになり、安定した家賃収入を得られなくなってしまいます。
対策:耐震性に優れた物件を選ぶ
日本は、世界で発生しているマグニチュード6.0以上の地震の約2割が起こっているとされる地震多発国です。また、南海トラフ地震と首都直下地震は、今後30年以内に発生する確率が70%と予想されています。今後起こりうる地震に備えるには、新耐震基準を満たした物件を選ぶことが大切です。
旧耐震基準では、震度5程度の揺れで倒壊・崩壊しないことを基準としています。一方、新耐震基準は昭和56年に改正・導入されたもので、震度6から7の地震でも倒壊の被害が発生しないことを基準としています。そのため、昭和56年以前の建物は、地震による被害が大きくなりやすいといえるのです。
中古物件を購入する際は、建築確認日をチェックし、新耐震基準を満たしているかを確認しましょう。
対策:ハザードマップを確認する
ハザードマップとは、地形や地盤の特徴、過去の災害履歴から、災害リスクのある危険区域などの情報を記載した地図のことです。自治体や国土交通省のホームページ、自治体窓口で入手できます。物件購入をする際は、災害リスクの低い場所であるかをハザードマップで確認しましょう。
修繕リスク
建物は経年劣化によって屋根や外壁、共用部分、室内のフローリングや壁紙、設備などの修繕が必要となります。修繕には多額の費用がかかるため、事前に備えていなければ、対応できない可能性があります。また、費用をカットしようと修繕を後回しにすると、空室リスクを高めたり、物件価値が下がったりする原因になるため注意が必要です。
対策:適切な建物の管理をする
修繕費用を抑えるには、定期的に物件を点検し、必要に応じて部分的な修繕をしておくことが大切です。小さな損傷や故障だとしても、早期に対処しておけば、大きな修繕費用が発生することを防げます。
なお、物件管理は、管理会社に委託するのが一般的です。管理会社を選ぶ際は、その会社が管理している物件に足を運んでみるのがおすすめです。清掃が行き届いているのであれば、信頼して任せられる管理会社といえるでしょう。
対策:修繕費用を積み立てる
適切に建物を管理していても、経年劣化によってある程度の修繕工事が必要になることもあります。大規模修繕に備えるためには、毎月の家賃収入から一定割合を修繕積立金として確保することが大切です。築年数や物件の種類から、いつ頃に修繕が必要になりそうか考慮したうえで資金計画を立てましょう。
物件価格の下落リスク
保有物件の価格が購入時より値上がりしていれば、売却時に利益を得られます。しかし、物件価格は必ずしも値上がりするわけではなく、値下がりするケースも多々あります。物件の老朽化や周辺地価の下落にともない、損失が発生することは十分に考えられます。
人口減少や少子高齢化が進む日本では、地方を中心に賃貸需要が減る可能性があります。また、地域や物件の状況によっては、買主が見つからず売却できないケースもあるでしょう。
対策:将来性のある物件を選ぶ
物件価格の下落リスクを抑えるには、将来性のある物件を選ぶことが大切です。たとえば、人口増加が見込まれるエリアや、再開発計画が予定されているエリアにある物件は将来性があるといえます。なかでも、東京23区や大阪市中心部は大規模な再開発が進んでおり、人口や企業が集中していることから、物件価格が下がりにくいエリアといわれています。
対策:出口戦略を立てる
不動産投資における出口戦略とは、「最終的にどのタイミングでどのように物件を手放すか」の戦略のことをいいます。不動産投資では、タイミングよく、いかに物件を高く売却するかが重要です。売却するときに大きな損失を出せば、今まで順調に家賃収入を得ていても、結果的には赤字になってしまいます。
出口戦略は、不動産投資を始めるときに立てるのが理想です。最初から売却するタイミングをある程度決めておけば、資金計画や経営計画を立てやすくなります。
経営上の精神的リスク
不動産投資では、管理会社に管理業務や入居者対応を委託できます。とはいえ、退室時の修繕・リフォームや再募集時の入居条件の打合せなど、賃貸オーナーが賃貸経営に関わる場面もあります。トラブルが起こったときの最終的な判断は貸主に委ねられるため、精神的なストレスを感じることもあるでしょう。
対策:信頼できる管理会社を選ぶ
管理会社に委託することで管理にかかる負担を軽減できますが、対応のよくない会社に依頼すると入居者の不満につながってしまいます。結果的にクレーム対応に追われる可能性もあるでしょう。
そのような状況を避けるには、信頼できる管理会社を選ぶことが大切です。管理会社を選ぶ際は、以下のようなことをチェックしましょう。
- トラブル発生時に迅速な対応ができる体制であるのか
- 担当者の対応に違和感はないか
- 顧客満足度は高いか
安定した賃貸経営をするためにも、自分に合った管理会社を見つけることが大切です。
対策:不動産に関連するほかの投資を選ぶ
物件の管理や経営によるストレスを避けたい人は、ほかの形の不動産投資を選ぶことも視野に入れてみましょう。不動産関連の投資には、主に不動産小口化商品とREIT(不動産投資信託)があります。
不動産小口化商品とは、特定の不動産を1口数万円から100万円前後に小口化し、投資額に応じた家賃収入や売却益を受け取れる商品です。一方、REITとは、不動産投資法人が投資家から集めた資金でマンションやオフィスビル、商業施設などを複数購入し、賃貸収入や売却益を投資家に分配する金融商品です。
不動産小口化商品とREITは、不動産の管理業務を事業者が請け負うため、管理にかかる手間やコストの負担がかかりません。不動産投資の初心者や本業が忙しい人でも、気軽に始めやすいといえるでしょう。
不動産の投資リスクをヘッジしたい方は「Vシェア」がおすすめ

不動産投資リスクを抑えたい方には、弊社の不動産小口化商品「Vシェア」がおすすめです。「Vシェア」では物件の取得から不動産戦略の立案、資金調達、プロパティマネジメント、出口戦略(売却)までワンストップで提供することで、さまざまな不動産投資リスクを抑えられます。
突発的なメンテナンスコストを平準化
「Vシェア」では、長期修繕計画に基づいて運用するため、突発的なコストを平準化することが可能です。また、不動産の管理および運営についても、業務執行組合員として弊社がすべてをおこないますので、オーナー様に煩わしい手間は一切かかりません。
空室リスクや賃料下落リスクが低い物件を選定
「Vシェア」は、多くの個人投資家が投資対象としているマンションやアパートではなく、都心の中規模オフィスビルを対象としています。都心の中規模オフィスビルは供給に対して需要が高く、賃料下落のリスクが低いといえるでしょう。
加えて「Vシェア」はグレードの高いオフィスビルを選定しているため、入居テナントの属性も良好であり、資産価値や収益の安定性を長期的に維持しやすい傾向にあります。
弊社独自の徹底的なリスクスクリーニング
「Vシェア」では、プロならではの視点から厳正なチェックと徹底的なスクリーニング(入居審査)を実施しています。良質なテナントを選定することで、家賃滞納のリスクを抑えられます。
出口戦略(売却)までワンストップで提供
弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、個人単位では購入が困難な都心の商業地にある中規模オフィスビルを小口化し、1口100万円単位・5口以上で購入できるように設計された商品です(最低口数は変更となる場合があります)。
一棟ビルを小口化することで購買層が拡大し、高い流動性を誇る独自のマーケットが形成されています。出口戦略までワンストップでサポートしているため、高い流動性を活かし、スムーズに売却・現金化が可能です。
最後に
不動産投資には賃料下落リスクや滞納リスク、修繕リスクなどがあります。リスクを抑えるには、賃貸需要が高く、将来性のある物件を選んだり、信頼できる管理会社に委託したりすることが大切です。不動産の管理や賃貸経営に煩わしさを感じる方は、不動産小口化商品とREITといったほかの投資商品を選ぶことも視野に入れてみましょう。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

監修者
吉田 美子よしだ よしこ
Plus-プリュス- 代表
株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング 所属
日本では数少ない独立系FPとして、資産運用、相続、不動産、保険、リタイアメントプランなど年間延べ450組超のコンサルティングを実施。
キャッシュフローによる人生の可視化と正しい知識を身に付けることの重要性を女性FPの視点からお伝えしている。
Plus−プリュス−(https://www.fp-plus.net/)
不動産投資の記事一覧に戻る