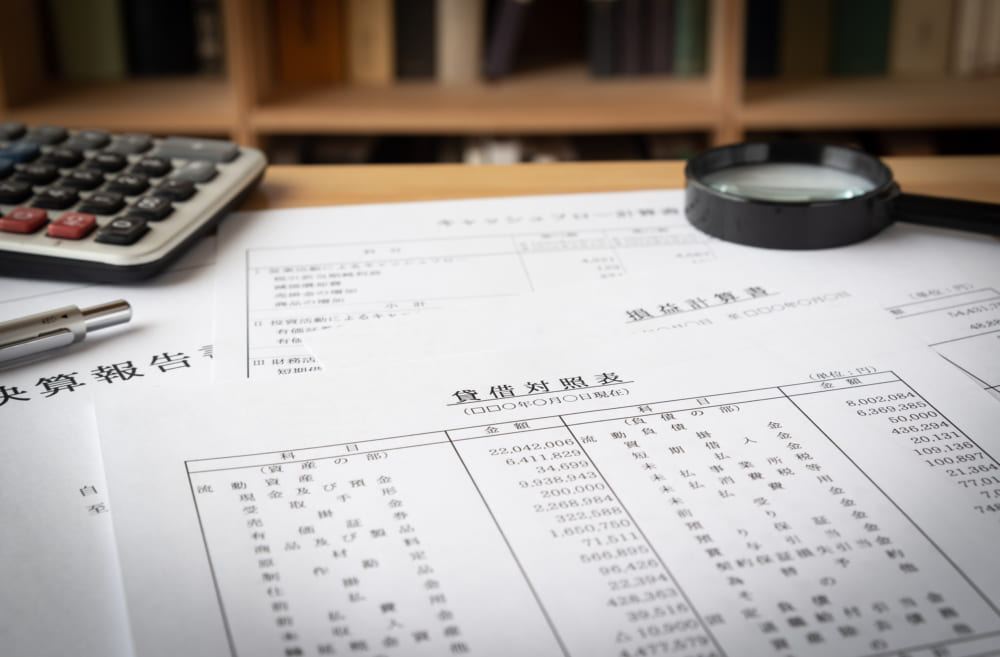初代の精神を受け継ぎ「想い出の場所」であり続ける【金森商船株式会社 代表取締役社長 渡邉 政久氏】

目次
函館を象徴する観光スポットの1つ、「金森赤レンガ倉庫」。連日多くの観光客でにぎわうこの商業施設を運営するのが、1869(明治2)年創業の金森商船です。函館の発展とともに歩みを続け、時代の大きなうねりの中で倉庫業から商業施設運営へと大胆な業態転換を図った同社。150年以上にわたり企業を存続させてきた、その根幹にあるものとは。8代目社長の渡邉政久氏にお話を伺いました。
青函トンネルの開通を機に業態転換を決断
2024年、私たち金森商船はおかげさまで創業から155年を迎えることができました。この1世紀半を超える歴史における最大の転機は、間違いなく1988年の、倉庫業から商業施設への業態転換です。
そのきっかけは、「世紀の大事業」といわれた同年の青函トンネルの開通でした。それ以前から企業による倉庫の自社保有が進み、当社の主力であった貸し倉庫業には少しずつ陰りが見え始めていました。そこに青函トンネルが開通し、貨物列車が本州と直接つながれば、物流は函館を素通りして大都市・札幌へ直行してしまう。北海道の物流が激変することが予測されたのです。これではますます、倉庫業に未来はない。明治期から受け継がれてきた「金森倉庫」という歴史的資産を守りつつ、業態転換を図る必要に迫られました。
この大きな決断を下したのは、先々代の6代目の社長です。私の大叔父にあたり、もともと大手光学機器メーカーに勤務し、ニューヨーク支社長も経験した人物でした。当時米国では港湾や河岸の古い倉庫を改装して新たなにぎわいを生み出すウォーターフロント開発がさかんに行われていました。おそらく、大叔父が駐在時に見た光景が着想の基になったのでしょう。こうして1988年、全3棟の倉庫をリノベーションした複合施設「函館ヒストリープラザ」が開業しました。
しかし、この「倉庫業から商業施設へ」という180度異なる業態への転換は、言うほど簡単ではありません。そもそも1980年代当時のこの倉庫一帯は、周りに商業施設もなく、夜になれば女性が1人歩きを避けるほど寂れた場所でした。そんな場所に、お客様が本当に来てくれるのか。その確信は誰にもありませんでした。
そこで、核となる旗艦店として作ったのが「函館ビヤホール」です。サッポロビールの工場から直送される200リットルの巨大なタンクを設置し、最適な管理の下で提供する生ビールは、当時どこにもないものでした。このビアホールが起爆剤となり、徐々に地元の方々に認知いただき、成功への大きな第一歩となりました。
その後、2000年代に入って政府がインバウンド政策に注力したことが契機となり、外国人観光客が増え始めました。2006年には韓国(ソウル・仁川)から函館への直行便が就航したことで韓国からのお客様が急増。世界的に認知されるようになりました。
「人を益し、世を利する」精神でテナントと長期的な関係を築く
私たちが事業を進めるうえで根底にあるのは、創業者である渡邉熊四郎の思想です。彼は大分に生まれ、長崎を経て函館に渡り、1869年に洋物店を開業。以降、倉庫業をはじめ船用品店、時計店から新聞社、銀行までさまざまな事業を独自で、あるいは函館の有志の方々とともに興しました。その傍ら、学校、公園、病院など公共施設を整備し、箱館戦争によって焦土となった函館の再生にも力を尽くしました。
「人を益し、世を利する」。この言葉を残した熊四郎の精神は、現在の当社の運営スタイルにも色濃く反映されています。私たちにとって第一のお客様は、施設を訪れる市民や観光客よりもまず、施設に入居してくださる「テナント」である、と社員には伝えています。テナントのために施設を少しでも改善し、お客様を呼ぶ努力をする。テナントが繁盛すれば、結果として施設全体が潤い、訪れるお客様にも喜んでいただける。この順番を間違えてはいけないと考えています。
そのテナントとの関係性を象徴するのが「固定家賃制」です。多くの商業施設が採用する、売り上げの数%をいただく「売上歩合制」とは異なり、当社では創業以来、毎月決まった額の家賃をいただく形を続けています。これは約35年前の商業施設への業態転換をした当初、当社もテナント側も売り上げ予測がつかない中で安定した事業計画を立てる必要があったためです。ただ、結果として、今日ではテナントとの良好かつ長期的な関係を築く礎になっている側面もあると感じています。売り上げがよい月も悪い月も家賃は同じですから、当社がテナントの売り上げに過度に介入することもありませんし、売り上げの低下による退店を促すこともありません。テナントとコミュニケーションを取りながら、良好な関係を築いていければと考えています。
「金森商船はまちづくりや社会貢献に取り組んでいて、函館にとって私企業を超えた存在ですね」と言っていただくこともあります。うれしいことなのですが、正直に言うと私は少し気恥ずかしさを感じています。初代は確かに函館のまちづくりに人生を捧げた人物です。しかし、それは彼が商売を成功させ、財を成したからこそできたこと。まずは自分の会社、社員、そして家族を守る。そのために事業を必死に行い、利益を追求する。その活動が、結果として周りの方々から「社会貢献している」と評価していただけるのであればうれしく思います。
歴史を「継ぐ」プレッシャーより未来に「託す」責任の重みと向き合う日々
私は2017年に、8代目の社長に就任しました。渡邉家には、初代が残した“家の憲法”たる「家憲(かけん)」があり、長男が会社の代表を継ぐことが定められています。私が社長を継ぐことはいわば宿命のようなもの。「継ぐ」こと自体にプレッシャーはありませんでした。
一方で、「未来への責任」に対するプレッシャーは日々感じています。この歴史ある会社を、社員たちの生活を、そしてこの金森赤レンガ倉庫という事業を、どのような形で次の世代に託していくべきか。
その責任を果たすために私が出した答えは、「守り」を固めること。私が社長を引き継いだ際に、今の商業施設の形はほぼ完成していました。だから、積極的な投資で事業を拡大するよりも、まずはしっかりと足元を固め、次の世代が新しい挑戦をしやすい環境を整えること。それが、今の自分に課された責務だと考えています。
この先、会社をどのような姿にしていきたいか。それは、この金森赤レンガ倉庫が訪れる人々にとって「想い出を重ねられる場所」であり続けることです。市民の方々にとっては、函館山とともにシンボリックな風景として認知していただいています。今日では、親子三代で訪れてくださるお客様もいます。たとえ中のテナントが変わったとしても、この歴史的資産のたたずまいは変えることなく、そこを訪れた人の数だけ大切な想い出が生まれ、幾重にも重なっていく。そんな場所を守り、未来へつないでいくことが、私たちの使命です。
私が「守り」を固めるぶん、次の世代には、この赤レンガ倉庫だけに頼らない新しい事業の柱づくりにチャレンジしてほしい。歴史を守る責任と、未来を切り拓く挑戦。その両輪で、次の200年に向けた金森商船の新しい歴史を紡いでいきたいですね。
[編集]株式会社ボルテックス コーポレートコミュニケーション部
[制作協力]株式会社東洋経済新報社

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。