【連載】インフレ時代の不動産投資論‐資産価値の氷山モデルによる再設計 【第4回】100年企業の資産戦略‐新会計基準が促す保有への転換
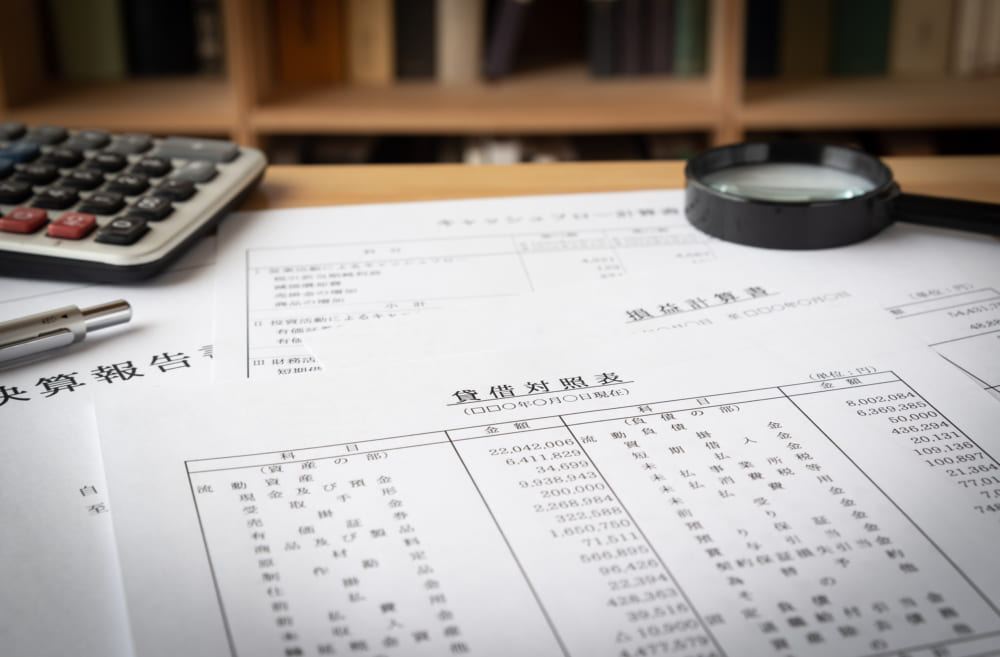
目次
はじめに‐分析の帰結としての戦略判断
本連載は、30年続いたデフレの常識が終焉した事実認識を起点に、インフレを収益に変える分析手段として「契約価値」を提示し、さらに日本固有の法制度下における永続性の条件として「時代価値」を論じてきました。
本連載で積み上げてきた議論は、インフレ環境下で時代価値を備えた資産の価値が増大していくという事実を踏まえると、すべての経営者が向き合うべきひとつの根源的な問いへと収斂します。
事業の中核となる不動産を「保有」すべきか、それとも「賃借」し続けるべきかという問いです。
インフレが常態化する時代において、保有か賃借かの二者択一は、短期的なコスト計算の問題にとどまらず、企業の貸借対照表の在り方、ひいては企業の永続性そのものを左右する根幹的な経営判断となります。
1. 新リース会計基準が促す財務構造の転換‐賃貸借契約の貸借対照表への計上と負債膨張リスクの顕在化
これまで多くの企業では、オフィスなどの賃貸借契約が貸借対照表に計上されない、いわゆるオフバランスとして扱われてきました。従来の会計処理では、賃料は発生時に経費として処理されるのみであり、借りているオフィスが企業の資産や負債として認識されることはありませんでした。しかし、長年の会計慣行が根本的に変わります。
国際会計基準との整合性を図るため、企業会計基準委員会は企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。公表された新基準は、上場企業等を主な対象として2027年4月1日以降開始の事業年度から強制適用される予定です。これまでオフバランス扱いだった不動産を含む賃貸借契約も、原則としてすべて企業の貸借対照表に資産および負債として計上されることになります。具体的には、貸借対照表の負債の部に将来支払うリース料の現在価値が「リース負債」として計上されるとともに、資産の部には借りた物件を使用する権利が「使用権資産」として計上されます。なお、2025年4月1日以後開始の事業年度からの早期適用も認められています。
新基準がもたらす影響は、本連載で論じてきた物価連動条項と組み合わさったとき、特に顕著なものとなります。新会計基準では、将来支払うリース料の現在価値がリース負債として貸借対照表に計上されます。インフレに連動して将来の支払賃料が増加した場合、会計基準に基づきリース負債が再測定され、増加分は貸借対照表の負債額に反映されます。
つまり、インフレ連動型の契約を賃借する選択は、インフレの進行が会計基準に基づき自社の負債を自動的に膨張させる仕組みを、貸借対照表に組み込む経営判断です。経営者が認識すべき会計上の現実は、負債が自動的に膨張する事実です。
インフレ環境下で不動産を賃借し続ける戦略は、もはやオフバランスという財務上の利点を失うことになります。賃借を継続する経営判断は、インフレ率に応じて残高が自動的に増加する負債を、自社の貸借対照表に受け入れることを意味します。
確かに、賃借には事業規模の変化に応じてスペースを柔軟に調整できるという明確な利点も存在します。しかし新会計基準の導入は、賃借の柔軟性と引き換えに、インフレによる負債膨張リスクを甘受せざるをえないというトレードオフ構造を可視化しました。事業の中核を担う不動産においては、短期的な柔軟性よりも、長期的な財務の安定性と資産価値の維持・向上を優先すべき局面にあるといえます。
会計基準の変更は、結果として経営者に基本的な二者択一を迫ります。インフレに連動して価値が増加する資産を貸借対照表に計上するのか、それともインフレに連動して残高が増加する負債を計上し続けるのかという選択です。新基準の適用が開始される以上、資産計上か負債計上かの判断を先送りすることはできません。
2. 保有という選択がもたらす長期的価値‐インフレヘッジを超える戦略的意義と次世代への継承
会計上の必然性を認識したうえで、不動産を保有する決断は多額の資本を固定化する経営判断を要求します。しかし、保有のための資本投下は、企業の永続性を支える長期的な投資として評価すべきです。インフレ時代の保有は、受動的なインフレヘッジを超えた、複数の具体的な戦略的価値を内包しています。
保有の選択は、まず企業の長期的な一貫性を示す意思表示となります。100年先も社会から必要とされる企業を目指すうえで、事業継続の物理的な裏付けとなる不動産を自ら保有する決定は、創業者の理念と覚悟を次世代へと継承する力強いメッセージとなるでしょう。
社会への貢献という側面も見逃せません。東京の都心部において良質で耐震性や環境性能に優れたオフィスストックを維持・管理することは、都市の国際競争力向上に直結します。その活動は、環境・社会・企業統治への配慮を通じて持続可能な社会の実現を目指すという、現代の企業に課せられた社会的責任を体現するものです。
保有がもたらす最も重要な価値は、未来を担う人材への投資です。知的資本が競争力の源泉となる現代において、優秀な人材を惹きつけ、創造性を育む質の高いオフィス環境は、事業継続に不可欠な要素です。したがって、質の高いオフィス環境の提供はコストではなく、企業の未来を創造するための根幹的な投資といえます。
さらに、不動産を保有するか否かの戦略的選択は、貸借対照表上の数値の問題にとどまりません。経営者が決定すべきは、次世代への資産継承戦略です。
賃借であれば支払った賃料は回収不能な支出として消滅しますが、保有であれば不動産は減価償却後も企業の資産として残り、将来の資金調達や事業承継の拠りどころとなります。企業の経営理念と長期ビジョンに基づき、判断されるべき重要な選択です。
3. 契約の未来‐テクノロジーが実現する検証可能な信頼
資産保有という戦略的決断がもたらす価値は、テナントとの公正なパートナーシップを長期にわたり維持する実務を通じて最大化されます。今後のパートナーシップに求められるのは、恣意性や属人的な判断に依存する旧来の信頼ではなく、客観的に検証可能な透明性によって構築される新たな性質の信頼関係です。
透明性を具体化する技術が、「スマートコントラクト」と「ブロックチェーン」です。スマートコントラクトとは合意した契約条件をプログラムとして自動実行する仕組みであり、ブロックチェーンとは取引記録の改ざんを計算量的に極めて困難にする形で分散的に共有する技術を指します。
物価連動条項にこれらの技術を適用する場合、まず賃料の改定周期や変動幅のルールをスマートコントラクトに組み込みます。しかし、プログラムは外部の情報、例えば政府が公表する最新のコアCPIを自律的に取得することができません。単一の情報源から得た情報が誤っていた場合、契約全体が破綻しかねないという課題を抱えています。
プログラムの自律性に関する課題の解決策が、外部データの信頼性を確保する仕組み、すなわち「分散型オラクル」です。独立した複数の情報源からコアCPIデータを収集・照合し、多数が正しいと合意した値のみを契約プログラムに採用することで、単一の情報源が持つ誤りや不正のリスクを合理的に低減し、契約の信頼性を確保します。
結果として、参照データから計算プロセスに至るすべての論理的根拠が、改ざん困難で検証可能な記録として蓄積され、「なぜその賃料額になったのか」という問いに対し、将来にわたり客観的な説明責任を果たせます。
もっとも、契約の自動化がすべてを解決するわけではありません。現行の日本法では、賃料不払い時の明渡執行など、不動産の権利に関する契約条項を完全に自動執行する運用には制約が残るため、当面は契約プロセスの透明化と記録保存における活用が現実的です。
また、実務導入では、当事者に限定したコンソーシアム型共有台帳の採用や厳格なセキュリティ監査が前提となり、コストと運用負荷を踏まえれば、超長期かつ高価値の資産から段階的に導入するのが現実的です。
自動化の仕組みは、日本の法制度の枠組みの中で機能します。平時は、合意済みのルールで算定・通知・記録を自動化して監査可能な履歴を蓄積します。そして、経済事情の著しい変動といった例外的な事態が生じたときは、蓄積された履歴を基礎資料として、法的な手続きに則った公正な協議へ移行します。例えば普通借家契約であれば、借地借家法第32条に基づく調整が行われることになります。平時における規律の自動的な維持と、例外時における協議の客観性担保という機能分担こそが、予見可能性と公正性の両立を可能にします。
ブロックチェーンとスマートコントラクトがもたらす根源的な価値は、業務効率化にはとどまりません。それは、客観的な記録と規律に基づき、オーナーとテナント間の公正な関係を長期にわたって維持するための、検証可能な枠組みそのものです。
結論‐新たな投資哲学の提唱
30年続いたデフレ時代の投資常識は、有効性を失いました。本連載が提示するのは、新たな分析枠組みとなる『資産価値の氷山モデル』です。第2層の契約価値を実装できるか否かが、第3層の時代価値の有無を決定づけるという構造を明らかにし、企業の100年を支える保有という選択の重要性を位置づけました。
表面的な利回りのみに依拠する判断は、資産価値の源泉を見誤ります。評価すべきは、その資産がインフレを含む環境変化に適応し、価値を持続的に高められるか、すなわち時代価値を備えているか否かです。
本連載で一貫して提示してきた結論は、東京の優良オフィスが示す低い利回りを、もはや欠点と捉えるべきではないという従来とは異なる視点です。低い利回りを欠点と捉える見方は、「即物価値」という海面上の一角のみを見た旧時代の評価に過ぎません。資産の長期的価値は、海面下に隠された契約価値と、100年後も価値が維持される時代価値にあります。
インフレ時代の投資家が、表面的な指標に惑わされず資産の全体像を正確に見抜くための分析道具こそが、『資産価値の氷山モデル』です。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。




