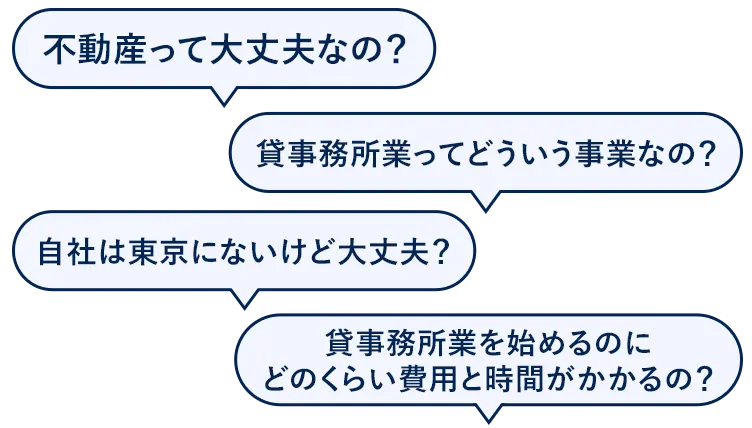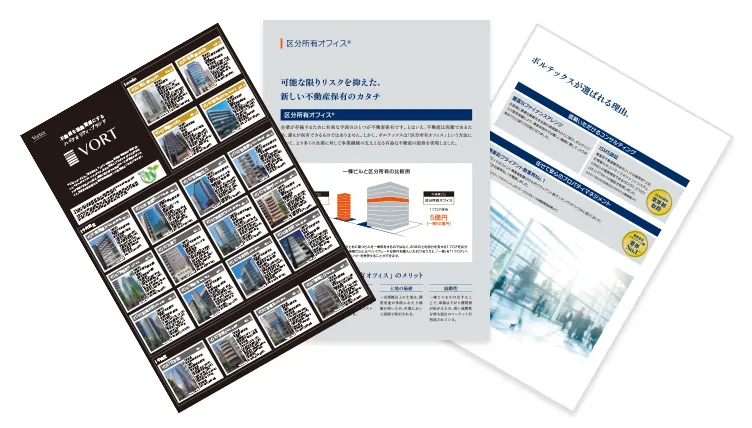デューデリジェンスとは?M&Aで企業価値を見極めるための調査内容と流れを解説

目次
企業の買収や合併を検討する際は、対象となる企業の実態や成長の可能性、リスクなどを正確に把握することが重要です。デューデリジェンスとは、取引の前に企業の財務や法務、人事など、さまざまな側面から総合的に調査するものです。
本記事では、M&Aにおけるデューデリジェンスの概要や進め方、各調査分野の内容、実施にともなう注意点について解説します。
この記事の要点まとめ
- デューデリジェンスは、M&A前に対象企業の財務・法務・事業などを多角的に調査し、リスクや価値を把握する重要なプロセス。
- 調査は財務・法務・人事・IT・環境など多岐にわたり、買い手企業の意思決定や統合計画に活用される。
- M&Aに不安がある場合は、不動産賃貸業など他の事業多角化手段も選択肢として検討できる。
デューデリジェンスとは
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&A(企業の合併・買収)や投資などの取引の際に、対象となる個人または企業や事業、資産について詳細に調査をすることです。日本語では「買収監査」や「適正評価手続き」とも呼ばれます。
具体的には、財務状況や法務リスク、事業の将来性、保有する不動産の価値など、多岐にわたる項目の調査をおこないます。
デューデリジェンスは、買い手企業がリスクを把握し、適切な価格で取引をするために不可欠なものです。売り手企業にとっても、自社の価値を客観的に評価し、買い手企業との交渉を有利に進めるための材料となります。
デューデリジェンスの目的
デューデリジェンスの目的には、主に以下の3つがあげられます。
- 買い手が売り手企業の価値を把握する
- 事業承継を円滑におこなう
- 成約前にリスクを洗い出す
買い手が売り手企業の価値を把握する
M&Aにおいて、買い手企業は売り手企業が提示する価値が妥当であるかを客観的に判断しなければなりません。そのため、デューデリジェンスで財務諸表の分析や事業計画の検証、市場調査などをおこない、売り手企業の収益性や成長性、資産価値などを詳細に評価します。
デューデリジェンスを実施することで、買い手企業は売り手企業の価値を過大評価することなく、適正な買収価格を算定できます。
事業承継を円滑におこなう
M&A後の統合(PMI)を円滑に進めるためには、売り手企業の経営状況や組織体制を事前に把握しておくことが重要です。
デューデリジェンスでは売り手企業の事業内容だけでなく、経営理念や企業文化、人事制度、従業員のスキルなど、多岐にわたる項目を調査します。これにより、買い手企業は売り手企業の強み・弱み、M&A後のシナジー効果などを事前に把握できます。
これらの情報に基づいて、買い手企業はM&A後の事業計画や組織体制、人事戦略などを具体的に検討でき、スムーズな承継が可能となります。
成約前にリスクを洗い出す
M&Aには財務や法務、税務などのさまざまなリスクがともないます。たとえば、売り手企業が抱える簿外債務や訴訟リスク、税務上の問題などは、M&A後に買い手企業の負担となる可能性があります。
デューデリジェンスではこれらのリスクを事前に洗い出し、その影響を評価します。リスクが発見された場合、買い手企業は買収価格の減額や契約条件の変更、M&Aの中止などの検討が必要になるでしょう。デューデリジェンスは、買い手企業がリスクを適切に評価し、M&Aを成功させるために欠かせない調査です。
デューデリジェンスの主な種類と調査内容
デューデリジェンスは、調査対象とする分野によって分類され、それぞれの専門家が調査をおこないます。ここでは、代表的な以下の種類について解説します。
- 財務(ファイナンシャル)デューデリジェンス
- 法務(リーガル)デューデリジェンス
- 事業(ビジネス)デューデリジェンス
- 人事(HR)デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- ITデューデリジェンス
- 環境デューデリジェンス
- 不動産デューデリジェンス
財務(ファイナンシャル)デューデリジェンス
財務デューデリジェンスは、対象企業の財務状況を詳細に調査・分析するもので、公認会計士や財務コンサルタントなどの専門家が実施します。
主な調査内容は、過去の財務諸表(貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、キャッシュフロー計算書)の分析、会計方針、簿外債務の有無、運転資本や収益性の分析などです。
財務デューデリジェンスの目的は、対象企業の財務上の問題点を洗い出し、企業価値評価の精度を高めることにあります。また、M&A後の財務計画策定に必要な情報を得ることも目的のひとつです。
法務(リーガル)デューデリジェンス
法務デューデリジェンスでは、対象企業の法務関連のリスクを調査します。弁護士が中心となって実施します。
主な調査内容は、顧客・仕入先・金融機関などとの契約、特許・商標・著作権などの知的財産権、定款・取締役会規則などの組織法務、コンプライアンス体制、訴訟・紛争の状況などです。
法務デューデリジェンスの目的は、M&A後に法的な問題が発生する可能性を把握し、そのリスクを評価することです。契約条件の見直しや、M&A後の法務体制の構築にも役立ちます。
事業(ビジネス)デューデリジェンス
事業デューデリジェンスは、対象企業の事業内容やビジネスモデルなどを調査・分析するものです。コンサルティングファームや業界専門家などが実施します。
主な調査内容は、市場の成長性や競合状況、対象企業の強み・弱み、事業計画の妥当性、シナジー効果の可能性などです。対象企業の事業価値を評価し、M&A後の事業戦略を策定するための情報を得ることを目的としておこないます。
人事(HR)デューデリジェンス
人事デューデリジェンスは、対象企業の人事制度や組織体制、従業員の状況などを調査します。人事コンサルタントや社会保険労務士などによって実施されます。
組織構造や人事制度(評価制度、報酬制度)、労働条件や福利厚生、従業員のスキルなどが主な調査内容です。人事デューデリジェンスの目的は、M&A後の人事統合を円滑に進めるための情報収集と、人事面でのリスクを事前に把握することです。また、キーパーソンの特定にも役立ちます。
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスは、税理士が中心となって対象企業の税務状況を調査します。具体的には、過去の税務申告の状況、税務リスクの有無、税務上の優遇措置の適用状況などを調査します。
税務デューデリジェンスは、M&A後に税務上の問題が発生する可能性の把握を目的としておこなわれます。税務効率の最適化や、M&A後の税務プランニングに役立つ場合もあります。
ITデューデリジェンス
ITデューデリジェンスでは、対象企業のITシステムやインフラ、IT戦略などを調査します。ITコンサルタントなどが実施します。たとえば、システム統合の可能性やセキュリティ対策、IT関連の契約関係などが調査対象です。
ITデューデリジェンスは、M&A後のシステム統合を円滑に進めるためにおこなわれます。また、ITコストの削減や、ITを活用したビジネスの効率化を図る場合にも、ITデューデリジェンスで取得した情報が役立ちます。
環境デューデリジェンス
環境デューデリジェンスは、対象企業の環境問題に関するリスクを調査・分析します。環境コンサルタントや専門機関などが実施します。主な調査内容は土壌汚染や大気汚染、水質汚染、廃棄物処理、有害物質の管理といった環境リスクや、環境関連の許認可などです。
環境問題のリスクを把握するほか、環境対策費用の見積もりやM&A後の環境コンプライアンス体制の構築にも役立ちます。
不動産デューデリジェンス
不動産デューデリジェンスは、対象企業が保有または利用する不動産について、その価値やリスクを調査・分析するものです。不動産鑑定士や弁護士などが実施します。
主な調査内容は、不動産の市場価格や権利関係(所有権、賃借権など)、土地の境界や建物の状態などです。不動産に関するリスクを特定するだけでなく、M&A後の不動産活用計画を策定するための情報を得る目的でもおこなわれます。
デューデリジェンスにかかる期間
デューデリジェンスにかかる期間は、事業の規模や業種、調査範囲など、さまざまな要因によって異なります。一般的には数週間から数カ月程度ですが、大規模なM&Aや複雑な案件では、さらに長期間を要するかもしれません。一方、事業規模や調査の対象範囲など、条件によっては2週間程度で完了する場合もあります。
デューデリジェンスの期間を短縮するためには、事前に調査範囲を明確にし、効率的な調査計画を立てることが重要です。
デューデリジェンスの流れ
デューデリジェンスは、以下の流れで進めていきます。
- 資料開示請求
- 資料分析
- 現地での確認作業
- ヒアリング
- 報告書の作成
1.資料開示請求
デューデリジェンスは、買い手企業が売り手企業に対して、必要な資料の開示を請求することから始まります。一般的に買い手企業が必要な資料リストを作成し、売り手企業に提出します。
売り手企業は、リストに基づいて資料を準備し、買い手企業に開示します。資料の開示方法は、物理的な資料の提出やデータでの共有など、さまざまな方法があります。
資料開示請求は、デューデリジェンスの成否を左右する重要な手順です。買い手企業は、必要な情報を漏れなく収集できるよう、詳細かつ網羅的な資料リストを作成する必要があります。
2.資料分析
買い手企業のデューデリジェンスチームは、開示された資料を詳細に分析し、対象企業の実態を把握します。分析の結果、疑問点や不明点が生じた場合は、売り手企業に追加の資料請求や質問をおこないます。
資料分析には専門的な知識と経験を要するため、買い手企業は各分野の専門家(公認会計士、弁護士、コンサルタントなど)をデューデリジェンスチームに加えることが一般的です。
社内に専門チームが無い場合は、専門家を招集しチーム体制を整えましょう。
3.現地での確認作業
資料分析に加えて、現地での確認作業も重要です。特に、不動産デューデリジェンスでは、対象となる不動産の現地調査が不可欠です。
不動産鑑定士や建築士などの専門家が現地を訪問し、建物や土地の状態、周辺環境などを調査します。工場や店舗などの事業用不動産の場合は、設備の稼働状況なども確認します。現地調査の結果は、資料分析の結果とあわせて総合的に評価されます。
4.ヒアリング
資料分析や現地調査に加えて、売り手企業の経営陣などへヒアリングもおこないます。資料だけでは把握できない情報を収集し、対象企業の事業や組織の実態をより深く理解することが目的です。
また、ヒアリングは売り手企業との信頼関係を構築する機会でもあります。買い手企業は、ヒアリングを通じて、売り手企業の経営陣や従業員の考え方、懸念点を理解し、M&A後の統合を円滑に進めるための準備をしていきます。
ヒアリングは、一般的にデューデリジェンスチームのメンバー(コンサルタント、会計士、弁護士など)が同席し、専門的な観点から質問をおこないます。
5.報告書の作成
デューデリジェンスの最終段階では、デューデリジェンスチームが報告書を作成します。報告書には、各分野のリスクや問題点、評価結果などがまとめられます。
買い手企業は報告書の内容を踏まえ、買収価格の調整、契約条件の変更、M&Aの中止などの判断をします。また、報告書はM&A後の統合(PMI)をする際の資料としても活用されます。
デューデリジェンスをおこなう際の注意点
デューデリジェンスは、M&Aの成功を左右する重要なものであり、慎重に進めなければなりません。売り手企業と買い手企業、それぞれの立場での注意点を解説します。
売り手側の注意点
売り手企業は、買い手企業に対して適切な情報開示をおこなう必要があります。また、開示する情報の正確性にも注意が必要です。虚偽の情報や不正確な情報を提供すると、M&Aの交渉が破談になったり、M&A後に損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
さらに、秘密保持契約(NDA)を締結し、開示する情報の機密性を確保することも重要です。競合他社に情報が漏洩すると、自社の競争力が低下する場合があります。
売り手企業は、自社の価値を適切に評価してもらうことで、M&Aを成功させることを意識するとよいでしょう。
買い手側の注意点
買い手企業は、必要な情報をデューデリジェンスで漏れなく収集し、リスクを適切に評価する必要があります。そのために、デューデリジェンスチームの編成も重要です。財務、法務、事業など、各分野の専門家をチームに加えることで、専門的な観点から調査ができます。
さらに、売り手企業とのコミュニケーションも大切です。疑問点や不明点があれば質問し、追加の資料を求めるなど、情報収集に努める必要があります。
買い手企業は、デューデリジェンスで売り手企業の実態を正確に把握し、M&Aのリスクを最小限に抑えることを目指しましょう。
まとめ
デューデリジェンスは、M&Aを成功させるために欠かせないプロセスです。買い手企業はこの調査を通じて、売り手企業の価値や潜在的なリスクを正確に把握します。
事業買収の際には、買収後に事業を円滑に運営できるか、または自社の主力事業との相性が適切かなど、数々の不確定要素が存在し、不安を感じることもあるでしょう。
M&Aに不安を感じるものの、事業の多角化は進めたいという場合、(行頭から)M&A以外の方法で本業以外の事業を取り入れる(事業を多角化する)ならば、不動産賃貸業の導入という選択肢もあります。保有不動産の賃貸契約によって賃料収入を得られるため、特別なノウハウを必要とせず、新たな事業を持つことが可能です。
不動産賃貸業で成功する可能性を高めるには不動産の選び方がポイントになります。商業地にあるオフィスビルは空室リスクが低い傾向にあり、安定して賃料収入を得られる可能性があります。しかし、商業地のオフィスビルは10億円から100億円を超えることもあり、大企業や一部の投資家しか購入ができないことが課題でした。
そこでボルテックスは、一棟のビルを1フロア(物件によっては1部屋)ごとに区分化して販売する「区分所有オフィス」というサービスを展開しています。区分所有オフィスによって、都心のオフィスビルをより多くの方々にご取得いただいております。
※空室リスク、価格変動リスク、運用コストなどがともなう点にご注意ください。
区分所有オフィスの詳細については、以下のページをご覧ください。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。