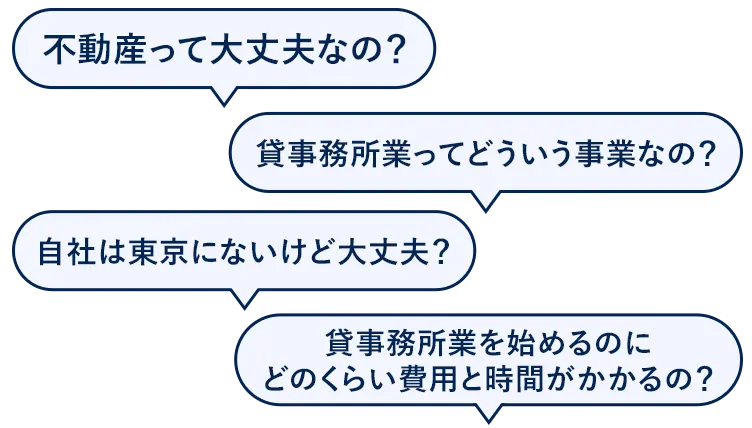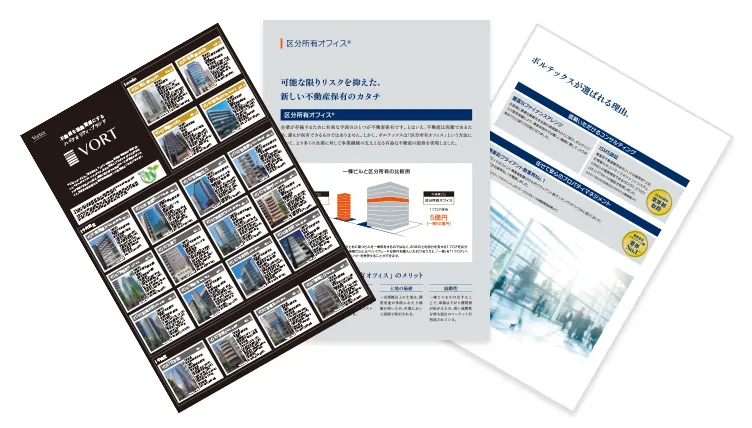事業承継税制に必要な特例承継計画とは|書き方と提出方法を解説【税理士監修】

目次
本記事に掲載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
事業承継税制の特例措置を活用するためには、特例承継計画の提出が必要です。事業承継税制の特例措置を活用すると、円滑に相続を進め次世代に資産を引き継ぐことが可能です。後継者の税負担は事業承継における大きな問題であるため、特例承継計画への理解を深めておきましょう。
本記事では、特例承継計画の概要、記載方法、および提出方法を解説します。事業承継税制の特例措置を受ける際にお役立てください。
特例承継計画とは
特例承継計画とは、事業承継税制の特例措置を受ける際に必要となる書類です。事業承継税制は、中小企業の後継者が経営者から受け取った株式などにかかる贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度です。
事業承継では、事業を引き継ぐ後継者への贈与税や相続税などが負担となり、円滑な承継を妨げることも少なくありません。
事業承継税制の種類
事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。一般措置と特例措置の違いは下記の表のとおりです。
| 特例措置 | 一般措置 | |
|---|---|---|
| 事前の計画策定 | 特例承継計画の提出(2026年3月31日まで) | 不要 |
| 適用期限 | 10年以内の贈与・相続等(2027年12月31日まで) | なし |
| 対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
| 承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要 |
| 経営環境変化に対応した免除 | あり | なし |
| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
参考:経営承継円滑化法申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】
また、事業承継税制については以下のページで詳しく解説しています。
特例承継計画提出の流れ
特例承継計画提出までは、以下の流れで進めていきます。
- 特例承継計画を策定する
- 認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける
- 特例承継計画を提出する
1.特例承継計画を策定する
特例承継計画には会社の基本情報のほか、後継者の氏名や今後5年間の経営計画を記載します。そのため、まずは後継者を選定する必要があります。
後継者が決定したら、特例承継計画の書類を作成しましょう。書類の記載事項や書き方は、本記事の「特例承継計画の書き方」で解説しています。
2.認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける
特例承継計画を策定後、認定経営革新等支援機関から計画内容について指導を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関とは、支援機関として認定された税理士や会計士などです。
指導内容は特例承継計画の別紙に記載してもらいます。記載事項については、本記事の「指導・助言を受けた機関と内容」をご確認ください。
3.特例承継計画を提出する
特例承継計画の書類を作成し、認定経営革新等支援機関からの指導内容を記載したら、必要書類を添えて提出します。
提出先や提出期限、必要書類は次の章で解説します。
特例承継計画の提出期限と提出先
ここでは、特例承継計画の提出期限と提出先、提出書類について解説します。
特例承継計画の提出期限
事業承継税制の特例措置の適用を受けるには、令和8年(2026年)3月31日までに提出する必要があります。提出期限を過ぎた場合は、特例措置を受けられず、一般措置が適用されます。
また、特例措置の適用期限は、2027年(令和9年)12月31日です。提出期限と適用期限は異なり、提出期限は特例承継計画を都道府県に提出する期限を指しており、適用期限は贈与・相続により会社の株式を取得する期限を指します。
なお、相続発生後でも特例承継計画の提出は可能です。
特例承継計画の提出先
特例承継計画は、上述した提出期限までに事務所の所在地を管轄する都道府県知事から確認を受ける必要があります。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
特例承継計画の提出書類
特例承継計画の申請にあたって、提出が必要な書類は下記のとおりです。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 【様式第21】確認申請書(特例承継計画)(原本1部、写し1部) | 経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた確認申請書 |
| 履歴事項全部証明書の原本 | 確認申請をする日の前3カ月以内に取得したもの |
| 返信用封筒 | A4を折らずに返送可能なもの、返送用の宛先を記載し、切手を貼付 ※配達記録が残るもの推奨 |
特例承継計画の書き方
特例承継計画に記載する内容は、企業情報や代表者・後継者の氏名、承継後5年間の経営計画などです。記載事項は、添付する履歴事項全部証明書の内容と一致させる必要があります。こちらでは、特例承継計画の項目ごとの書き方を解説していきます。
会社・代表者・後継者
1. 会社
事業承継税制の特例措置の適用申請をする事業者情報を記載します。
申請する事業者がクリーニング業の例を使用して解説します。
| 主たる事業内容 | 生活関連サービス業(クリーニング業) |
|---|---|
| 資本金額または出資の総額 | 3,000,000円 |
| 常時使用する従業員の数 | 6人 |
役員や個人事業主は、常時使用する従業員の数には含めません。
2. 代表者
特例代表者の項目は、代表者だった人または提出時に代表者である人の氏名と代表権の有無を記載します。すでに退任している場合には退任日を記載しましょう。
| 特例代表者の氏名 | サービス 太郎 |
|---|---|
| 代表権の有無 | □有・■無(退任日:2022年5月18日) |
3. 特例後継者
特例後継者は、特例代表者から株式を承継する後継者の氏名を記載します。特例後継者は最大3人まで記載可能です。
| 特例後継者の氏名(1) | サービス 一郎 |
|---|---|
| 特例後継者の氏名(2) | サービス 二郎 |
| 特例後継者の氏名(3) | サービス 三郎 |
なお、特例後継者を変更する際は、変更手続が必要となります。
後継者が株式などを取得するまでの期間の経営計画
株式を承継する予定時期や株式を承継する時期までの課題と対応策を記載します。
後継者がすでに株式などを取得している場合は、「当該時期までの経営上の課題」と「当該課題への対応」の記載は不要です。
| 株式を承継する時期(予定) | 2022年5月1日相続発生 |
|---|---|
| 当該時期までの経営上の課題 | 株式などを後継者が取得した後に本申請を行う場合には、記載は不要 |
| 当該課題への対応 | 株式などを後継者が取得した後に本申請を行う場合には、記載は不要 |
経営者と後継者で経営上の課題を認識し、後継者が承継後に課題に対応できるよう話し合いましょう。
承継後5年間の経営計画
事業承継後5年間の持続・発展に必要となる経営計画を記載します。経営計画では、売り上げや利益の目標数値を記載する必要はなく、事業承継後に事業を持続・発展させていくための具体的な実施内容を1年ごとに記載します。(下表は記載内容の例)
| 実施時期 | 具体的な実施内容 |
|---|---|
| 1年目 | ・地域密着型のマーケティング活動を展開。具体的には、店舗周辺3キロ圏内におけるポスティングや、地元イベントへの協賛を実施。 ・SNSを活用したデジタルマーケティングを開始し、店舗の魅力を発信。InstagramやFacebookの公式アカウントを運用し、クリーニングサービスの品質やお得なプランを紹介する。 ・初回利用者向けの特別割引キャンペーンを実施し、新規顧客の獲得を目指す。 |
| 2年目 | ・最新クリーニング機器を導入し、特殊素材や高級衣類への対応力を強化。これにより、顧客満足度を向上させる。 ・スタッフ向け研修プログラムを整備し、接客スキルやクリーニング技術の向上を図る。外部講師を招いた研修や、定期的な技術コンテストを実施することで、モチベーション向上にもつなげる。 ・顧客の声を反映した品質改善プロジェクトを立ち上げ、定期的なアンケート調査を実施。 |
| 3年目 | ・本店の改装工事を実施し、明るく清潔感のある店内デザインへリニューアル。顧客に快適な体験を提供するため、待合スペースや受付カウンターを改良する。 ・店舗内に小型カフェスペースを設置し、待ち時間を有効活用できる環境を提供。地元のベーカリーと提携し、地域との連携を強化。 ・環境に配慮したエコクリーニングサービスを導入し、持続可能性をアピール。これにより、環境意識の高い顧客層を取り込む。 |
| 4年目 | ・リピーター向けのポイントプログラムを導入。利用頻度に応じて特典を提供し、顧客ロイヤルティを高める。 ・クリーニング後の最大半年間の預かりサービスを開始。特に季節外の衣類に対する需要を取り込み、利便性を強化する。 ・定期利用者を対象とした会員限定イベントを開催し、顧客との関係性を深める。例として、衣類のメンテナンス講座や季節のトレンド紹介を実施。 |
| 5年目 | ・コインランドリー事業に進出。既存店舗の隣接地に新しいコインランドリースペースを設置し、家事代行サービスとの連携を図る。 ・地域内の複数店舗化を検討し、新たなターゲットエリアでの出店計画を進める。市場調査を実施し、具体的な立地選定を開始。 ・リアルタイムでの顧客ニーズを分析するため、ITを活用した顧客管理システムを導入。これにより、マーケティング施策やサービス改善につなげる。 |
「特例後継者が株式などを承継した後5年間の経営計画」に記載する内容は、すべて新しい取り組みである必要はありません。「なぜその取り組みを行うのか」「取り組みの結果どのような効果が期待できるか」が記載されているか確認しましょう。
指導・助言を受けた機関と内容
特例承継計画には「認定経営革新等支援機関による所見等」を記載する必要があります。認定経営革新等支援機関とは、中小企業の経営を支援するための専門家として国から認められた税理士や弁護士などです。
認定経営革新等支援機関による所見等の記載は、指導・助言をした支援機関が行います。
記載する内容は以下の3点です。
- 認定経営革新等支援機関の名称等
- 指導・助言を行った年月日
- 認定経営革新等支援機関による指導・助言の内容
認定経営革新等支援機関による所見等は、申請者が記載するものではありません。認定経営革新等支援機関に依頼しましょう。
特例承継計画の内容に変更があった際の対応
特例承継計画に記載された内容に変更があった際、後継者に株の贈与・相続を行う前であれば、「特例承継計画の変更届」を都道府県に提出することで変更が可能です。変更箇所は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を再度受ける必要があります。
なお、事業承継税制の適用を受けている場合は、後継者の変更はできないため注意しましょう。
特例承継計画の変更届(様式24)は、中小企業庁のWebサイトの申請手続関係書類一覧ページから入手できます。
特例承継計画の提出は期限と書き方が重要
事業承継税制の特例措置を行うことにより、円滑に相続を進め次世代に資産を引き継ぐことが可能です。適用を受けるためには提出期限までに都道府県に申請する必要があります。トラブルなく事業承継するためにも、特例承継計画への理解を深め、事業承継税制を利用していきましょう。
事業承継は相続や株式譲渡などの手続が複雑になるため、専門家を交えて早期に事業承継計画を立てましょう。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。