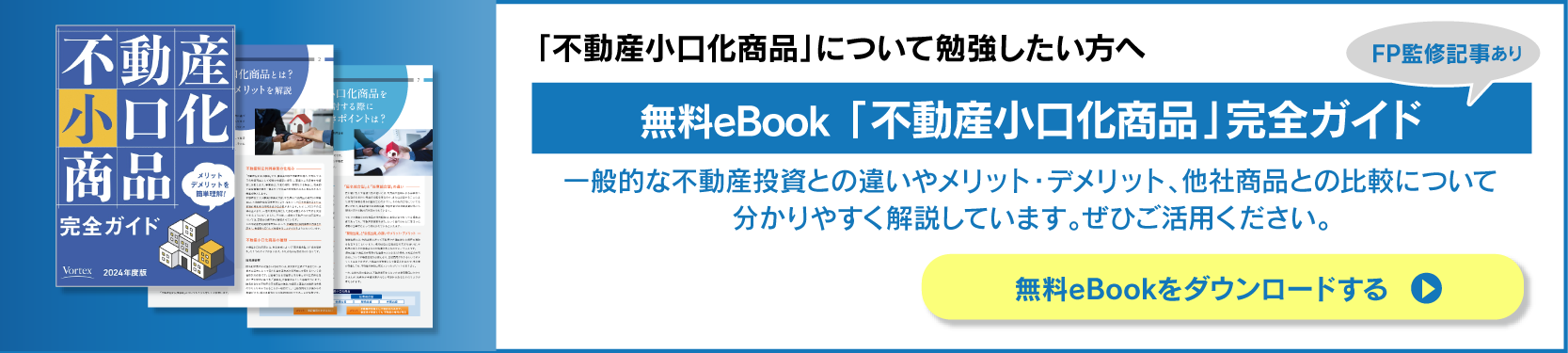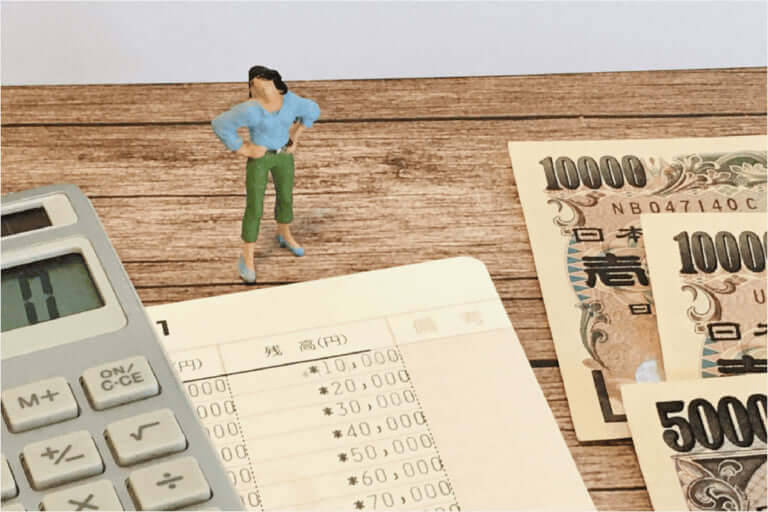目次
不動産クラウドファンディングは「1万円から投資できて、運用は事業者任せ」という手軽さが特徴で、初心者にもおすすめの投資方法です。しかし、投資である以上デメリットも存在します。
不動産クラウドファンディングを成功させるには、仕組みやリスク、トラブルに備える対処法を学んでから始めることが大切です。
そこで今回は、投資を始める前に押さえておきたい不動産クラウドファンディングのデメリットやその対処法などについて解説します。
1.不動産クラウドファンディングとは
不動産クラウドファンディングとは、事業者がインターネット上で資金を集めて不動産を購入し、物件の賃料収入や売却益で得た利益を出資者に分配する投資法です。不動産特定共同事業法という法律に基づいて運営されます。
通常の不動産投資では、一部屋や一棟単位で物件を購入するため、まとまった初期費用が必要です。また、物件の運用は自ら行うか、管理会社を探して依頼する必要があります。
一方、不動産クラウドファンディングは複数の投資家との共同出資なので1口1万円からと、非常に少額から投資できます。運用は出資を募った事業者が行うので手間がかからず、専門的知識も不要です。
さらに、登録手続き、出資、利益分配まですべての手続きをネット上で完結できます。
投資初心者も忙しい投資家も、だれもが始めやすいシステムが整っていることが、人気の理由でしょう。
2.不動産クラウドファンディングのデメリット
不動産クラウドファンディングの手軽さは、よい面ばかりとは限りません。デメリットも把握しておきましょう。
2-1. 好きなタイミングで換金できない
不動産クラウドファンディングでは運用期間中に換金できないのが一般的です。不動産相場が下がり始めるなど不穏な気配を感じても、満期日が到来するまで投資金の回収はできません。原則として元本保証もないので、投資の際は元本割れリスクを考慮しましょう。
2-2. 大きなリターンを得るためには多額の自己資金が必要
不動産クラウドファンディングは金融機関から融資を受けられません。ローンを組める現物不動産投資のようなレバレッジ効果は得にくいでしょう。利益配分は投資額に比例するため、大きなリターンを得るには多額の自己資金が必要になります。
2-3. ほかの投資方法より手数料が高い場合がある
事業者ごとに金額や対応はことなりますが、不動産クラウドファンディングではいくつかの手数料が発生します。出資金送金の際の「入金手数料」、分配金の「出金手数料」などです。
ごく少額な場合がほとんどですが、少額出資では金利との兼ね合いで手数料負けする可能性も考慮しておくと安心です。見込み利益に対する手数料の比率がほかの投資方法より高いケースも多いので事前に確認するようにしましょう。
2-4. 案件によっては応募できない場合がある
不動産クラウドファンディングには先着順、抽選制の案件があり、希望の案件に投資できない場合があります。優良物件やリターン上限を設けないような人気の高い事業者への投資を狙うなら、複数登録するなどスピーディーに動ける備えも大切です。
2-5. 現物不動産と同じリスクがある
不動産クラウドファンディングでも不動産に投資する以上は、不動産価格の変動や建物の老朽化、天災などによる損害など、現物不動産と同様のリスクが存在します。プロが運用しているからと油断せずに、物件を精査することも重要です。
3.不動産クラウドファンディングのデメリット対処法
ここでは、不動産クラウドファンディングのデメリットへの対処方法を5つご紹介します。投資の基本ともいえる内容なので、投資前のルーティンとして身につけておきましょう。
3-1. 投資に関する知識や情報を収集する
事業者選び、案件選びで適切な判断ができるように、まず「不動産クラウドファンディング」についての知識を身につけましょう。仕組み、事業者、運用方法、リスクやメリット、必要な資金、どのような資産形成に向いているのかなど、できるだけ詳しく学んでから投資を始めることが重要です。
3-2. ほかの金融商品と組み合わせる
不動産クラウドファンディングはローリスク・ミドルリターンの投資方法ですが、レバレッジが低いのがデメリットです。ほかの金融商品との組み合わせで投資リターンの最大化を狙うのがおすすめです。例えば、株式投資と組み合わせると堅実かつ収益を狙える資産運用となるでしょう。
3-3. 出資者のリスクヘッジが行なわれているか確認する
収益減や元本割れのリスクに備えて、事業者が優先劣後方式やマスターリース契約を採用しているか確認しましょう。
①優先劣後方式
優先劣後方式とは、不動産価値の下落や空室などで損失が発生した際に、先に事業者が損失を負担し、所定の比率まで投資家の元本を守ってくれる仕組みです。事業者が損失を負担する割合は、投資家と事業者の出資比率で決まります。
例えば、投資家が70%と事業者が30%の出資比率の場合、全体の30%までの損失は事業者が負担します。この場合、投資家が「優先出資者」、事業者が「劣後出資者」に当たります。
投資家の優先出資比率が高いほど元本割れリスクが低くなりますが、その分、リターンが下がるケースが多いので相対的な判断が求められます。
②マスターリース契約
マスターリース契約とは、事業者が不動産会社に物件をまとめて貸し、その転貸を認める契約です。この契約期間中は不動産会社が借りている形になるため、家賃相場や空室状況などの影響を受けずに済み、投資家にも一定の収益が保証されます。
ただし、収益保証はマスターリース契約期間中に限られる点と、契約先の不動産会社の倒産による収益減の可能性には注意が必要です。
3-4. 複数の案件に分散投資する
不動産クラウドファンディングもほかの投資と同様に、複数の案件に分散投資してリスクに備えるのが基本です。運用期間中に解約・現金化できないので、リスク対策は必要になります。案件だけでなく、事業者も分けておくと、倒産リスクにも備えられるでしょう。
3-5. 運用会社の信頼性を確認する
不動産クラウドファンディングは出資後、ほぼすべてを事業者にゆだねることになります。大事な資金を運用させる会社は信頼できる所を選びましょう。過去の実績や扱う物件数、経営状況などを調べ、手数料やリスクヘッジについても複数の会社と比較してじっくりと検討することが大切です。
4.不動産クラウドファンディングの運営会社の選び方
不動産クラウドファンディングの運営会社を選ぶ際は、以下の3つがポイントです。
- 応募機会(案件数や募集口数)が多いか
- 物件の情報量が充実しているか
- 不動産業の実績や資本金は十分か
条件のよい案件は公開後、すぐに募集枠が埋まってしまうことも珍しくありません。案件数や募集口数などの応募機会は多ければ多いほど有利なので、案件数が多い運営会社を選びましょう。
また、物件情報の充実度も判断基準のひとつです。不動産クラウドファンディングは途中解約ができません。投資に値するかの判断材料が豊富なサイトほど信頼できます。物件の外観や築年数といった基本情報に加えて、駅からの距離やそのエリアの家賃相場まで公開されていると便利です。
そして、不動産クラウドファンディングは運営会社がなにより大切です。不動産業者としての実績がしっかりしているか、資本金は十分かなど、企業の信頼性をしっかりと見極めましょう。
5.まとめ
不動産クラウドファンディングは1口1万円から投資できる、スマホで完結する、プロに運用を任せられるのがメリットですが、当然デメリットも存在します。
好きなタイミングで換金できない、大きなリターンを得るためには多額の自己資金が必要、ほかの投資方法より手数料が高い場合があるなどのリスクを理解し、事前に対処しましょう。
不動産クラウドファンディングのリスク回避は、投資方法や物件の情報収集や分散投資といった投資の基本と同時に、運用をゆだねる事業者の信頼度を見極めることが何より重要です。実績や資本金までしっかりと調べましょう。
分散投資には不動産投資を組み込むことでリスクを軽減できる場合があります。近年は少額から投資が可能な不動産小口化商品や不動産クラウドファンディングなどの商品が増えているため、分散投資がしやすくなっています。
また、ボルテックスでは不動産小口化商品「Vシェア」を展開しています。「Vシェア」は、個人では購入が難しい都心のプライムエリアにあるオフィスビルを500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資が可能です。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
不動産投資の記事一覧に戻る