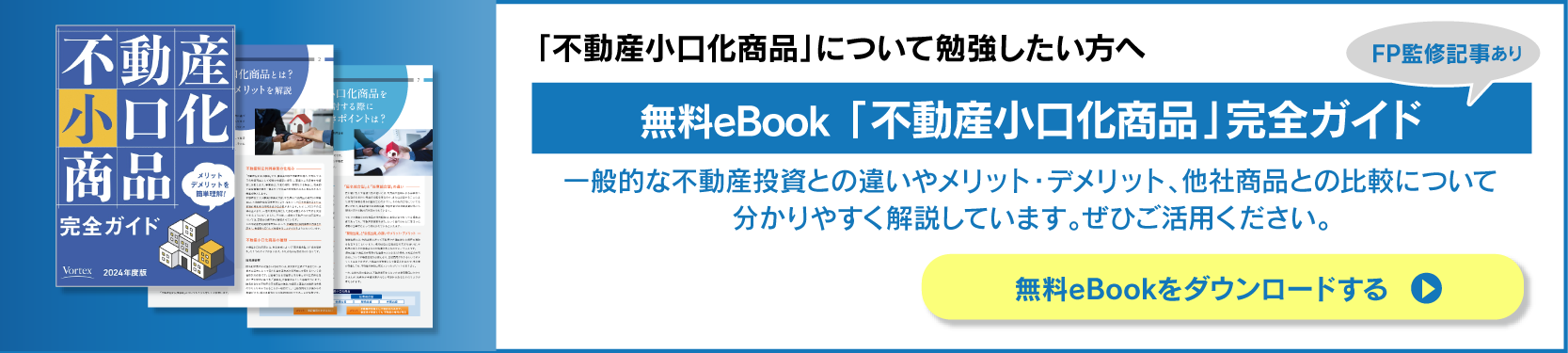目次
REIT(不動産投資信託)はインフレーション(物価上昇)に対して強い投資先として知られています。しかし、マイナス影響を受ける場合もあるため、リスクに備えたポートフォリオの構築が重要です。
そこで、この記事ではREITがインフレに強いといわれる理由や、インフレがREITに与えるマイナス影響、リスク対策について解説します。
1.REITの仕組み
REIT(不動産投資信託)はReal Estate Investment Trustの略称です。不動産投資法人が投資家から資金を集めてオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を購入・運用し、そこから得た賃料収入、売却損益などを投資家へ分配します。
REITはアメリカで生まれた金融商品で、日本ではJapanの頭文字をとって「J-REIT」と呼ばれています。J-REITを運営する投資法人は利益の90%以上を分配することで法人税が非課税となるため、ほとんどの収益が分配されます。投資家にとって、定期的な分配金を期待できることは大きなメリットでしょう。
REITは数万円程度から購入できるうえ、証券取引所を利用して売買するため流動性の高さが魅力です。実物不動産に比べ、購入のハードルが低い投資方法といえるでしょう。
2.REITがインフレに強いといわれる理由
なぜREITはインフレに強いといわれているのでしょうか?その理由を3つみていきましょう。
資産価値の高まりで売却益が増加する
インフレはモノの値段が上がる状態のことです。別の角度から見ると「お金の価値が下がる」とも言い換えられます。例えば、ある商品が1万円から2万円になった場合、同じ商品を購入するために2倍のお金が必要になるため、お金の価値は2分の1になります。
つまり、インフレ時にはお金より実物資産の価値が高くなるため、REITを保有することで資産の目減りに備えられるということです。
また、一般的に物価上昇にともなって不動産の価格は上昇します。インフレで不動産価格が上昇すれば売却時により多くの利益を得られるでしょう。
賃料の上昇で分配金が増える
不動産投資において、賃料は消費者物価指数とともに上昇していくとされています。賃料上昇は分配金の増加につながります。
また、多くの商業用物件や通信塔などの長期契約時には、インフレ率に連動して賃料を引き上げるエスカレーション条項を定めていることがあります。これにより、物価上昇にともなって収益も引き上げられるため、有効なインフレの防衛策になります。
さらなる資産価値の値上がりが期待できる
賃料の上昇によって分配金が増加すれば、REITに魅力を感じた多くの投資家から資金が集まりやすくなります。資金が流入すれば不動産の価格が上昇し、投資家も積極的に投資し続けるという好循環が生まれやすくなるでしょう。
3.REITで知っておきたいインフレによるマイナス影響
REITはインフレに強いといわれているものの、最大のメリットである「分配金の安定維持」が難しくなる側面も指摘されています。その理由を2つご紹介します。
分配金の増加が間に合わない
不動産の賃料上昇は、土地や建物の価格上昇に遅れて現実化することが知られています。これを「賃料の遅行性」といい、例えば、オフィスビルでは2年契約が一般的で、その間インフレが進んでも賃料は増加しません。インフレに対して緩やかに賃料が上昇していくため、分配金の増加にすぐ直結しない場合があります。
ポートフォリオの縮小・分配金規模の低下が起こる
インフレと景気後退が同時に起こるスタグフレーションになった場合、不動産価格が上昇する反面、賃料は低下しやすくなります。REITは新たに不動産を取得し続けることが難しくなるでしょう。
この状況下でも、高い期待利回りに応えるために物件の売却益で分配金を補てんする動きを行うと、ポートフォリオの縮小が進みます。将来的に、分配金規模の低下につながります。
4.REITファンドを活用した分散投資で備える
REITには、複数のREITに投資できる投資信託(REITファンド)という選択肢もあります。ホテル特化、住宅特化など、あるセクターに強いREITに投資をすると景気の影響を受けやすくなりますが、REITファンドであればリスク分散できます。
また、実物不動産に分散投資する方法もおすすめです。近年は、不動産小口化商品、不動産クラウドファンディングなど、REITと同額程度からインターネットで始められる実物不動産投資が増えています。
5.まとめ
REITは不動産を購入・運用し、得た収入を投資家に分配する投資信託です。日本ではJ-REITと呼ばれ、小口で購入できる点や流動性の高さが魅力です。
REITがインフレに強い理由は、資産価値の高まりによる売却益の増加や、賃料の上昇による分配金の増加、資金流入によるさらなる価値上昇が期待できるからです。
しかし、インフレによるマイナス影響も考えられます。景気動向に対する賃料上昇の遅れや、スタグフレーションでポートフォリオの縮小、分配金規模の低下が起こる可能性があります。
REITファンドや、不動産小口化商品・不動産クラウドファンディングなどの実物不動産への分散投資でリスク対策を行いましょう。
また、ボルテックスでは不動産小口化商品「Vシェア」を展開しています。「Vシェア」は、個人では購入が難しい都心のプライムエリアにあるオフィスビルを500万円(1口100万円単位・5口以上)から投資が可能です。
「Vシェア」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
- 本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。
- 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
- 評価額は物件により異なります。
- 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
- 税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
不動産投資の記事一覧に戻る