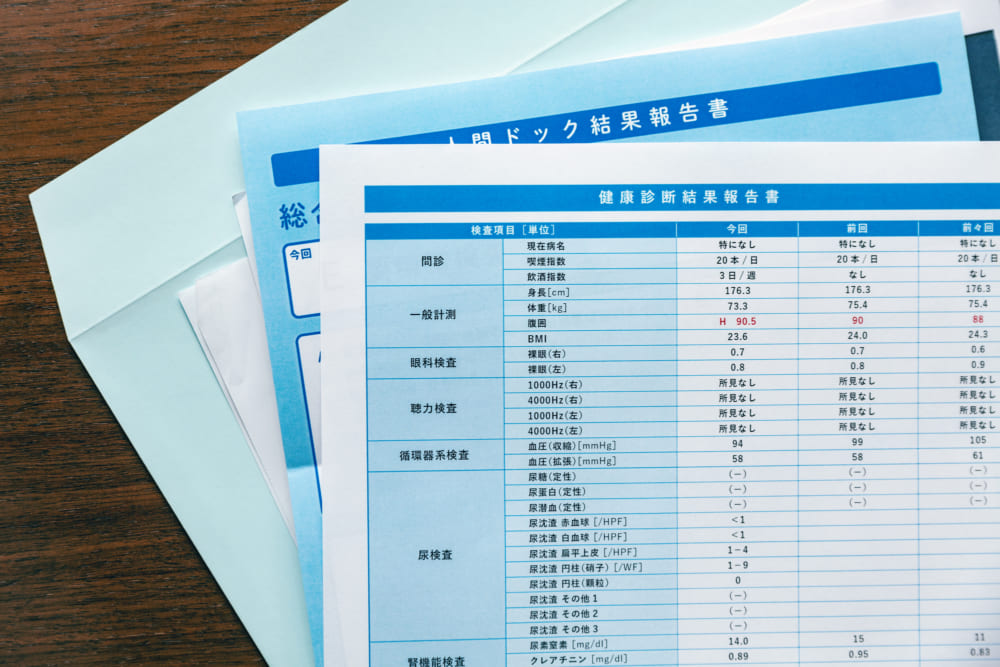慣習からの脱却で生まれた「獺祭」
負けを認められる強さが逆境を乗り越える力となる
【旭酒造株式会社 会長 桜井 博志 氏】

目次
純米大吟醸酒としては日本有数の生産量を誇り、世界的にも人気が高い「獺祭(だっさい)」。そんな銘酒を生み出したのは山口県の山奥にある倒産寸前の酒蔵でした。常識破りの酒造りに挑んだ旭酒造株式会社の桜井博志氏に話を伺いました。
他と違うことをする逆張りの発想で「獺祭」が誕生
旭酒造は“負け組の酒蔵”でした。先代である父の急逝を受け、私が3代目の社長に就任したのは1984年のこと。当時は焼酎ブームなどの影響から日本酒業界は右肩下がりで、旭酒造も例外ではなく、売り上げは前年比85%、10年前と比べると3分の1にまで落ち込んでいました。
実は、私は大学を卒業して西宮酒造に勤務した後、20代半ばで家業に入りました。ところが、程なくして父と衝突し、クビを言い渡されています。だから社長として復帰するにあたっては、亡き父を見返すためにも盛り返してやろうという気概に満ちていました。
でも、売れないんですよ。山口県内はおろか地元の岩国市内でも4番手の弱小酒蔵でしたから、縮小する市場では相手にされなかったのです。先代の手法を踏襲して値引きをしたり、ノベルティーを付けたりしましたが効果はなく、廃業寸前にまで追い込まれました。ただ、手を尽くす中であることに気づいた。当時、旭酒造の看板商品は「旭富士」という銘柄の普通酒でしたが、ほんのわずか純米大吟醸酒を造っていました。これだけは評判がよかったのです。
日本酒の消費量が高かった高度経済成長期は造れば造るほど売れました。業界も消費者も「お酒は酔えればいい」という認識で、質よりも広告宣伝費を含む資本力や営業力が売り上げを左右していた。ところが焼酎やビールが台頭してきて選択肢が増えたことで、酔うための酒より味わう酒を求める消費者が増え始めていたのです。資本力のない負け組の酒蔵が他と同じことをやっていても勝ち目はない。そこで純米大吟醸酒に特化した酒蔵へと舵を切り、1990年に「獺祭」が誕生しました。
常識の風穴を開け事業を成長へと導く
獺祭は現在、日本のみならず世界約30カ国に輸出されています。山口の山奥にある廃業寸前だった酒蔵がなぜこのような日本酒を造れたのか。私は「逆境」こそが獺祭を生み出したと思っています。
そもそも純米大吟醸酒は「幻の日本酒」といわれていました。米と米麹(こうじ)を原料とし、精米歩合(玄米を精米して残った部分の割合)を50%以下にした純米大吟醸酒は、原料や精米歩合の決まりがない普通酒に比べると手間がかかり、安定した量産が難しいからです。そんな酒を造ろうというわけですから周囲はみんな懐疑的でした。
まず、酒どころの新潟や広島が米どころでもあるように、いい日本酒にはいい酒米が重要ですが、山口では良質な酒米が手に入りにくかった。米の仕入販売を仕切る県の農業団体に生産を掛け合っても、見通しが立たないからと相手にされません。そこで地域のしがらみを超えて生産者を開拓し、酒米の最高峰とされる山田錦を直接仕入れました。
しがらみは販路にもありました。当時、地酒は地元で流通するのが一般的で、販売店では1番手、2番手の酒蔵が優先されます。だから私は東京進出を目指したのです。「地元を捨てるのか」などといわれることもありましたが、負け組にとってはレッドオーシャンの地元よりも、市場が大きい東京のほうが受け入れられる可能性があると考えました。
幸い大学の先輩の紹介で地酒を扱う飲食店に置いてもらえたのを機に、東京での販路を開拓。そして1992年に発売した精米歩合23%の「獺祭 磨き二割三分」が話題となり、市場が拡大しました。当時の吟醸酒は24%が最高だったので、それを上回る日本一の酒を造ったのです。これも、他がやらないことをやろうという負け組の発想です。

窮地に立たされたときこそ飛躍のチャンスと捉えよ
負けを認める強さが力になる
しかし、最大の問題は造り手にありました。従来の酒蔵は杜氏(とうじ)が酒造りを取り仕切り、蔵元は販売に専念します。杜氏の多くは農家で、農閑期になると部下を連れて酒蔵に来る、いわゆる季節労働者です。純米大吟醸酒に特化すると決めてから、私は杜氏に味や品質などさまざまな要望を出しましたが、それまですべてを任されていた彼らにしたらやりにくいようで、なかなか要望に応じてくれません。
そのような状況の中、ビール事業で失敗して2億円もの負債を抱えてしまった。日本酒は基本的に冬に仕込むため、夏の収入を確保しようと始めた新事業でした。当時の年間売上高を超える負債でしたから倒産すると思ったのでしょう、杜氏が辞めてしまいました。残ったのは私と3人の社員だけ。しかし、これが大きな転機となります。
実はその数年前から自分でも酒を仕込めないかと研究を重ねていました。そして、精米歩合や温度などをデータ化してマニュアルに落とし込めば可能だとわかった。酒造りには勘が重要だといわれますが、天才とうたわれる杜氏の頭の中にはデータがぎっしり詰まっています。圧倒的なデータがあるからこそ勘が生きるのです。
2000年、私たちはデータを活用してみずから酒造りを始めました。杜氏が去ったことで妥協せず、おいしい酒を追求できるようになった。やがて年間を通して酒を造る四季醸造も開始。これも常識を破る取り組みでしたが、温度管理ができれば冬でなくとも酒は造れるのであり、これで安定生産が可能となりました。獺祭はデータ化することで杜氏の伝統技術の再現に成功したといわれています。しかし、従来の慣習や技術では満足のいく酒が造れないから新しいビジネスモデルを確立したというのが本質です。
現在、旭酒造では200人の蔵人(くらびと)が酒造りに携わっています。社長就任時に1億円に満たなかった売り上げは、2022年度には165億円を計上。そのうち43%が海外輸出によるもので、これは国の日本酒輸出総額475億円の15%を占めています。国内市場が縮小する中、より広い市場を求めて展開してきた結果だと思っています。
2023年4月にはアメリカのニューヨークに酒蔵「DASSAI BLUE SAKE BREWERY」が完成しました(9月に正式オープン)。世界最大規模の料理大学「カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ(CIA)」から打診されたのがきっかけです。同国の酒類市場における日本酒のシェアは0.2%しかなく、難しいと思われるかもしれません。しかし、見方を変えればシェアを広げる余地があるということ。もちろん製造に関する法律の違いなど課題もありますが、シェアが小さいぶん凝り固まった慣習がなく、大きな市場も近い。日本ではできない取り組みにも挑戦できるので、日本の酒造りにもよい影響を与えられるのではないかと期待しています。今後は現地での山田錦の生産も進める予定です。

窮地というのは、見方を変えればチャンスになります。コロナ禍で飲食店が閉まり、輸出が止まったときも同じで、山田錦を食用米や消毒用エタノールに加工して販売したことが需要とマッチし、結果として売り上げは増加しました。ただ、現状を認めなければ原因も打開策も見えてはこない。負けを認められる強さが、逆境を乗り越える力となるのです。そして、それを繰り返していくことが、企業が伸びる秘訣なのだと思います。
[編集]株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課
[制作協力]株式会社東洋経済新報社
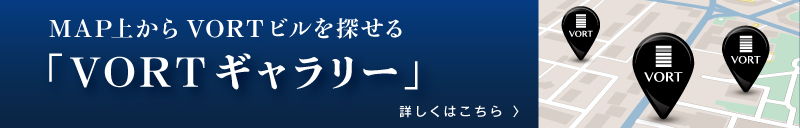
- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。